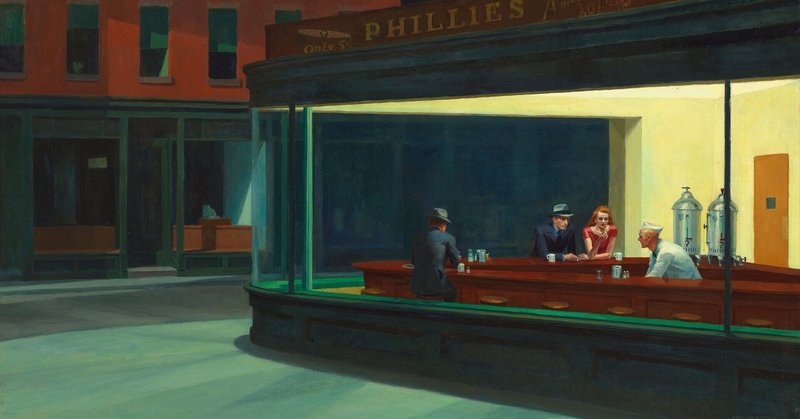
小説『ジェダイだってあの体たらく』 最終回
【登場人物】
菊池慎一 語り手。盗撮の過去あり。
佐恵子伯母 菊池の父親の姉。菊池は十七年ぶりに彼女を訊ねる。
菊池澄子 角田の母親。スピリチュアルにはまり、育児を放棄した彼女を菊池は恨み続けていた。
父親 故人。不倫の常習者だった。
姉 母親と一緒に暮らしている。母の具合が悪いという彼女からのメールを菊池は無視した。
直江千佳 菊池に、盗撮犯のためのカウンセリングや自助会を紹介した。
「慎二のために離婚するとか、言いたい放題だな」
「伯父さんは口から出まかせだと言ってたけど、片親の方が良い施設に入れるとか、手当が増えるとかそんな話だったね。でも、澄子さんはそんな理由で離婚はしたくないって、あの人にしてはすごく頑張ったんだよ。それで、毎日のように喧嘩になって――このままじゃお母さんがどうにかなってしまうと思った愛ちゃんがうちに電話してきたから、私と伯父さんが間に入ったわけ」
「それで親父は離婚をあきらめたのか?」
「慎太郎はそういう子でしょ。澄子さん相手なら偉そうなことも言えるけど、伯父さんなんかがこんこんと説くと、すぐあきらめてしまう。あの子があきらめても、娘の方はあきらめられなかったみたいだけど。あの娘は、お母さんを訪ねて来て、土下座して、ご主人と別れて下さいと言ったんだよ。これは、愛ちゃんがお母さんから聞き出したことだけど。もちろん、澄子さんの中では、自分が至らないから他人にそんなことをさせてしまったということになっているんだけどね、あの人の宗教だか何だかは、自分を高めれば、他人も世界も変わるって教えらしいから」
「おふくろがスピリチュアルに凝り出したのは、ちょうどあの頃だ。親父の不倫相手が訪ねて来たのがよっぽどショックだったのかな」
「慎太郎に、お前のせいであの娘が自殺を図ったと責められたせいだよ、もちろん。自分の弟だけど、ほんと、慎太郎はどうしようもない男だよ。自殺未遂されて、あの娘を捨てたくせに、澄子さんにも文句を言わなきゃ気が済まないんだから。澄子さんが宗教だか何だかにはまった時、子どもを放っておいてそんなことをするなんて馬鹿げていると思ったから、言い聞かせたんだけど、私が至らないせいで命を失いかけた人がいる、二度とそんなことがないようにこうして自分を良くする努力をしているんだと言われると、何も返せなかったよ。全部、慎太郎が悪いんだから。あんたたちには気の毒だったけど、あんな目に遭って、それでも正気を保てという方が酷だって、恵も言ってた。恵は、叔母さんがあんな風になる前は、私に叱られるたびに澄子さんに電話して、慰めてもらっていたからねぇ。澄子叔母さんはお母さんの百倍優しい人だから、百倍生きづらかったんだと今も言ってるよ。だからね、慎ちゃん、あんたも澄子さんを許してあげなきゃ。慎二ちゃんが死んでしまった時、あの子はここより幸せな場所に行った、あの子は今が一番幸せだと言うなんて、私だって、何を馬鹿なことをと思ったけど――あのかわいい慎二ちゃんによくまあそんなことって。だけど、どこかに幸せになれる場所があると信じなきゃ耐えられない、それだけの重荷をあんたのお母さんは背負っていたんだとも思うんだよねぇ」
◆
慎二が死んだ後におふくろが言ったことのせいで、俺はおふくろを憎むようになったのだろうか。慎二はもっと良い世界に行ったのだという、あの言葉のせいで。
そうかもしれないし、違うかもしれない。あの言葉が引き金になり、母親を憎んでもいいと自分に認めるようになったのかもしれない。自分は母親に見捨てられた哀れな子どもだと思いたかったのかもしれない。いずれにしても、そんな気持ちのまま、今まで生きてきたのは間違いない。
認知の歪み。伯母は娘の家族の認知が歪んでいると言ったが、親父も似たようなものだ。子どもが障碍児だからって、家出して不倫を始めるなんて、マトモな奴のすることじゃない。
父親がそんな奴だから、そりゃ、俺の認知も――いや、そうやって責任転嫁ばかりするな。自分が悪いんだ。おふくろを責めてばかりで、おふくろの苦しさやどうしてスピリチュアルにすがるようになったのかを考えようともしなかった。自己中のガキ。ガキ。自己嫌悪の波が押し寄せる。自分を殴り、大声で叫びたい。
何時間か闇雲に歩き、疲れて果てて公園のベンチに座った。涙がとまらない。おふくろに謝りたいが、おふくろは俺を覚えているだろうか。
認知症になった母親は、十七年会っていない息子を思い出せるだろうか。
十七年間、姉貴は一人で……。
親父の葬式にも、俺は帰らなかった。
おふくろを恨み、姉貴を見捨てて。
名前も知らない女子高生の下着を盗撮し、警察に捕まり、不倫と中絶を繰り返してモンスターになった女と付き合ってしまった。
今更、どのツラ下げて帰るのか。
「大丈夫かい?」
そう言われて目を上げると、柴犬を連れた老人が、俺を見ている。
「大丈夫です、どうもありがとう」
老人はうなずき、通りすぎる。柴犬が俺に尻尾を振った。
あんな風に見知らぬ他人を気遣える人もいる。
涙を拭こうと、ズボンのポケットをさぐった。ハンカチの代わりに、硬い紙が手に触れた。
直江千佳の名刺だ。裏に、自助会を主催している弁護士の連絡先が書いてある。
「ジェダイだってあの体たらく」
小声で言ってみたが、まったく気は晴れない。俺のダメっぷりはジェダイの比ではないし、ジェダイは俺とは違い、数多くの善もなした。
もちろん、千佳は、唱えれば気が晴れる魔法の呪文を教えてくれたわけではないが。同じ罪を背負う者たちとつながり、支え合えばいいと教えてくれたのだ。
名刺に書かれた直江千佳の名前を眺めるうちに、心が定まった。
おふくろと姉貴に謝ろう。おふくろは俺がわからないかもしれないが、何かできることはあるはずだ。
姉貴の支えにもなりたい。
だが、まずは弁護士に電話して、俺自身の罪、誰のせいでもなく、俺が自分の意志で犯した罪を見つめなければ。俺の中にある闇を見つめ、二度とその闇に負けないように、手を差し伸べてくれる人たちに教えを乞うのだ。その後で……。そう考えながら、東神奈川駅に向かって歩き始めた。
人は悲しみでしかつながれない
アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
完
読んでくださってありがとうございます。コメントや感想をいただけると嬉しいです。
