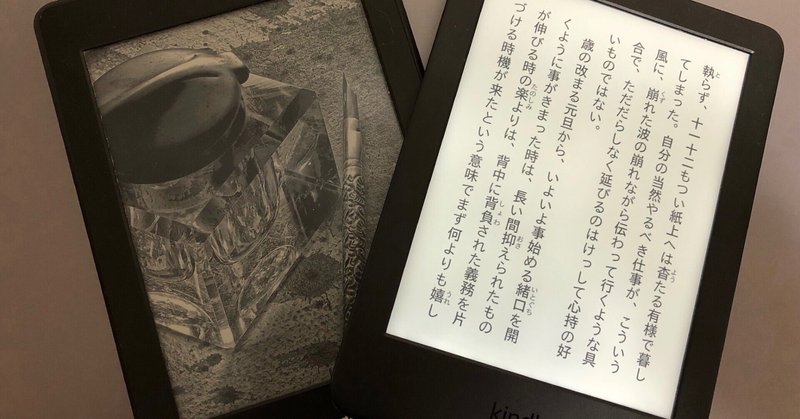
「ただ自分らしいものが書きたい」 夏目漱石『彼岸過迄』 【読書感想文】
前回取り上げた『門』同様、『彼岸過迄』も地味な印象があります。後期三部作の一作目なのですが…後期三部作って、『こころ』以外は未読という方が結構多いのではないでしょうか。
『彼岸過迄』には、つい最近まで柴又にあった川甚という鰻屋が登場するんですね。川甚も、駅の広告で「当店、漱石の小説に出ております」と宣伝していました。それを見ながら、「どうせ誰も読んでないと思って、こんな広告出しているんだろうなー」と考えたものです。なぜなら、作中には、川甚の鰻は甘ったるくて食べられないと書かれているのですから…。
『彼岸過迄』があまり読まれていないのは、「個々の短編を重ねた末に、その個々の短編が相合して一長編を構成する」という漱石が編み出した手法に馴染みが薄いためかもしれません。短編をつなぐテーマがあるわけでもなく(例えば、村上春樹さんの連作短編集『女のいない男たち』なら、女のいない男が統一テーマ、というような)、誰が主人公なのかもよくわからない。
Wikipediaには、「自意識の強い男と、天真なその従妹との恋愛を描く」と内容が説明されていますが、その話が出てくるのは六つある短編中、最後の二つだけです。
前期三部作のような、物語の最初から最後まで登場する主人公がいて、まとまりのあるストーリーが展開されて…というタイプの小説を想像していると、「ちょっとよくわからない…」と感じてしまいそうです。
もちろん、世の中には筋やテーマが曖昧な小説が数多くあるので、そうした作品を読み慣れた方なら、『彼岸過迄』に戸惑うこともないでしょうが、そうでないなら、この作品を枕元に置いて、気が向いた時に少しずつ読み進めた方がいいかもしれません。読む間隔があいて、話を少し忘れてしまっても、特に問題はないと思います(筋を回収するような作品ではないので)。
一気に読んでそれで終わりというのでなく、一度読み終えてもまた読みたくなるような、適当に頁を開いて拾い読みしたくなるような…不思議な魅力のある作品だと思います。
*
先ほど書いたように、『彼岸過迄』は六つの短編から成る小説です。
第一短編「風呂の後」では、就職浪人中の青年、田川敬太郎の日常生活が描かれます。高校生の時にスティーヴンソンの『新アラビア夜話』を読んで以来、浪漫主義の冒険に憧れている敬太郎ですが、現実には、無味乾燥な日々を送っています。唯一の楽しみは、同じ下宿に住む森本の話を聞くこと。森本は波瀾万丈な人生を送ってきた男で…というところから、話が始まります。
私自身、若い頃は、三四郎のような純真なタイプではなく、といって『それから』の代助のように高等遊民を気取れる境遇でもなく…型にはまった生き方はしたくないと思いつつも、ぐうたら過ごしていたので、敬太郎に共感しながらこの短編を読みました。
第二短編「停留所」では、モラトリアム生活から卒業すると決めた敬太郎が、友人・須永の叔父、田口に就職の斡旋を頼むところから物語が始まります。就職するからには、当然、ロマンチックな冒険心など捨てた気でいたでしょうに、田口に頼まれたのは、探偵めいた仕事で…という話。
若い頃の漱石は、神経衰弱にかかって探偵に見張られていると思い込み、探偵という職を憎んでいた筈ですが、この話では、敬太郎の探偵ぶりがコミカルに描かれています。
第三短編「報告」では、「停留所」の種明かしが語られます。他愛もない話なのですが、敬太郎はこれをきっかけに、職を得て、重要人物である田口の家に出入りできるようになります。
第四短編「雨の降る日」は、田口の娘・千代子が敬太郎に語る話です。内容は敢えて書きませんが、非常に美しく、かなしい物語です。漱石にこれほど繊細な物語が書けるのかと少し意外なほどに。第一話から読み始めて、敬太郎の話が退屈だと感じる方は、途中とばしてこの「雨の降る日」を読んでもいいかもしれません(この作品だけ独立して読んでも、問題ない作りになっています)。夏目漱石の新たな魅力が発見できる短編です。
第五短編「須永の話」と第六短編「松本の話」が、Wikipediaに書かれている「自意識の強い男と、天真なその従妹との恋愛を描く」話になっています。第五短編は須永、第六短編は須永の叔父である松本が敬太郎に語って聞かせる形です。敬太郎にはお似合いの二人に見える須永と千代子がなぜ結ばれないのかを、本人と第三者がそれぞれ語ることになります。
二人が結ばれぬ理由は、今となってはなかなか想像しにくいですが、『それから』の代助や『門』の宗助にも通じる、人生に対する消極的な態度が須永にも感じられました。
理由は違えど、現実生活にコミットしたくない男達を描くのが漱石文学の特徴の一つなんでしょうね。そして、敬太郎という、冒険を諦めて現実に生きると決めた青年が登場することで、その特徴がより鮮明になっている気がしました。…などと読み解くのは蛇足かもしれませんが。何も考えず、ただ漱石の語りに身を委ねればいい、『彼岸過迄』を読むと、そんな風にも感じるのです。
自分はすべて文壇に濫用される空疎な流行語を藉りて自分の作物(作品)の商標としたくない。ただ自分らしいものが書きたいだけである。
読んでくださってありがとうございます。コメントや感想をいただけると嬉しいです。
