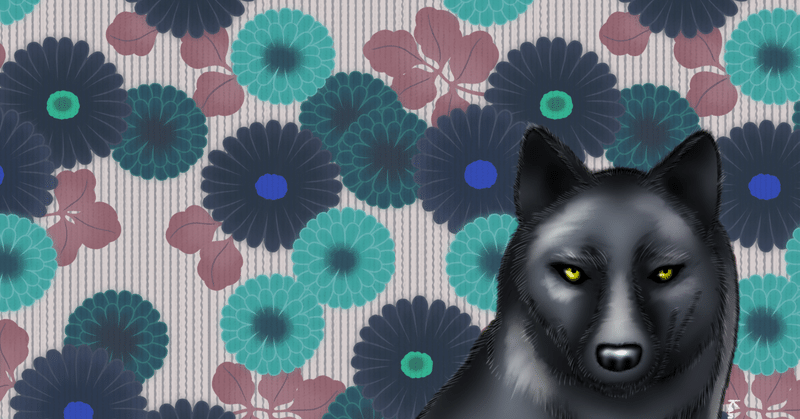
天地伝(てんちでん) 4-2
二
「でも、失礼な話よね」
登紀子は、わしの背の上でつまらなそうに、つぶやいた。夜のつめたい風に吹かれる赤茶色の髪の毛は、きめが細かく、外灯の火に照らされてきらきらと、かがやく。蜘蛛の糸のようだった。わしは、白い息を吐き出しながら「何がじゃ」と、言って鼻を鳴らした。
「こちとら、必死にかけずり回ってるってのに、何で疑われなくちゃいけないのよ。まともに考えたら、女と犬一匹に地震なんか、起こせる訳ないじゃない」
「乱心している人間にまとも、が通じるはずがあるまい。恐怖は人の心を歪める。否、元の姿に戻すとも言えるな」
「ねえ、それだと面白いことになっちゃうわ」
登紀子は急に、声を上げて笑い始めた。わしは、眉間に皺をよせて「何がおかしいんじゃ」と、低くつぶやいて、丘をかけのぼった。
「だって、お父さんは恐怖することがないから、歪まなかったってことでしょう。強かったからよ。だから、あれだけの義を貫けたってことよね」
「それは、そうだろうな。だが、紙一重だったはずじゃ」
「どういうこと?」
登紀子はわしの背にしがみつきながら、頓狂な声を上げた。わしは、苦笑を浮かべて、坂を駆け下りてゆく。
「あいつは、強いからこそ、弱いものを簡単に扱うこともできた。つまり、強いか、弱いか、が問題な訳じゃない。そいつが、何を選択し、それを信じて貫くのか、に人の心の現れを求めたんじゃないのか?」
「八枯れのくせに」登紀子は、そうつぶやいて、後ろからわしの鬚を引っ張った。「ちゃんと、わかってるんじゃない。馬鹿ね」と、言って笑った。わしは、「あまり、ふざけるな。落っことすぞ」と言って、走る速度を上げた。
更地にたどりついてすぐ、登紀子は「止まって」と、声を上げた。闇の中、激しく吹きつけてくる風には、礒の香りがまざっていた。海が近い証拠だろう。
「この辺りじゃない?なんか、すごい耳鳴りがする」
「だろうな」わしは、ちらと、大地を眺めながら舌を出した。「土地の脈動が、もうわしの毛を逆立てとる。近くて明日、もって明後日までだ。可哀想にな。無理矢理、地盤の形を変えられて、苦しそうじゃ」
「明日ですって?」登紀子は頓狂な声をあげてすぐ、「あー」と、うなりながら、しゃがみこんだ。赤茶色の髪をかきまぜながら、大きなため息をついた。
「帰ろうか」
「なぜだ」
「意味がないからよ。決まってるでしょう」
そう言って、登紀子は不機嫌そうにわしの背に跨った。訳がわからず、眉間に皺をよせていると、後ろから鬚を引っ張られ「ほら、早く行って」と、八当たりをしてきた。何なのだ。
「言ったでしょう。少なくとも、一週間は前の種を見つけなくちゃいけないのよ。いま、破裂させたところで、大した規模の縮小は認められない。ましてや、夜よ?明日か明後日なら、きっと朝か、昼にこの地盤は壊れるはず。その方が、避難しやすいはずだわ」
登紀子はあくびをもらしながら、億劫そうに言った。わしは鼻を鳴らして、また丘を駆けのぼりはじめる。
「面倒なことだな。これだから、わしらが歩いた後の土地は壊される、などと言うくだらぬ吹聴が流れるんだ」
「帰ったら、京也おじさまにたっぷり文句を言ってやるわよ。本当、あの人の情報って遅いって言うか、あてにならないって言うか、いい加減だわ」
「科学は、あてにしとらんのだろう?」
「それとこれとは別よ」
この夜の、登紀子の判断の正誤は不明だが、翌日十四日、午前十時三十七分、千葉県下で揺れの激しい地震が、発生した。被害は、土砂崩れによる数人の生き埋めであったが、大規模な倒壊はなかったようだ。しかし、その報道を新聞の紙面で目にした時の、登紀子の表情は、平生のものよりほんの少し歪んでいた。妙なところでくそ真面目なこの娘は、地震被害の拡大は、己の責任とでも考えているのだろう。
そもそも、人に自然災害を防ぐ手立てがあるのかどうか、それさえも甚だ眉つばものだと言うのに、妙な性格と妙な能力が、人が人であることを忘れさせているのだろうか。ずいぶん、傲慢な話のようだが、登紀子はあまりに真剣なのだ。ゆえに、この娘はまったく、タイマによく似ている、としか言いようが無い。
だが、一つだけ根本的に違うことは、己の周囲外のことに手を出すとき、タイマは責任の所在だけは、明確にしなかった。それが、あいつなりの護り方だったのかもしれない。自分も他者も傷つけずに済む方法を、つねに模索しているようだった。それは、あいつがやはり、化け物であるからなのか。影響の発生と言うものを、冷静に見据えているからなのかもしれない。
登紀子は違った。人であるがゆえに、心がもろかった。人は、さまざまの行いに責任の所在を求める。だから、あの娘は新聞報道の一面を見て、苦渋に顔を歪めたのでは、なかったか。おそらく、タイマも同じように心を痛めはするだろう。だが、あいつは、それさえも次の行動を起こすための準備段階として、消化してしまうほどの冷徹さがあった。何が二人を分け隔てていのるか。それは明確だ。
化け物は、過去を、あるいは事実を歪めることなく、ありのまま受け入れてしまうのだ。そこに人の抱くような主観性、感情性などの視点はない。つまり、みずからを守るための嘘さえも排除すると、言うことだ。だからこそ弱いものには弱いと言い、強いものには強いと言う。生きられないと悟れば、死を受け入れるし、殺さなければならないと思えば、迷わず殺すのだ。実際的と言えばそうだが、実質は機械のようなものだ。
それならわしは、いったい何なのだろうか?
「八枯れ」
呆然としながら、縁側で丸くなっていると、耳慣れた声に名を呼ばれた。振り向くと、由紀が小さな荷を一つ抱え、藍色の着物姿で、微笑を浮かべて立っていた。わしはそれに鼻を鳴らして、あくびを一つもらした。朝日が目にまぶしい。
「行くのか?」
「ええ、恭一郎さんは、もう先に東堂さんの用意した車で行きました。私はあいさつをしようと思って、昨夜から、こちらに泊まって居たんです」
「余計な気を回すな。わしらが居ない時に、火でも放たれてみろ。死ぬぞ」
「ふふ、そうですね」
由紀は目をつむったまま、目尻に皺をよせて、やわらかく微笑んだ。隣にしゃがみこむと、庭先でゆれている楓の葉の香りを吸い込み、大きく息を吐き出した。
「ごめんなさい」
そうつぶやいて、うつむいた白い横顔を、ちら、と見つめた。思えば、タイマが姿を消してから、由紀とこうして二人きりで、口を訊いたのは、はじめてではないだろうか。
「貴様らは、いつも終わってから謝るな。なぜだ」
「黙っているほうが、優しいことだと勘違いしているから、かもしれませんね。そうして、過ぎ去ったあと、はじめて過ちに気づくのでしょうね」
「後悔しているのか?殊勝なことだ」
「私たちを怒っているのでしょう?」
「そう見えるか」
苦笑を浮かべてつぶやくと、由紀はわしの額にそっと、触れた。微かな女のぬくもりにのって、白粉の香りがした。
「見えません。私には、あなたの顔も、姿も、どのようなものか、わからないのです。でも」
「わかっている」わしは、由紀の手の平に鼻をすりよせて、ちろり、と舐めてみせた。「お前が、すべてをわかっていて、なお黙し、そばにいたことを、とっくに知っている」
由紀は、微笑みを崩すことなく、指先を微かに震わせていた。ゆれる小さな肩を見つめながら、なぜこの女はいつまでも強情なのだろうか、と微笑を浮かべた。
その小さな姿が気丈に振舞うたびに、わしは胸が、背の骨が震えるような、抑えようのない熱を感じているのだから、それはまったくタイマに輪をかけたような狂気である。
「誰よりも、お前が一番傷ついていることを知っている。だから、自分を責めるな。人はすぐに何かを責めたがるからな。だから弱いと言うのだ。だから」
愛おしいのか。その言葉にみずから驚き、すぐに飲み込んだ。由紀は、わしの頬を両の手でつつみこみ、頬をよせてきた。わしの額に鼻をうずめて、小さく微笑みを浮かべた。白粉の香りが、鼻をついた。
「獣の匂い。でも、枯草の匂い。やわらかくて、温かくて、くすぐったいのですね。知っていますか?八枯れ」
「何をだ」
「どこでも、心の鼓動を感じることはできるのですよ。ほら」
そう言って、わしの眉間に人差し指を押し当てて、一定の速度で律動していた血管の筋を、なでた。その感触に、一瞬、身を震わせて「さわるな」と、つぶやいた。ふふ、と声をもらして笑った由紀の顔を眺め、ずきずきと痛む後頭部のうずきを感じながら、眉間に皺をよせた。
台所に適当にこしらえたご飯があるから、登紀子が目を覚ましたら食べてほしい、と言われた。由紀は睡眠と食事の心配だけを、最後までしながら、坂島の家を出て行った。
サポートいただいた、お金はクリエイター費用として、使用させていただきます。 いつも、ありがとうございます。
