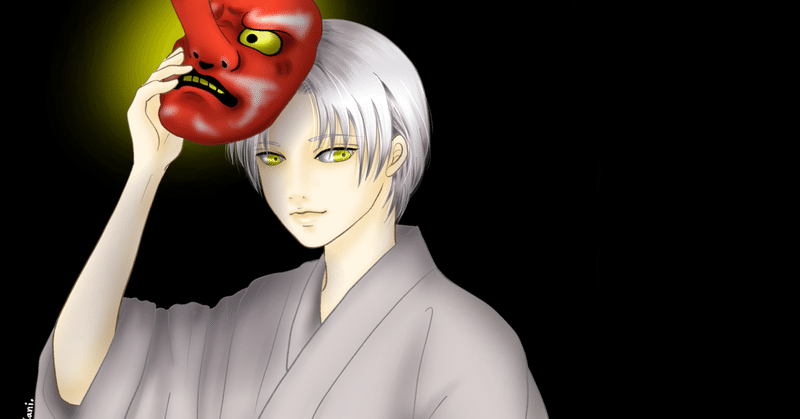
天地伝(てんちでん) 3-15
十五
夕餉もすませ、京也が帰るとようやっと落ち着いたと、くつろいでいたときだった。慌ただしい足音が近づいてきた。襖を開けた由紀の顔は、狼狽し、青白くなっていた。
タイマの体調が急変したと言う知らせを聞いて、わしと登紀子は言葉を無くした。医者を呼ぶ、と言って聞かない由紀を、登紀子に任せて、わしは部屋へと急いだ。
座敷に上がると同時に、熱に浮かされた黄色い双眸と、目があった。室内にこもっていた埃と、汗の匂いに眉をよせる。
冷えた畳の上で足を折り、息の荒い、青白い顔を見据えて微かに笑んだ。
「もういくのか?」
小さく声をかけると、タイマは億劫そうに瞼を上げて、「勝手に殺すなよ」と、言って笑った。
口元によった皺に、影ができる。吐き出す息が、熱い。ぐっしょりとぬれた前髪からは、嗅ぎ慣れたなつかしい匂いがする。
死の匂いだ。
「お前には、すまないことをしたな」
苦笑を浮かべた顔を眺めながら、鼻を鳴らした。
「今わの際のようなことを言うな。らしくないぞ」
「らしさなど、もはや保てまい」
「そういうものか」
「生きるのは、なかなか楽しかったな」
低い声の響きに目を見張った。
快活に笑い、わしを見上げる双眸は黄色く、尊大に光っていた。天狗の風を頬に受ける。背の毛が逆立つ、あの圧倒的な力をいま感じている。
「覚えているか?はじめて会った時のことを」
「もう忘れたな」
目を細め口元を歪めて笑うと、タイマは苦笑を浮かべて「嘘つきめ」と、白い歯をのぞかせた。ゆっくりと伸ばしてきた手を、わしの頭の上に置くと、毛をかきまぜるようにして撫でる。皮膚から伝わるその熱は、異様に高い。
「お前はもう、大丈夫だな」
「何を言っているんだ」
「俺はお前に逢えたから、人の心を持てた」
「馬鹿なことを言うな、おい」
「もうすぐ消える。それだけが惜しい」
そう言って笑んだタイマの顔は、かがやいていた。
光の粒子が、全身を包みこんでいた。その白い粒が、わしの頬に、背に、尻尾に、降り落ちるたび、言葉を無くす。ぐっと歯噛みすると、タイマを睨みつける。
「まるで、わしにあって、貴様には無いようではないか」
「すまない」
「何を、謝っているんだ。やめろ」
「良いんだ。いま、言わせてくれ」
「やめろ」
「本当にすまない」
わしはつい、犬の肉体を脱いだ。
震える手で、タイマの胸倉をつかみ、ぐっと顔を引き寄せる。熱に浮かされた黄色い双眸を、三つの眼で睨みつける。
くたりとした座りの悪い首は、重たい。まるで全身がゴムまりの人形のように、ぐにゃぐにゃとしている。
弾けそうな心臓を飲み込んで叫ぶように言った。
「貴様の志には、はじめから心があったろうが。そんなこともわからないのか!馬鹿な化け物め」
タイマは目尻に光った透明な雫で頬をぬらした。震える息を吐き出しながら、「すまない」と、くぐもった声でつぶやいて、微笑を落とす。
のばしてきた両腕が、わしの首にしがみついた。汗や、涙が、光の粒子と共に、畳の上をすべって消えてゆく。それの行方に目をこらしながら、しばらく黙りこんだ。そうして、襖の開いていることに気がついた。間からのぞいていた、暗い影が、じょじょに深く染まってゆくのを見つめ、ハッとした。
何もない。ただ胡乱なだけの闇がある。嘲笑っている。がらんどうな闇、闇、闇だ。わしはそこから生まれ、そこで生きた。それにも関わらず、
「死」はわしではなく、目の前にいるこの脆弱な生物を、容赦なく引きずりこもうとしている。
「これが、わしなのか」
まるで鏡でも見ているかのようで、ぞっとした。
それから数時間と少し眠り、夜が更けたころ、もう一度タイマの部屋へと向かった。つめたい廊下を静かに歩き、部屋の前で立ち止まった。空に登る月は、丁度大きな雲にかかるころだった。
襖を開けて座敷に上がると、布団に横たわる白髪の男の、青白い顔を真上から見下ろして、息をついた。
まだ、生きている。そう安堵した時だった。
タイマは、鋭い両目を開けて、わしをじっと見据えて来た。その双眸は胡乱で、何がなんだかわかっていないようだった。
否、もっと言うなら、まるで犬を見るような眼で、わしを見つめてきたのだった。
声をかける前に、タイマはゆっくりと上体を起こして、布団の上に座り込んだ。
「何で、野良犬が迷い込んでいるんだろう。なあ、お前どこから来たんだ?腹が減っているのか?」と、言って苦笑を浮かべていた。
はじめ目の前の現実が、どのような形をしているのか、わからなくなった。何を言われたのか、理解できなかった。景色が歪み、タイマの顔が左右にゆれた。いや、わしの脳がゆれているのか。
落ちつけ。冷静になれ。そう囁いた声に従い、一度大きく首を振った。
そうだ。タイマは、能力の消失と同時に、天狗であったことも、わしのこともぜんぶ忘れると、言っていた。
大丈夫だ。由紀や、登紀子のことは覚えているはずだ。それなら、生活に困るはずがない。タイマは「坂島恭一郎」に、なっただけだ。
わかっていたことだ。
タイマは、じっとわしを見つめながら頭に手をのせてきた。
「腹が減っているんだな。おい、おい」
呼ばれて由紀が座敷に上がると、タイマは、あの快活な笑いを浮かべた。
「迷い犬だ。腹が減っているらしい。何か、食わせてやってくれ」
由紀はすぐ様子のおかしさに、気づいたのか「ええ、そうね。待って」と、うすいくちびるを震わせてつぶやいた。
じりじり、と畳の上で足を引きずりながら、廊下へと出て行った。心配するな、大丈夫だ。
これは、わかりきっていたことだ。わしが、由紀の混乱を抑えてやらなくちゃいけない。わかっているんだ。だが、なぜか体が動かない。
「いま、由紀が何か持ってくるから、待っていろ」
そう言って、鋭い双眸を細めたタイマの顔を、ぼんやり見つめるしかなかった。
目の前にいるのは、ただの人間だ。
では、声を出す訳にはいくまい。
では、どのようにして、この座敷を出ようか。
簡単だ。手足を動かせば良い。だが、体は硬直し、ぴくりとも動かなかった。
脳が混乱したままなのだ。
動けるはずがない。
事態が目の前を勝手に流れ去ってゆく。その流れに身を乗せようともがくが、それに反して体は自由を失った。
わしは、いま、自分が冷静なのか、そうじゃないのか、それさえも判然としていなかった。
ただ胃が熱い。痛む。痙攣しているようだ。きゅうきゅうと、しめあげてくる痛みに、顔を歪めた。その痛みは背に向かい、首筋を通り、頭の後ろを熱くした。
喉が枯れる。牙がのぞく。震える息を、吐き出した。知らず、タイマの肉からただよう、うまそうな匂いが心を奪う。
こいつには、もう天狗の意志も、記憶も、力もない。
「タイマ」は、もうどこにもいない。わしを置いて、消えたのだ。
背負っていた荷を、すべてわしにぶん投げて、あの勝手な化け物は、また勝手に飛び去った。
ああ、それならもう良いだろう。
わしは、喉を鳴らしてタイマの喉元を、じっと、見据えた。
脈動する血液の音を間近に聞きながら、つばを飲み込んだ。
いまここで、喰ってしまおう。
「八枯れ」
突然、耳元で名を呼ばれた。後ろから強い力で、押さえつけられ、さらに動けなくなる。
長い両手がわしの体を抱いて、胸元を軽くぽんぽん、と叩いた。
ハッとして、首を後ろに回そうとしたが、頭を押さえつけられて、それはできなかった。ちら、と目を動かすと、横には登紀子のやわらかな笑みがあった。硬直していた体がほどけてゆく。わしはようやく、息をすることができた。
「お父さん、困ります。八枯れは私のものですよ」
そう言って苦笑すると、登紀子は藍色の着流しを翻し、わしの前に歩み出た。その凛とした後姿に、息をつく。赤茶色の髪に隠され、恭一郎の顔が見えなくなった。
「ああ、そうだったかな。またお前の式神か?」
「そうです。だから、餌など食いません」
「では、なぜこんなところにいるんだ?迷ったのか?」
「お父さんの様子を見に行かせたのですが、どうやらお元気なようで」
「俺か?どこも、悪くないようだが」
「ええ、もうおやすみになった方がいいですね」
「少しくらい良いだろう」
「いいえ」
ゆるやかに立ち上がった登紀子が、目を細めて出るよう示した。
襖の方に目をやると、由紀が立っていた。少し顔色は悪いが、それでもうっすらと微笑んでいる。
その白い頬に、涙のあとなど見えない。こちらの様子をうかがうようにして、笑んでいる。はじめて会ったときと同じように、温かなまなざしを、わしにそそいでいる。
こんな時でも、お前は笑うのか。
ぐっと、奥歯を噛んで、のろのろと歩きはじめた。それまで黙っていた恭一郎が、わしを見つめながら「またおいで」と、微笑んだ。応えることなく、尾を振ると、うす暗い廊下に向かって駆けだして行った。
サポートいただいた、お金はクリエイター費用として、使用させていただきます。 いつも、ありがとうございます。
