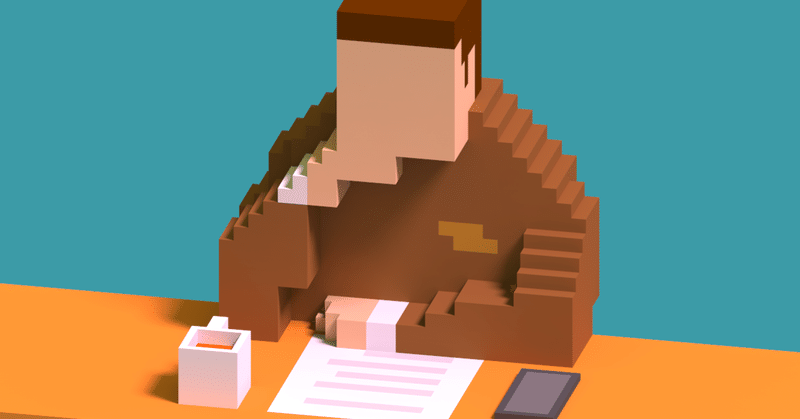
今週のふりかえり_200621
今月は、3週に渡ってプロジェクトマネジメントの講義を会社のみんなで受講した。 講師は、プロジェクトマネジメント、戦略立案、コンセプト立案などを専門にお仕事をされている野村隆昌さん。
ロフトワークでは、「PMBOK」とよばれる国際標準のプロジェクトマネジメントの知識体系を、あらゆるプロジェクトのベースにしていて、今回の講義もこれに沿うものだった。講座を通じて考えたことをまとめておく。
プロジェクトマネジメントとはなんなのか
普段会社の先輩を見て感じていることや、今回の講義を改めて振り返って、プロジェクトマネジメントを一言で言うなら「事前に対処する」ということではないかと思った。PMBOKに準ずるプロジェクトマネジメントは、10の知識エリアから構成されているけれど、どの要素も「あらゆる事象に対していかに事前に対処しうるのか」を追求している点で共通している。
シンプルに言えばこうかなと思ったきっかけは、野村先生が講義の中でおっしゃっていた「事後対応ならだれでもできる」という言葉で、そこに考えるべき余白を感じた。
今の自分は、まずい状況になってから対応の仕方を考えていることがまだある。それによって取り返しのつかない失敗をしてしまったこともある。
どんなプロジェクトもリスクはあるから、結果的にまずい状況になってしまうことはあると思うけれど、それが想定外のことなのか、あらかじめ少しでも想定されていたことなのかではぜんぜん違う。起きたときに全く初めてその事象について考えたのであれば、プロジェクトマネジメントはその時点で失敗なのかもしれない。
「事前に対処する」
言葉にするととても簡単なことのように聞こえるし、実際、プロジェクトマネジメントのスキル自体は分解すると特殊なものは多くないように思える。でも、プロと言えるレベルまでそれを極めるには、訓練や経験が必要で、きっとそう簡単ではないし、確かな技術なのだと思う。
プロジェクトマネジメントの目的
価値観、スキルや経験、バックグラウンドなど、個人の持つ要素が多様化する今の社会では、人と一緒に仕事することの難易度は上がっているのではないかと考える。とくに、様々な業界や職種の人とチームを作って色々なものを作るロフトワークのような会社では、同じ日本人であっても、まるで共通言語が違うかのごとくコミュニケーションの複雑さを感じることもある。
そんな社会で、
プロジェクトに関わる全ての人が、始まりから終わりまで気持ちよく働けること。その上で、質の高い価値ある何かをチームで生み出すこと。
このような状況を作り、コントロールすることがプロジェクトマネジメントの目的であると講座を通じて解釈した。
拘りを手放す
講座の中でとくに印象的だった時間の1つは、中観を扱ったときだった。
プロジェクトマネジメントには、いつも全体を見る習慣(あるいは思考)が必要で、これを身につける方法をいくつかご紹介いただいた。その中で、観ていない部分に気付くための中観という概念と実践の仕方を教わった。
■ 中観
天台宗の三観の一。あらゆる事物が固定した本質をもっておらず、しかも現象としてあるがままに存在していることを観ずることにおいて、同時に絶対的な真理を観ずること。中道観。(weblioより)
プロジェクトの過程では、拘りによって見落とされてしまう視点が多くあるものの、それを捨てるのは簡単ではない。(個人的には、「拘り」は、仏教文脈で「執着」と言い換えた方がよりしっくりくる)その拘りは、以下のAまたはBのXXXに当てはめ、4象限マトリクスに書き出して考えることで打ち消すことができるという。
<A>
・XXX をやめるべき理由
・XXX をやめない理由
・XXX をやめるかやめないか考える理由
・XXX をやめるかやめないか考えることを否定すべき理由
<B>
・XXX が好きな理由
・XXX がキライな理由
・XXX が好きかキライか考える理由
・XXX が好きかキライかを考えない理由
試しに実際にやってみると、少し引いた視点から冷静な気持ちで行動を見直せるように感じた。中でもポイントは「やめるかやめないか考える理由」「やめるかやめないか考えることを否定すべき理由」の2項目だと思った。この2つは意図しないと普段あまり考えることのない視点だし、これらを一緒に並べて可視化して見渡すというのは意味があるように思った。こういった思考が普段から当たり前にできるように、何らかの形で自身の習慣として取り入れる仕組みを作りたい。
自分なりの原則を定義する
もう1つ、とく興味深く感じたのは「原則」という項目だった。
すごいプロジェクトマネージャーは、単に知識があるだけではなく、自分なりの原則を持っているという。原則というのは、持論、ルール、考え方の基準のようなものだ。
例えば、野村先生の原則は、
・人として正しいコトを行おう
・全ての人を無条件で信頼しよう
・顧客の靴を履け
・あらゆるリスクと変更を楽しもう
・時間は未来から現在に向かって流れている
・私から社会まで、全ての人について考えよう
・一つ上のレイヤーで考えよう
・賛同者が一人も居ない仕事をしよう
・革命は辺境から
といったもので、「プロジェクトマネジメントってその人の生き方そのものみたいな話だな」と半ば感じながら聞いていた。
プロジェクトマネジメントは、大小含めて判断の連続だし、その正解はいつも1つではない。とくに、ロフトワークのような会社が取り組む答えのないプロジェクトでは、たった1つの判断に頭を抱えるシーンも多々あるだろうし、そこに注がれるエネルギーは時に半端ではないものがあると思う。
これまでも、精神的なエネルギーを最も消費する行動は、物事を判断(あるいは決断)する瞬間だと強く感じてきた。責任を持って何かを決めるというのは、やらなくていいならきっと誰だってやりたくないのではないか。こわいし、勇気のいることだと思うから。
だから、答えのない事象に対して判断し続けるには、個々の哲学、あるいは何を信じるのかといった信仰にも近い何らかの基準が必要で、それを自分の内にルールとして握ることはとても大切だと思った。
入社したときから、「プロジェクトマネージャーってすごく属人的な仕事なだな」と感じる側面があって、いくらか理由を考えてみたときもあったのだけど、そのうちの1つはおそらくこういうところにあるのだろうし、その意味ではとても納得する話だった。信じるものや、判断基準が違えば、1人1人色の違うプロジェクトマネージャーになるし、そこにおもしろさがあるのかもしれない。自分は、まだまだ積み上げるべき基礎がたくさんあるから、自分のカラーがどうだとかは自信を持っては言えないのだけど、いづれそういう景色を見れるようになりたい。
自分にとっての原則はなにかと仕事を通じて考えながら、そして時に見つめ直しながら、更新していければと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
