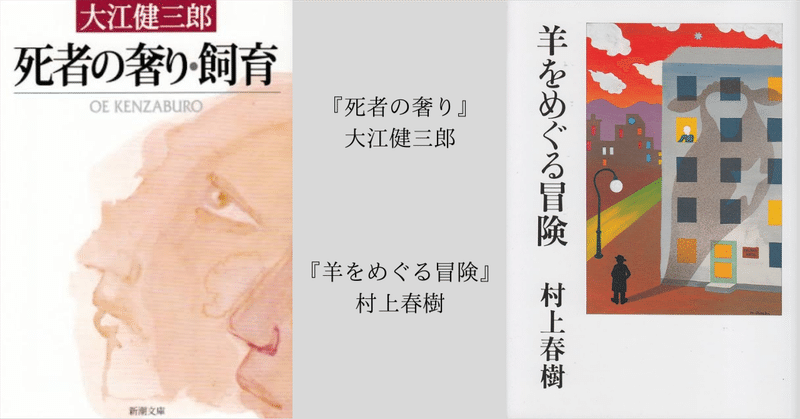
読書の記録 11月
読書
2023年は月に二冊ずつ読もう。それで何かしら感想を書き残そう。
①死者の奢り 大江健三郎
あらすじ:「僕」は大学医学部の事務室に行き、アルコール水槽に保存されている解剖用死体を新しい水槽に移しかえるアルバイトに応募する。アルバイトには、「僕」だけでなく「女子学生」も参加していた。「女子学生」は妊娠しており、子どもを堕ろすための手術料を稼いでいた。しかし「女子学生」は、水槽の中の死体を見ているうちに出産しようと思い始める。また、医学部教授会での正式な決定により、古い死体は全部火葬し、両方の水槽は清掃することになった。こうして、「僕」たちの仕事は徒労に終わるのだった。(https://amaikahlua.hatenablog.com/entry/2020/08/22/183000より)
感想:「奢り」とはどういうことであろうかと思った。「得意になること」であるとすれば、子どもを産もうと考えた女子学生に対して「全く、この女子学生は罠に引っかかってしまっている」と答えた僕の意図は、「死体」に同情して、或いは別の言い方をすれば「死体」を得意な気にさせて、情けが生まれていることを蔑む言い方のようにも考えられた。
「希望を持っていない」という僕は思弁的であるが故に言葉で思考を相手に伝えることを半ば諦めており、対人のコミュニケーションを煩わしく思っている。しかし、兵隊だった死者との交信的対話では本音を語っており、死体に対して《物》を超越したものとして情けを先に感じているのは女子学生ではなくむしろ「僕」の方なのではないかと思った。
「僕」のニヒルな態度は、戦争の終わることを希望として生きてきたある時代に特有の気分なのであろうか。一方で、女子学生が倒れて看護婦を呼びにいく場面と、最後の場面で事務室へ向かうときに溢れる「感情」は、無期的に生きることを阻む、情が立ち込める人間らしさが溢れているように感じられた。
印象的だったのは、「僕」が労働に対して充足感を感じている点(「仕事をした後の快活な生命の感覚が僕の躰に充満した」)で、とても人間らしいなと思ったからである。
一点引っかかるのは、十二歳の少女の死体に「生」と「性」の興奮を感じている点である。大学生の若い男性を主人公に据え、「生と死」を扱う以上、性にまつわることに触れないのはかえって嘘になるのかもしれない、と考えて解釈を試みたが、それにしてはあまりに唐突で前後とのつながりを感じられなかった。
「生と死」や「労働」など、人の営みが主題であると感じた。50ページ程度の短編にこれほど大きなテーマを丁寧に織り込んでいること、管理人、女子学生、僕のキャラクターが皆、楽しくなさそうに、それでもそれぞれが保守したい地位やスタンスのようなもの(「死体管理室の管理」・「生むか生まないかという選択権」・「勉学に励む学生」)を持っている点には何かしら新鮮な感覚を覚えた。
②羊をめぐる冒険 村上春樹
あらすじ:村上春樹の「鼠三部作」三作目である本作は、「僕」がその友人「鼠」から届いた手紙をきっかけに羊をめぐる冒険に巻き込まれていくというお話。無駄な文章は文章は一つも無く、特に北海道の自然の描写には本当に綺麗だと思った。好きだった文章をいくつか引用します。
「問題は」と僕は言った。「あんたの言ってることの方が筋がとおってることなんだよな」
道路はひどくすいていて、車は産卵期の鮭が川を溯るみたいに空港にむけてひた走った。
MGMのライオンが吠え終ってメイン・タイトルがスクリーンに浮かびあがった瞬間にもう後ろを向いて席を立ちたくなるような映画だ。
誰かが僕を氷と一緒にシェーカーに入れて、でたらめに振りまわしたみたいだ。
窓から射し込む秋の朝の太陽が彼女の膝に薄い光の布をそっとかぶせていた。
村上春樹の文章は記号的で、都市的で、からっぽだ。その記号的で交換可能なポップさや広告的な実体のないおしゃれさみたいなものが、時々読みたくなる所以だと思う。雑誌・ポパイのタイトルや文体が、誰のどの気持ちも代弁していないのに似ていると思う。どこにも根を張らない気楽な人間というものに時々自分を投影させて(それはまさに大学生のような人間だったりする)、観念的な旅に連れて行ってほしいのだ。ポパイの記事をコピーしたような週末を消費するほど虚しくはならないし、なんだか活力が湧いてきたりする。
村上春樹の描く言葉については、「〇〇を思い出すな」とか「〇〇の描写が素敵だ」とかその程度の話に留めておきたい。彼以前以後の文豪が描いてきた人間の機微が春樹の作品内では描かれていないなどということよりも、春樹の作品の数百ページの文字群を読んでいる間、読者としての自分の中に生じたものを愛でられれば良いかな、と僕は思っている。
最近、大学のゼミで大江健三郎を扱った。ノーベル文学賞という立派な賞を取る前に触れてみたかった感は拭えないが、あれが文学なんだろうだな、と思う。短い文章の中に、考えられることがたくさんある。
だから春樹が読み物としては良いが文学ではないと言われてきた所以はよく分かる。
村上春樹の本をもう結構な数読んできた。文体や生活スタイルは影響を受け過ぎてしまった。例えばコーヒーを飲むにしても、湯気の立ち上るのをいやな秒数見つめてしまったり、缶ビールをまるで何も思っていないかのように飲み干してみたり、ああいうのは中二病ならぬ大二病と呼べるんじゃないだろうか。大学に入り、今まで見たことのない人々や集団をたくさん見る。それで、「自分」がまだ曖昧な大学二年生の自分は自分を喪失しそうになったり、集団の中にいて自分を融かしてわからなくさせようとした。
ノルウェイの森を読んだ後の文章が、大二病の典型例のような気がするので、恥を忍んでここに書きます。(その代わり、後で載せるブログを見ることを条件に読んでください。身が持ちませんので)
この作品について書かれたどんな文章も今は目の前をすらすらと流れてしまって捉えられない。この作品と僕との間に割り込める言葉の何も無いことを知ってひとまず安心している。結末には些か満足のいかないところがある。それでも二十歳の僕にとって大きな作品であることに相違ない。(2021年、秋ー)
↑本文はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
