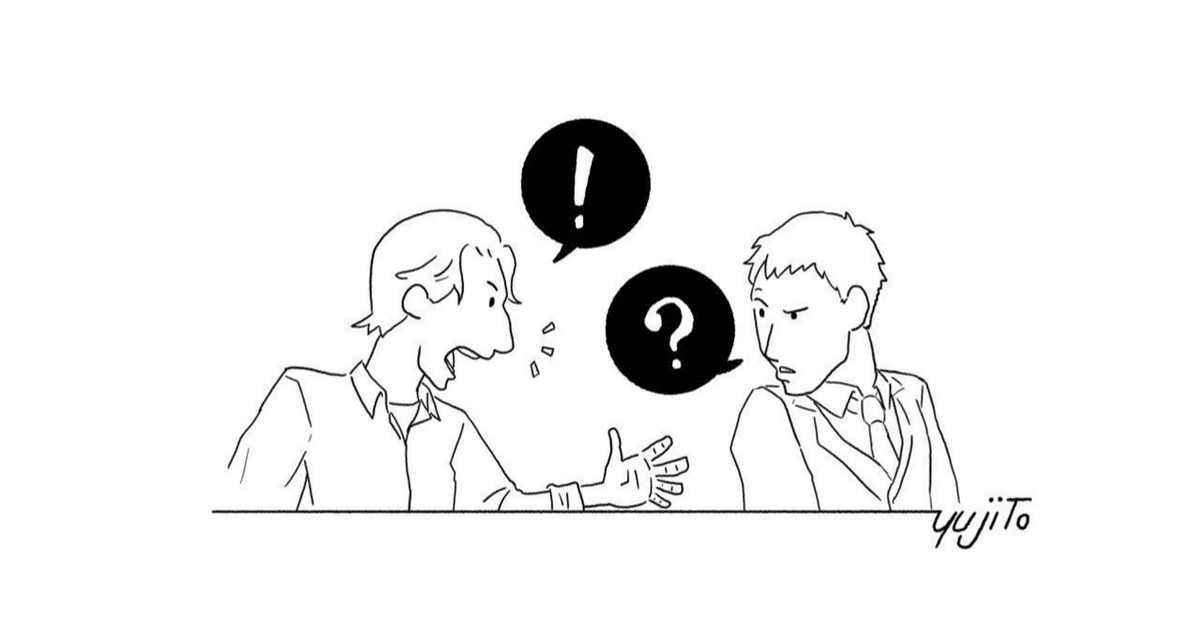
わかりたいと思って近づくとだいたいよくわからなくなる
自分って一体なんだろうといわれると、実際のところその実態はよくわからないものである。
「いつも笑っている」「コツコツやるタイプ」「話を振れば喋る」「静かなほう」「あんまり人を寄せ付けない感じ」…私個人が私についてよく言われるのはこんな調子である。
他人がわたしを論評する時、その人から見えているわたしは人生のごくごく一部だ。ゆえ、一面的に「こういうところがある」と判断をしてくれてわたしにとって思いがけない気づきや発言につながることも多い。
もっとも、その言葉も間違ってはいまいと思いつつ、個人的にはそんなに笑っている気もないし、飽きっぽいし,喋る時は人並みには喋るし、人と会うのは好きである。
わたしはわたしにとって最も近い存在である。それゆえいろんな面が見えてきてしまって、結果的に自分というものがよくわからなくなってしまう。
記者として仕事をしている時、デスクから「わかった気になるな」と言われたことがあった。
要は当事者でもない記者がたかだか数時間ほどの取材で全てを理解できるわけはない、という話だ(だからこそ取材前の準備こそ記事の出来不出来を決めるのだということなのだろうが)。
確かに、適当に取材しているとなんか分かった気になるのだが、深く取材をしていくと事実がどこにあるのかよくわからなくなることがある。
企業であればよりシンプルなのだが、たとえばナラティブが論理的に破綻して「結局この取り組みの新規性や意味がよくわからなかった」となることは珍しくない。
記者の理解が甘いと言われればそれまでだが、近づけば近づくほどよくその実態がつかめなくなるというのは、世の中ではよく起こるような気がする。
しかし、わかりたいと思って近づくのに近づいていくほどよくわからなくなるというのはなんとも皮肉なものである。
今の世の中には、教育やら何やらでたくさんの「わかりやすい話」がある。それによって「知るのって面白い」と思うことには価値がある。
ただ人間怠惰なものでそれを聞いてわかった気になって満足してしまう、という一面もある。
こういう世の中だからこそ、実は「よくわからないもの」をそのまま逃げずに見続ける努力って必要なのではあるまいか、と思う。
そもそも、世の中にあるあまねくものが自分などにそう簡単に理解できるはずもないのだ。
自分を知ろうと思索を深めたり、人からの声をヒントにしたりしながら、それでも「よくわかんねーな」と思いながら対象に近づき続ける日々が、実は「わかった」にいつかつながる知的遊戯の喜びだったりはしまいか。
マックス・ウェーバーは「職業としての学問」で知的廉直というものを指摘したが、そういった知に対する謙虚さみたいなものが、わかりやすさの溢れるいまに求められているのだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
