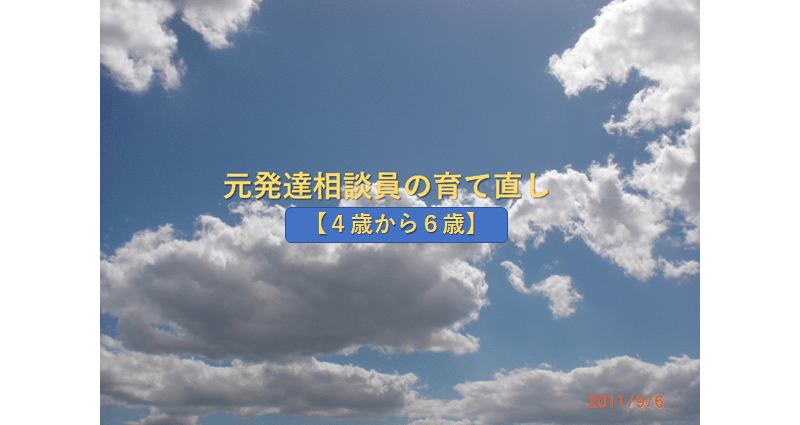
- 運営しているクリエイター
2021年4月の記事一覧
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 2 登校から、1時間目までの過ご し方 その1
この項目には、3つの補助項目が付いています。まず、それを紹介します。
1️⃣ 持ってきたものを片付ける。
・宿題と提出物を出す。
・机の中に教科書などを入れる
・机の横に体操服、赤白帽などをぶら下げる
・水筒を、ロッカーの上に置く
・給食袋を、教室の横にぶら下げる
・ランドセルや手提げ袋を、後ろのロッカーに入れる
2️⃣ チャイムが鳴るまで、教室で待機している。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 2 登校から、1時間目までの過ご し方 その2
1️⃣ 持ってきたものを片付ける。 【解説】
・宿題と提出物を出す。
・机の中に教科書などを入れる
・机の横に体操服、赤白帽などをぶら下げる
・ロッカーの水筒を上に置く
・給食袋を教室の横にぶら下げる
・ランドセルや手提げ袋をロッカーに入れる
1年生になると、登校してから1時間目までに、こんなにたくさんのことをやらないといけません。もちろん、5月末を目処にできればいい
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 2 登校から、1時間目までの過ご し方 その3
2️⃣ チャイムが鳴るまで、教室で待機している。 【解説】
・保健係による健康チェック
・教室内での自由遊び
ここで1番難しいのは、先生がやってくるまで教室から出ていかないことです。凸凹タイプの子どもは、どうしてもうろうろしたくてお茶を飲んだり、廊下に出たり、トイレに行ったり、廊下で鬼ごっこしてたりしてしまいます。
この時間は、片付けが終わったら椅子に座って待機する時間になってい
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 2 登校から、1時間目までの過ご し方 その4
3️⃣ チャイムが鳴ったら、朝の学習を始める。早く終わったら、先生が来る
まで指示されたことをして待つ。 【解説】
・学習課題 ➪ 読書 折り紙 自由帳
学習課題で何をするかは、各学校によって違います。簡単な計算問題や漢字の書き取りするところが多いようです。視写に取り組んだり、クイズやパズルをしたり、読書をする学校もあります。
ここで問題になるのは「やった!!課題が終わった
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 3「チャイム」と「時計の見方」 その1
この項目には、2つの補助項目が付いています。まず、それを紹介し【解説】します。
1️⃣ チャイムと共に行動することの意味とその大切さを知る。
【解説】
小学校は、自立にむけて育てていく方針があります。そのため「自分で時間を見て行動すること」を求められます。しかし、各自が時計を持つのが難しかった慣習が残っていています。つまり「時計を持っていないので、チャイムで時間の変わり目を知らせます
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 3「チャイム」と「時計の見方」 その2
1️⃣ チャイムと共に行動することの意味と、その大切さを知る。【育て方】
これを育てるためには、音を合図に行動を切りかえることを経験するといいでしょう。生活の中で、クッキングで使うキッチンタイマーを使います。
もちろん、本当にクッキングで使って、ゆで卵のゆで時間やホットケーキの焼き時間に使ってもいいでしょう。
お薦めの使い方は、何かの行動を切り替えのときに「やりとり」して使うことです。6
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 3「チャイム」と「時計の見方」 その3
2️⃣ チャイムの補助として、時計を読めるように指導する。どこにあるか
、いつ見るのかも覚える。【育て方】
数字を覚えているのでデジタルでいいかと思わないで、アナログの時計も教えて教えていきましょう。その理由は、2つです。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 4 休み時間の過ごし方 その1
この項目には、3つの補助項目があります。まず、それぞれを紹介し
【解説】します。
1️⃣ 長い休み時間とお昼休み以外の休み時間は、トイレ休憩であって遊び時
間ではないと知る。 【解説】
最近の小学校の休み時時間は、5分のところが増えています。この時間内に、遊ぶことを想定してません。「トレイに行き、次の勉強の準備をする時間だ」と考えています。だから、先生の声かけは「トイレに行きたい人は
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 4 休み時間の過ごし方 その2
1️⃣ 長い休み時間とお昼休み以外の休み時間は、トイレ休憩であって遊び時
間ではないと知る。 【育て方】
凸凹タイプの子どもは「一つの言葉は、一つの意味しか持っていない」と考えています。例えば、次のようなことがありました。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 4 休み時間の過ごし方 その3
2️⃣ チャイムが鳴る前に時計を見て行動し、次の時間の準備をして座って先生を待つ。 【育て方】
Ⅰの2や3で、「登校してから先生を待つ方法」や「時計を見方」の
【育て方】については書きました。その記事を参照してください。
一つだけ付け足しておきます。「教科書とノートを時間割通りに並べて、机の中に入れておく」を育てるための方法です。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 4 休み時間の過ごし方 その4
3️⃣ 長い休み時間の過ごし方を知る。 【育て方】
「友達に一緒に遊ぼうと誘うスキル」と「ルールを守って、最後まで楽しく遊び切るスキル」を育てるためには、大人と遊ぶ必要があります。大人が2つのスキルを育てる意識を待って、遊んであげることです。大人と遊べないのに、子ども同士ではなかなかうまく遊べません。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 5 イスの座り方 その1
この項目には、5つの補助項目が付いています。まず、それを紹介し
します。
1️⃣ イスが、自分に合っているかどうか知る。
2️⃣ 先生の話を聞くときは、背筋と腰を伸ばしイスに深く座って背もたれに
背をつける。
3️⃣ 課題をするときは「おなかと机の間」「背中と背もたれの間」に握りこ
ぶし一つ分だけ開ける。
4️⃣ 発言するとき、イスから立ち上がりイスを机の下に入れる。その際、音
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 5 イスの座り方 その2
1️⃣ イスが、自分に合っているかどうか知る。 【解説】
「イスが合っている」というのは、机とイスと身体の3つが正しい位置関 係にあるということです。次の状態を言います。
・机の上に手を乗せたら膝と平行になる
・足の裏をぺたんとつけたら、膝が直角に曲がる
イスが合っていないと、疲れやすいし注意集中もとぎれやすくなります。だから、先生は、学期ごとにイスと机が合っているか確認するこ
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 5 イスの座り方 その3
3️⃣ 課題をするときは「おなかと机の間」「背中と背もたれの間」に,、握り
こぶし一つ分だけ開ける 【解説】
何か課題するときは、背もたれにもたれてやってはいけません。プリントの問題を解いたり、ノートを書いたりするときです。背骨が曲がったり、注意集中が落ちたりします。下のイラストのように「おなかと机の間」「背中と背もたれの間」に隙間を開けます。
4️⃣ 発言するとき、イスから立ち上が















