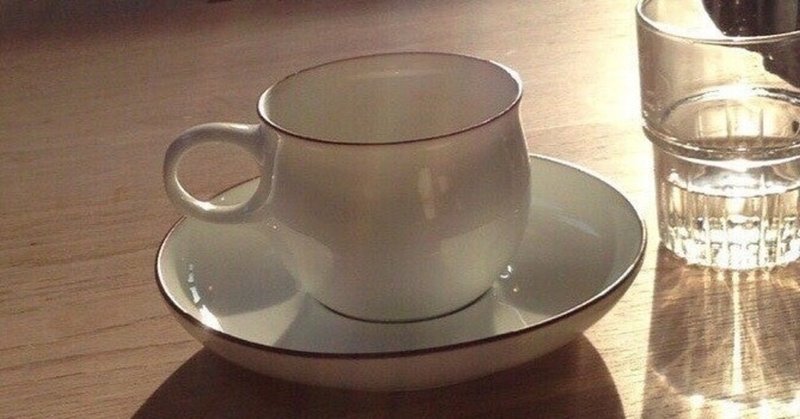
オンライン・ワークショップの可能性
ワークショップをあえて訳すと「作業場」などとなるらしいが、実態に合っていないので、そのまま「ワークショップ」で通用している。オンラインミーティングはこの1年でかなり社会に浸透したが、それによりワークショップ型イベントも、オンラインを媒体として以前よりも増えるのではないか。
note などのオンラインメディアにおいて知識やノウハウを売る個人は増えつつある。しかしながら、商品価値のあるとされる情報や知識を、実際のところ買い手はどのように判別するのか。私にはまったく知見がない。私に考えられるのは、自分に特別な専門性や興味がある分野に限って、半ば寄付のような形でお金を払うことだけである。
一般的な商品としての情報ではなく、特定の相手にカスタマイズしたコンサルティング的なアドバイス情報であれば、あるいは「売れる」のではないか。しかし、売り手にとってはカスタマイズにかかる工数(手間、原価)発生することになるので、利益率の高い商売とはならないだろう。(副業として利益を目指すのではなく、自分の専門知識で社会とつながるというくらいの軽い意識(と低い料金設定)であれば、満足感と情報・経験は得られるであろうか。変な比喩であるが、占い師的な商売スタイルを、専門知識でもって行うものである。(敷居の低いカウンセリングといえようか。)
上記のようなビジネスモデル(というほど大げさなものでもないが)はもちろんすでに存在しているが、どうも私には、はっきりとした「市場」が見えてこない。需要も供給もあるはずだが、どこで取引が成立しているのか(あるいは成立していないのか)が、わからない。ポータルサイト、マッチングサイト的なところは、存在しているのだろうか。
情報(専門性)の売買とは別に、同じ興味関心を持った複数の人間によるワークショップも考えられよう。専門性の売り手が存在しない市場において、買い手だけが集まって情報交換会(ワークショップ)を実施し、その議論を成果物として共有する。そのような場から、付加価値は生まれるだろうか。
・ファシリテーター(的な人)がいたら、議論の生産性は高まる。
・議事録を作る人がいたら、成果物の共有が容易となり事後の発展性もある。
・会議の全文を書き起こす人がいたら、議論した内容の検証も容易となるだろう。(もうすぐ草稿程度ならAIが書き起こしてくれるようになるので、実作業は少なくなる。)
・議論された内容の根拠について、ファクトチェックをしてくれる人がいたら、成果物はより正確なものになる。
・議論の全体を土台にして、改めて費用を出し合って専門家に解説やアドバイスを依頼することも考えられる。
個々人が持つ漠然とした疑問をワークショップ形式で具体化する場を、ポータルサイト(マッチングサイト)のような形で恒常的に設置し、需要を掘り起こす。簡単なことではないが、少なくともインフラは整いつつあるといえよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
