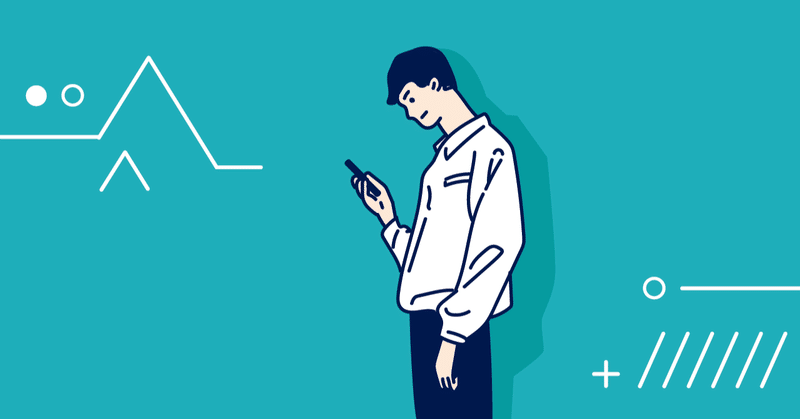
井上ゆずるの副業…系列施設に情報共有ツールを導入する
介護施設にて電子記録ができるケアコラボ(とLINEWORKS)を系列施設ショートステイ縁(以下:縁)に導入・運用して行く過程をこちらに共有します。
こんな人に読んでもらいたい
・介護施設で情報共有ツールを探してる人
・介護施設の情報共有をなんとかしたいと思ってる人
・ケアコラボ導入検討してる介護施設
役割として・・・
私が所属しているショートステイ輪(以下:輪)で行なっている
情報共有(ケアコラボ、LINEWROKS)を導入、運用が目的。
今回の施設(ショートステイ縁)
1ユニット10床 ショートステイ
職員数17名 うち介護職員8名、看護師2名
情報共有ツール↓
ケアコラボ
https://page.carecollabo.jp
LINEWROKS
https://line.worksmobile.com/jp/
まずはケアコラボからその後LINEWORKSという流れでやっていきます
情報共有を入れることによって
施設がどう変わっていくのか、
可能な範囲で共有していきます〜!
前提・・・
1.会社としての情報共有を円滑にするため行なっています
私が来た2016年は施設が1つだったが2020年には3つの施設
(秋田市、大館市、能代市)になった。今後も施設が増えていく中で
「どう、情報共有をしていくか」が課題となり
電話、メール、、、ではなくLINEやFacebookのようなSNSでの
情報共有が次世代の若い人材には良いと判断し導入。
2.今回、導入した縁は情報共有のほとんどが紙媒体だったのでレクチャーを何度かしました。初めから一括で切り替えて導入ではなく段階をみて徐々に電子記録の割合を増やしていってます。
まずはじめにやったこと
1.縁リーダーを招きケアコラボの説明(職員側)
2.試し打ち(職員側)
3.現状の情報共有ツールの確認(担当)
4.各職員へレクチャー(担当)
詳細
1.縁リーダーを招きケアコラボの説明
→今後、情報共有を変えていく旨とそれに伴って縁に担当を3名つけること。実際に使用しているところを見てもらい感じを掴んでもらう
2.試し打ち
施設へ職員を勤務時間内に呼び(大館市から能代市へ)各役職(介護職員なら介護職員、看護師は看護師、事務は事務)についてもらい時間をみてケアコラボを「試しうち」、「一緒に閲覧」をしてケアコラボの接点数を増やし触れてもらう
3.現状の情報共有ツールの確認
施設で行われてる情報共有は「何の媒体で行なっているか?」の確認(ほとんどが紙媒体)とどの順番で紙から電子にするかを考える
例)食事・水分→電子に。ケース記録は慣れて来たらでOK
4.各職員へレクチャー(担当)
業務に差し支えない時間を職員と話、ケアコラボについてレクチャー
こんな感じで:
すでに導入している輪の入力状況を共有しながら説明
加えて似たような利用者がいれば「この人は縁で言うと◯◯さんにのような感じの人です」「この人のこれって縁だと◯◯さんじゃないですか」と状況がイメージしやすいように説明をする。必要最低限のことを教えて慣れて来たら時に再度新しいことについて教える流れで
反応
良い:「手書きだったことが一括で入力できるのは助かる」と言う声が多かった
→現状、利用者10名分の定期記録 (例:夜間排泄時以外良眠)や特記事項(物音なり訪室。トイレのため離床しようとしていたが起き上がれず介助にてトイレ誘導を行う)を全て手書きで書いていた。日中はともかく、夜間は1人でコール対応と合わせて記録を行なっていたらしく…記録が終わらずに残ることもあったと言う
悪い:「細かい字は見えなくて打てないです」と60代看護師より
→スマホ・タブレット・パソコンに記録できることを伝える。同時に看護師の業務を共有し、どのぐらいの量をどの時に記入しているかを確認しその時間を少しずつ、ケアコラボへ入力してほしい旨を伝える。この看護師さんはパソコンを主に入力してもらってます。
悪い:「打ってる時間がない」30代介護職員より
→入力時間の目安を伝え(10名の1食分、食事・水分なら5分)その時間は他職員に見守りやトイレ対応をお願いするように全体周知と介護リーダー、管理者へ共有。「5分なら…」と話を聞いてくれました。
導入にあたっての課題
反応は人それぞれなのは当たり前。ただ1人の意見を強く(やりたくない・めんどくさいなど)聞くことは難しい。マイナスな感情を持っている職員が少しでもプラスに動くようにはどうすればいいのか
例:教えることを小出しに、雑談の中で一緒に進めていく
例:いきなり全てをやるのではなく、少しずつ慣れてもらう
プラスな職員の「あれやりたい!」「これはどうですか!?」を可能な範囲伸ばせるようにはどうすればいいのか
例:業務を見直して時間を捻出する。入力する担当を分け時間を調整する
方向性を示しながら1人ずつの歩く速度と、歩幅は違うこと、お互いが尊敬しあえる環境を電子記録で整える。
目指すところは施設内の情報共有が円滑なことはもちろん、会社的に風通しの良いこと。遠くにいても何をやっているのかがある程度見える化できて何かあれば「これって何?」と上下間で連絡しあえる関係。「これやったら良かったからそっちでもやってみて」と横の連携もあればなお良い。「情報共有」この言葉に意味は多岐にある。その中から「うちはこれだよね〜」が各施設で言えて方向性が同じになるようなところまで持っていきたい。
さいごに
井上ゆずる1人の力で圧倒的な業務改善は難しいです。
私を含め3名(上司1名、同僚1名)が交代で入り、情報共有し日々改善しているので速度ある課題解決、導入・運用ができています。
主な役割(柔軟に変わりますが・・・)
上司:全体の確認、設計。管理者、リーダーとの面談し方向性進捗を共有
同僚:業務、ケアに入ってもらい課題や改善点を出す
井上:業務、ケアには入らず課題や改善点をヒアリンングし職員へフィードバックしチームにとっての最善を試行錯誤する
井上の主な役割と考え
全部の確認を隅々までしていない。井上は「はじめの1歩」と「全体の流れ」に口を出してます。働く職員が仕事しやすくケアコラボを使えるかを考えてます。詳細は働く職員さんたちが考える。なので「これにします」と決めても次くると「あれやめて、こっちにしました」はよくある。理由があれば良い。考えがあれば変えてみる大歓迎。
まずはやること、そこから変えることが大事。というスタイルでやってます。
ありがとうございます! おいしいものを食べて、エネルギーにします!!
