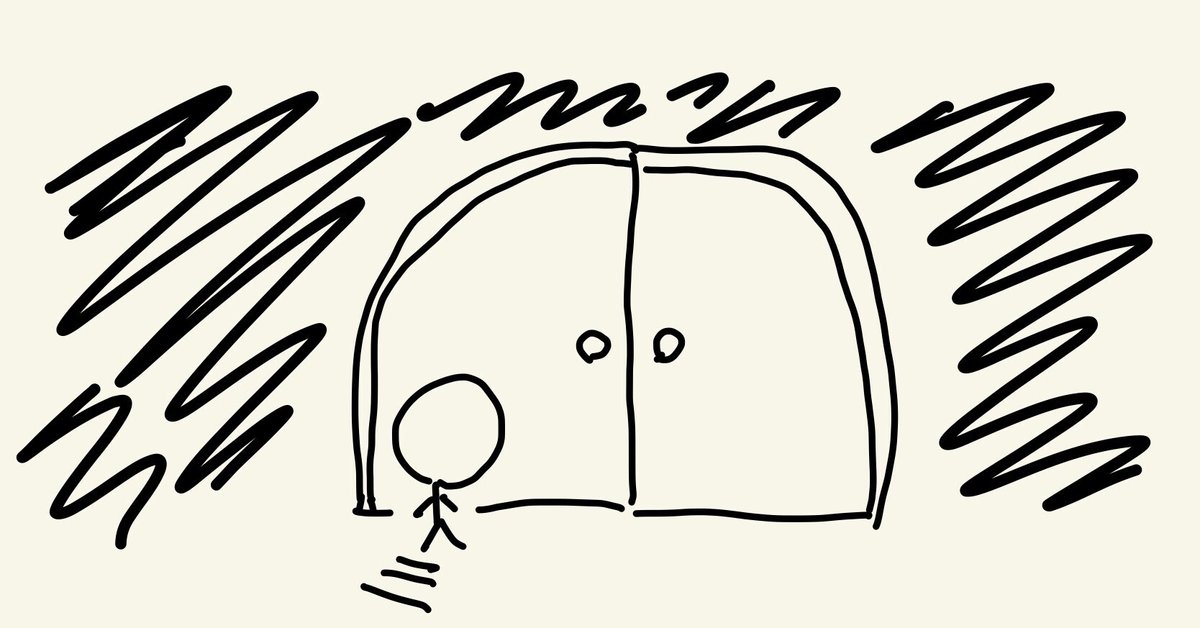
【ボランティア編】暗い階段を下った先にある扉
※ちょっとスピリチュアルかもしれませんので、お気をつけを。
ボランティア初日。
わたしは、初めて担当した子供に、
泣かれた。
あ、はい。
泣かれました。
ショックですよ。
ショックでしたよ!!!
ここでも記載したが、子供にマンツーマンで宿題を教えることになるのだが。
なんだろう。
もう、その泣かれたことがショックすぎて。
初日で辞めようかと思った。
本当、あれはきつかった・・・。
そして、その日、占いの鑑定を受けに行った。
占いというか、もはや人生相談だった。
「わたしー、初めてのボランティアでー、子供を泣かせましたー」
「一体ーどうしたらーいいんでしょうかー。死んだ方がいいですかねー」
相手の占い師さんは、こんな馬鹿げた内容にさえ、導きを示してくれた。
「ゆずさんは、インナーチャイルドってご存じですか?」
彼女はこれまでの経緯と、わたしが何をしにボランティアをしにいったのかを聞いたあと、同情するような表情で、そして、探るような声で質問した。
「知りませんけど」
「ああ、こういうの嫌だったらいいんですよ?わたしも専門家ではないので。無理にとは言いませんし。」
「ただ、そんな危険なことでもないので、もし良かったらやってみませんか?」
何をさせられるんだ?
とは、思ったが、この時わたしは藁にもすがる思いで。
とりあえず、頷いたのを確認し、彼女は音叉を取り出した。
「まず、目を閉じてください」
音叉の音色が響く。
「貴女の前には暗がりに向かう階段があります。」
「その階段をゆっくりと降りて行ってみてください。」
目を閉じたわたしの脳裏には暗い地下へ進む階段があった。
「ゆっくりと、焦らないで」
ゆっくりとゆっくりと。
そろそろと、光のない地下へ続く階段を壁伝いに下りていく。
「しばらく降りると、目の前には扉が出てきます」
思い描く扉。観音開きの。重厚な。
「そこにカギはかかっていそうですか?」
カギは・・・鍵穴らしきものはない。
「それでは、その扉をゆっくり開いてみてください」
重い扉を体重をかけてゆっくり開く。
「部屋の中はどうなっていますか?」
暗い。真っ暗だ。
「窓は、ありますか?」
窓はない。
「そこに誰かいませんか?」
探すには部屋に入らなければならない。
「入れそうですか?」
入れそうですか?
・・・いや、怖くて入れない。
「どうしても難しいでしょうか」
扉から覗きこんだ空間。
真っ暗だ。
だが、
気配がする。
誰かいる。
「・・・一歩だけ、踏み出せそうですか?」
一歩。
一歩だけ、踏み出すのに、
恐らく、2~3分は要したと思う。
早く入らなければ。
だが、怖いのだ。
もし、これを目にしてしまったら・・・。
「・・・無理はなさらなくていいですよ?戻りましょうか?」
占い師さんの気遣う声。
「ちょっとだけ、ほんとうにちょっとだけ待ってください」
うわ言のように何回も言っていたと思う。
最終的に、
わたしは一歩を踏み出した。
崖から飛び降りる心境で。
「誰かいますか?」
一歩、二歩、三歩。
恐る恐る、一歩目からの勢いで歩みを進め。
わたしは、絶句し、歩みを止めた。
暗がりの部屋。
まっすぐ進んだ先の突き当りの壁。
わたしが見下ろしていたのは。
三角座りで、顔を膝にうずめた
長髪の黒髪の
細い腕の女の子。
占い師さんの声が遠くで聞こえる。何を言っているかわからない。
女の子は、ゆっくりと顔をあげる。
きつく真一文字に閉じた唇。
睨むような上目遣い。
その瞳に映る、わたしの影。
声にならない悲鳴を、あげたのか、あげなかったのか。
ただ、占い師さんの、音叉の音が
わたしを我に返らせた。
「ゆっくりでいいですから、戻りましょうか」
地下から、誘導されるまま戻り。
目を開けたわたしは、
ここで自分が初めて泣いていることに気づいた。
そこから、ただひたすら
目からこぼれる涙が止まらなかった。
わたしも訳が分からなかった。
催眠なのか?なんなんだ、これは。
ただ、一つだけ確かなことがあった。
「その女の子がゆずさんなんですよ」
占い師さんは、ひとしきり泣いているわたしを気遣いながらも、そう告げた。
それは、分かる。
あれは紛れもない、子供の頃のわたしだ。
あの、世界の全てを恨んでいる空気。
間違いない。
「私としては、一度専門家にかかられることをお勧めします」
「今回のご様子を見ていると、相当根深いように思いますので」
彼女はそう言いながらも、今後の道筋を示してくれた。
要は、その暗闇の部屋の中の女の子をなんとかしないと、
わたしの中の色々な問題に、決着がつかないというのだ。
ゆくゆくは、女の子が笑って過ごしている状態。
それが目指すところだが、焦ると元も子もないし、
無理矢理進めるとろくなことがないので、専門家を
とのことだった。
正直、もうこれ以上、
あの空間を認知し関わる人間を増やしたくない、
という理由から、専門家を頼ることは心の中で却下したが。
道筋が見えた分、心は幾分か晴れやかだった。
あの女の子を笑顔にすればいい。
それだけのこと。
ただ、
そこまではいい。
そこまではいいが。
今日も久々に、あの女の子を思い出しながら、ここに記しているが、
いまだにぞわっと鳥肌が立つ。
読んでいただいている方に、あの恐怖が伝わっているか定かではないが。
あんなホラー体験、金輪際ごめんこうむりたい。まじで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
