
The Rascals「The Island of Real」(1972)
ここ最近、ラスカルズのラストアルバム「The Island of Real」が超名盤じゃないかなあと思い始めてます。昔は聴くのも嫌だったアルバムだったんですが(苦笑)。
ラスカルズは初期のR&B路線から徐々に音楽的変化を遂げ、70年代に入り、メンバーだったエディ・ブリガッティ、ジーン・コーニッシュが脱退。フェリックス・キャヴァリエとディノ・ダネリの2人となったラスカルズは、バジー・フェイトン(G)、ロバート・ポップウェル(B)、女性コーラスにアニー・サットンとモリー・ホルトを迎え入れ、ファンクやジャズといった要素を取り入れるようになります。コロンビアへ移籍して発表した2枚のアルバムはそんな魅力的な音楽が詰まってます。特にラストアルバムは皆さんもう存在すら忘れていると思いますが、聴けば聴くほど味わいあるアルバムかと思います。
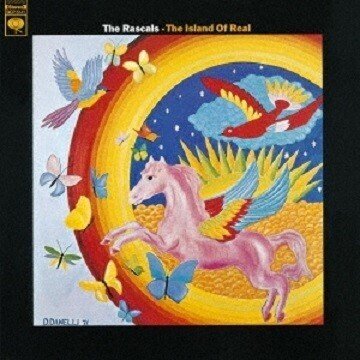
プロデュースはフェリックス・キャヴァリエ。ヒューバート・ロウズ(Flu)、ジョー・ファレル(Sax)、デヴィッド・サンボーン(Sax)、ラルフ・マクドナルド(Per)等ジャズ界の面々がゲスト参加。参加メンバーからお分かりの通り、従来のR&Bのみならず、ニューソウル、ファンク、ジャズの要素が入り交じった楽曲が織り成すアルバムに仕上がってます。全11曲中、9曲がフェリックス・キャヴァリエの作品。ロバート・ポップウェル、バジー・フェイトンが各々1曲提供しております。
まずはオープニングは聴いているだけで幸せな気分になれる①「Lucky Day」。これがまたいいんですよね。気分が穏やかに、そしてほっこりするような感覚、これって「Groovin’」を彷彿させます。幸せを噛みしめるような歌詞、それをソウルフルなフェリックスに歌われたら、こちらも幸せを感じますよね。メロディも高揚感を煽るような感じだし、フェリックスと対を為すような女性コーラスも素晴らしい。ラスカルズのサウンドがここまで熟成された感がある名曲。
続くナンバーはバジー・フェイトンのギターがかなりロックしている②「Saga of New York」。
ラスカルズにしては珍しくロックしてますね。しかも結構ソウルフルなロック。そして間奏にはジャズのサックス奏者のジョー・ファレルの熱いソプラノ・サックスのソロが…。ディノのタイトなドラムはロックそのもの。ちょっと聞き取りづらいですが、ハイハットワークも凝ってますね。
ロバート・ポップウェルが提供した③「Be on the Real Side」は一転、時代を先取りしたようなファンク、ヴォコーダーを用いたヴォーカルが印象的。そして続くバジー・フェイトン作の超ファンク・チューンの④「Jungle Walk」も従来のラスカルズからは想像出来ないナンバー。この③④はフェリックスには書けない楽曲ですね。
鋭く切り込んでくるカッティングギター、そして随所に唸りを上げたり、シャープなソロを披露するギター。バジーの曲らしく、バジーの独壇場。スライ&ザ・ファミリー・ストーン辺りからの影響を感じます。新生ラスカルズのサウンドをご堪能下さい。
ハープが美しいちょっとイージーリスニング調の⑤「Brother Tree」からメドレーで続く⑥「Island of Real」。
こちらもジョー・ファレルのフルートが16ビートのリズム、女性コーラスと相俟って、実に心地いいんです。①「Lucky Day」に通じる心を快適にしてくれる、ある意味ヒーリング・サウンドかも。ここでもバジーのギターが非常に心地いいプレイをしてくれてます。
女性ヴォーカルをフューチャーした⑧「Echoes」も「Island of Real」と同様に心地いいソウルミュージックですね。
本作にはモリー・ホルトとアニー・サットンの2人の女性コーラスが目立ってますが、ここではモリーをフューチャー。オーケストラはこの当時のソウル系に聞かれるようなアレンジで、パーカッションがペットサウンズ的にメリハリを利かせてますね。フェリックスが歌うものとは全く違う、包み込まれるような優しさを感じさせます。
⑩「Time Will Tell」ってなにかの曲に似ているって思いませんか? 私には「太陽にほえろ」のテーマソングに似ていると感じます。
「太陽にほえろ」の放送が1972年7月ですから、同時期に発表されてます。作曲者である大野克夫やバンドの井上堯之は、絶対にこの「Time Will Tell」からインスパイアされて、「太陽にほえろ」を作り上げた筈と思ったのですが、どうも私の妄想のようです(苦笑)。でもイントロのコード進行は似ているなあ。
フェリックスと寄り添うにデュエットしている相手はアニー・サットン。「Echoes」のモリーが優しさを表現しているとすれば、こちらのアニーはパワフル、力強さを感じますね。
ここまできてエンディングは白熱したソウルか…と思ったら、なんと4ビートジャズです。それが⑪「Lament」。
いや~、これも渋いトラック。もちろんこちらもフェリックス作。ディノのドラムも完全にジャズしているし、ロバート・ポップウェルとバジー・フェイトンもすっかりジャズ・バンド風な演奏に徹してます。そして何と言ってもフェリックスのソウルフルなヴォーカルとジャージーなオルガンが最大の聴き所。最期の最期まで飽きさせないアルバムです。結局、ラスカルズは器用なバンドだったんですよね。
ついつい素晴らしいアルバムだったもので、ご紹介曲数も多くなってしまいました。ここに紹介していない残りの楽曲も味わい深いので、未聴の方は是非チェックしてみて下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
