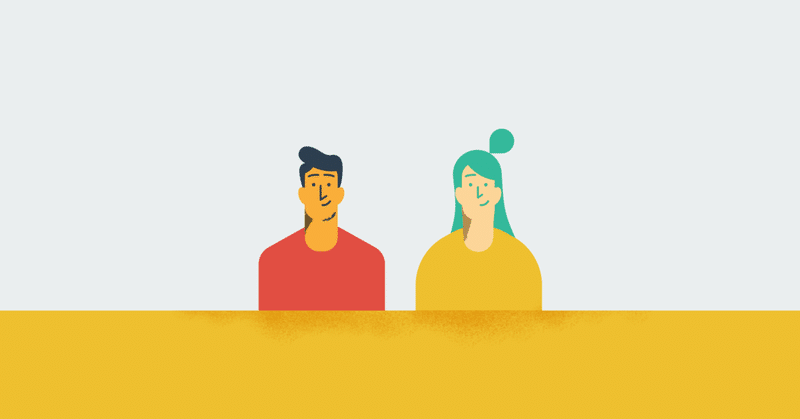
相手の話に共感できないときにも我慢して聴かないといけないのか?
上司部下間のコミュニケーションでよく挙がる悩みに、「相手の話に共感できないときにどうしたらよいか」というものがあります。
相手の話を聞いていると、「それは違うんじゃないか」「考えが甘いんじゃないか」であるとか、「上司は考えが古いんだよな」「現場のことがわかってない」などという考えがムクムクと起きて来て、その声が脳内にこだまして相手の話を聴けなくなる瞬間があります。
信頼関係をつくるためには、相手の話を否定せずに、共感を持って聴きなさいと言われることも増えましたので、こうした自分の心の声とどう向き合えばいいのかわからなくなる人もいます。
私は、このような問題に対処する際、「同感」と「共感」の違いを理解し、明確に使い分けるスキルを身につけることがとても助けになると感じています。
同感とは、自分の価値観、考え方と一致していて、相手にシンパシーを感じることを指します。自分の視点からみて、自然な感情として理解できるという状態です。
友人や仕事の同僚と話をしていて、「自分もそう思うな」「その考え方はわかるな」と思うようなことから、たとえば、痛ましいニュースを見聞きしたり、感動的な映画を見たりする時に、涙したり、喜んだり、自分がもしそういう場面に遭遇したらと想像し感情移入できる時には、自然と同感していることが多いかもしれません。
一方で、「共感」は上記のことに似ているようで、明確に異なるスタンスをとります。
先ほどの例と同じように痛ましいニュースを見聞きしたとしても、共感というのは、自分をそこに投影するのではなく、相手はどう感じているかというのを自分の主観を排して理解しに行く行為、あるいはスキルを指します。
非常に理知的であり、自然な感情というより意志としての行為であるという印象が強くなります。
日本語では、どちらも相手の話に賛成する、理解するという意味合いで、区別されずに同じ「共感」という言葉で使われたりすることもありますが、英語では同感を意味する単語としてはシンパシー、そして共感にあたる単語にはエンパシーという別の言葉があてられているそうです。
ちなみに、エンパシーを「相手の靴を履く」と表現する方もいます。
ニュアンスがイメージしやすい例えだと感じます。
冒頭の事例のように、相手の話を聞いているとついムクムクと起きてくる自分の考え、心の声は、まさに”同感できるか、できないか”というスタンスで話を聞いていることを示しています。それは「相手の靴を履く」ということができていないがゆえに起きることだといえます。
相手の話を聴くときに、ここで言う「共感」のスタンスに立つことができていれば、相手の話の中に、そういうことだったのかという新たな気づき、発見をする可能性もあり得ますし、相手に対する理解が深まるということにつながっていきます。そのことが相手との信頼関係をつくっていきます。
また、共感のスキルが高まっていくことで、自分の感情ではなく、相手の感情を理解できる力がつくので、より自分の行動や発言が相手にどんなインパクトを与えるかということも客観的に気づき、理解できる力がついていくとも言えます。
つまり、相手とコミュニケーションをとるときに、自分を客観視できているので、相手に意図しない印象を与えてしまったり、関係性を壊したりということが減っていくことににつながっていくのです。このことは個人的に大きな意味があると考えています。
今年も一年、noteブログにお付き合いくださいましてありがとうございました。また来月もよろしくお願いします!
2021/12/31 VOL134 sakaguchi yuto
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
