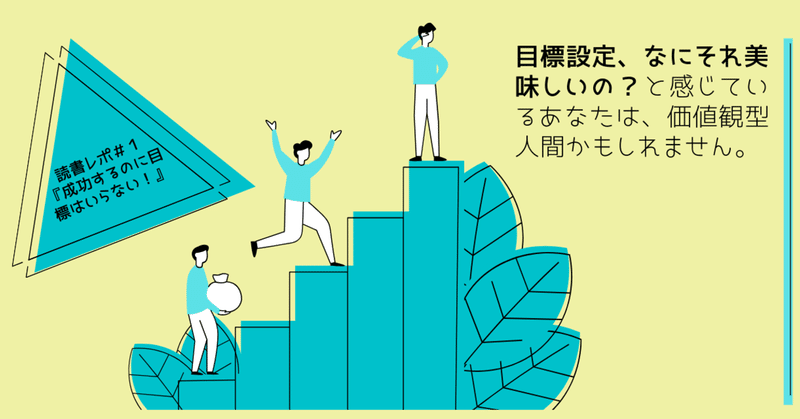
『成功するのに目標はいらない!』読書レポ#1 ~自分の傾向を知る大切さ~
『事業目標の他に、個人目標を立てることも大切。』
今年の1月にベンチャー企業に転職して、1、2週間目くらいにCEOと会話したときに言われた言葉だ。
『目標を立てよ』という言葉は、仕事や学業、自己啓発本でも良く聞く言葉で、私も目標設定の重要性を頭では分かっている。しかし、私の人生はことごとく『目標設定』からかけ離れた人生だった。
唯一「目標」を立てて頑張ったのは、大学受験くらいと言っていいほど、いい意味で行き当たりばったりの人生を歩んできた。(全然自慢にならないけど、そんな自分の直感や心の声に従ってきた人生が割と気に入っている。)
今を生きる!みたいな生き方をしているもんだから、「目標」という言葉にずっと違和感を持っていた。でも、うまく言語化できていなかった。今回紹介するのは、そんな違和感を見事に言語化してスッキリさせてくれた本だ。(中古700円で買ったけど、プレミア価格になっている……!)
仕事で留学生の就活相談に対応したときに、『周りはみんなやりたいことがあるのに、自分はやりたいことが無い。だからすごく焦る。』という学生がいた。これはどうしたものかとGoogleでいろいろ検索して出会った記事の中で紹介されていたのが本書だった。
ちなみに、本書を紹介する記事を何本か読んだが、『表紙は胡散臭そうだけど、中身は良い』という評判だった。私も全くの同感だ。
著者について
本の著者は、コーチングを専門にしている平本相武(ひらもと・あきお)氏。1965年神戸生まれ。東大大学院修了後に、心理学講師やカウンセラーとして教育機関に勤めた後、1997年に渡米。シカゴの大学院でカウンセリング心理学の修士課程を修了し、カウンセラーとして現地の小学校や州立刑務所などで活動した。2001年に帰国し、企業や官公庁でコーチングを中心とした研修を行う傍ら、経営者・投資家・アスリートへの個人セッションも行う。(2007年当時のプロフィール)
読んだ後に調べると、今はYoutubeでも活動していた。ちょっと想像していたタイプと違った。笑
ビジョン型と価値観型の人間がいる
平本氏によると、世の中には「ビジョン型」と、「価値観型」の人間がいるらしい。
「ビジョン型」は、目標ドリブン。具体的な理想や目標へ近づくために努力することがモチベーションになるタイプ。
ビジョン型の人は、何年後かに自分はこんな仕事がしたいというのを先に決めます。たとえば、「5年後にイベントプランナーになりたい」それが実現した場面を思い浮かべるだけでワクワクしてくる。
そこで、就職は今すぐ企画会社に入るよりもまずは必要な知識を得たり、人脈を拡げたりしたほうがキャリアアップにつながる。企画会社に入った時点で即戦力になれるよう、5年間経験をつもう、そのためにはどんな会社でどんな仕事をしたらいいいか・・というふうに決める。
一方、「価値観型」は、自分の大切にしている価値観が満たされている状態にいることが大切なタイプ。
価値観型の人は、たとえば「クリエイティブな発想が活かせる」「マイペースでルーティンをこなす」「チームワークで成果を出す」・・「人とのつながりを大切にする」「自己成長できる」「人の役に立てる」などの価値観が満たされることでやる気が出ます。・・・何の仕事をするかではなく、めぐりあったその仕事で自分の価値観を十分満たせるか、つまりどんなふうに仕事をするかが大事なのです。
本書には、自分がどちら寄りか確認できるチェックテストがある。私は16問中15問が片方に寄っており、がっつり価値観型だった。そして、それぞれの特徴の違いを読めば読むほど、私は典型的価値観型人間だということが分かった。
例えば、初めての就職も転職も、私が仕事を選ぶときに一番大切にしたのは会社のビジョンだった。1つ目のNPO法人も2つ目の今の会社も、どちらも『多様性を大切にする社会を作る』というビジョンを掲げている。ビジョンに自分の価値観とのズレが無ければ、どんな仕事でも納得感を持って働けると思った点はまさに価値観型だ。
また、今の会社が運営しているLinc Internという留学生のキャリア支援事業に興味をもったのは、自分の軸である「人の成長」に携わることができると思ったからだった。数年後の明確なキャリア目標はないが、今この瞬間の自分の気持ちと関心に沿ったサービスに関われるなら、強い職種へのこだわりは無かった。この点もまさしく価値観型だ。
そんな結果で、今の会社では、新規事業作り、キャリアアドバイザー、リクルートアドバイザー、法人営業、マーケティング、広報、コミュニティ運営など全部が初めての仕事をしている。
学びの動機づけの違い
物事を選ぶ基準が違うことに加え、ビジョン型と価値観型は学びの動機づけ方法も違う。
ビジョン型は「近づいている感」が大事で、未来のビジョンにどれだけ近づいているか、もっと近づくためにできることは何か、という視点で行動する。例えば、3年後独立したいから、そのために今から経理を学んでおこう、となる。
価値観型は「満たされている感」が大事で、今どれだけ自分の価値に沿ったことができているかを考えて行動する。例えば、人の役に立つことが好きな人は、「3年後の独立のために経理を学ぶ」よりも「今目の前のこのお客さんにより満足してもらえるよう、質の高いサービスを提供し続けるためには、経理の知識も必要だ」と思うとやる気がアップし、行動に繋がる。
ビジョン型は、「こうありたい」という具体的な未来があって、それを達成するために必要なことを具体的な目標に小分けし、大目標を◯月までにクリアするためには、少目標を△月までにやる、など未来から逆算して日付や期限を設けたほうが、行動しやすい。
一つ一つの出来事を検証し、中にはあんまり気がすすまないと思うことがあっても、ビジョン達成という長期的な視点で必要だと納得できれば、頑張れる。
価値観型は、「日々の生活や仕事のなかで、どんな出来事が起こっていたら、自分が大切にしている思いが満たされる?そのために具体的に何ができる?」「ちゃんと自分らしく、一つ一つの行動にとりかかれているか?」と問いかけ、価値観を満たしながら進んでいくうちに、成果がついてくる。
長期的な視点よりも、本当にそのこと自体、自分がしたいか感じられるかが必要。頭でやるべきだと理解するのではなく、腑に落ちる納得感が必要。
これも、まさしく私だと思った。私は日頃からCEOにインプットとして本をたくさん読まないとレバレッジがきかないと言われている。しかし、頭では分かっていたけど、なかなか行動に移せない日々が少し続いていた。特にビジネススキル関連の本はなかなか手を付けることができなかった。(ちなみに読書自体は嫌いでなく、平均よりも読むと思う。)
価値観型のモチベアップ方法から考えると、行動に移せなかった原因は、本を読むための動機が、私が大切にしている「誰のために頑張るか」という価値観に繋がっていなかったからだと気づいた。
この仮説を証明するかのように、ビジネススキル本は読めなかった一方、学生面談することが増え、コーチングや就活本は能動的に読み始めていた。まさしく、目の前の学生をどうにかサポートしたいという想いが読書のモチベーションになっていたのだ。
また、最近の私の変化も証明することができる。実は、最近ビジネススキル本も自ら読むようになっている(『イシューから始めよ』が難しすぎて、頭がもげそう)。どんな心境の変化があったか振り返ってみると、関わっているサービスの価値への納得感が高まり、愛着が湧いてきたことがキーポイントじゃないかと思った。一方で、どんなに価値あるサービスだと思っていても、推進するためには圧倒的にビジネススキルが足りていない。この事実に対して自分の中で納得できたから、自然にスキルアップのために学ぶ気持ちが湧いたのだと思う。
私はちゃんと意義のあるサービスを作っている→でも目の前のサービス作りがなかなか上手くいかない。→じゃあどうしたらいいか?→私は圧倒的にビジネススキルが足りない→ビジネススキルアップ系の本を読まないと!みたいな。
人によって『やる気の素が違う』認識を持つこと
ビジョン型と価値観型。これら二つの違いに良し悪しは無い。ただ、人によって「やる気の素が違う」ことの認識が大切なのだ。
相手の傾向を知り、受け入れ、相手の傾向に合わせたコミュニケーションを取る方が、より効果のあるマネジメントに繋がり、信頼関係構築にも繋がる。そして、みんながそれぞれ自分に合ったやる気の素を知り、そこから自分に適した成功方法で実践するほうが、充実した人生を生きることに繋がる。
読書後の変化
この本は本当に掘り出し物だと思う。読んだ後に一番良かったと感じるのは、自分が価値観型だということが言語化されて、すごく安心したことだ。そして、おもしろい変化としては、ビジョン型への変な反発心が無くなった自分がいることだ。たぶん、自分は間違ってなかったんだ、ただ人と違っていただけなんだと、自分で自分を肯定できたからだと思う。
今まではビジョン型があたかも正解かのように押し付けてくる自己啓発本やビジネス記事を読んではイラっとしていた。でも、どんなに自分が価値観型だと言えども、ビジネスの上では目標設定大事だよなと素直に思えるようになった気がする。
心理学の本をたくさん書いている、加藤諦三さんも、以下の本でこんなことを言っている。
人はそれぞれの現実のなかで生活している。おなじ現実のなかで生活しているのではない。(中略)この人たちは自分たちとはちがうのだと気がついたことで、ずいぶんよけいな怒りがさけられたと思う。
人をパターン化しすぎるのは良くないが、人間には様々なタイプがいることを腹で分かっていると、自分と違う人への反応が小さくなり、生きるのが楽になると思う、そんなことを思った。自分についての理解度を更に深めてくれた本との出会いに感謝だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
