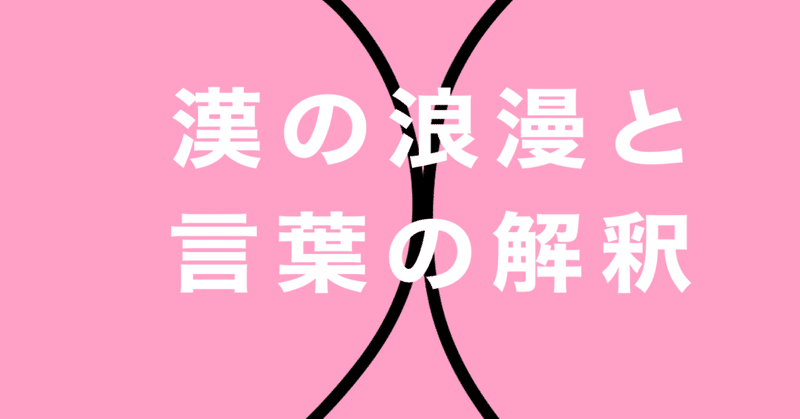
男の浪漫と言葉の解釈。
【立つ】という言葉は、いろいろなものに喩えられる。
単語として聞いた時には、英語で言う【Stand up】を想像することが多いと思う。
役に立つ、歯が立たない等、別の意味が含まれている場面が多々あり、翻訳するときに【cast Stand up】とか、【teeth don't Stand up】などと書いていても訳がわからないであろう。
立腹と言う言葉の場合は、腹に抱えたものが立っている。
つまり、倒れていない、折れていない、と解釈する事もできる。
そもそも腹が立ったり、座ったりするものかどうかは、置いておいて、だ。
肝が据わっているともいう、座ると据わるはほぼ同意味なのだが、据わるの方がよりどっしりとしたイメージをもつだろう。
根性があったりする人に、『お前は、肝が据わっているね。』と言ったりするのだが、
そもそも、肝は動き回るものなのであろうか?
赤ん坊の首が座るように、ふらふらしたものがしっかりする意味で使われているのだと思うが、
【肝が据わっている】と言うのは肝【臓器】を人間が生きていく上で、欠かせない機能と捉えて、それがしっかりと芯を持っているという事なのではないだろうか。
そう考えると、立つと座るは真逆のように感じるが、近い意味合いを兼ね備えていると言えるだろう。
昔の人間にとって、根性というのは、人間の活動で欠かせないもの、しかし外からは見えないものという考えから肝(腹を掻っ捌かない限りはちゃんと動いているか解らない)に例えて、肝が据わると言っていたのかも知れない。
そう考えると、しっかり嘘偽りなく話すことを、【腹を割って話す】というのも納得がいく。
同じように、腹を割る行為でも切腹と云う文化もあった。
悪事を働いたものが命じられる刑のようなものだと思うのだが、腹を割るという行為はお互いに切腹しあう、己の悪事など腹に溜まった黒いものを見せ合うという解釈の方がしっくりくる気もする。
腹に関する言葉は多いが、胸はどうだろう。
胸中を明かす、明かす。
ということ胸の中は暗いのか?
恐らくだが明かすというのは、夜が明けるみたいな、日の入らない心の部屋の窓を開けて風通しを良くする、のようなことであろうか。
胸と腹、どちらも人間の心理的側面に沿った意味合いの言葉に使われている。
体の部位という点では同じようだが、どうだろう。
胸には心臓がある。心はどこにあるか、と訊けば胸を叩く人が多いだろう。
腹には胃や腸、栄養を得るための消化活動に使われる器官が多い。
ならなぜ、腹黒いと言われるのだろうか、腹に逸物抱えたり黒い物も溜まる。
気分がすぐれない時には食欲不振になったりなどメンタルの影響も受けるし、悪いものを食べたら体調も優れなくなるので、腹に溜まるのだと私は考える。
胸には漢の浪漫がある。
だから、あまり黒いものが溜まったり、割ったりしないのかも知れない。
胸や心は割るのではなく、開くものだ。
かくゆう私も、胸か腹かと言われると胸と即答する。
このように潜在的な思いが、言葉の成り立ちに関わっているするのならば、いつの時代になっても男というものは助兵衛であると言えるのかも知れない。
↓こちらも面白くかけました。
サポートして頂いた方には足を向けて寝れません
