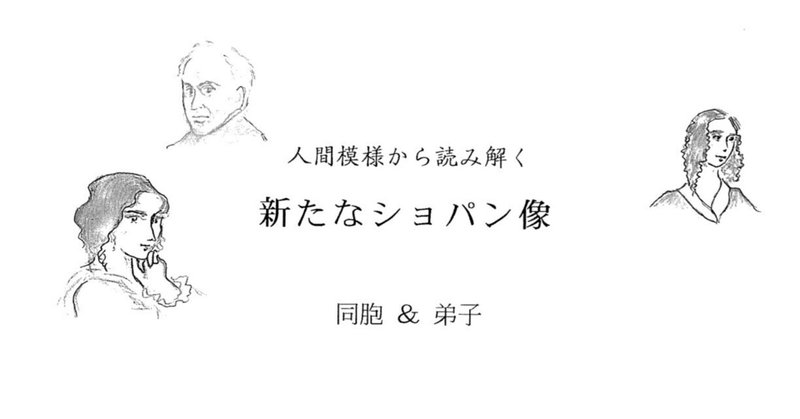
人間模様から読み解く 新たなショパン像 ⑨ 同胞、弟子
ポーランドの同胞
ワルシャワ時代からの親友ヤン・マトゥシンスキにユリアン・フォンタナ、カフェで語り合った「自由ポーランド」の親しき仲間たち、革命の首謀者レレヴェルに、憧れのミツキェヴィチといった詩人、芸術家、政治家に大貴族。ポーランドから亡命、移住してきた大勢の同胞が、パリのサロンに集っていた。
果たしてここはワルシャワか? と思い違えるほど懐かしい顔ぶれに異郷の地でも会うことができたのは、ショパンにとって実に恵まれた環境であった。
中でも、チャルトリスキ公爵の一族が住んでいたセーヌの小島に佇む美しいランベール館は「パリのポーランド王国」と称され、亡命者の支援、政治や芸術活動において同胞の重要な拠点となっていた。
アダム・チャルトリスキ公爵
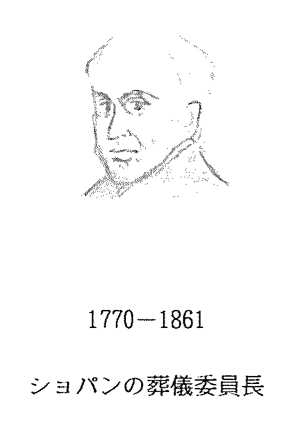
リトアニア大公国統治者の流れをくむポーランドの大貴族、チャルトリスキ家の一員で、政治家。
帝政ロシアで外務大臣をしており、アレクサンドル大公(のちの皇帝アレクサンドル1世)と親交を結ぶことで、ロシア国内におけるポーランド語学校の発展に貢献、ロシアの保護下においても自治的なポーランド王国を創設するべく尽力していた。
ワルシャワ蜂起の折は既に政界を引退しており、当初は武装を伴う革命に反対の姿勢をとっていたが、やがては高貴な身分故の責務から、そして祖国への深き思いから、否応なしに革命の首謀的立場をとらざるを得なくなる。
ワルシャワの陥落で、革命がロシアにより鎮圧されるや、一族と共にやむなくパリに亡命。ポーランド亡命者の中心的存在となり、革命の後方支援を続けていく。
ショパンもまた、公のランベール館における月曜恒例の「夕べの音楽会」や、亡命者支援のチャリティー舞踏会などの常連であった。
⑥パリの音楽仲間の項でも記したが、ショパンがパリに到着した当初は、どう生活したものかと途方に暮れていたものの、パリで活躍する音楽家らの紹介や、こうした同胞のサロンでの豊かな交友関係から、ピアノの教え子にも恵まれていく。
周囲の計らいで設定された破格ともいえる高額レッスン料により、ショパンから受ける個人指導は格別なものと認識される。否応なしに人気は高まり、その収入が彼の生活を支えてゆく。
プロ、アマ問わず、裕福な貴婦人らが次々とレッスンを申し込む。その中には、かのラジヴィウ家(⑤ 恩人の項で前述)からチャルトリスキ家に嫁いでいた、マルツェリーナ・チャルトリスカ公妃もいた。
ショパンの弟子
ショパンはパリ中に数え切れないほどの教え子を抱えるようになる。弟子の中にはあらゆる芸術家のミューズであり、ショパンの大切な友となりゆく歌手のポーリーヌ・ヴィアルドや、ピアノ業者プレイエルの奥方、マリ・プレイエルといったプロの音楽家や、アマチュアでも、デルフィナ(⑦ 恋人の項で前述)のように、ショパンと互角に共演できる才能をもつ優れた弟子も大勢いた。
ショパンの指導は非常に丁寧であったという。
身体を完全にリラックスさせ、どこも緊張せず、形の美しい手で柔らかく奏でることで、最高に美しい音色が生み出されると説いていた。
歌うことの大切さを伝えつつも、それはあくまでも自然な歌い方でなければならず、メロディーを奏でる右手は、そよ風によって木の葉がごく僅かに揺れ動くように。けれどリズムを刻む左手は、大地にどっしり根差した木の幹が完全に支えているように揺るぎないものでなければならないと。
人の歌声が音域や音量によって微妙に変化するのと同様に、左右5本の指も、各々果たす役割も力加減も異なるのだから、それを活かすべきで、全ての音を無理やり均一に奏する必要はないと、当時の主流であった、大劇場で映えるヴィルトゥオーゾ奏法に異を唱える姿勢も見せていた。
それでありながら、モシェレス(別項~名曲にまつわる愛の物語「〈悲愴〉を密かに愛した少年」)や、ショパンの為に演奏会を企画するなど親切な援助を惜しまなかったのに、弟子入りを断られ嫉妬していたなどと理不尽な誤解を受けがちなカルクブレンナーといった大御所のピアニストらが、自分の息子をショパンに弟子入りさせていたことは──親子間のレッスンは往々にして難しい傾向になりがちという事情を考慮しても──、ショパンのレッスンは革新的でありながらも筋の通った、信頼に値するものであったことを示していよう。
独自の教則本を残したくも叶わなかったショパンの、正統な後継者とも言えるマルツェリーナ・チャルトリスカ公妃や、アドルフ・グートマンは、師弟という枠を超えた貴重な存在となり、晩年のショパンに最後の最後まで家族のようにつき添っていた。
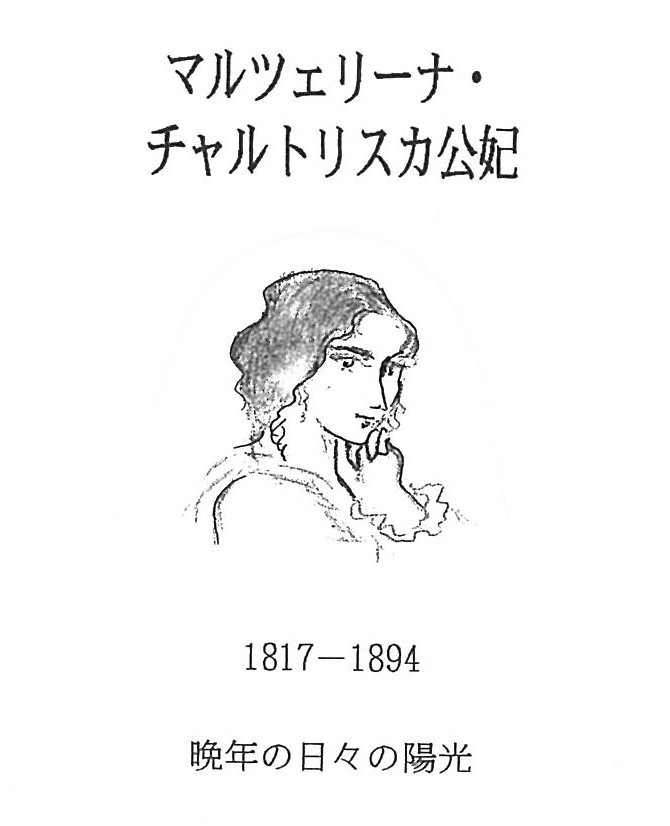
最晩年、病床で起き上がることもできなかったショパンから、彼がベッドに横たわったままの状態で、レッスンを受けることができた、ごく限られた数名の弟子の1人。
ピアニストとしての音楽的才能もさることながら、飾らぬ品格に、穏やかで、決しておしつけがましくない女性らしい心づかいができる公妃は、ショパンにとって天使のような存在であった。
ショパンは死の前年、2月革命の余波を受け、弟子のスターリング嬢(後述)の提案で渡英するも、中々思うような収入は得られず、体調は悪化するばかりであった。
善良なスターリングの親切すらもことごとく重みに感じ、心身共に最悪の状況に至る中、旅の途中でマルツェリーナ公妃が見舞いに訪れ、祖国の言葉で話し、看病してくれたことは、塞ぎ込んでいたショパンに何にも変えがたい幸福をもたらしたという。
ショパンが亡くなる2日前、彼の願いに応じ、公妃はフランショーム(⑥ 音楽仲間に前述)と共に、最晩年に作曲されたチェロ・ソナタを演奏する。ショパンのあまりに激しい咳で、幾度か中断しながらも。
弟子として、家族同然の同胞として、臨終の瞬間まで、優しく温かく見守り続けたのだった。
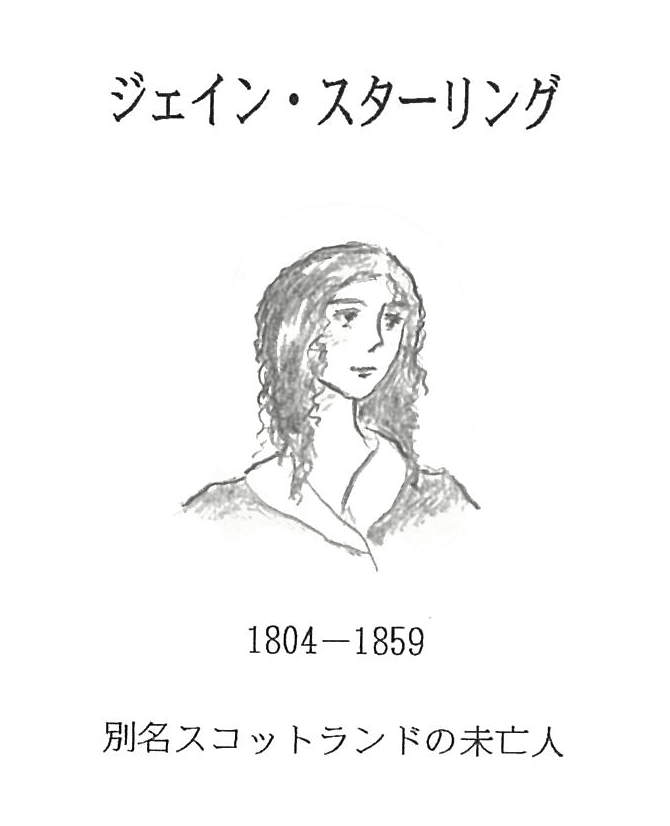
ジョルジュ・サンドと同じくショパンより6才年上の、裕福なスコットランド人。有能な弟子にして、ショパンがサンドと別れた後、その財力で経済的にショパンを援助する。
ショパンに演奏の機会を与え、収入源となりゆく新たな生徒や王候貴族といった有力な人物に引き合わせるべく、ヴィクトリア女王の御前演奏なども含め、イギリスとスコットランドを巡る綿密な旅を計画するも、ショパンの体調や機嫌は悪化を辿る一方で、結局は何もかもが大変な裏目に出てしまう。
英国中を散々連れ回し、既に弱りきっていたショパンの病を悪化させ死期を早めただの、自慢したくて親戚中に見せびらかしただの、結婚を目論んでいたが本人につれなくされ、願いは叶わなかった片思いの未亡人だの、手紙などに残されたショパン本人による心ない言葉も含めて、かなり理不尽な評価を下されてしまっている損な役回りの女性である。
しかしながら実際は、パリに戻れど生活に困窮気味のショパンを匿名で援助しようとしたり、莫大な葬儀の費用を立替えたり、貴重な遺品が散在してしまわぬようオークションで買い集め、それを決して独り占めすることなく、ショパンの姉ルドヴィカに寄贈するなど、音楽史に果たした役割も大きかった。
ショパン自身の手による彼女の楽譜への詳しい書き込みは大変貴重な資料として、今日でも楽譜を出版する際の参考とされている。印刷ミスの指摘や、加筆や補正といった譜面の修正に加え、演奏時の細かな指示として、ペダリングやテンポ、運指法、強弱の変化のつけ方、装飾音の奏法等々。
そもそも人脈も財力もあり、音楽的才能もある人物が、何よりショパンの音楽を心から愛していたとしたら、経済的に困っている本人に援助の手を差し伸べようとするのは当然の流れとも言えように、彼女が独身であったことからか、ショパンの新たな恋人、あわよくば妻の座に収まりたがっていたはずだなどと勝手に憶測され、英国の旅が最悪な結果をもたらしたといった事実から、不当な印象ばかりが目立ってしまうのは残念なことだ。もっと正統な評価を受けて良い存在には違いなかろう。
彼女には、〈ノクターン〉Op.55が献呈されている。
ショパンが父親の訃報を受けた年の作品で、哀愁に満ちた主題や、決然とした感情のほとばしりを見せる中間部が印象的な第15番と、美しい田園風景や涼風を思わせる爽やかな16番とが、対を成しているようだ。
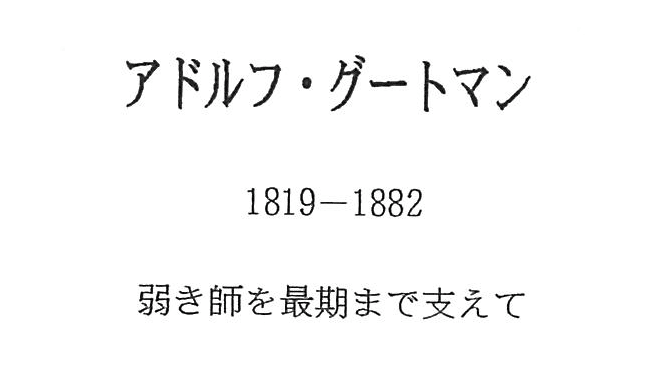
「私は後継者を育て上げましたよ!」と、ショパンに言わしめるほどの、お気に入りの弟子だったが、その豪快で、いささか乱雑ともいえる演奏ぶりは、ショパンの繊細なスタイルとはかけ離れていたらしい。
男性の弟子の中では、唯一作品の献呈を受けており、〈スケルツォ〉第3番の、ミステリアスな序奏に続く豪快な和音の連打は、まさにヘラクレスのような強靭な体格であった彼の為に書かれたとも思わせる。
マルツェリーナ公妃ともに、最後までショパンのレッスンを受け続ける。
やがては動くのもままならなくなってしまう師を抱えて移動させるなど、常に側についていた逞しきグートマン。強い男友達を心から必要としていたショパンにとって、たいそう頼もしい存在であったことだろう。臨終の場でも、彼の腕にしっかりと支えられていたという。
儚くも世を去った妹エミリア、大親友であった2人のヤンの死。異郷の地で受け取った、恩師ジヴニーや父親の訃報。革命の同志モフナツキもヴィトフィツキも逝ってしまった……。
ジョルジュ・サンドは去りゆくも、彼女の娘ソランジュがここに居る。慰めをもたらしてくれるデルフィナの歌声。フランショームのチェロの調べ。あちらの世界にモーツァルトを届けてくれるだろうか。優しい天使のマルツェリーナ公妃。
ルドヴィカ、家族を置いてまで、ずっとそばに居てくれたね。僕の心臓だけは、どうかワルシャワの故郷に持ち帰って欲しい。帰ったら母さんに……、ああ! 気の毒な母さん!
ティトス……、一目会いたかった。
僕の手を握ってくれてるのは誰かな? ティトス、来てくれたの?
ああ、グートマン、きみなんだね。きみの存在が、どんなに心強いか──。
死の床の、こうした状況はあくまで推測にすぎないが、ショパンが生涯に渡り、自分を支えてくれる圧倒的に強い存在を必要としていたことからも、死が差し迫る恐怖と哀しみ、苦痛と混乱、絶望の淵で、かつての大親友で心から頼りにしていた存在、死の間際まで再会を願い続けていた力強きティトスと、弟子のグートマンを重ね合わせる想いもあったのではなかろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
