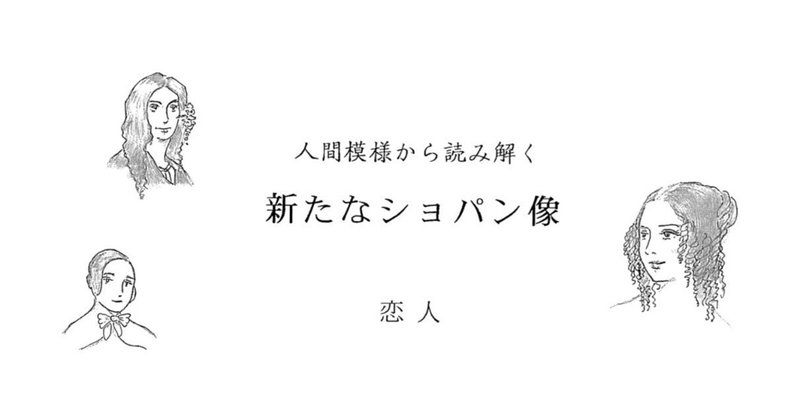
人間模様から読み解く 新たなショパン像 ⑦ 恋人
※ 今回の「⑦ 恋人」は、『名曲物語』として既に公開済みの記事、
~ 楽譜に秘められた愛のメッセージ ~
ショパン 〈別れのワルツ〉 〈小犬のワルツ〉
こちらと、ほぼ似かよった内容となっております。
とはいえ、各々のテーマに沿って別途、追加されている内容や、あえて微妙に変えてある表現などもありますので、どちらの記事も互いに参考にして頂けますと幸いです。
~ 人間模様から読み解く 新たなショパン像 ~
ショパンの恋人
ショパンが愛した女性としては、ワルシャワ時代の初恋の人とされるコンスタンツィアや、〈別れのワルツ〉を贈った昔なじみのマリア、そして言わずと知れたジョルジュ・サンドが有名であるが、没後100年も経って新たに恋人として浮上したのが、年上の伯爵夫人デルフィナ・ポトツカである。
互いの名誉の為に破り捨てるようショパンが厳命していた手紙を彼女が大切に保管していた為、後に公にされた次第だが、贋作の疑惑もあり、真偽のほどは定かではない。
しかしながら、ここでは数々の情報を元に、やはり彼女こそがショパンにとっての永遠の恋人として紹介したい。恋する想いなど本人どうしですら計り知れず、ましてや後世の人間が憶測で語ることなどできないが、2人が長年の美しい絆で結ばれていたには違いなかろう。
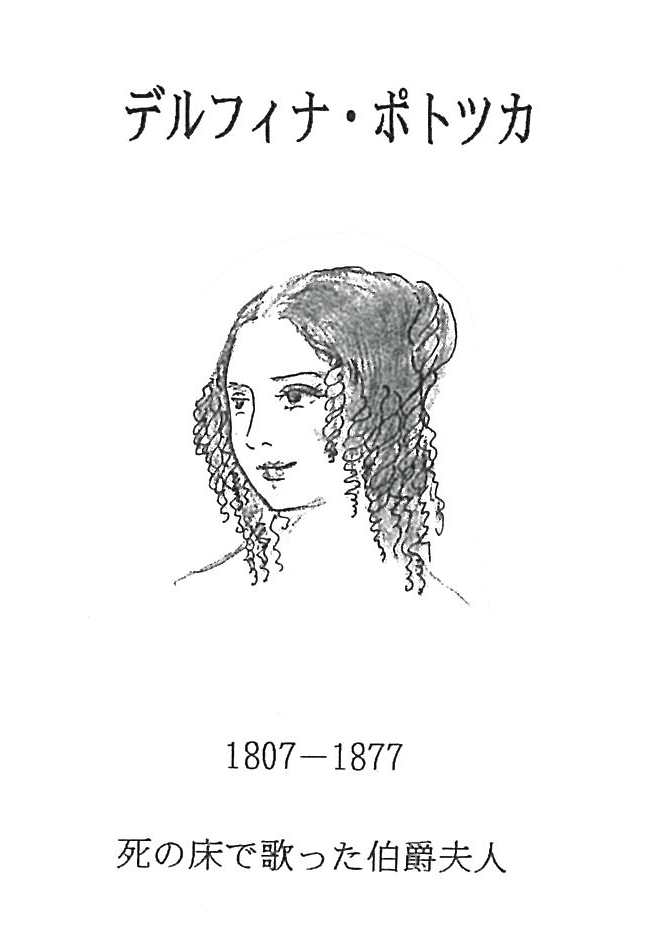
ショパンと同じポーランドの出身、栗色の巻き毛の、すらりとした美貌の歌い手であり、優れたピアノの弟子でもあったデルフィナ。
アマチュアながらも、音楽を深く理解していた彼女を、ショパンは1人の芸術家とみなして接していた。
手紙では「フィンデルカ、愛しい恋人よ」と独自の愛称で呼びかけ、自作品への思いを語り、解釈、運指、ペダリングといった練習法なども詳しく指示。バッハを弾くことの大切さを伝え、バッハを暗譜することを強く勧めるなど、ショパン自身の音楽観を、思いやりと愛情のこもった言葉で丁寧に綴っている。
横暴な夫と別居し、芸術家の集う高級サロンをパリで構えていたデルフィナとは、ショパンが21才でパリで暮らし始めた頃から3年ほど親密に付き合うも、別居中とはいえ彼女が人妻である以上、2人の交際に関しては、仲間うちでも沈黙が保たれた。
そうした配慮があろうとも、気品があり、性格も素晴らしかった絶世の美女で、世の男性陣に対しては、ファム・ファタル(運命の女性=魔性の女)とも噂されていたデルフィナのこと、嫉妬に狂うあまり、ショパンに決闘を申し込んだ男性もいたという。
デルフィナは年下のショパンに対して、常に優秀な生徒として、そして洗練された大人の女性として接していた。
恋人の関心が、幼なじみの純朴なマリアとの平穏な家庭生活を夢見ることに向けられ始めると知るや、潔くパリの屋敷を引き払い、夫の元へ帰ってゆく。
余談ではあるが、恋人の心が離れつつあると察しても、相手に追いすがったりせず、自ら去りゆく、こうした引き際の態度は、ファム・ファタルの習性でもあるようだ。
泥沼の破局が避けられたこともあってか、2人の友情はショパンが亡くなるその日まで大切にされ、臨終の時も去りゆくショパンを、その素晴らしい歌声で安らかに送ったのであった。

コンスタンツィアへの憧れの想いから生まれたと、ショパン自身が語っていたはずの〈ピアノ協奏曲第2番〉と、後年、ジョルジュ・サンドとの破局が近づきつつあった頃の作品、〈小犬のワルツ〉が、デルフィナに献呈されている。
デルフィナ・ポトツカ伯爵夫人。あたかもショパンにとっては、叶わぬ恋、失われた愛のむなしさを解消させ、忘れさせてくれる救世の女神ともいえそうな存在ではなかろうか。
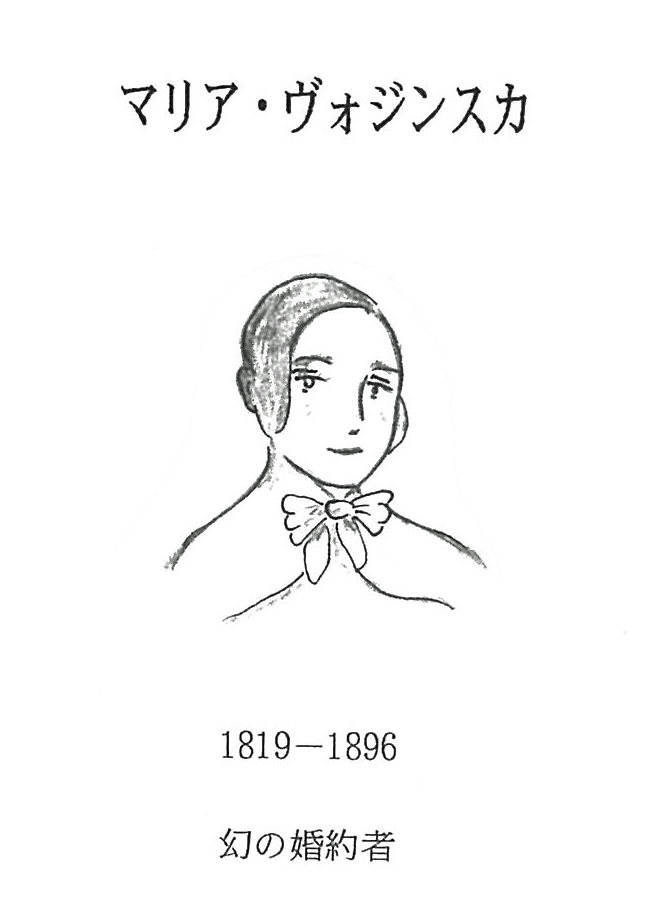
マリアの3人の兄は、ワルシャワのショパン家の寄宿生で、フレデリック・ショパンとも兄弟同然で、ワルシャワ時代、ショパンは幼いマリアにピアノを教えていたこともあった。
ヴォジンスキ家は裕福な貴族の家庭で、ワルシャワ蜂起に息子らが加わったこともあり、動乱後は一家でドレスデンに移住していた。
1835年夏、チェコの保養地で両親との5年ぶりの再会を果たしたショパンは、亡命の落ち着き先であったパリへ帰る途中、ドレスデンのヴォジンシキ家に立ち寄った。
10日間の滞在中、懐かしい一家の大変温かな、心からのもてなしにショパンはこの上ない幸せを感じていた。美しく成長したマリアと、その優しい家族に穏やかな愛情を抱いてゆく。パリでの生活も安定していた頃のこと、温かく落ち着いた家庭生活の可能性に、ショパンは夢を思い描くようになる。

これは当時マリアが描いた水彩画で、ショパンの肖像画として、大変貴重な資料とされている。
このように、マリアは絵や音楽の豊かな才能を備える、穏やかな性格の少女であった。
ただ、何事においても両親に依存しがちで、恋愛に関しても、自分の想いよりも親の意向が気になるようだった。
翌年の再会で、マリアとショパンが互いに魅かれ合う様子に、マリアの母親は「試験期間」という条件で、2人に仮の婚約を交わす許可を与える。しかし婚約は周囲に秘密とされ、パリに戻ったショパンへの手紙も、主にマリアの母親から健康を気遣う数々の忠告に、マリアの短い添え書きが加わる程度であった。
残念なことに、その後の再会の約束は果たされず、いつしか婚約も自然消滅と化してゆく。
ショパンが病弱であったこと、ワルシャワで秘密結社に加入していたという政治的立場、加えて、そろそろショパンの人生に現れ始めていたジョルジュ・サンドの誘いを受けようかと、ショパンがこともあろうかマリアの兄に打ち明けていたことなど、様々な原因が考えられる。
マリアの手紙も含むヴォジンシキ家からの手紙をショパンがリボンで束ね、「我が哀しみ」と記して生涯大切に保存していたとは、多くのショパンの伝記に写真付きで登場するエピソードである。
確かに当時は絶望の思いから「我が哀しみ」と書いたとはいえ、その行動から、マリアだけを最も大切な人として生涯思い続けたように解釈するのは筋違いではなかろうか。
1835年の、ヴォジンスキ家での最初の滞在の折、ショパンが別れ際にマリアに贈った変イ長調のワルツは、哀しみを伴う〈別れのワルツ〉として今日知られている。
しかし実際は、「楽しく幸せなひとときでした。素敵な思い出をありがとう。また会いましょう」といったニュアンスで、淡い恋の切ない想いは含まれていたとしても、哀しい嘆きの別れではなかったはず。
しかもこのワルツ、マリアだけに捧げられたものではなく、後年、別の女性2人にも各々献呈されているのだが、そうした事実は黙殺されがちで、婚約破談の事実と、リボンで束ねた「我が哀しみ」の証拠から、「哀しみの別れのワルツ」のイメージがすっかり定着してしまい、この曲の人気を更に高めているようだ。
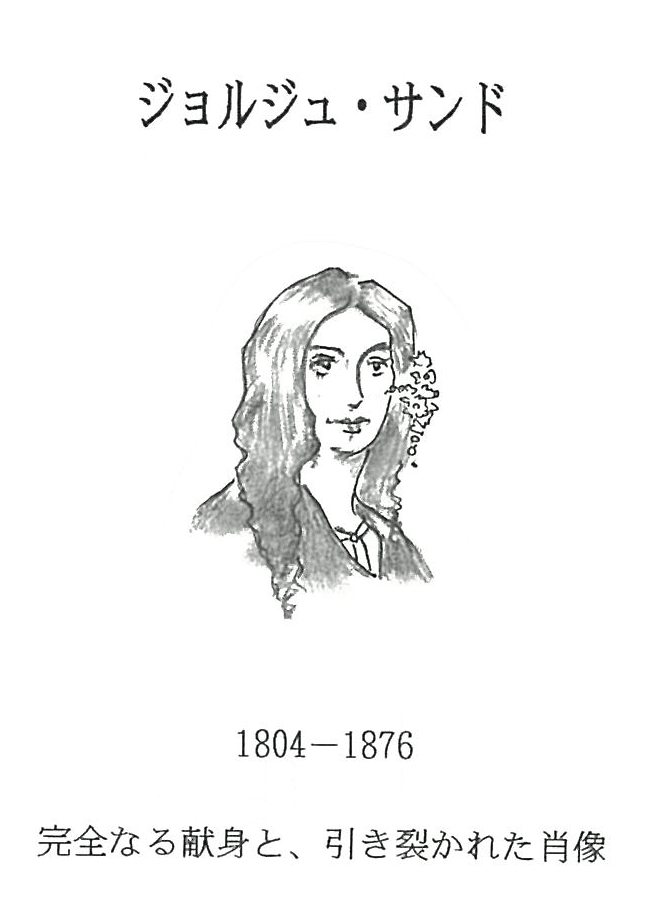
デルフィナは去り、やがてマリアとの縁談も幻想に過ぎなかったことを悟り始めたショパンは、男装の麗人であり、既に女流作家としての地位を築き上げていたジョルジュ・サンドと急速に親しくなる。
「ぼくがピアノを弾いていると、彼女は瞳をしっかり見据えてくる。あまりにも黒い瞳がぼくの目を捕らえて離さないので、魔力で硬直してしまうほどだ。ぼくを燃え上がらせ圧倒し、心を虜にする。彼女はぼくを愛してくれている。きっと。
オーロール……、なんと魅惑的な名なのだろう」
~ ショパンの日記より
オーロールは彼女の本名で、サンドはペンネームをあえて男性名のジョルジュとし、社交サロンでは男装を貫いていた。
我が国では、自らの少女時代をモデルに、フランスの美しい田園風景が見事に描かれた爽やかな恋物語「愛の妖精」で、名が知られているジョルジュ・サンド。
繊細なショパンにとって、サンドの強烈すぎる装いや、押しの強さ、厚かましさは異様に感じられ、初対面の印象は最悪であったものの、先の日記にあるように、ほどなくしてショパンは彼女に魅せられ虜になってしまう。
彼女もまたデルフィナ同様、芸術家や作家を虜にしつつ彼らの才能を最大限に引き立て、最高の高みへと導く力のあるファム・ファタルであるとはいえ、病弱のショパンへの献身は並大抵のものではなかった。
やはり夫と別居中の人妻の身とはいえ、サンドの場合、数々の男性遍歴は常に周知のものであった。かの有名なマジョルカ島への逃避行の折など、最初のうちこそは、こっそり2人が別々にパリを出発したりもしていたが。
パリでの半共同生活では連れだって優雅な社交界に身を置き、豊かな自然に囲まれた彼女の実家ノアンの邸宅で過ごす恒例の夏の日々は、ショパンに作曲に専念できる完璧な環境をもたらすのだった。
澄み切った空気に色鮮やかな緑、美しい木立の散歩道、新鮮な食物、花や草木の香りに小川のせせらぎ、小鳥のさえずり、のどかな鐘の音、サンドによる朗読、そしてお気に入りのプレイエルのピアノ。
サンドはショパンの部屋に、朝は熱いココアを、午後には栄養満点の特製スープを届けるのを日課とし、必要以上に声をかけたりせず、恋人がピアノに向かう時間を神聖なものとみなしていた。
サンド自身が小説家であるが故に、芸術に携わる者の繊細な神経を理解することができ、そこに身ひとつで我が子2人を育ててきた年上女性の母性が加われば、尚更のことであった。
そしてショパンも彼女のそうした気遣いを、心から有難く思っていた。ショパンの心の平穏も、仕事も、健康も、すべてはサンドの上にかかっていた。
恋人のあらゆる心遣いがショパンの創作に多大な影響を及ぼし、より自由に大胆に、豊かな創造力が導き出されていき、数年に渡り、円熟味を増した数々の不朽の名作がノアンの地で生み出されてゆく。
バラード、スケルツォ、ソナタ、舟歌、幻想ポロネーズ……。
しかしサンドの子どもたちとの微妙な関係、家庭内の不和が、やがて深い溝となり、仲違いに嫉妬と、互いの態度も次第に冷淡になっていく。
家庭という、最も必要としていたショパンの身の置き場所は失われつつあった。
ショパン不在の際に起きた、斧や拳銃が持ち出される暴力沙汰に、愚かな誤解と意見の相違が加わって、2人は10年の付き合いから、いともあっさり、充分な別れ話も交わさずに破局を迎えてしまう。
サンドとの別れはショパンにとって、それは確実な死への前奏曲となるのだった。

2人の共通の友人の画家、ドラクロワ(⑩「夢の王国の住人」にて後述)が描いた、有名な肖像画がある。
これは元々は上のように1枚の絵で、2人が親しくつき合い始めた頃に描かれたものであった。ピアノを奏でるショパンの脇で、耳を傾けながら縫い物をするジョルジュ・サンド。
2人の仲睦まじい様子、穏やかなその場に居合わせたドラクロワも友として、この上ない幸せを感じたのではなかろうか。
大切な個人の思い出としたかったのか、ドラクロワは公開することなく自ら保管していたのだが、画家の亡き後、心なき何者かの手によって、2枚に分断されてしまう。
各々は競売にかれられ、ショパンの絵はルーブル美術館の所蔵となり、サンドの方はデンマークの収集家によって買い取られ、現在はコペンハーゲン近郊の美術館に展示されている。

ジョルジュ・サンドとの破局後、ショパンは殆ど作曲に取り組まず、⑥「パリの音楽仲間」で紹介したフランショームに贈った〈チェロ・ソナタ〉を初演したくらいであった。大切な友人らに支えられながらも、ショパンは気力も体力も失い力尽き、2年後には亡くなってしまう。
サンドはショパンの葬式にも顔を見せなかった薄情な女と、しばしば取り沙汰されるが、実際は、彼女は別離の後もショパンの病状を心配し、彼の姉のルドヴィカへ手紙を書いたりしていた。
しかしショパンから「サンドに捨てられた」と聞かされていたルドヴィカは返事を書かず、葬式の招待状もサンドには出さなかった。ショパンの葬儀には招待客しか出席を許されず、従ってサンドが望んだとしても、参列は難しかったであろう。
招かれざる客には決してなりたくない、というファム・ファタルの習性を考えても、群衆に紛れて、せめて遠目にだけでも……といった行為すら、やはりあり得まい。
ショパン本人にしても、冷酷な恋人に棄てられた挙げ句、死に至り、当の恋人は葬式にすらも現れなかった薄情者という誤解よりも、創作の円熟期に精一杯尽くし、数々の名曲を生み出すことに貢献した恋人として、ジョルジュ・サンドは世の記憶に残るべき存在であって欲しいと願うのではなかろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
