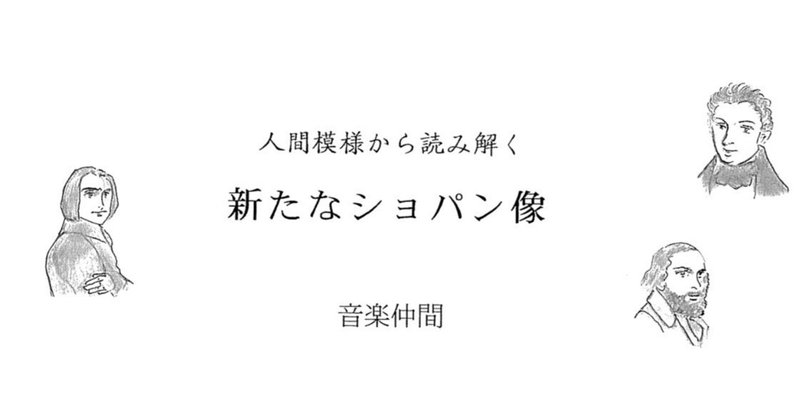
人間模様から読み解く 新たなショパン像 ⑥ パリの音楽仲間
Prelude
〜 フランスの音楽事情 〜
ルネサンス時代にイタリアで発展したバレエが、16世紀にフランス宮廷にもたらされ発展してゆき、やがて太陽王ルイ14世(1638ー1715)が、王立音楽舞踊アカデミーを設立する。
余談ではあるが、ルイ14世が「太陽王」と呼ばれていたのは、太陽のごとく偉大な王であったというよりも、バレエ好きで舞踏の才能にも恵まれていた王が、太陽の役を好んで踊っていたことに由来する。
イタリアから帰化するリュリ(1632ー1687)、フランス人のクープラン(1668ー1733)やラモー(1683ー1764)の後は、既に自国で成功を収めていたイタリアやドイツの作曲家らが、新天地を求めてパリへとやってくる。
王立音楽演劇学校の学長に就任するケルビーニ(1760ー1842) 、マイアベーア(1791-1864)、ロッシーニ(1792ー1868)、ベッリーニ(1801ー1835)、ヴェルデイ(1813-ー1901)といった面々だ。
しかしここフランスにおいて生まれゆく、ことピアノ音楽に関しては、殆ど有史以前とも言える状態であった。
1789年のフランス革命を経て、ナポレオンの登場、そして復古したブルボン王政の頃、ハンガリー出身の少年フランツ・リストがパリを訪れる。
王政は1830年の7月革命により、オルレアン朝のルイ=フィリップ(1773ー1850 在位1830ー1848) に引き継がれた。
以降18年間、上層ブルジョワジーに支えられ、思想も芸術も文化も、世界がパリを中心に回っていた豊かな時代。動乱のポーランドを後にした青年ショパンがパリに到着する。
既にリストは華麗なる社交界に君臨しており、若きショパンもフランスを舞台に、ピアノ音楽史上に重要な役割を果たしてゆく。
── パリ時代 ──
新たな音楽仲間
ショパンが後半の人生を過ごしたパリの18年間は、1830年の7月革命から1848年の2月革命に終わるルイ=フィリップ王の時代と、ほぼ時を同じくする。
情勢が比較的安定し、芸術家にとっても活動しやすい時期であった。
ショパンはパリに到着して、しばらくの間は明日のパンをも心配する必要があったようだが、ほとなくして大御所のピアニスト、カルクブレンナーや同年代のリストといった、新たな音楽仲間や同胞の助力を得ることができた。リサイタルの開催や、口コミによる貴族や有力者関係の個人レッスンも人気を博し、生活も安定してゆく。
ショパンの洗練されたふるまいや、パリっ子に負けない抜群のファッションセンスから、
「ショパンが流行をつくる」
「ショパンはパリのエレガンスのシンボル」
とまで言われるようになる。
リスト、ベルリーニ、メンデルスゾーン、ベルリオーズに、フランショーム、ヒラーといった仲良し青年音楽家グループに、ショパンもしっかり溶け込んでいく。毎日のように食事を共にし、談笑し、芸術論に花を咲かせ、あちこちのサロンに出向いては、その腕前を披露し合うのだった。
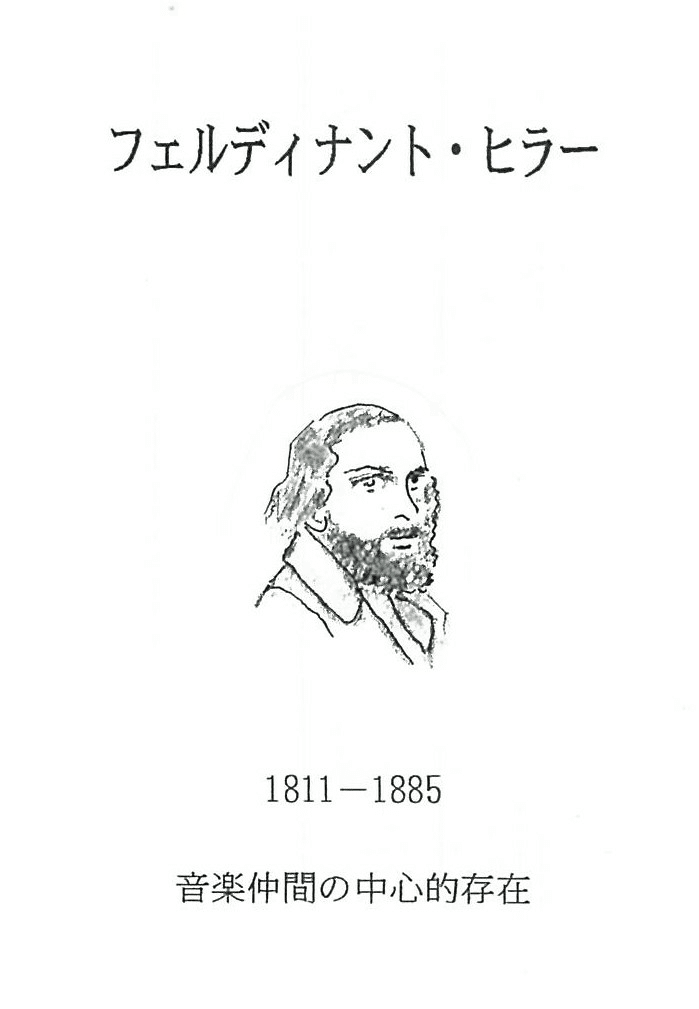
ドイツの一流ピアニストにして、作曲家で指揮者であり、ケルン音楽学校の校長も務めている。
作風はメンデルスゾーン風で、古典的な均衡とロマン派の色彩が格調高く調和されていた。
ショパンはパリに来て間もない頃、彼の自作の演奏会を聞いて感激し、
「詩情、情熱、精神性にあふれた男だ」
と、故郷のティトゥスに書き送っている。
モーツァルト弾きとしても高い評価を得ていたことから、無類のモーツァルト好きのショパンとも意気投合。早速、リスト、ハイネ、メンデルスゾーンらをショパンに紹介してゆく。
ドイツに帰国するまでの5年間、ヒラーはショパンがたえず必要としていた心の支えとなり、ヒラーもまた、ショパンを崇拝していた。
「ショパンはぼくを愛してくれていた。そしてぼく自身も心底彼に惚れ込んでいた。彼が傍らにいるだけでとても幸せだったし、いくら聞いていても、彼の話は飽きることはない。しばらく会えずにいると、淋しくて仕方ないほどだった」
と、ヒラーは回想録で語っている。
そんなヒラーへのショパンからの最高の贈り物は、彼に献呈された〈ノクターンOp.15〉であった。

歴史に名を残したピアニスト、作曲家として、世間
一般にはショパンとはライバルとして比較されがちだが、実際は親密な芸術的絆で結ばれ、互いに尊敬し合っていた。
大音量で、豪快で、目も眩む華麗な名人芸が特徴のリストは、繊細で柔らかな音色、洗練されたショパンの内に潜む大胆さ、独創性、新鮮さに魅了されていた。
初見でどんな曲でもたやすく弾きこなせるリストが、ショパンから作品10の〈練習曲集〉の楽譜を渡された直後、パリから忽然と姿を消したことがあった。
それから数週間後、リストは〈練習曲集〉を引っ提げて帰還。毎日何時間も練習し、曲の魅力を最大限に引き出すべく、細かなニュアンスや、めりはりの付け方などを研究していたのだった。
完全に完成されたリストの演奏を目の当たりにした作曲者のショパンはすっかり圧倒され、
「どう弾けばいいのか、彼から盗みたいくらいだ」
と、友人のヒラーにぼやくほどだった。
ショパンからリストへの難曲の献呈は、ライバルへの挑戦状だったと誤解されがちだが、感激したショパンが素直に献呈したというのが真相である。
リストがパリから離れてからは、やや疎遠となるも、敬愛する芸術家どうしの絆は変わらずに続いていた。
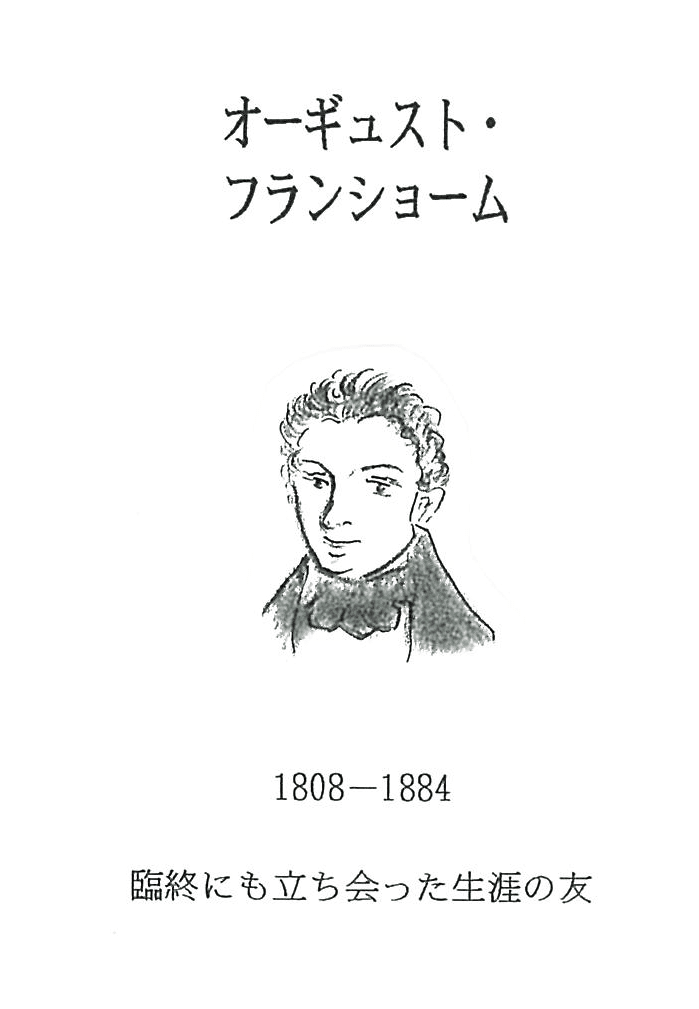
パリ音楽院の若き教授で、当時のフランスで最も優れたチェリストとして活躍。正確かつ軽やかな技巧に、優美で甘美な表現力を備えていた。
正しくは「フランコム」が、フランス語に近い発音とされるが、我が国では「フランショーム」の名で、より多く知られている為、こちらの名での表記とする。
多国籍の音楽界であった中、生粋のフランス人として生涯の殆どをパリで過ごし、作曲家としても50曲以上のチェロ作品を残している。
ショパンがパリに移り住んで間もない頃、リストの紹介で知り合い、生涯にかけて愛する親友となる。作品3の〈華麗なるポロネーズ〉のチェロパートの改訂を手伝うなど、心強い音楽仲間でもあった。
〈チェロソナタOp.65〉を献呈され、1848年、ショパンのパリにおける最後の演奏会となった「伝説の演奏会」で、ショパン自身のピアノとの共演で初演している。
ショパンは死の2カ月前に、大切な使用人をコレラで亡くし、家族共々パリを離れていたフランショームに、切実な思いで手紙を送った。
「どうしてもひと目会いたい。2、3日でいいから君と過ごしたいんだ。2、3行でも良いので、どうか手紙を下さい」1849.9.17
この手紙こそが、ショパンが生涯に渡って書き続けたおびただしい手紙の絶筆となる。そんな思いに応えて駆けつけるフランショーム。
死の間際、ショパンは友に語るのだった。
「いつか君がぼくを思い出すような時があったら、どうかモーツァルトを奏でてくれないかな」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
