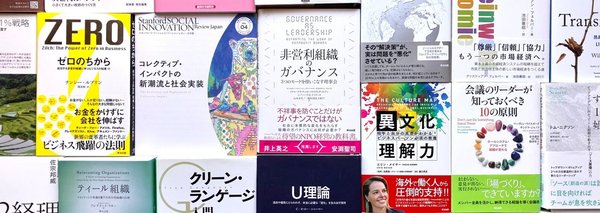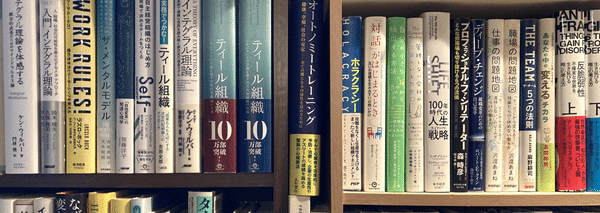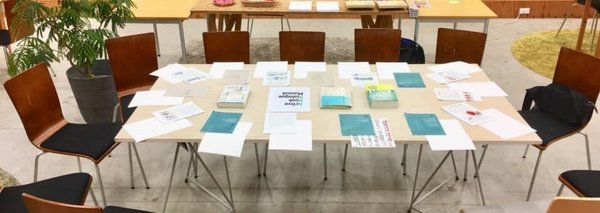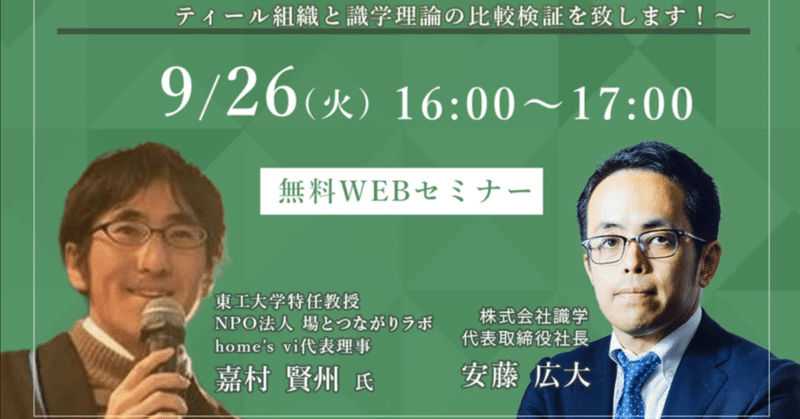最近の記事
- 固定された記事
- 固定された記事
マガジン
記事

『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』読書会レポート:ティール組織ラボブッククラブ『”パーパス探求”を紐解く〜個人パーパスってどう探るの?』
この章で特に惹かれたのは、衝動やそれを感受する感受性と身体感覚、具体的な小さなアクションの関係性です。 今回の記事は『ティール組織ラボ』が主催した、谷川嘉浩著 『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』を扱ったオンライン読書会のレポートしたものです。 今回の企画は、株式会社コパイロツトに所属するABD認定ファシリテーターの長谷部可奈さんをファシリテーターとしてお招きし、『ティール組織ラボ』編集長・嘉村賢州さんからは今回の企画の位置付けや今回の読書会シリーズに関しての紹介を、

【書評掲載】池田めぐみ、安斎勇樹『チームレジリエンス―困難と不確実性に強いチームのつくり方』:人と組織の力を高める人材開発情報誌『企業と人材』第1139号
今年度4月より、産労総合研究所が発行している専門誌『企業と人材』の書評コーナーの連載を担当することとなりました。 『人と組織の力を高める人材開発情報誌』である本誌ですが、『人を活かす組織づくりのヒント』と題して毎月、関連する書籍を紹介しております。 『人を活かす組織づくりのヒント』を提供する書籍として今回、取り上げたのは池田めぐみ、安斎勇樹著『チームレジリエンス―困難と不確実性に強いチームのつくり方』(日本能率協会マネジメントセンター)です。 安斎勇樹さん(株式会社MI