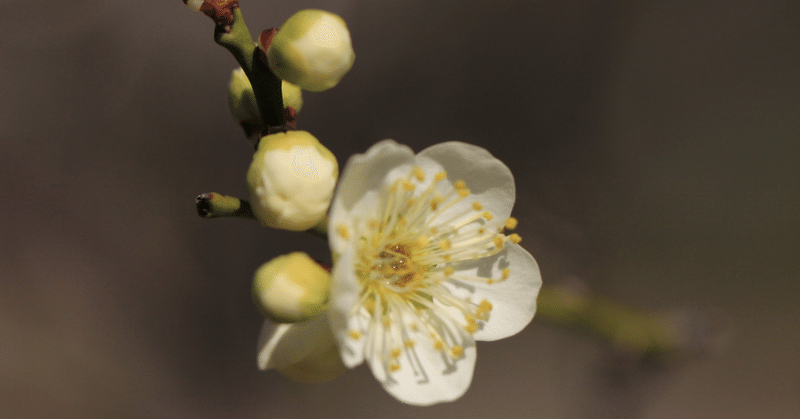
令和源氏物語 宇治の恋華 第百十三話
第百十三話 姫宮のご降嫁(一)
新しい年は例年になく盛大な御賀が開かれました。
寵愛の深い匂宮が父になるということで、恙なくあるようことさらに心をこめた帝の言祝ぎもめでたく、また裳着を迎える愛娘・女二の宮を思うと感慨もひとしおでいらっしゃるのでしょう。
帝は晴れて婿になる薫中納言を呼び寄せては何くれと御声を掛けられるので、それを陰でやっかむ者達の多いこと。
実際薫の横に並ぼうとすれば霞んでしまうような取るに足らぬ者たちばかりであるのに、薫君が慎ましく謙っているものでそれとは気付かぬのでしょうが、時の帝その人こそが薫の優れた人格や鋭利な頭脳をよくご存知なのでした。
匂宮は中君が大きくなったお腹に苦しむのを見るのが辛く、霊験あらたかという評判の寺で安産祈祷などをさせております。
何しろ初めての経験ですので、人はこのように苦しみながら新しい命を世に送り出すのだとその偉業に圧倒されるばかり。
一月の終わりになり、そろそろ子供が生まれる気配が近くなっても中君はなかなか産気づきません。
二条院には数多の僧侶が集められ、日夜読経が絶えず行われておりました。
今の匂宮は中君と子供のことしか頭になく、六条院には足も向けません。
それを夕霧の左大臣は苦々しく思っているようですが、そもそも中君は桐壺院の八の宮の姫宮であらせられるので、身分から言えば六の姫に劣るものではないのです。
世間でも中君を北の方のように見なし始めているのがなんとも気に食わないわけで、そうかといってそれでへそを曲げては天下の左大臣の度量に関わるもの、涼しい顔をして産養いの品々などを揃えているのでした。
二月になると春の除目の後に追加で任命される直物(なおしもの)が発表され、薫は権大納言へと昇進し、右大将の兼任も拝命しました。
さすが帝の婿となると待遇が違うと一目置かれる所ですが、実際に薫ほどその任に適した者はいないのです。
新大納言の誕生を嬉しく、誇らしく思っていたのは兄の夕霧でした。
異例の出世でありますが、さすが我が一門、と鼻が高く、近頃匂宮が足を向けぬ憂さなども解消するほどに気が晴れるものでしょうか。
夕霧は新任の祝いを六条院にて盛大に執り行うことを決めました。
夕霧が六条院にて宴の支度をしている間に薫は御礼言上にあちこちの邸を周り、新任披露の宴へとお誘いしているうちに二条院へも参上しました。
「薫、とりこんでいてすまぬな」
読経する僧侶たちを除けるようにやって来た薫を庭先で迎える匂宮です。
「いや、君こそもうすぐであろう。大変な時にすまぬ」
「今日か明日かという状況のようなのだが、何せ男は近くに寄れないからなぁ。心配ばかりで数日過ごしている次第だよ」
「これから新任の宴があるのだが、誘いに来たのはまずかったかな」
「おお、そのこと。さすが帝の婿になる男よ。大出世ではないか、おめでとう。このままここで心配ばかりしてるのも体に悪い、宴にでも出たほうが気が紛れよう」
宮はそのように薫と共に六条院に参上したものの、やはり中君の様子が気になって仕方がありません。
「君、やはり二条院に戻りたまえよ」
「しかし夕霧の大臣の機嫌もとらぬといけぬしなぁ」
「なに、兄上はそんな度量の狭い御方ではない。それよりも子が生まれる時に夫が側にいないとなれば後々の禍根になるかもしれぬぞ」
「それは避けたいな」
「行きたまえ。うまく取り繕っておくから」
「すまぬな、薫」
気もそぞろな宮を慮って薫は早々に宮の退出を促したのでした。
いつもふわふわと雲のように捉えどころなく、落ち着かなかった宮があのように気を揉んで父親らしい顔を見せるのが薫には可笑しく、それこそが中君の幸せに通じると信じられるのです。
盛大な宴は朝まで続き、明け方に宮の元に元気な男御子が誕生したという吉報が入りました。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
