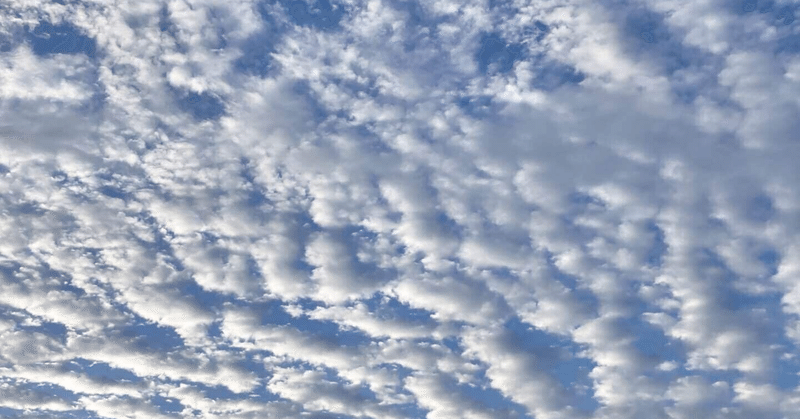
令和源氏物語 宇治の恋華 第百七話
第百七話 迷想(十七)
二条院で過ごす中君は数日の不在は仕方のないことと諦めておりましたが、あれからふっつりと半月近く戻らぬ夫を恨めしく感じておりました。
何度も誓いを重ねた匂宮を信じようと己を励ましますが、宮という殿方を知るばかりに不安に慄くのです。
しかしながら世間からは中君の物思いなど何ほどのことかと見られるでしょう。
匂宮はただの親王ではありません。
いずれは帝へと上るかもしれぬほどに尊いご身分なのです。
世間並みの身分ならば正妻を一人と定めるのが世の習いですが、後宮にて数多のお后を持たれる立場となってもおかしくないもので、宇治の山からわざわざ迎えられた中君こそ幸運な人であるよ、と娘を持つ貴族ならば考えずにはいられないのです。
さりとて中君という一人の女人の心はこの方だけのものなれば、杓子定規な見方で納められるものではないでしょう。
わたくしのようなつまらぬ者が京へなぞは来るべきではなかった。
ああ、宇治へ帰りたい。
中君は遠く秋色が滲む青空を眺めて宇治に思いを馳せておりました。
山は色づき始めた頃であろうか。
幼い時に姉と走り回った池の端には今年も桔梗が咲いたであろうか。
懐かしさに涙が湧いてきて、中君は嗚咽を漏らしました。
そうして固い決意をもってして唯一頼れる薫君に書をしたためたのです。
薫は中君からの手紙を何度も読み返し、下に置くことが出来ませんでした。
匂宮が六条院から離れられずにいるのを人から聞いてよく知っているだけに、中君が心細くあるのを思うと胸が痛むのです。
先頃訪れた折には仄かに慕情を滲ませたのをあの人はどう思っているのであろうか。
薫は中君が実は芯がしっかりした女人であるということを心得ております。
なかなか人に頼ろうとしない人が恋心をもつ男に手紙をよこすのはよほど切羽詰っているのか、何か大きな決断を下したとしか思われないのです。
そうかといって「親しくお会いして相談致したきことがございます」などと書かれていると大きく心が動かされるのは薫も男ですので詮方なきところでしょうか。
考えているばかりでは埒が明かない、と意を決した薫は二条院を訪れる旨を使者に伝えたのでした。
久しく女ばかりで過ごしていた園に薫君がお越しになるということで女房たちは明るく気持ちが華やぐようです。
加えて中君は薫君を御簾の内へお招きするという。
中君は心の裡を漏らす性質ではありませんでしたが、此の度の薫君に対しての厚遇はなにか思う処があるのではないか、と女房たちも勘ぐらずにはいられません。
それは離れてゆく夫を見限る女の決意であるのか、それとも・・・。
同じく中君の真意を読み取れぬ薫はいつものように真面目ぶった面で伺候しました。
薫中納言は淡い色合いの直衣に海老染めの下襲ねを纏い、それがなんともなまめかしく艶な風情に蝙蝠(かわほり)で涼を取っておられます。
このような御方だからこそ女人は惹かれずにはいられまい。
そう感じると共に中君は大きな賭けにでようと心を決めました。
「薫さま、どうぞ近くにお寄りください」
このように言われてはいくら自制心の強い君とて期待せずにはいられません。なかば見捨てられたような状況に陥ったからこそ芽生える女心もあるものか、と願わずにはいられないのです。
「私はいつでもあなたの味方ですよ。遠慮をなさらずに御心の裡を吐露してくださいませ」
そうして几帳の側に控える薫君の瞳には艶やかな光が宿っております。
「薫さまに隠し立てはできませんわね。どうぞわたくしを宇治へ連れ戻ってくださいまし」
やはりそういうことであったかよ、と薫は内心溜息を吐きました。
「宇治での暮らしが今では懐かしゅうございます。あの頃は物思いなど瑣末な程度でありましたもの。わたくしのような者が京に来るなど出過ぎた振る舞いでしたわ」
「宮さまは御身を忘れているわけではありませんよ」
「わかっておりますわ。ほんの少しばかり亡き姉上を宇治で偲んでもよいのではないかと思いますの。もうすぐ一周忌ですわ。せめてわたくしの手で法要を営みたいと考えております」
あの大君とは最も近しい中君の言葉ゆえ、それをすぐには否定できない薫です。
「匂宮さまがご承知のことなれば、私は喜んで御身を宇治へお連れ致しましょう」
その卒のないいらえに、やはり薫君を動かすには一筋縄ではいかぬ、と考えた中君は半ば情に訴えるように泣き伏しました。
「わたくしは迷っておりますの。このままここにあるのが相応しいのかどうか、と。いくら世間知らずといえど左大臣様の姫君と張り合う気概など持ち合わせておりませんわ。京に来てこそ己が分不相応な幸を得たと思い知りました」
「そのようなこと仰ってはいけません。あなたほど素晴らしい女人はおりませぬ」
「薫さまがそのようにお優しいことを仰せになるからわたくしは思いあがってしまうのですわ。正直辛うございます」
そうしてすすり泣く姫をどうして放っておけようか。
薫は御几帳の内へ滑り込みました。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
