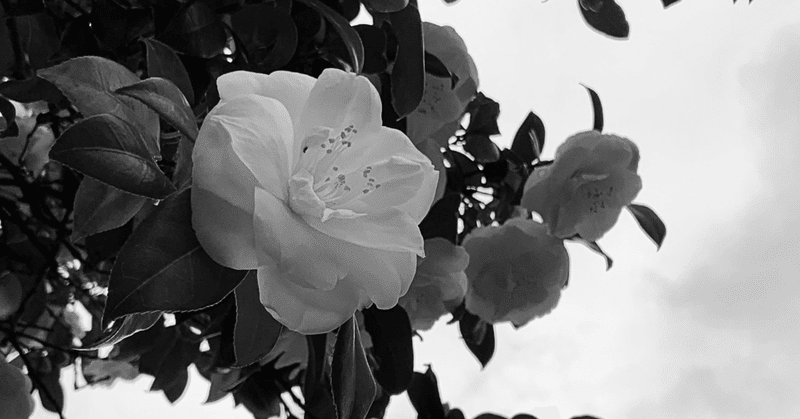
令和源氏物語 宇治の恋華 第九十二話
第九十二話 迷想(二)
京に戻り、訪れた春も薫の心を癒してはくれません。
すべてが墨色に染まるように思われて、何を見てもつまらなく、味気なく感じられるのです。
やはり私の心は半分死んでしまったようだ。
救われたいと足掻くように勤行する薫の姿を母である女三の宮の尼は哀しく眺めるばかりです。
息子が熱愛する姫君を亡くしたという話は長い留守の間に女房たちから聞かされました。しかし母として接したことのない尼宮にはどのように慰めてよいのかわからないでいるのです。
「薫、少しお話を致しましょう」
「はい」
素直に従う薫の面はやつれて修行僧のように清くあります。
「あなたが昔から仏門に帰依する志があるのは知っておりましたが、なんだか今にも世を捨てるようで不安でならないわ。わたくしの至らなさを御仏が責めておられるように思われて」
この尼宮は変わらずに言葉も足りぬ様子で己の保身ばかりを訴えるように感じる薫です。
「ご心配には及びませんよ、母上。私は世を捨てたりは致しません」
薫は毅然と言いました。
世を捨てるということは、すべての感情をも捨てるということ。
それはあの亡き人への想いも捨て去るということなのです。
それだけは耐えられぬ、と薫はまた己を情けなく思わずにはいられません。
誰かと想いを分かちたい、それには中君が一番ですが何分遠い宇治の里。
薫の足は自然と匂宮の御殿へと向かうのでした。
匂宮は端近の廂の間で筝のことを掻き鳴らしながら梅の香を愛でておりました。
「薫よ、春の香が大気に満ちてうっとりするような宵であるな」
一瞥もくれずに心のままに奏でる琴には中君への想いが込められているものか。
「よく私だとわかったな」
「わからないはずがない。薫は梅の花と同じだ。その存在を香りでしめしているではないか」
「そうだな、なんとも厭わしいことよ」
匂宮は琴を脇へ押しのけて、親しみのこもった笑みで友を迎えました。
「厭わしいか。私は子供の頃から羨ましくて仕方がなかったがな」
「隠れ鬼などしようものならばすぐに見つかったものだ。忌々しいではないか」
「それもそうさな」
匂宮が近くの女房に声をかけると酒が運ばれて来ました。
「さて薫中納言にはどのような肴をお持ちくださったかな」
「これはうっかりしていた。それではもっとも香りのよい一枝を御身に献上しようほどに」
そうして薫は庭先の咲き初めた紅梅の一枝を手折りました。
薫る中納言と言われる所以の芳香が梅の香とまつわり馥郁と漂うのはやはり不思議です。
「どうだ、京へ戻って少しは落ち着いたか?」
「うむ、私は駄目だな。何をしてもあの人を思い出してしまうよ」
そうして薫は日々の折々に思い出す大君のことなどを心に浮かぶままに語り始めました。
宇治での恋を共有できるのは唯一この宮だけなのです。
宮も親友の傷心を慮ってじっと話に耳を傾けました。
時折涙を溜めながら親身に頷く匂宮の存在がありがたく、見栄を張っていたことも莫迦らしくなった薫はとうとう秘密を話しました。
「君は驚くだろうが、実はな。大君とは清い仲であったのだよ」
「なんと」
「この手に抱いたこともあったがあの人の意志を捻じ曲げることなどできなかった」
「お前らしいな。しかし大君はお前を愛しておられたのに何故拒んだのであろうか」
「行く末の短いのを悟っていたのかもしれぬ。それゆえに中君と娶わせようとされたこともあったのだ」
匂宮はまさか大君が中君と薫を結婚させようとしていたとは露とも知らぬことでしたので、内心いたく動揺しました。
「心配せずとも中君とは何もないぞ」
「わかっているともさ」
しばしの沈黙の後、煩悶を鎮めた宮は薫を励ますように言いました。
「私は羨ましいぞ。心の繋がりが深かったということではないか。まことの愛だ」
「そういってくれるか、君」
「うむ、しかし女心とは難しいものだな」
「ふふ、まったくだ」
薫はしばらくぶりに笑みを漏らしました。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
