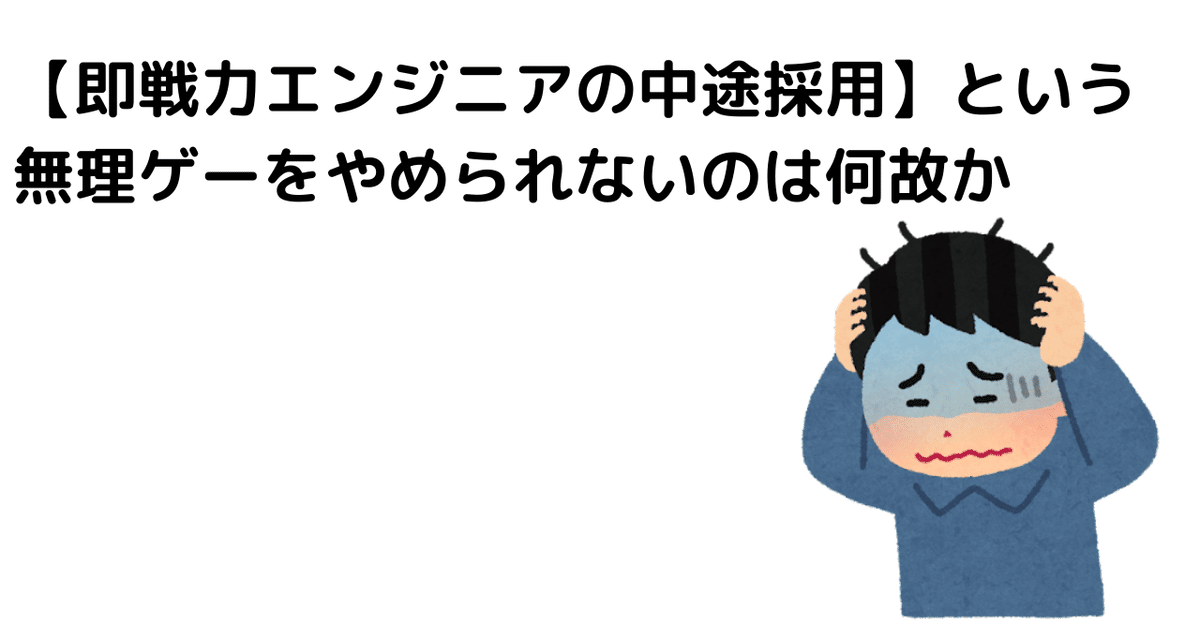
【即戦力エンジニアの中途採用】という無理ゲーをやめられないのは何故か
こんにちは、ITメガベンチャー周りに生息しているエンジニア えらぶ ゆかり @yukari_erbです。
最近SNSやらリアルの周囲の人にやらでよく
「採用市場で即戦力エンジニア人材は枯渇してるから、
そこそこの額でエンジニア雇いたいなら代案として海外人材やジュニアからの育成に力を入れないと、業界的にもう無理」
って趣旨の話をしています。
そんな話をしていると、反論として良く言われるのが
「日本向けのサービス開発に海外人材を使うなんて、上手くいくわけがない」
「手間が大きい、やりたくない」
「今すぐに活躍してくれる日本の即戦力人材を、そこそこの給料で雇えばいい」
ナドナド。
だから!
その!!
日本で即戦力エンジニアをそこそこの給料で中途採用って手段が!!!
今や無理ゲーなんだってば!!!!
・・・って叫びが、なかなか通じない場面があるな、と最近特に感じております。
「即戦力採用が無理ゲー」という話の前提条件が噛み合わないせいで、
代案を申し出ても潰され、無理ゲープレイ続行を強いられる方の悲鳴も聞こえてきます。
(個人的に叫んだこのツイートが、辺境アカウントの我が人生トップクラスで伸び続けておりまして、
世の中の皆さんどんだけ無理ゲープレイを未だ強いられてんスか・・・と切なくなるほど)
海外エンジニア採用やエンジニア育成の話をすると
— えらぶ ゆかり @Yukari_erb (@yukari_erb) October 1, 2021
「それは無理」
「そんな回りくどい方法でなくても即戦力中堅エンジニアをそこそこの給与で採用したい」
と言われる時があるんですが
そのレベルの人材需給バランスが完全に枯渇して採用市場にいないんだから無理なんだと100万回叫びたい。
どうしてこんなにも話の前提条件が噛み合わないのか。
今回はその原因の一つが
「数年前まで、実際に即戦力採用できていた成功体験のせいではないか」
という話です。
前提知識:コロナで即戦力の数と需要が釣り合わなくなった
コロナでさすがにこの国のデジタルシフトも様々な面で加速。
実際ITメガベンチャーの隅っこに在住するイチ現役エンジニアの私のところにも、いわゆるDX人材としてスカウトが来る回数が一気に増えております。
今すぐにでもデジタル化を加速させたい企業が一気に増加した一方で、この国のIT人材育成は社会的なシステムとしてきちんと整備されてきませんでした。
地方で情報系の大学院を卒業した身としてはこのへんの残念さや理不尽さを当事者として山ほど語りたいのですが、それは別のnoteにするとして。
現実として今いる日本の即戦力エンジニア人材数と、それを求める企業の数が釣り合っていない。
前者の絶対数が全くもって足りていない。
となれば
「即戦力の日本人エンジニアを、そこそこの給料でサクッと採用する」
そんな楽な手段は存在しません。
主な代案は下記のような3パターンでしょう。
代案1:むっちゃ高いレンジの給料を払う
コロナ初期のマスク価格のごとく、市場の需給バランスが崩れた希少な商品は極端に値上がりします。
エンジニアの給料も同じ。
私のもとにも「そこそこいい金額でしょ?」って言いたげな給料レンジでのスカウトがよく来ます。
が、マジで血眼になってエンジニアをとる気らしい企業はその2倍のレンジを提示してきます。
1.5倍くらいの金額にならもっとザラにあります。 バラツキがひどい。
人材の需給バランスを考慮した値付けをしないと勝負の土俵にすら乗れません。
代案2:海外人材にパイを広げる
日本だけに閉じると人材の母数が絶望的ですが、グローバルに目を向けると
・お金より日本に住む/働くことに興味がある人が来てくれる
・物価の差により、日本企業が安くエンジニア雇っても向こうにとっては高給でWin - Win
といった事情があります。
なので、メルカリさんのようにエンジニア組織の多国籍化を進めたり、LIGの久松さんが下記で紹介されているように東南アジアでオフショア拠点を作る、といった選択肢をとる企業も増えてきました。
代案3:筋のいいジュニアを見つけて育てる
人材がいないなら自分で育てるしかないわけです。
外部の研修を頼るか。
既に中堅エンジニアを確保できている一定規模の企業なら、業務の一貫にジュニアの育成も盛り込むか。
上記日経の記事にあるように、もっと企業規模の大きいところでは大学との連携も含めて育成を行っているとのこと。
Zホールディングスは21年度から5年間でAIエンジニアを5000人規模増員する。ダイキン工業は大阪大学と社内大学を設け、23年度までにAIやIoT人材を1500人育ててサービスや営業の現場に配置する。
もともと日本の大手製造業でも現場メンバー育成のための学校が数多く存在しています。 企業自身で人材育成に投資するのは、新しいようで実は古くからある話なんですね。
「日本で即戦力を雇えばいい」派が代案を潰してしまう
・・・とまぁ代案の一連を挙げましたが、実際に実行しようとなると、各方面からあーだこーだ反対に遭うとの声を伺いました。
・【うちのエンジニアに対する給与レンジはこれくらいだから、これ以上は出せない】と採用市場事情より社内事情を優先する会社
(他からむっちゃ高い給与レンジを提示されるエンジニア側からすると「そんなん知らんがな」案件)
・【日本のサービスなのに海外の人材で開発しても上手くいくわけがない】と、ハナから海外メンバーと分かり合おうとしない現場メンバー
(ただでさえIT人材足りてない我が国で、海外IT人材にそっぽ向かれたらマジで詰むんですが・・・)
・筋のいいジュニアがいるから中堅メンバーで育成してやれないか、と現場が申し出ても【中途採用で即戦力メンバー補強が先】とマネージャーに断られる
(そして一年たっても即戦力メンバー採用できなかった上に、失望したジュニアが成長できそうな企業へ引き抜かれる。二兎を追うものは・・・)
そして代案を潰した末に言うのです。
「今すぐに活躍してくれる日本の即戦力人材を、そこそこの給料で雇えばいい」
と。
・・・どうしてそんな「パンがなければケーキを食べればいいじゃない」的な答えが返ってきてしまうのでしょうか。
ましてや言われたほうは、即戦力採用エンジニアの中途採用という無理ゲーの続行を強いられるのですから溜まったものじゃないはずですが・・・。
数年前までは即戦力採用できていた成功体験の罠
即戦力エンジニアの中途採用という無理ゲーを続けてしまう理由はいくつか考えられますが、今回言及したい理由は一つ。
それは
「確かに数年前までは、日本で即戦力エンジニアをそこそこの給料で中途採用が可能だった」
ことです。
私のいるような、新興から急成長したメガベンチャー界隈周辺だと
どの会社のどのチームもほぼ中途で即戦力としてどっかの会社からやってきた人々。
僭越ながら私もそうやって数年前にSIerから今の会社に転職しました。
むしろ新卒組のほうが「あそこはxx年入社の新卒組で〜」と希少ラベルが貼られています。
前職のSIerでは中途採用組のほうがどこか浮いていた記憶があるので、まるっきし真逆です。
ああ、そりゃこの環境だと「即戦力の中途採用ができないはずがない」と思い込んでしまうのも分かる気がしました。
そんな採用環境も、コロナをきっかけに激変。
「デジタルシフトを進められる人材求む」と、どこもかしこも即戦力人材の確保に躍起です。
コロナ前の経験を元に
「前に即戦力エンジニアを中途で採用できたから、これからもできるに違いない」
と思うのは、見えざるコロナの影響を軽視していると言わざるを得ません。
昨日までの常識的手段は、明日の非常識かもしれない
また、もっと大局的な視点で日本の採用手法の歴史を眺めると違う様相が見えてきます。
かつて終身雇用が一般的だった我が国において、中途採用が一般的になったのは平成の話。
昭和の頃は終身雇用の前提のもと、企業がじっくり人材を育てることが常識的でした。
即戦力採用を中途採用できるという常識自体、たかだが直近20年前後でしか通用しない常識なんです。
歴史を踏まえると、むしろなぜ「数年前までは楽して即戦力が中途採用できた」かのかは
「終身雇用が崩壊するなかで伝統的な企業から多数放出される人材を獲得できた、一過性のボーナス期だったから」との見方も可能です。
終身雇用の崩壊が進んで伝統的企業が育成した人材を一通り放出し、コロナによる急激なデジタルシフトも相まって、どこの企業も需要に比べて希少なエンジニア人材を取り合う状況になった現代。
かつての「即戦力人材を楽して採用できる」の必勝パターンが、もはや通用しなくなりつつあります。
昨日までの常識的手段は明日の非常識的手段で、
昨日までの非常識的手段は明日の常識的手段かもしれない。
中途即戦力採用という昨日までの常識的手段が上手くいかないと感じているのであれば、
その常識的採用手段がもはや非常識に移り変わりつつある可能性を疑うべきではないでしょうか。
最後まで読んで頂きありがとうございます! いただいたサポートは記事を書く際の資料となる書籍や、現地調査に使うお金に使わせて頂きますm(_ _)m
