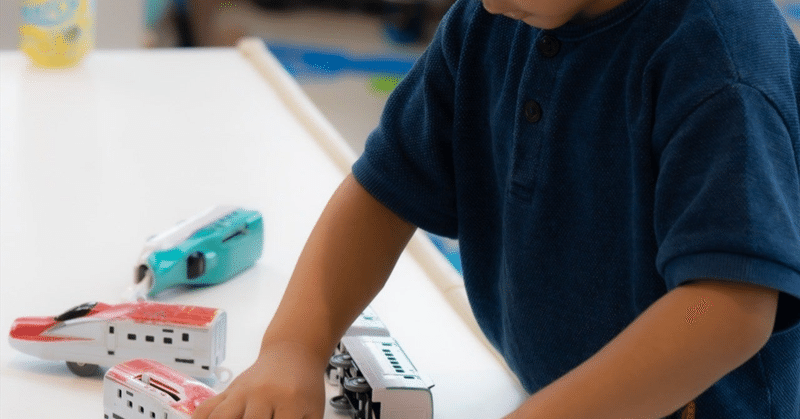
臆病な子どもの幼稚園、年少で入れないと出遅れてしまう?
子育てほど「正解がなくて迷う」ってこと、ないんじゃないかなぁと思う。
過ぎ去ってみればどうってことなかったな、ということも、初めての育児はめちゃくちゃ悩む。
すべての瞬間が未経験で、分からないことだらけ、そして相手は生身の人間で、その子の未来への責任は、ある程度自分にかかっているからだ。
子どもを産んだ瞬間から、母はそういうプレッシャーを背負って手探りの毎日が始まる。
わたしもそんな時期を経て、息子が15歳になった。繊細ちゃんなのでまだまだ目が離せない部分もあるが、人間としてはある程度ものがわかるようになり、気持ちを言語化することもできるようになった。
そんな今、悩んでいた過去を振り返ってみて分かったことを書いてみようと思う。
それは息子の「幼稚園入園」について。今となっては「そんなこと」だが、当時は死ぬほど悩んだ。そして今、そういう悩みに直面している人に、少しでも助けになればと思い、当時のことを振り返ってみようと思う。
1.警戒心の強い息子の子育てに悩む
息子は警戒心が1歳過ぎた頃から、知らない場所や同じくらいの年齢の子がたくさんいる場所を嫌がるようになった。
公園で遊んでいても、誰か来ると帰ろうと泣くし、子育て広場に行っても、終始泣く。
子育て広場の人は「たくさんお出かけすれば、慣れるわよ」と言うけど、いろんな場所に出かければ出かけるほど、警戒心が強くなり「今度はどこに行くの?」と不安げに聞くようになった。
2.幼稚園に入れるか否か、それが問題だ
そうこうしているうちに息子は3歳になり、幼稚園選びの時期がきた。周りは幼稚園選びの話題でもちきり。わたしも近所のママ友と一緒に、子どもを連れて幼稚園見学に行き始めた。
けれど周りの子は遊具に大喜びで遊ぶのに、息子だけは帰りたいと泣き叫び、わたしにくっついて離れない。
幼稚園は、入園の前年10月から申し込みが始まる。わたしはわたしなりに、息子でもやっていけそうな園を探したけれど、しっくりくる場所が見つからなかった。
それと同時に、息子はとにかく同い年くらいの子の集団が苦手なようなので、そもそもこの年齢で幼稚園に入れるべきなのか?もう1年待っても良いのかも?と思いはじめていた。
けれど当時のわたしは、「幼稚園入園が1年遅れると、周りから遅れを取ってしまう」と思い込んでいたので、さらに悩みは深まった。
「最初はみんな泣くけど、すぐ慣れるから大丈夫です」と、どの幼稚園でも言われた。けれど、どこに行っても拒否反応を示す息子を、無理やり幼稚園に行かせる気になれず、「年少で入れなくちゃ遅れる」「でも今はまだ早いかも」の狭間で悩みまくっていた。
旦那は「そんなの考えすぎだよ」といって取り合ってくれず、余計にひとりで抱え込んでしまい、もうたぶん育児ノイローゼ気味になっていたと思う。
3.「焦らなくて大丈夫よ」と言われて泣いた日
そんなとき、広々とした園庭を持つ幼稚園に、遊びがてら息子を連れて行った。ここは広いし、いつでも園庭開放をしていて、小さい子が苦手な息子でも大丈夫。すいている時間に訪れて、園長先生と話すことができた。
わたしが息子のことを相談すると、園長先生は「そんなに無理して早くから入れなくて大丈夫よ」と優しく声をかけてくれた。
園長先生曰く、年少さんで入園してくる子のうち、ほとんどの子はすぐに慣れて楽しく過ごせるけれど、おうちに帰りたくて、ずーっと窓の外を見ている子もいるとのこと。そういう子を見ると、もう少しお母さんと一緒でも良いのかなと思います、と話してくれた。
「子どもはお母さんとしっかりつながって、もう大丈夫と思ったらちゃんと自分から離れていくから、焦らなくて大丈夫。安心してあと1年一緒にいてあげてね」と言われて、悩み続けていたわたしは思わず涙が出た。
そして、幼稚園申し込み日を直前にして、入園を1年遅らせようと決心することができた。
4.プレ保育で親子分離の準備
ちょうどその頃、近所にプレ幼稚園のようなクラスがあることを知った。YMCAで週に3回、午前中だけ。おそらく息子は幼児がたくさんのカオスな状況が怖いのだろうと思っていたので、少人数で時間も短い上に、リーダーが2人もついてくれるという条件なら、息子もやっていけるかなと思った。
たまたま知り合いのママ友も、幼稚園を年中から入れたいと思っていたようで、年少の入園を辞めて、ママ友を誘ってそのクラスに入ることになった。
当然、最初の数回は泣いたけれど、たった2時間なので、息子もすぐに慣れた。こちらも相当心配だったので、毎回子どもの様子を事細かに報告してくれ、帰りに心配なことを相談できるので、それも安心材料になった。
5.いよいよ年中から幼稚園入園へ
1年間、母子分離の準備をし、晴れて年中から幼稚園に入園した息子。「焦らなくて大丈夫よ」と声をかけてくれた園長先生のいる幼稚園に入園した。園長先生はこの界隈では「カリスマ園長」と呼ばれていて、わたしのようにこの園長に感銘を受けて入園を決める人が多いとのこと。
前年、園長の言葉に背中を押されて年中からの入園を決めて、いよいよ登園初日。全然怖くないからね、怖いことがあったら先生に言っていいよ、どうしていいか分からなかったら先生にくっついてればいいよ。とありとあらゆる「大丈夫」を伝え、登園初日を迎えた。臆病な息子はなんと、登園初日のバスで泣かずに行った。感動した。
それから2年、広々とした森のある幼稚園で、カリスマ園長と暖かい先生に見守られ、おとなしい息子も徐々に心を開いて幼稚園生活を楽しむことができた。
6.息子自身に当時のことを振り返ってもらった
そんな息子ももう中学3年生。いまだに警戒心は強く、新しい場所が苦手だけど、小学校、中学校と友達もでき、まあ集団行動に疲れつつも、それなりに学校に通っている。
息子に幼稚園時代のことを聞いてみると「小さい子どもがごちゃごちゃしているのが怖かった」そうだ。
大勢で遊ぶこともあまり好きではなかったという息子。「みんなで鬼ごっことか面倒くさかった」と言っていた。
いまだに人の多いところは疲れるようで人混みにも酔いやすいので、そういう部分が、子育て広場や幼稚園を嫌がっていた原因だったのかな、と今になって分かった。
7.その子にとってベストな選択ができたらいいな
幼稚園を年少から入れるかどうか。今となっては、なんであんなに悩んでいたのだろう?と思うようなことだけど、当時はそのことが息子の将来を左右してしまう気がして真剣に悩んでいた。
きっと、現在、そのくらいの年齢のお子さんを持っているママさんも、似たような悩みを持っているかもしれない。
だからわたしの当時の悩みと、振り返ってみて思うことを書いてみた。
子どもは千差万別。そして正解もない。さらに母親の性格や価値観もさまざまだ。だから母親ができることは、子どもの個性をできるだけ客観的にしっかり見て、その子にとってベストと思う育て方、選択をするして、もしそれで違うなと思ったら別のやり方を模索する。そうやって試行錯誤をしていくしかないのかなぁと思う。
わたしも今は今で試行錯誤中だ。あと5年で成人する息子が、自立や成長していけるように、母であるわたしは何をしてあげられるか?がいまの問いだ。
地味に幼児の頃より問いの難易度は上がっている。けれどやっぱり子育てって、それの連続で、それがしんどくもあり、ありがたくもあり、母である醍醐味であるなぁと思う今日この頃だ。
今日もお読みくださりありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
