
<書評>『Black Magic(黒魔術:オールブラックスラグビーの歴史)』
『Black Magic』 Graham Hutchins著 1988年 MOA Publications New Zealand

1987年の記念すべき第一回ラグビーワールドカップに優勝し、翌年のブレディスローカップも防衛したNZオールブラックスの輝かしい歴史を、1970年代以降から1988年までの期間を限定して取りまとめたもの。
著者は、NZの著名なラグビージャーナリストで、オールブラックス及びNZラグビーについて精通しており、本書の他にも多数の著書がある。
この中で第一回ラグビーワールドカップがなぜ開催にこぎつけられたのかを、著者が簡潔に取りまとめているところ、私がラグビーマガジンなどを通じて間接的にしか把握していなかった事柄が、当時の事情を熟知する評論家による説明を読むことで、ようやく様々な疑問や曖昧な点が氷解できた。そのため、関連部分を私の拙い翻訳でご紹介したい。
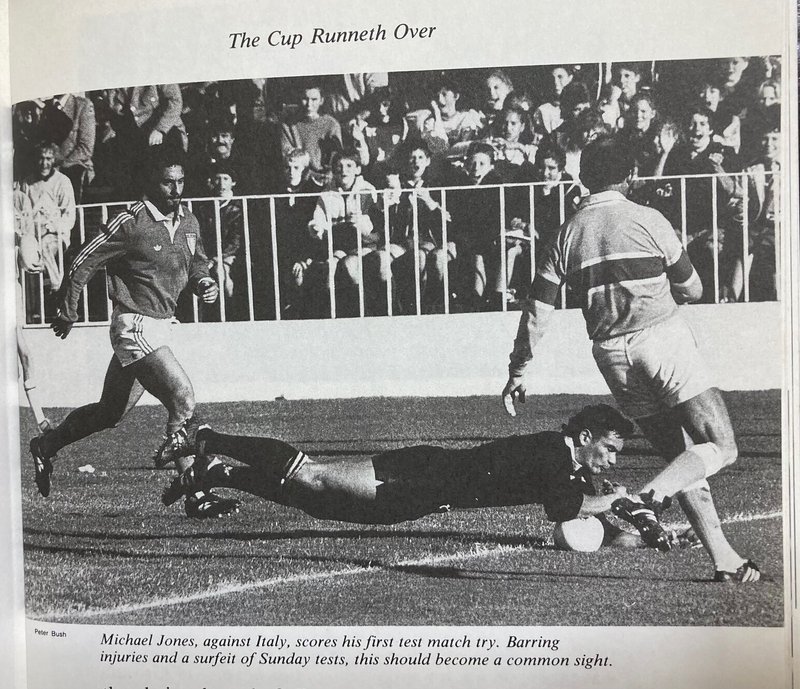
**********
第10章 ワールドカップの始まり
ワールドカップの構想は、数年間にわたり漂流していた。保守的な空気に閉じ込められている中で、支配的な上層階級(注:イングランド協会などの守旧派ラグビー協会)による疑いなき障壁があったが、ワールドカップ構想に対して守旧的な姿勢を維持していくことに対しては、変化を受け入れざるを得なくなっていた。(守旧派による)悪夢のような管理体制の網は解かれるようになる。(しかし、ワールドカップ構想に伴う)殺人的なほど過酷な(準備)期限、驚くように(多い)ロジスティクス(事務作業)がある中で、ラグビーにもワールドカップを実現したいという思いは、一般の人々の中にも浸透してきた。そうした普通の要望に対する(管理組織からの)回答は、守旧的な観点による「うまくいかない」というものに終わっていた。
サッカーは、4年ごとに開催されているワールドカップで、まぶしいくらいに輝いていた。その興奮(と盛り上がり)は、参加各国に大きな残像(成果)のすべて(の権利)をもたらした。また、その高度なドラマ性を持つサッカーワールドカップの決勝は、(世界中に対してその魅力を)説き続け、(物語を)ひらめかせ続けた。そうして、ラグビー界の人々は、ラグビーワールドカップ(RWC)開催へ向けた検討を継続すべきと思ったのだ。
そして、世界ラグビーの母体であるIRB(国際ラグビー連盟、現在のWR⦅世界ラグビー協会⦆)は、頑固な態度を維持する中で、少しだけ公平に話を聞くことを認めた。一方でIRBは、1958年に馬鹿げた布告を出していた。それは、数ヶ国が参加する大会開催は、不法であるとされていたのだ。
また、北半球所属のラグビー協会(注:イングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズ)からは、IRBによるRWC実現可能性を継続して無視すべきと提案していた。しかし、(RWCが)ラグビープレヤーにとって最も好ましい構想であるのは、目に見えて明らかなことだった。IRBは、1983年にRWC構想については否定的である旨を(改めて)表明したが、プロ化という観点からは、多くのプレヤーにとって(RWC)は、魅力ある構想になっていった。
アマチュアラグビー界は、ワールドカップを必要としたのだ。全てのラグビープレヤーは、他のスポーツのゲームを見た経験から、そこに良い見本があると考えた。ラグビーリーグにはワールドカップがあった。クリケットは、(それまでの一週間かかる試合時間を短縮して)壮観な一日だけの試合に変化していた。
ラグビーにとって、変わるべき時が既に来ていた。過去の歴史からの(ワールドカップによる)影響という事実を無視していれば、ラグビーは、しっかりとした神話的なアピール力を失うだけでなく、より活気に満ちた(観客の)選択の結果、(ラグビーという)ゲームへ導くための競争力も失うだろう。
南半球所属のラグビー協会(NZとオーストラリア)は、(北半球協会よりも)成功にこぎつけた。1983年、NZ協会とオーストラリア協会の連合は、ワールドカップ実現に向けた草案を強く主張した。IRBは、(NZとオーストラリアという)二つの角による攻撃に当惑したように見えた。そして、より深い分析と計画立案の提出を(NZとオーストラリアのアンザック連合に)求めてきた。その結果、ついに1985年、青信号が灯った。最初のワールドカップ開催に向けて、IRBの頭の中にある地雷原を通過できたのだ。
しかし、ワールドカップ開催組織は、多くの驚くべき障害に直面する。(わけても)スポンサー探しが苦しい課題だった。一方TV業界は、31~32ゲームの生中継実施を決めたが、これは(スポンサー探しにとって)大きな前進だった。そして、全体を漏れなく(TVが)カバーする野心が浮上した中で、プレーとゲームの質を維持するための担保をどこで得るかが問われていた。最終的に、日本の電信会社のひとつであるKDD(現KDDI)がメインスポンサーを申し出(ることで解決し)た。(その背景には)熱狂的な日本のラグビー関係者が、この決定をするための明らかに大きな一部になっていた。この結果、ワールドカップ大会開催の活力(体力)は、保証された。
**********
この「熱狂的な日本のラグビー関係者」とは誰なのかが、ちょっと気になった。単純に想像できるのは、当時人気絶頂だった大学ラグビーの関係者(早慶を中心に日本の政財界にOB人脈を持つ)を基盤とした、社会人ラグビーチームを持つ大手企業だろう。そして、ラグビー議員連盟を中心とする国会議員たちだろうか。ただ、こうした人たちは、対抗戦に象徴されるように大規模なトーナメント戦を嫌い(大学選手権は支持しているが)、伝統的な毎年の対抗戦を尊重する文化を維持している。つまり、北半球所属チームと同じ意見を持つ人たちだったので、南半球所属チームが熱望するワールドカップ開催を後押ししたこととは、考え方が相違している。
これらの北半球協会は、毎年のファイブネーション(フランスを加えて5チームになり、その後イタリアを加えてシックスネーションズに拡大)が、そのまま「ワールドカップ」に相当すると考えていた一方、ブリティッシュアンドアイリッシュライオンズが、NZ・オーストラリア・南アフリカの南半球に交互かつ定期的に遠征すれば、それだけでラグビーという「興行」は十分すぎるほど成立していたこともあり、敢えてワールドカップを開催する経済的な必要はなかった。また、もし開催して北半球協会が上位に入らない、南半球協会との実力差を見せつけられてしまう結果となることを恐れていたと思う。
こうした上述の抜粋説明のとおり、第一回大会はNZとオーストラリアの共催になったのだが、第一回大会が経済面でも大成功を収めると、もうKDDのスポンサーは不要となる一方、北半球から多くのスポンサーが出てきた他、北半球で開催することを熱望するように急変していくのが、第二回大会以降の歴史となっている。そして今やサッカーワールドカップ、オリンピックに次ぐ世界で三番目に(経済的に)大きな「興行」にRWCはなっているが、こうした諸事情を考慮すれば、第一回以降から既にラグビーのプロ化という方向性は厳然と内在していたわけで、むしろ様々な抵抗により、1995年の第三回大会までプロ化の実現が遅れてしまったというのが実情だろう。
こうした世界のプロ化に向けた諸事情を知らず、また大きく立ち遅れていた日本は、大学ラグビーの一時的な盛り上がりと経済効果に満足することで、一種の鎖国状態になっていた。その後、2003年頃にようやく世界水準を目指すようになり、これが実現したのが2015年であり、最終的な成果を得たのが2019年だったとみなせるだろう。
ところで、本書の最後はオールブラックスが1987年に日本遠征した結果で終わっている。ご承知のとおり、この日本遠征でオールブラックスは日本との対戦をキャップ対象試合にしなかったばかりか、圧倒的なミスマッチとなるスコアで圧勝した。そのため、オールブラックスが日本遠征したことについて、NZでは批判的な意見が多かったという。しかし筆者は、そもそも1987年のオールブラックスと良い勝負ができるチームは当時ほとんどない上に、サイズ不足を克服し、アメリカ進駐政策で形骸化された神風特攻隊に象徴される強い精神力を発揮できれば、日本は1987年RWCのワラビーズ戦で見せたような優れたプレーを発揮できたと述べている。
また、世界のラグビー界からは「日本の登場が求められているのだ」と強調している。これは、RWCでラグビーが世界的スポーツとして認められた一方、オールブラックスが一躍世界のアイドルになったことも関係している。オールブラックスが世界のラグビー界で継続して輝くためには、日本のようなスキル溢れるチームが求められているというのだ。そして著者のこの願望・希望は、2015年RWCでようやく実現した。それまでには、実に28年間もかかってしまった。
その一因はなによりも日本ラグビー界が現状に固執しすぎたことにある。日本ラグビーは、トップリーグからリーグワンの創設、選手契約のプロ化、外国人選手枠の拡大、代表の多国籍軍化、オリンピックのセブンズ強化、女子ラグビーの強化など、世界から見れば周回遅れとしか見えない速度でしか進化できていない。日本ラグビーを本当に強化・進化させるのであれば、もっとスピードを上げて必要な改革を行い、もっと前に進むことが求められているのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
