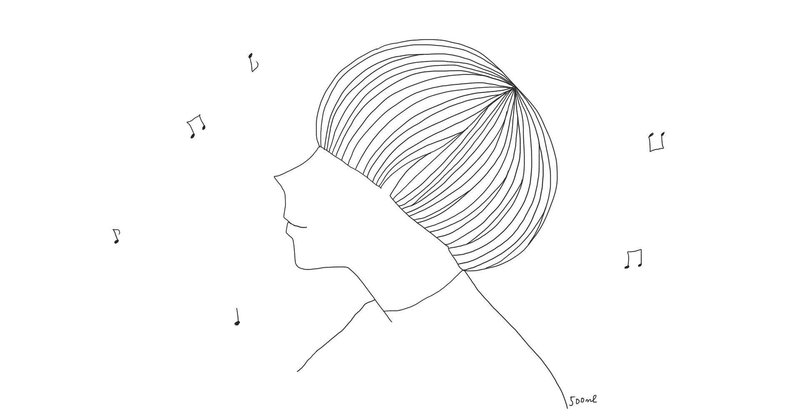
2021年に向けて #おとあそび日記
2020年も明日で終わりですが、2021年は「おとあそび」していこうと思っています。今月はこのことをずーっと考えて準備してきたのですが、自分のためにも整理しておきたいので書きます。いつもより長くなります。
--- ☕️ ---
「おとあそび」とは
文字通り「音遊び」のことです。「音楽がつくりたい!」とか「ビートメイクしたい!」という表現もできるのですが、僕の中での感覚としては「音遊び」が一番しっくりきています。
「おとあそび」とひらがな表記しているのは、(自分のために)ゆるーい雰囲気をだしたいのと、経験ゼロのど素人からのスタートなので「まだ何にも変化していない」という意味合いも込めています。
なぜ次は「音」なのか
2年ブロガー(テキスト)、3年Youtuber(動画)と経験してきたので、次は「音」かなぁと好奇心がこっちに向いています。動画制作で音の大事さは学んだので、ある意味で「音」に片足つっこんでいたのですが、いよいよ「音オンリーでコンテンツをつくってみたい!」という感じになりました。
現在の音声市場
昔からポッドキャストはありますが、最近になってVoicy、stand.fm、RadioTalkなどの「音声版SNS」が盛り上がりを見せています。コメント機能があったりライブ配信ができたり、リスナーとの交流がしやすくなっている印象です。
Youtubeに比べると「稼げるのか?」という部分ではまだ不透明ですが、収益化プログラムをstand.fmが8月に、RadioTalkが9月に発表。Voicyは月額課金サービスを9月にリリース、来年には収益化プログラムも開始するようです。一部のトップ配信者であれば「生計を立てる」というのが見えてきていそうな雰囲気があります。
今からの参入タイミングとしては🔵ブルーオーシャンではないけど🟢グリーンオーシャンくらいかな、まだ過ごしやすそうな水温かな、くらいに思っています。
ちなみに海外では日本より先行してポッドキャストが盛り上がってきていて、広告単価がYoutubeの10倍という話もあるそうです。
YouTubeのように10万人100万人のオーディエンスが必要なく、副業(Side Hustle)規模として1,000〜2,000人のリスナー規模はかなり現実的な数字。
じゃあぼくはどう発信していくのか?という話なのですが、その前にまず、ぼくが感じている「質を決める3つの要素」の話をします。(さっき思いついたので内容は粗いです)
質を決める3つの要素
「トーク」「内容」「編集」の3つかなと今のところ思っています。「トーク」は喋るスピード、トーン、滑舌、声質とか。「内容」は「情報」とも言い換えられて、その人がどれだけスキルを持っているのか?にも依存しそうです。尺(時間)も「内容」に含まれます。
音声コンテンツで不思議なのが、どれだけ貴重な情報をしゃべっていても、その人の声質とか喋り方が好きじゃないと聴くのをやめちゃうことがあります。逆に内容が薄くてもトークがうまい人は、結果的に面白い音声コンテンツをつくれそうなイメージです。
動画制作をしていたとき、「音」にはけっこう気をつかって編集していました。これは「画質が粗い映像」と「質の悪い音」を比べたときに、後者が圧倒的にインパクトが強いなと思っていたからです。例えるなら、前者は隣でグチを聞くくらいのもので「まぁ聞いてあげるよ」と我慢できるけど、後者はいきなりパンチくらうくらいの不快さがあるのですね。
で、最後の「編集」ですが、これは編集ソフトを使うって意味です。音素材を集めて、それをマッシュアップ料理して面白いコンテンツにする、という感じです。
これはプロダクションとかがやっているイメージです。海外だとGimlet社のオーディオドラマ『ホームカミング』(Amazon Primeでドラマ化)とか、NYTの『Rabbit Hole』とか。日本だとJ-WAVEがSPINEAR(スピナー)というサービスをやっていて、どの番組もクオリティがやばい高いです。
ただ、この「編集」でクオリティを上げようとしている個人はあまり見かけません。これはたぶん、発信側としては「編集なしで投稿がラク」、聴く側としては「無加工の生の声が聴ける」という魅力が大きくて、編集しちゃうとこの魅力が損なわれる雰囲気があるからかもしれません。
音で編集して(遊んで)みたい
ぼくは実はこの「編集」に一番興味があります。日々音声コンテンツを聴いている自分としては「無加工の声」の魅力はすごくわかっているのですが、「編集」の先にある面白いコンテンツを自分でつくってみたいな、という好奇心が強い。ここはまだイメージが全然わいていないので、まずはスタートしてみて、だと思いますが。
一番イメージとして近いのはNYTの『Rabbit Hole』です。さすがNYT!って感じで、さまざまな素材を使うなかで音質を使い分けることで聴いていてレイヤーが感じられて、かつ臨場感がある。全編英語ですが、気になる方は聴いてみてください。
おとあそびの発信場所
前置きが長くなりましたが、「おとあそび」は音声版の「おとあそびラジオ」、テキスト版の「おとあそび日記」、動画版の3つで発信していく予定です。
音声版は、聴く側の人がいつも聴いているプラットフォームで聴けるように、Apple Podcast、Google Play、Spotify、Himalaya、Amazon Music、stand.fmなどでマルチ配信します。stand.fmにはコメントやライブ配信機能があるので、リスナーとの交流がしやすそうです。
テキスト版はこのnoteです。というか、このnoteが「おとあそび日記」に含まれるので、すでにテキスト版はスタートしている感じです。
来年1月に音声版「おとあそびラジオ」をスタートします。(すでに自分のなかで日付は決めてあるのですが、ここで明言するとプレッシャーになりそうなのでやめておきます。笑)
動画版はYoutubeの予定ですが、これはタイミングをもうちょっと考えます。まずは音声版をしばらく継続してみて、なんとなくなペースがつかめてきたところでコンセプトなど詰めていく予定です。
おとあそびの発信内容
「おとあそびラジオ」のコンセプトは、経験ゼロのビートメイク初心者がSpotifyにアルバムを公開するまでのプロセスを聴いてもらう、です。はい、とりあえずの大きな目標は「Spotifyに楽曲を公開すること」です! ブルブル
これ、ぱっと聞いて自分でも「面白くなるのかな?」と不安で仕方ないのですが、色々と考えてみた結果これになりました。
大きかったのは、アルのけんすうさんの「プロセスエコノミーが来そうな予感です」という言葉。
「アウトプット・エコノミーが一定の規模まで到達したことで、もう差別化するポイントがプロセスにしか無い」となったからなのかなと考えています。
アウトプットの差がなくなったことで、価値を出すならプロセス、という感じになっているのではないかと。
そもそも僕は音楽経験がほぼゼロなので、33歳のこのタイミングで「楽曲」としてのアウトプットクオリティで勝負するのは無理ゲーな気がしたので、「じゃあ上達のプロセスをコンテンツにするか」となりました。
プロセスエコノミーが来るかどうかは置いておいても、プロセスで稼げるようになったらめっちゃすげー!という興奮があるので、挑戦してみようかなとも思いました。
この「プロセスを面白くする」というのは、まだ全くといっていいほどイメージがわいていないので、来年スタートしてみて試行錯誤しまくる感じです。最初はトークだけの投稿もあるだろうし、そこに少しずつビートメイクの練習音も入れていって自分のスタイルを作りたいところです。
あとこれはあくまで僕の「音楽つくりたい!」という1つの側面にすぎないので、サンプリングして周囲の環境音で遊んでみたり、外で収録してみたり、編集してみたりと、少しずつ「おとあそび」していきます。
--- ☕️ ---
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。これを読んで少しでも「おもしろそう」「応援するぞ」と思った方は、主にツイッターとnoteで発信してますのでフォローいただけると感激して飛び上がります。
ではでは、良いお年を。
いただいたサポートは、おいしいご飯か、さらなるコンテンツ制作の費用に使わせていただきます。
