
平安京はブラックな職場か?―貴族社会を支えた下級官人― 井上幸治
皆さんは「平安貴族」と聞くと雅で華やかなイメージを持つかも知れません。ただし、それはほんの一握りの上級貴族のお話。
平安京でのお仕事を支えていたのは、多くの身分の低い「官人」と呼ばれる人々の働きがあってこそ!!
そんな下級官人にスポットを当てた『平安貴族の仕事と昇進―どこまで出世できるのか―』。
井上幸治先生の軽快なエッセイをぜひご堪能ください。
一〇~一二世紀頃の平安京には、藤原道長や紫式部のような、誰もが知る人びとをはじめとする、多くの貴族らが暮らしていた。そうした身分の高い公卿(一~三位の位階をもつ)や殿上人、女房といった人びとは、広くイメージされているような優雅な平安文化を、十分に享受していたであろう。しかし当然ではあるが、そうした生活ができたのは、ほんの一握りにすぎなかった。
平安京で仕事をしている人びとの大半を占めているのは、諸大夫身分(位階は四・五位)・侍身分(六位以下)に属する者たちであった。平安時代の政治や経済は、彼らの働きに支えられていたのであるが、なかでも侍身分の官人について、具体的な様子は、なかなかイメージしにくいのではないだろうか。平安時代中期になれば、藤原道長の記した『御堂関白記』をはじめ、質・量ともにすばらしい史料が、いくつも残っている。それらによって、公卿や諸大夫の働きは、ある程度明らかにできる。だがそうした史料においても、侍身分の官人たちの情報は、断片的であることが多く、詳細を明らかにすることは容易ではない。
こうした史料上の制約もさることながら、実情に迫るには、別の問題も存在していた。それは例えば、次のようなものである。
『類聚符宣抄』という史料があり、その第七(左右弁官史生可任内官事)には、永延三年(九八九)五月一七日付の宣旨が収められている。そこでは、当時の太政官史生の仕事を次のように記している。
書き上げる文書は、二〇〇~三〇〇張もあり、それが連日であったり、隔日であったりする。書写すべき長案も同じようにたくさんあり、それが山のように積み上がっている
太政官史生というのは、太政官で勤務する下級の官人であるが、位階はもっていても六位、そのうえ毎日勤務しているわけではない。そうした立場ではあっても、出勤した日にはいつも、大量の仕事が待っているというのである。では、そうした勤務に対する報酬は、いかほどだったのだろうか? この宣旨には、その点についても史生本人の言葉が載せられている。
一〇年以上、がんばって働いても、与えられる官職は、「最亡国」の二分(目)でしかない。ちょっと抜擢されることはあっても、年齢も重ねているので、それ以上のことは望めない。だから、在職者は、将来に希望がもてないし、史生になってがんばろう! と思う若者もいない
おおむね、こういった内容が記されるのだが、仕事はつらく、でも報酬はたいしたものではないという。これらが事実であったならば、なんと悲しいことだろうか。
この宣旨が出されたのは、ちょうど一条天皇の時代である。摂関政治や国風文化といった言葉はイメージしやすいが、そうしたものごとのまさに最盛期に出された宣旨といってもよいだろう。そこに記された史生の言葉が、これである。高位高官の者たちによる文化・政治の華やかさの陰には、それを支える身分の低い官人たちのブラックな仕事環境・条件があったことを知ってしまうと、華やかさも違ったものに見えてくるのではないだろうか。
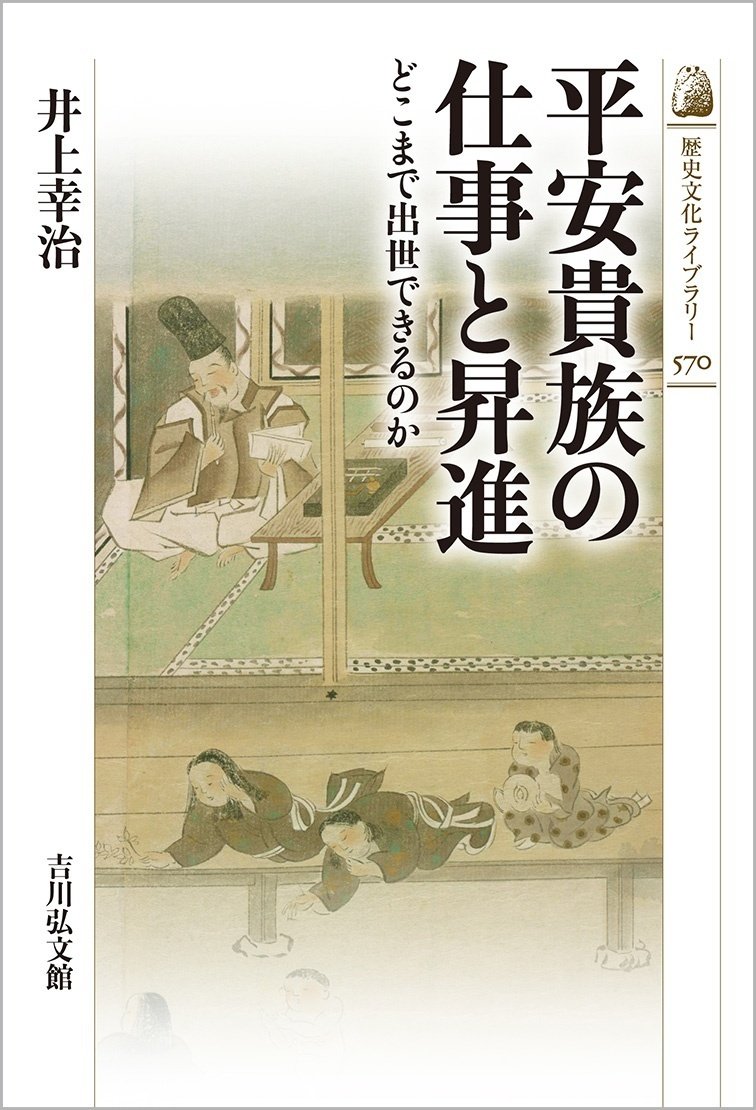
ところでこの宣旨は、太政官の奏状に応じる形で出されているのだが、この奏状では、太政官史生が期待通りの仕事をしていないことを指摘し、その原因をこうした冷遇に求めている。そして、史生の待遇を改善すれば、業務成果も改善されるはずだと主張するのである。こうした提案をしたのは、宣旨中にも名を記される大外記中原致時であろう。宣旨は、致時の提言をそのまま採用し、史生の待遇を改善するよう命じている。
中原致時は、なぜ、こんな提言をしたのであろうか。少し詳しく見ておこう。実は致時は、この宣旨が出される直前に五位大外記となっている。つまり、史生たちの管理職に就いたばかりであった。管理職となった致時は、保管してあるはずの文書がなかったり、保管してある文書も破損したまま修繕せず、放置しているような状況を見て、驚いたのだろう。こうした文書の不備は、将来の職務遂行に不安をもたらすものであった。すぐに改善しなければ、管理職である致時本人も責を問われかねない。そこで致時は、史生の待遇を改善し、史生が意欲的に勤務に励めるように改め、期待通りの業務成果をもたらそうと考え、奏状提出へと進んだのであろう。
このように経緯を推測してゆくと、中原致時という人物は、仕事をきっちり遂行しようというモラルを備え、また部下思いでもある理想的な上司のように見えるだろう。しかし本当にそうなのだろうか?
よくよく確かめてみると、おかしなところがあらわれてきた。待遇の改善というのが疑わしいのである。というのも、元来、史生の昇進は次のようになっていたという。
史生 → 外国の目 → 内官の主典
これをこの宣旨では、次のようにするよう命じている。
史生 → 内官の主典
つまり「外国の目」を経由させることを止めたのであるが、最終的に内官主典(諸司の令史など)に任じる点は変わっていない。昇進が少し早くなるのは確かだが、上限は変わっていないのである。しかも、こうしたバイパス人事は、条件付きで既に行なわれていた。改善後の新制度というのも、既存のものなのである。
どうやら、致時が冷遇だとしているものは、いわば原則である。実際には、ショートカットするバイパス人事も行なわれていた。とはいえ、パイパス人事は条件付きで行なわれていたから、無条件で全員が享受できるようになったことは改善に違いない。だが、この改善によって、史生たちが仕事に励むようになるかといえば、それは違うだろう。彼らの実態は、ほとんど変化していないのだから。
さらに、そもそも前提となっている仕事量の多さというのも、本当なのだろうか。仕事量が多いのであれば、改善すべきは待遇ではなく定員では? と思うのだが、いかがだろうか。もしかするとこの点においても、提言が採用されやすくするために、「盛っている」可能性があるようにも思える。
宣旨の文章だけを眺めていると、史生の待遇は改善されたかのように見えてしまう。しかし周辺事情をよく確認してゆくと、たいした改善ではなかったことがうかがえるのだ。結局のところ、身分の低い官人らの待遇は、簡単には変わらなかったのではないだろうか。それでも、いかにも改善したかのような虚飾を講じることは、いかにも平安貴族らしく見えてしまう。もちろん、こうした虚飾は、身分の高下に関係なく、官人たちの誰もが行なっていたようだ。なぜこんなことをしたのか、事実をそのまま書かないのはなぜなのか、疑問はつきないが、実情に迫るためには、こうしたトラップや、深読みのしすぎなどに気をつけながら、慎重に史料を読み解いていかなければいけないだろう。
こうした事例は他にいくつも探し出すことができ、『平安貴族の仕事と昇進』でも紹介している。本書を通じて、政権を支えていた侍身分の官人たちのような人びとにも、関心をもってもらうことができたなら、望外の幸せである。
(いのうえ こうじ・佛教大学非常勤講師)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
