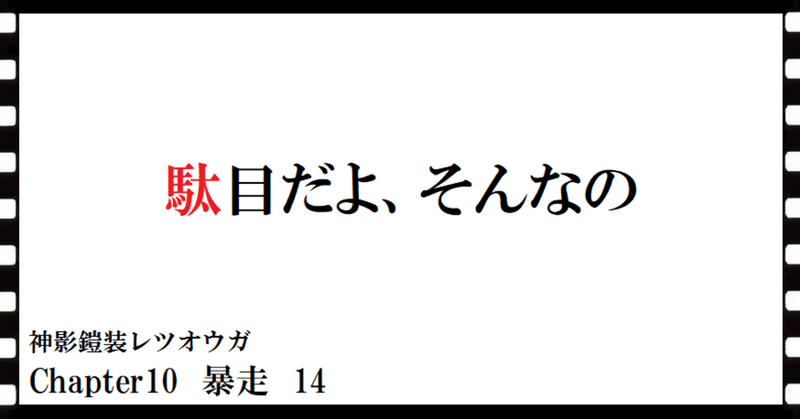
神影鎧装レツオウガ 第九十三話
Chapter10 暴走 14
ぐちゃ、ぐちゃ、ぐちゃ。
その音は、辰巳《たつみ》の耳へ、酷く明瞭に届いた。
ぐちゃ、ぐちゃ、ぐちゃ。
その音を、感触を、辰巳は良く憶えていた。
それは、潰れる音だ。
肉と、血と、骨が。
混ざり合って、ひとつの、よくわからない、赤黒い、カタマリになってしまう音だ。
そう、憶えている。
二年前。辰巳はその音を、他でも無い自分の手で、鳴らしたのだから。
「……、、ぁ。か」
辰巳は動かない。動けない。
あれだけ固く握り締めていた拳すら、力無く解けて虚空を泳いでいる。あまりに無慈悲な眼前の光景へ、待ったをかけるが如く。
しかして、現実とは往々にして無情なものだ。
咀嚼を止めた巨大な顎《あぎと》は、一つごくりと喉を鳴らした。そうして酷くゆっくりと、上空へ戻っていく。
ぼと、ぼとぼと。
その弾みに、唇の端から三つ、何かが落ちた。
「……あ。」
それは、手首と、両足だった。
手首は右だった。足は膝から下で、まだビーチサンダルを履いていた。
それらは無造作に、白い雪の中へ落ちて転がった。
拳を解いてなお、辛うじて掲げられていた辰巳の両腕が、だらりと下がった。
「……」
ず、ず、ず。
みしみしと、ぎしぎしと。
雪原が、霊泉領域《れいせんりょういき》そのものが、悲鳴のような鳴動を始めた。
だが、それも当然だ。ローブの男に掌握されていたとは言え、依然として風葉《かざは》はこの場、フェンリルの中枢だった。
それがなくなったとあれば、この光景はむしろ当然の帰結ではあったのだ。
「く、く。くは、は」
そんな帰結の引金を引いたローブの男は、腹を抱えていた。さも楽しげに。
その声を、辰巳は聞いた。視線を、そちらへ向けた。
くぁーっはっはっはっはっは!! いやはややっちまったよ我慢できずにさぁ! まあ安心しとけよ、あれはあくまで精神体! いくら傷つこうが身体の方はピンシャンしてるさ! もっとも、精神の方にどんな後遺症が残るかは分からんがな! さてはてこんな光景を見たならゼロツー、オマエの精神はどんな昂ぶりを――などと、ローブ男は言うつもりでいた。
だが不思議な事に、声は出なかった。
「ぬ、ぐ?」
正確には、出せなかったのだ。何者かがフードへ手を突っ込み、顔面を握り掴んでいた為に。
指の隙間辛うじて見える右目から、正体を探る。
それは、左手だった。鈍い銀色に輝く、手首に腕時計型のデバイスが一体化した、鋼の腕。
ファントム4の、五辻辰巳《ゼロツー》の左腕であった。
辰巳は、あれだけ離れていた距離を踏破したのだ。一瞬で、しかもブーストカートリッジを用いずに。
「――」
遮蔽したフェイスシールドの奥。うっすらと透ける瞳に、爛々と凍る殺意を、ローブの男は確かに見た。
そして、その右手へ寄り集まる霊力光すらも。
振り上げられた掌へ実体化するのは、銃では無い。ましてやクナイでも、ブレードでさえもない。
肉厚で、幅広で、クナイよりもやや長い片手用の両刃剣。かつて辰巳のオリジンが、愛用していた武器の一つ。
「ぐ、ら」
「喋るな。黙れ」
斬。
響く刃音と共に、銀弧を描く両刃剣。一歩。大股の残心を、辰巳は雪面に刻む。
「ぁ、」
そして辰巳に鷲掴まれた左手の中で、男は自分の背中を見た。
首を、切断されたのだ。先程の辰巳の銀弧によって。
その事を男が理解すると同時に、辰巳は首を宙へ放っていた。
「、ぁ、は、ハ! 素晴らしいぞゼロツー!」
――確かにここは、精神の奥底にある霊力の原点、霊泉領域。ここならば術式を用いずとも、意志や妄想に形を与える事は容易い。だが、まさかこうも上手く行くとは。
故にこの致命傷は、ローブ男にとってすれば、福音以外の何物でもなかった。
「闘争! 征服! 侵略! オリジンの神性をこう昇華させたか! 良いぞ良いぞこれなら虚空領域《ヴォイド》への接続「黙れ」
斬。再び唸る銀弧が、お喋りな口を頭ごと両断した。
「黙れと、言ったハズだ」
手首が翻る。再び銀弧が閃いた。
斬撃が響く。
斬撃が響く。
斬撃が響く。
斬撃が響く。
斬撃が響く。響き続ける。
斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬撃斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬斬。
既に寸刻みとなった男の頭を、尚も斬り裂くべく翻り続ける右腕。それとは対照的に、酷くゆっくりと口元へ寄った左腕の手首へ、辰巳はつぶやく。
「セット。モードヴォルテック」
『Roger Vortek Buster Ready』
応える電子音声。それと同時に、頭が無くなった事に気付いたローブの胴体が、ようやく両膝を突いた。
白雪を舞い散らし、傾ぐ首無しの身体。しかしてそれが倒れきるよりも先に、辰巳は左手を向けた。
「ヴォルテックバスター」
轟。
溜息じみた声とは真逆の、濁流じみた霊力の暴風が、首無し胴体を地面ごと消し飛ばした。同時に、閃き続けていた右腕の銀弧がようやく止まる。
微塵に解体された男の首が、音も無く消えていく。ようやく自覚したのだ、自分が死んだ事を。
かくしてファントム6を暴走させた原因は、砂埃のようにあっさりと吹き飛んだ。
だが。
だからといって砂埃が起こした現象までは消えない。消えるはずも無い。
「どう、する」
辰巳の手から両刃剣が落ちる。制御を失った霊力の武器は、雪面へ触れるよりも先にかき消えた。
そして、今。その雪面すらもが、がらがらと崩れ去ろうとしていた。
ばきばき、ばきばき、ばきん。
ガラスのような音と共に、末端から割れ砕けていく雪原と黒い森。ローブ男が持ち込んだ芝居の舞台を、新たな管理者が排除しにかかったのだ。
そう。魔狼《フェンリル》という、ローブ男の置き土産である赤い術式に未だ蝕まれた、新たな管理者が。
G、R、R、R、R、R。
よくよく見れば、赤い線そのものは末端から少しずつ揮発している。もっとも、その機能不全こそが魔狼の暴走に拍車をかけているのだろう。
それにもし赤い線がすっかり消えたとしても、こうまで昂ぶった獣性は、そう簡単に収まるまい。
G、R、R、R、R、R、R、R、R、R、R、R。
刻々と割れていく足場。全方向から吹き付けてる殺意。
崩壊し続ける空間の只中で、辰巳は立ち尽くしていた。
「どう、すれば」
どうすれば良い。
どうすれば、この状況を解決出来るんだ。
解決、出来るのか? ここまでねじくれた状況を? 戦闘しか能の無い五辻辰巳《じぶん》如きが?
そうして迷っている合間にも、足場はどんどん狭まっていき――かつてファントム5の一部だった手と足が、虚空へ落ちていく。
「あ、」
思わず、辰巳は手を伸ばす。
その肘から先を、黒い風が掠めた。
「あ、?」
辰巳は目を見開いた。伸ばした右手の肘から先が消えていた――いや、食われていたのだ。今し方の黒い風、もとい、高速で飛来したフェンリルの顎に。
「あ、あ」
喪失感はある。だが痛みはあまり無い。まぁ当然だ。今の辰巳は、五辻辰巳《ファントム4》側の霊泉領域の管理者。痛覚を遮断する事くらい、無意識に出来てしまうのだ。
G、R、R、R、R、R、R、R、R、R、R、R、!
そんな辰巳の身体を、魔狼の牙は削り取っていく。少しずつ、少しずつ。
サイズは、バスケットボールくらいだろうか。牙だけを生やした黒い塊は、辰巳の肩を、腿を、脇腹を、四方八方から削り取っていく。少しずつ、少しずつ。
「な、ぜだ」
ヘッドギアを破壊されながら、辰巳は呻いた。襲い来る魔狼の顎が、余りに小さいからだ。
人体ひとつ分なぞ、容易く噛み砕ける顎を持っている筈の魔狼。それで、いっそひと思いに食ってくれれば良いのに。
それなのに、魔狼はそうしない。こちらをいたぶっているのか? それとも――。
「出来ない理由が、あるのか?」
呟いた辰巳の脳裏へ、電撃が閃く。
そうだ。恐らくフェンリルは、辰巳を食い殺したくないのだ。
屈服、させたいのだ。
辰巳を殺す事、それ自体は簡単なのだろう。それを成せる暴力を、魔狼は有している。だがそれをやると、この領域自体が真っ二つに割れかねない。
何故なら現状の霊泉領域は、風葉と辰巳の精神が、インペイル・バスター経由で一時的に繋がった代物だからだ。不安定なのである。
そして接続の主導権は辰巳が持っており、そのまま殺してしまうと取り返しのつかない事になる。
だから魔狼が辰巳を嬲るのは、単なる嗜虐嗜好というだけではない。心を折ろうとしているのだ。折って辰巳を浸蝕し、インペイル・バスターを、引いては神影鎧装をすら、手に入れるために。
――明らかに、獣の本能を逸脱した行動だ。恐らくは赤い術式の、ローブ男の残滓が、何らかの形で影響したのかもしれない。
だが。
「は。」
もはや、辰巳にとって、そんな事はどうでも良かった。
「は、は」
ボロボロの身体を揺らしながら、辰巳は笑う。その様に、今こそ好機と確信したフェンリルの顎が、辰巳の顔面めがけて急襲。自己防衛本能が崩れた頭に牙を突き立て、本格的な精神の浸蝕を実行する――。
「はは。は」
そんな野望が込められた顎を、辰巳は着弾直前に掴み取った。
G、G、G、!?
開くタイミングを完全に失い、辰巳の手の中で震えるフェンリルの牙。よくよく見れば毛玉のような、落書きのような見てくれのそれを、辰巳は力の限り握りしめる。
「俺を食うつもりだったか。こんな出来損ないで。征服するつもりだったか。このおれを」
征服。普段なら絶対に言わない単語を呟きながら、辰巳は牙を握り潰す。
更には身体中に穿たれた傷跡から、右の瞳から、青色の霊力光が溢れ出す。
「ケダモノ、如きが、」
G、R、R、?
フェンリルは慄いた。今まで散々に食い散らした、半死半生である筈の獲物に、恐怖したのだ。
「おれの、道をッ、」
辰巳は左手を掲げた。鋼の掌が、軋みながら拳を造った。全身に漲っていた霊力光が、Eマテリアルを経由して拳へと集中していく。
強烈な、ちりちりとした熱すら感じる光が、霊泉領域の暗闇を引き剥がす。
G、G、G、R、R、R、R、R、!、!、!
この光を放置していたら、大変な事になる。本能でそれを察知したフェンリルは、刻み込まれていた無貌の男の残滓は、渾身の牙を辰巳へ向けて放った。
もはや形振り構わない。風葉を噛み砕いたものよりなお巨大な、オウガの腕すら食い千切れそうな暴力の塊。
それを前にしてなお、辰巳は一歩も引かない。逆に、その顎を睨み返す。
「阻むなあァァ!!!」
そして辰巳は、輝く左拳を顎へ向かって突き出した。インペイル・バスターのように。
迸ったのは光の奔流である。ヴォルテック・バスターを超え、ブレード・スマッシャーにすら匹敵する青色が、まばたきするより先に顎を蒸発。更に背後の空間を形作っていたフェンリルをも容易く貫通すると、霊泉領域に巨大な『穴』を開けた。
「ふ、う、う」
たっぷり九秒間もの照射の後、奔流はようやく止まった。辰巳はゆるりと手を下ろし、真正面に空いた『穴』を見やった。
『穴』の、向こうには。
虚空が、顔を覗かせていた。
そこには、何も無かった。
同時に、すべてが在った。
辰巳は、ただ、得心した。
「ああ、なるほど。おれは」
G、R、R、R、R、R、R、R、R、R、R、R、!、!、!、!、!
辰巳の得心を、フェンリルの金切り声が塗り潰した。風葉側の霊泉領域そのものと化した身体が、虚空の穴へ吸い込まれ始めたためだ。
「は、」
思わず、辰巳は笑った。笑いながら、拳をもう一度構えた。
このまま、虚空への穴をもっと増やせば。あの領域への入り口を、確たるものにすれば。
あの忌々しい魔狼《イヌ》も、てんで役に立たない自分自身も。何もかもを、自壊術式以上にブチ壊す事が出来る。
そんな確信と共に、辰巳は拳を振りかぶる。
『駄目だよ、そんなの』
しかして、その拳が放たれる直前。
聞き慣れた声が、辰巳の耳朶を叩いた。
「え」
辰巳は動きを止めた。その拳へ、柔らかなぬくもりが触れた。
ぬくもりは、人の姿をしていた。辰巳はそのぬくもりの名前を、良く知っていた。痛いくらいに。
だから。辰巳は、名前を呼んでいた。
「霧、宮。風、葉」
そう。
辰巳の拳を、風葉が優しく押し止めていたのだ。
だが果たして、この風葉は何なのだろう。
幻、と断ずるには些か妙な姿をしている。
水着で、黒髪で、黒目。それだけなら先程と同じだ。
だがその左目はフェンリル顕現時と同じ金色に輝いており、前髪にもいくらか灰銀色が差している。更には尻尾も生えていた。
どうにもデタラメな、ツギハギのような姿をした霧宮風葉。
けれども。
彼女は本物の風葉なのだと、他でも無い辰巳自身が確信していた。
根拠なぞ、何一つとしてないのに。
「きみ、は。どうして」
今すぐ消えそうなくらい希薄な輪郭の風葉は、ひとつ、小さく息をついた。言葉を、思考を、まとめるために。
『言いたい事はいくつかあるけど……うん、まず最初に言っとくよ』
風葉は、辰巳の拳を握る手に、力を込めた。
『ありがとね』
そうして、ほがらかに、笑ったのだ。
「……なに、がだ?」
辰巳の右目から、青い光が消えた。
『そんなの決まってるじゃない。私を助けてくれたでしょ』
「……? 何を言ってるんだ? 俺は結局、キミを」
『ん? あ、あぁーそっか、そうだった。ややこしいなぁ』
訝しむ辰巳の視線を、風葉は慣れない咳払いで誤魔化そうとする。
『と、とにかく。私は大丈夫だから。それに今大丈夫じゃないのは、私じゃなくて五辻くんの方だよ』
「俺、が?」
戸惑う辰巳。その双眸を、風葉のまっすぐな眼が射貫いた。
『そう。覚えてる? 随分前に私が言った事。レツオウガが初めて合体した時、だったかな』
「さぁ、な。最近、物覚えが悪くて、な」
少しずつ、辰巳の光が収まっていく。少しずつ、虚空の穴も小さくなっていく。
『……誰かの都合で自分を無くすのは、悲しい事だよ。でもね』
そして、その消失へ呼応するように。
『自分の都合で自分を無くすのは、もっと悲しい事なんじゃないかな』
風葉の輪郭も、少しずつ滲み始めた。
「そうだな。そうかもな」
自嘲するように、自問するように。
辰巳は拳を開き、肩をすくめた。
全身から発されていた光は、既に跡形もなく消えていた。
「しかし、なんだ。まるで本物みたいだな、キミ」
『む。そりゃ当たり前だよ、本物なんだから』
もうほとんど消えかけながら、見慣れたふくれ顔を風葉は浮かべた。
「そうか、当たり前か」
言いつつ、辰巳は改めて状況を検分する。霊泉領域の主導権は、既に完全に辰巳へと移っていた。
フェンリルは――どうやら、かなり損耗している様子だ。先程辰巳が負わせた損傷もあろうが、何より風葉との、霊力供給源との繋がりが切れかかっているのが大きい。このままでは、数分もせぬ内に消滅してしまうだろう。早急な補修か、あるいは代替要員が必要だ。まぁ準備は出来ているので、心配はいらないが。
なので、ふ、と。
辰巳は、息をついた。
「なら、戻って来るのも当たり前だろうな」
息をつきながら、何気なく、辰巳はそう言った。
それは、もはや気休めにすらならないタワゴトだ。霊泉領域の状況は、それに繋がっている風葉の精神状態は、他でも無い辰巳自身が理解している。
もう、もどらないのだと言う事を。
だが、それでも。
『……うん!』
消え際に見た、泣き笑うような風葉の表情は、絶対に幻ではなかった。
◆ ◆ ◆
霊力を鎮め、霊泉領域から浮上し、辰巳の意識は己の肉体へと戻って来た。
「あ」
そうして最初に見えたのは、レックウの前輪へめり込んだ自分の左拳であった。マリアのサポートを受けて渾身のインペイル・バスターを叩き込んでから、実際には一秒すら経っていないようであった。
呆ける辰巳の掌中で、破壊を伴う霊力の嵐が渦を巻く。ぐるぐると荒れ狂うそれはレックウの車体を内側から食い破り、霊力経路を伝って風葉へ迫ろうとする。
「や、べ」
辰巳はその嵐をすぐさま制御し、風葉へ当たらぬよう形を変える。ハンドルへ辿り着く寸前に両断された青い嵐は、そのまま風葉の鎧装を掠めると、フォルテシモ・アローが開けた魔狼の傷口へ激突した。
嵐は魔狼に、食われない。それ以前に魔狼は身動きすらせず、末端から淡雪のように溶け消えていく。
理由はどうあれ、風葉とフェンリルの接続が途切れた事を、今が最適なタイミングである事を、マリアは理解した。
「今、こそッ」
マリアはライフルを再構成し、消え行くフェンリルへと照準、射撃。着弾と同時にスタンレー謹製の捕縛術式が作動し、フェンリルの一部が切り取られる。
かくてマリアの手元へ戻って来たのは、直径三十センチほどの黒い球体。この中に、フェンリルの構成情報が封入されていると言う訳だ。
「ですが、あまり長くは持ちません。早く戻っ、て」
そこでマリアは、言葉を失った。
辰巳は、既にオウガのコクピットへ戻っていた。コンソールの手前に。
救出した風葉を、その腕に抱きながら。
風葉は目を閉じたまま、動かない。胸が動いているのは見えたので、辛うじて呼吸はしているのだろう。
だがその髪は灰銀でなく、元の黒色に戻っている。
その顔を。その髪を。
あえて覗き込まないように、辰巳は海を見ていた。
まっすぐに、立ち尽くしていた。
その、背中に。
マリアは声をかける事も、一歩近付く事さえも、出来はしなかった。
少しして、まずは傍らに着陸した朧《おぼろ》が、次いで戦闘を終えた冥《メイ》が通信を送ってきた。
だがそのどちらにも辰巳は取り合わず、やはりひたすらに海を眺めていた。
「……はやく」
逃げた巨大戦艦の行方。ハワード・ブラウンの真意。自分とグレンの関連性。謎のローブ男。
そして何よりも、顕現した辰巳《ゼロツー》の能力。
きっと嵐が来るだろう。凪守《なぎもり》のみならず、世界中の魔術組織を激震させる、特大の暴風が。
その基点となってしまった辰巳は、やかましく着信を告げるコンソールの隣で、ただ一言呟いた。
「はやく、戻って来いよ」
あまりにも儚いその祈りと共に、あれだけ巨大な影を落としていた魔狼が、風に吹かれてかき消えた。
【神影鎧装レツオウガ 用語解説】
虚空領域
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
