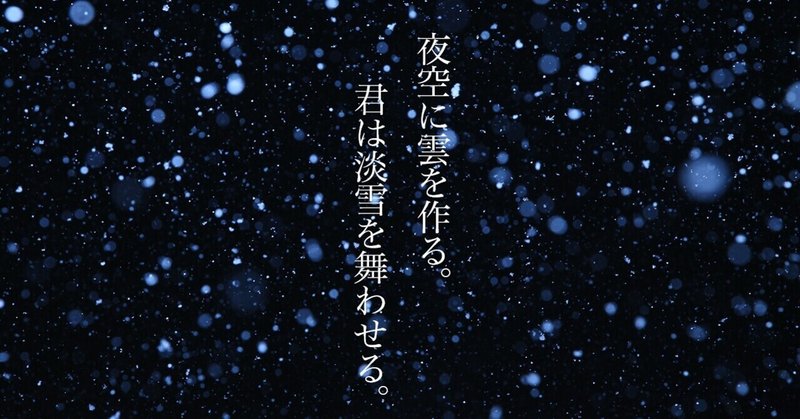
【小説】夜空に雲を作る。君は淡雪を舞わせる。
ある夜君と吐息を重ねるうち、気づいてしまった。
必死に抑え込んでいた胸の痛みと、目の端に溜まる無色透明な感情。
その瞬間から、薄い皮膚と皮膚のあいだの微かな温度差が気になってしょうがない。
少しでも気を緩めれば涙がこぼれてしまいそうで、きっとそれは君を困らせてしまうから、息を止めてなんとか堪えた。
そこからどうも気持ちを入れきれないまま「すべきこと」をさっさと終わらせた。
カーテンを開けた窓から差し込む街明かりが、君の右頬を照らす。
「うーん」と伸びをしたあと、君は目を細めて笑う。
僕はそのまぶしさから逃げるように、床の抜け殻を拾い集める。
この関係が世間的に良く見られないことなんてわかっていた。
夜の隙間を埋めるため、互いを利用しあったまでだ。
でも、僕たちにとっての正解はここにあったのかもしれない。とは思う。
この「居心地の良さ」は離岸流のように僕らを日常から遠ざけた。
いつしか元の自分なんてものは見失っていた。
そもそもそんなものなんてなかったのではないかと疑ってしまうほどだ。
この胸の痛みは残酷に僕を現実に引き戻した。
痛みは消えない。
それどころか意識すればするほど強く、深くなる。
後悔の波が瞬く間に押し寄せる。
正直いつかくるとは思っていた。
だから僕は、なんとか踏みとどまっていた。
こうなってしまえばこの先、僕は君の明日をどうでもいいなんて思えなくなってしまう。
困ったもんだ。
僕らの関係性は、互いに停滞を望む事でしか維持できないというのに。
僕はいったん全部忘れて煙に巻いてしまいたくなった。
メビウス一本とライターを持ってベランダに出た。
春とはいえ、この時間はまだ冷える。
首元から入り込む風は鳥肌を誘う。
ライターの端を押し込む。
一度ではつかず、二、三度でようやく頼りない炎が揺らいだ。
その中にふっと先端をくぐらせる。
右手の親指から力を抜くと、静寂が訪れた。
吐き出すのは白い色のついたため息だ。
これから僕らがどうなるかなんて知らない。
ただ、この日々がそう長くは続かないことだけは分かる。
数年後、僕は君をどんなふうに思い出すだろうか。
くちびるが覚えている君の湿度や、指先に残る君の輪郭。
そんなんじゃなくて、もっと儚くて壊れやすいもの。
駅から僕の家までの道すがら、「カップルみたいに見えるかな?」とふざけて手を繋いだあの8分半。
「お腹すいたね」と深夜に歩いたコンビニまでの400メートル。
僕はどんな些細な瞬間を、過剰なほど大事に思い起こすだろう。
なんども、なんども。
今までの日々が、もやもやと霞んできた。
煙か、涙かは分からなかった。
煙が大きくたなびいたのは風向きが変わったせいではなくて、君が窓をあけたからだとすぐに気づいた。
「どうしたの?」
君は目を合わせないまま僕の隣にそっと佇んだ。
僕は何も答えないで、ただ煙を揺らした。
この気持ちは、君には分かるまい。
「雲みたいだね、それ」
予想していなかった二言目に、はっとした。
そういう所だ。
何か言い返したくて、でも壊してしまうのが怖くて、曖昧な返事しかできなかった。
こんな形じゃなく、君と「ちゃんと」出会うことができていたなら。
でも考えてみれば、こうでなければ出会わなかったような気がする。
それならいっそ———
その時だった。
ほのかな光が僕の眼前をはらはらと舞う。
静かに黒をたたえた空に舞ったのは、雪だった。
そんなはずはない。
もう三月も終わる。
この地域では冬の雪すら珍しい。
君は僕の思考がひと巡りするのを待ってから、
「雪かと思った?」
と笑う。
左手にはピンクのプラ容器、右手には同じ色のパイプ。
「シャボン玉か。」
いつの間にそんなものを。
見覚えはないから、バッグに忍ばせていたのだろう。
君は目元で笑いながら、ふーっと安っぽいパイプを吹く。
立て続けに舞い上がる。
風に誘われ、いくつも連なり漂う。
夜空に浮かぶ様子は本当に雪みたいだ。
君の顔がどうしようもなく耀う。
胸がまた静かに鳴る。
君の方を見ることはできない。
ただ雲と、淡雪を見つめていた。
「私さ」
なんとなく、どんな言葉が続くかわかった。
わかったから、聞こえないふりをしようとした。
君はもう一度、言い直した。
「私さ」
振り向かざるを得なくなってしまった。
君の表情は鏡だ。
僕がひどい顔をしているのは、すぐにわかった。
「キミとするのも好きだったけど、した後の時間はもっと好きだったんだ」
「なんでそんなこというの」
咄嗟に口をついた言葉はひどく掠れていた。
いまさらそんなことをいうなんて。
質問には答えないまま、目を伏せて君はつぶやく。
「ずっと朝が来なければいいのにね」
少ししてから僕も、と言いかけて口をつぐんだ。
それを見ていた君は
「ごめん、聞きたくない」
と僕に背を向けた。
君のずるいところさえ、愛おしかった。
僕らの日々は小さめのハンドバッグになんとか詰め込むことができた。
持ち手を握る華奢な手は心なしか震えているように見えた。
さよならなんて陳腐な言葉を告げたくなかった。
子供な僕は君にすがるように、後ろから抱きつく。
皮肉なことに今までした中で一番不器用で、純粋なハグだった。
君の顔は見えない。
見えなくてもいい。
むしろこのまま面影だけを残して去って欲しい。
僕の腕を春風のようにすり抜けた君はそのまま外へと吹き抜けた。
「げんきでね」なんて一言残して。
僕の明日を思う、最初で最後の言葉だった。
部屋がずいぶん広く感じた。
ぺたぺたと廊下を歩く音がやたら響く。
立つ鳥跡を濁さず。
君のものはもうなにもない。
なにもない。
…はずだった。
机の上に残されたシャボン液と、プラスチックのパイプ。
丁寧な配置に、君のたしかな意図を感じる。
気がつけば手に取り、窓を開けていた。
寒さの中にかくれた春のにおいが胸をつく。
プラ製のパイプを石鹸水にひたし、浅く息を吐く。
にせものの雪が風に舞う。
ゆらめいて、儚くはじける。
口元には君の体温が、ほのかに残っていた。
やっと、頬に雨が伝った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
