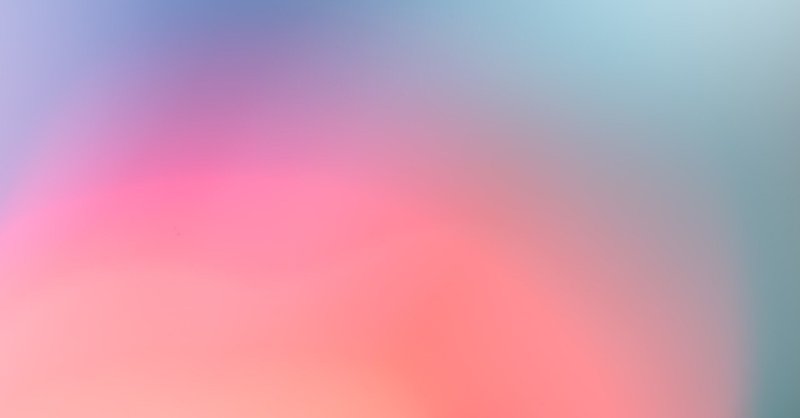
【小説】あるいはパッションフルーツ
*第五回林芙美子文学賞最終候補作、原稿用紙換算114枚(くらい)
平面はテーブルを動かすことができない。そのため、机を動かす作業はわたしが一人で行うことになる。大変な作業ではない。和室で使うために足を低くした長机がまとめて置いてあるのを並び替えてコの字型にするだけだ。
それだけなのだが、平面は毎回ほんとうにありがとうと連呼する。
「いつも助かる、私も手伝えたらいいんだけど」
平面は言う。
「向き不向きだよ」
私は答える。
平面は重いものを持つことができない。平面といっても彼女にはほんの少しの厚みがある。五ミリほどだろうか。固い板のような感じではなくぺらぺらであるので、あまり重いものを手にすると体がぐにゃぐにゃに曲がってしまう。
冗談ではなくほんとうに食事に使う最低限の道具より重いものを持ったことがないのだと平面は以前言っていた。
「受付お願いしていい?」
「いいよ」
平面は私の返事を聞いてから、机に使い捨てのプラスチック製コップを等間隔で並べはじめる。そこに冷えたジェルをスプーンですくってぽんぽんと放り込む。平面はスプーンを持つことができる。手の部分で巻き込むようにして持つのだ。
私は和室の入口に小さなテーブルを持ってきて、持ち歩きのできるタイプの金庫と参加者の名前を印刷した表を置いた。きょうは六人が活動に参加する予定である。もし仮に飛び込みで誰かが来ることになっても十人を超えることはないだろう。
公民館の一室を借りて行っている小さな講座である。月に二日開催で、継続して通うことを推奨しているが、単発の受講も可能だ。材料の準備の都合で事前に大まかな人数の把握が必要であるため、要申し込みということになっている。実際は予約なしでふらっと来る受講者も少なくない。講師を務める平面が、来たいときに来てもらえればよいというスタイルでやっていきたいというので、当日飛び込みでの受講も断らないことにしている。
開始時間の十五分前ごろから受講生たちが集まってくる。長く継続して受けている宮本さん、山田さん、吉村さんに、気が向いたときに受講するスタイルの江川さん、最近通い始めた市倉姉妹の六人である。今日は飛び込み受講者はいなかった。全員女性であるのはこの講座ではめずらしいことではなかった。
私はそれぞれから材料費を徴収し、名前を確認して、自由に座ってくださいと伝えた。
宮本さん、山田さん、吉村さんの三人は年齢こそばらばらであるものの仲がよく、きゃあきゃあとおしゃべりをしながら講座がはじまるのを待っている。山田さんが一番年若でおそらく三十代半ば、吉村さんと宮本さんはどちらかが四十代でどちらかが五十代だと話していたのを聞いたことがある。どちらがどうなのかは忘れてしまった。江川さんは夢想家なのか、どこか遠くを見てふんふんと鼻歌を歌っていることが多い。いつも品のよいワンピースを着ている。市倉姉妹は制服姿で現れた。双子ではないはずなのだが似た背格好で、とくに揃って制服姿だと、どちらが真奈でどちらが千佳であるかよくわからなくなる。
和室の隅に正座していた平面が立ち上がるとおしゃべりが止む。
平面はコの字に配置した机の真ん中部分に入って、挨拶をはじめる。季節の話とかそんなことを一分くらいでさっとまとめて話している間に、私は水が二リットル入ったペットボトルを持ってきて平面の後ろで待機した。
では、と平面に目配せされて私は頷いた。受講者たちの前に配られた、ジェルの入ったコップの中に適量の水を注いでいく。受講生たちはストローで水とジェルをよくかきまぜる。混ぜられた液体は軽く濁って、すぐに透明になった。
最初に水を注がれた宮本さんは手慣れていて、指示をする前にもうコップを両手で包んで目を閉じはじめている。いいのか、と平面に目で尋ねるが、平面はにっこり笑うばかりなので、私は宮本さんになにも言わなかった。
「では、コップを両手で包むようにして持ってください」
平面が言うと宮本さん以外の五人が動きはじめる。全員がコップを手に包んで目を閉じたところで平面は再び口を開く。
「どんなエピソードでも構いません。最近起こったことでも、遠い昔の悲しかった思い出でも、嬉しかったことでも、頭に思い浮かべやすいものを想像してください。そのエピソードはあなたの気持ちをどう揺るがしますか?」
コの字の真ん中から平面は全員を見渡す。受講生が目を閉じてエピソードの中にいることを確認して平面は続ける。
「気持ちの揺れをそのまま手に伝えてください。振動として伝えるのではなく、気のような形で、手からのみものに送ってください」
毎回全く同じ台詞を平面は言う。受講生たちはこの説明で理解できているのだろうかと私は心配になる。使っている言葉が難しいわけではない。ただ、実際に行うときの感覚としては、平面の説明の中でいえば、気のように伝える、というところがとにかく芯であるのだ。気の部分に関してもっと掘り下げて説明しないとわからない受講生もいるのではないかと私は思う。
実際受講生たちは、指導なしではほとんどうまくできたためしがない。
唯一、山田さんはどうやればいいのか直感的にわかっているらしい。山田さんの眉間にしわが寄ってくる。のみものの色が真っ白に変わりはじめる。隣に座っていた吉村さんが目を細く開けて山田さんののみものを見て、わあ、と小さく声を上げる。山田さんも目を開けたが、無表情で色を確認すると再び集中の状態に戻った。
気が散ってしまった吉村さんのところへ私は行き、吉村さんの手を外側から包んでコップにしっかりと密着させる。
「エピソードをはっきり想像してください」
私は吉村さんに言う。
「まずはそれでいいです」
吉村さんは目を閉じる。のみものに少し色が現れる。鮮やかなピンク色だ。
「そう、上手です」
私は吉村さんの手を包んでいた手を外す。とたんに色の表れ方はにぶくなった。吉村さんはやや集中力が足りない傾向にある。集中力を上げるためのトレーニングを講座の前に行うことをすすめてもいいかもしれないと私は思った。吉村さんがそこまで真剣に講座に取り組む姿勢があれば、の話である。そこまでではないだろうと私は予想した。
平面に背中をつつかれて私は振り向く。市倉姉妹がかなり苦戦しているようだった。
「エピソードはよく思い浮かべられているみたい」
平面の言葉に私は頷く。
「それを手にうまく伝えられていないから、手の感じを教えてあげてほしい」
平面は言う。平面はのみものに関して完璧な能力を持っている。受講生のどこがどう欠けているかということも瞬時に見抜くことができる。しかし、手が平面ではない人へどう指導してよいかわからない部分があるようだ。平面は言葉で伝えることもそこまで上手ではない。擁護するならば、のみものというのはかなり感覚的なところが大きいので、言葉にするのは確かに難しいところがある。そのため私が平面ではない手を持つものとして感覚を伝える手伝いをしているのだ。
みんなの手が平面であれば私は全員をのみもののプロフェッショナルにできるのに、とよく平面は言っている。なかなかそうはいかないものだなと私は思う。
市倉姉妹の姉、真奈の前に私は座った。真奈は目を開けて私にお辞儀をする。
「できません」
真奈は悲しそうに言う。
「だいじょうぶ」
「でも」
「できるようになる」
私は真奈の手を自分の手で包み、指先を丁寧にコップに貼りつけていく。
「指紋をコップにべったり付けるみたいな感じにして」
言われた真奈は指の形を調整する。すでにのみものの色が変わりはじめている。
「そう、それからエピソードを頭に浮かべてください。なんでもいいけれど、たぶん悲しいものがいいと思う」
私が言うと妹の千佳ののみものの色が変わりはじめた。説明を横で聞いていて、こつを掴んだらしい。千佳ののみものを見た真奈は目を閉じて指先に力を込める。私はまた手を手で包んで、ほどよく力を抜いてやる。真奈ののみものにばっと色がついた。明るい黄色と水色のマーブル模様が広がっていく。
「やった」
「まだ、固定されるまで集中して」
言いおいて私は真奈の前を離れる。
江川さんののみものには色がつきかかっている。平面が指示をしているので、放っておいても大丈夫そうだ。江川さんは理解力があるので平面の指導が多少言葉足らずであってもうまく受けとめることができる。
問題なのは宮本さんだ。
宮本さんののみものは全く色のつく気配を見せていなかった。宮本さんの額からは汗が滴っている。渋い表情の宮本さんは焦っているようだ。焦ってはいけない。まずははっきりとエピソードを思い浮かべることが必要なのだ。宮本さんのところへ私は行こうとするが、平面が手で制した。
「やらせておいて」
「でも」
私は言う。
「なにが間違っているか、宮本さんは自分で気づかないといけない。わたしたちが指導してもどうしようもないよ」
「前回も前々回もずっとあの調子なんだよ」
「そうだよね」
「間違ってるってことを教えるのもだめ?」
「うん、だめ」
平面ははっきり言う。
宮本さんはちらりと私の方を見て、再びのみものに手をやり集中しはじめた。頭の中になにもエピソードが浮かんでいないことが端から見てもわかる。そうではない、こうするのだ、とやってみせたくなる。こつを教えたくなる。しかし平面からオーケーが出ない。それだけの理由でうんうんうなっている人を助けられないのはとてももどかしい。
そろそろのみものが固定しはじめる頃合いである。ジェルと水を混ぜてから十五分ほどで、のみものの色が変化しなくなってくる。十五分経った段階で色がついていればその色で落ち着き、色がついていなければ無色のままである。安定してもう色の変化の起こらなくなった状態を固定というふうに呼ぶのだ。
山田さんののみものは白に黒が差し込んできてマーブル模様を描いている。吉村さんののみものは色の出方がかなり弱いがうっすらとピンク色に染まっている。市倉姉妹ののみものはぼんやりと明るい色合いでかわいらしい。江川さんの飲み物は淡い緑色だ。
宮本さんの飲み物だけが色づいていない。
目を開けた宮本さんはがっかりした様子を見せる。他の受講生たちが上手でないながらも色のついたのみものを持っているにも関わらず、自分だけが最初と変わらない透明な色ののみものを手にしているのだ。それは非常に悲しいことだろうと私は思う。
平面はこうやってひいきをする。特定のひとりにだけ指導を行わないことや、逆にあるひとりにだけ付きっきりで指導をすることがあるのだ。いつもひいきをしない方がいいと思うのだが、これは私の講座ではなく平面の講座であるから強く言わないようにしている。
「そろそろ固定された頃と思います」
平面が、コの字に並んだ机の中央に座って言う。
「では召し上がってください。写真など撮られたい方はどうぞ」
平面は私に、ごめん机持ってきてもらっていい、と小さな声で聞いた。私は受付に使っていた小ぶりのテーブルを持ってくる。これでいいかと確認すると平面は頷いた。
ひとつ余っていた、コップにジェルを注いだものを平面は小ぶりのテーブルに運んできた。きゃあきゃあと写真を撮っていた市倉姉妹がいち早く気がついて平面の方を見る。それを合図にしたかのように受講生みんなが平面の方を向いた。
私はコップに水を注ぐ。平面はストローで水とジェルをよくかき混ぜ、コップを外側から両手で包み込む。
平面の手は、平面である。平たいので、プラスチック製コップによく密着する。あっという間にのみものに色がついた。虹をとろかして混ぜ合わせたかのようにたくさんの色が液体の中で回遊する。受講生たちから、ほう、というため息が漏れた。平面は自在にのみものを固定することができる。しかしあえてすぐには固定せず、ぐるぐると色が回っていくのを楽しんでいるようだった。
平面がどのように頭の中でエピソードを思い浮かべているのか、そしてそれをどう平面の手に伝えているのか、さっぱりわからなかった。きっと手が、あるいは体全体が平面であることとなにか関係があるのだろうが、それは自分が平面になってみないとわからないことに思われた。
コップから平面が手を離しても、のみものはまだ対流を続けている。きらきらと光るあらゆる色の集まりは止まる様子を見せない。受講生たちから自然に拍手が起こった。私も拍手をしていた。平面がすばらしい能力を持っていることは間違いなかった。
のみものを飲み終わった受講生たちが帰っていくと、私と平面は後かたづけをする。平面はコップを捨てる作業をし、私は机を元の位置に動かしたり、受け取ったお金の計算をして平面に渡した。
「では」平面は楽しそうに言う。「飲みに行きましょうか!」
公民館を出て少し歩いたところに飲み屋街がある。幅の狭い通りの両側に店がずらっと立ち並んでいる。脇道にも飲み屋があるので、全部でどれだけの店があるのかを数えることは難しいが、毎日通っても飽きないくらいたくさんの飲み屋があることは間違いなかった。
私と平面はあちこちの店に吸い寄せられながらふらふら歩いていく。特に行きつけの店は決めていない。その日の平面の気分で、チェーン店にでも、おしゃれなバーにでも、個人経営の古びたおでん屋にでも行くことにしていた。どこの店がいいか話し合うのはふたりで行うが、店を決定するのはだいたい平面だった。平面には食べられないものや飲めないものがかなりある。私がこれなら平面もオーケーだろうと思って選んだ食べ物も、実は平面には食べられなかったりすることも多々あった。そのため平面によくメニューを確認してもらってから店に入るようにしているのだ。
平面が今日選んだ店は、このあたりに何店舗かを展開している海鮮居酒屋だった。飲み物の値段が安いことや、日替わりで刺身を半額提供していることで有名な店だった。私と平面は店に入った。大きな声の挨拶で迎え入れられる。二名です、と私は告げ、席の空きがあるかを確認してもらう。カウンターと半個室どちらがいいかと問われたので、平面に確認すると、カウンターがよいと言う。カウンターでお願いしますと私は店員に声を張って伝えた。店内が騒がしく、かなり大きな声でないとコミュニケーションがとれない。なぜこの店を平面は選んだのかと不思議に思うが、それが今日の平面の気分なのだろう。
カウンター席に通されるとあたたかいおしぼりを渡された。平面の分は私が受け取って、平面の手にそっと乗せた。勢いよく乗せると、平面の手はぺらぺらしているから裏返ってしまうのだった。
飲み物の注文はふたりとも生ビールである。片方にはストローをつけてくれとお願いすると店員は不思議そうな顔をしたが、かしこまりましたあ、とすぐに笑顔に戻った。テーブルに置かれたストローの刺さった生ビールに、ストローの刺さっていない生ビールのジョッキを軽くぶつけて乾杯をする。平面はジョッキを持つことができないのだ。ぐぐっと飲んだあとうまいと言ったタイミングがふたりで揃って、思わず笑ってしまった。
「おつかれさまでした、いつもありがとう」
平面は冷奴と刺身とたこのからあげを頼んでから言った。
「大したことしてないよ」
平面に食べられるかどうかを確認してから、私はもずく酢を追加注文した。
「この飲みが楽しみで講座をやってるようなもんだわ」
平面は言ってジョッキに口を近づけ、ビールをストローでごくごくと飲んでいく。ビールはあっという間になくなっていき、冷奴が来るのと同時に二杯目を注文した。
「好きだねー」
「なにが?」
「飲むのが」
と私は言う。平面は笑う。
二杯目のビールが平面の元にやってきた。平面はジョッキを下げられる前に、ストローを二杯目の方に差し替える。そしておそるべき速さで飲む。私は平面の飲みっぷりをうっとりと眺める。薄い体のどこにビールがおさまっているのかいつも不思議である。
「ねえ、山田さんどう思う?」
平面は私に聞く。
「どうって」
「うまいけど」ストローでビールを吸って一拍置いてから平面は言う。「あのうまさはよくないうまさだよね」
「いっつも言ってるね、それ」
私は冷奴をうまく箸で掴むことができず、角をぐずぐずに崩しながら言う。
「白はよくない色なんだよね」
「よくないの?」
「うん、あの色がいつも一発で出せるのは結構まずい」平面は言う。「白を出せる人って他に見たことある?」
「ないかも」
私は言ってから少し考えて、
「平面は出せるんだっけ」
と聞いた。
「出せない。出したくもない」平面はきっぱりと言う。「白とか黒を出せるようになったら終わりだね」
「そんなに?」
箸の先にようやく冷奴をとらえた私はさっと口に運ぶ。
もずく酢が来た。
「山田さんはとんでもない苦労人か、やばい人か、どっちかだね」
「そんな印象ないけどな」
私は山田さんのことを思い出してみる。明るくよくしゃべる女性だ。落ち込むことがあったとき、吉村さんと宮本さんに愚痴を言って慰められていたこともあった。たしか仕事のミスのことで、そこまで重い話ではなかったような気がする。
「友達は多いみたいだよね」
と私は言う。
「辻君でしょ」呆れたように平面は言って、冷奴を箸で切り分け、薬味をたっぷりのせて口へ運ぶ。「辻君はね、女癖さえ悪くなければいい生徒なんだけど」
「ほんとそうだね」
もずく酢をずるっと飲み込んで私はむせた。平面は私がむせていることを気にせず、冷奴をスムーズに一口分だけ切り分け薬味をたっぷり乗せる作業をしている。
「人間関係は面倒だ」平面は言う。「ただのみものについて教えることだけしたい」
「そこまで関与しなくていいんじゃない」
私はおしぼりを口に当てながら言った。
「そうかな」
「成人している人たちに関してはほっとけばいい」
「そっか、そうだね」
人間関係は面倒だ、というのは飲むたびに平面が繰り返し言っていることだ。平面は講座以外ではほとんど外出をしない半隠居生活を送っているので、人と人との問題には関わりたくないという気持ちが強いらしい。
「もめそうだったら私が間に入る」
私は言った。たこの唐揚げと刺身が来た。
「ありがとう」
平面は言って、たこの唐揚げに箸を伸ばす。平面の指は当然平面であるが、箸を使ってじょうずに食べることができる。持ち方は平面でない人とだいたい同じである。指を絡ませるように持っていることだけが少し違う。
「わたしは平面だから、わからないことが多いよ」
「そうかな」
「多いよ。平面だもん。わたしの学生の時のあだ名知ってる? パラッパラッパーだよ」
「え、なにそれ」
「ゲームの名前」
「知らない、そのゲームは知らないけど、そんな風に呼ぶ? 普通」
「ねー」
三杯目のビールを平面は注文する。ヒラメの刺身を二枚重ねて取った平面は醤油をつけてから、あ、ごめん二枚重なってた、と私に謝り、口に運んだ。私は一杯目のビールをだらだらと飲んでいる。今日も平面は酔っぱらって家に帰りたくないと言い出すだろうと予想して、酒量を抑えているのだ。
案の定平面は酔っぱらって、家に帰るのめんどくさい、泊めて、と言い始めた。私が店員に会計を頼むと、うとうと眠りかけていた平面は姿勢を正し、ポケットから一万円を出して、おごる、と言い張った。
「いいよ、出すよ」
「お世話になってるからいいの、はい店員さん」
店員に一万円札を渡して、平面はカウンターに突っ伏した。ゆるいカーブを描いている平べったい背中を私は見つめた。腰の部分は六十度ほどの角度で折れ曲がっている。平面の腰は細い。細くて、当たり前だがぺらぺらしている。華奢で折れそうな腰というのは本来こういうことを指すのかもしれないと私は思った。
お釣りを受け取り、平面のポケットにねじこむ。平面は完全に眠っているようだった。私は平面の頭の縁を両手でつかみ、背中の方に向かってくるくると巻いていく。腰まで巻き終わったら足先まで一気に転がすようにして巻く。
巻かれた平面を小脇に抱えて店を出ようとすると、
「あの、丸めちゃって大丈夫なんですか」
と店員が話しかけてきた。
「いいんです、寝てるから」
私は答えた。
私の家は公民館から歩いて行けるところにある。当然飲み屋からも歩いて帰ることができる。
くるくるに巻いた平面はたいした重さではない。スーパーでちょっと多めに買い物をしたときくらいの重量である。右腕に平面を抱え、左肩にクーラーボックスをかけて歩いていく。ジェルを入れるために必要なクーラーボックスを平面は持つことができないので、普段は私の家で保管している。講座の時には十駅ほど先にある平面の家までクーラーボックスを持っていき、平面がそこにジェルを詰めて、再び私が肩に掛けてジェルを公民館まで運ぶという手順になっている。面倒といえば面倒だが、平面は重いものを持つことができないのだから仕方がない。
家に着いてまず平面を床に下ろした。平面はぐっすり眠っているようで、床に置いても目を覚まさなかった。私は着替えて、シャワーと洗顔と歯磨きと体操と軽い読書を済ませてベッドに入った。
平面は寝息をたてている。すー、すー、というリズムに合わせて、平面の巻き具合がほんの少しずつゆるんだり締まったりするのを私は夜が明けるまで眺めていた。
六時頃に平面は目を覚ました。ぽん、と音を立てて一気に四肢を伸ばしたのがおもしろかった。
「おはよう」
私は言う。
「ごめんまた泊まっちゃった、帰るね」
「お風呂入ってってもいいよ」
「ありがとう、じゃあちょっと借ります」
平面がシャワーを浴びる前に次回の講座の打ち合わせをした。打ち合わせといっても、基本的にはいつも通りでよろしく程度の話であった。
次回は私が受講生の前で手本を見せることになった。久しぶりののみものをうまく扱えるか不安に思っていると、平面は、
「だいじょうぶ、できるよ」
と言って、風呂場へ向かった。
シャワーを浴び終えた平面はすぐに家に帰った。早くしないと電車が通勤ラッシュを迎えるからである。濡れた髪を乾かす必要がなく、体の水気をふき取るだけでいいというのは平面の大きなメリットかもしれないなと思いながら私は平面を見送った。
そしてようやく眠りについた。
「あの」
受付に座っている私に、宮本さんが話しかけてきた。
「はい」
「どうやって助手になったんですか?」
またか、と私は呆れた気持ちになる。宮本さんは何度も私に同じ質問を投げかけてくる。そのたびに私は、
「友人だからです」
と答える。
宮本さんはさらに、
「どこで先生とお知り合いになったんですか?」
と尋ねてくる。
「この講座の前身にあたる講座を受けていたからです」
私はいつもと同じ返答をする。
「そうですか」
宮本さんは音を立てずに立ち上がって受付から離れていき、山田さんと吉村さんが話しているところにぐっと割り込んで、二人を笑わせた。
私はなんだか疲れてしまってため息をついた。三人は明るくなんのことだかさっぱりわからない話をして盛り上がっている。山田さんはときどき、隣に座っている辻君に話をふり、辻君がそれに答えると三人はどっと笑った。
きょうは辻君が来ているのだ。
辻君は山田さんの友人で、ときどきやってきて講座に参加する。のみものに色をつけるのが受講生の中だと二番目に上手である。一番うまいのは山田さんだ。山田さんは色合いこそ白と黒で地味であるが、かなりはっきりとした色をつけることができる。平面に言わせると白はよくない色であるということだが、山田さんが実力者だということは間違いないと私は思っていた。
辻君は反対どなりの江川さんに話しかける。天井を眺めていた江川さんはゆったりとした動きで辻君の方を向き、聞かれたことに答えた。辻君はそれに対して何か言い、江川さんは笑った。江川さんは四十歳に近い年齢で、辻君はおそらく二十代後半か三十歳くらいと年齢差があったが、ふたりの会話は自然であった。辻君は、人見知りをするのでなかなか友達ができないのだと私に話してくれたことがある。しかし受講生同士の会話からも、辻君と話してみたときにも、人見知りという感じを私は受けなかった。
かなりうまくなりそうな予感があった江川さんがもう講座に来なくなるだろうことはとても残念だった。
辻君と仲良くなった受講生はほとんどの場合講座に来なくなってしまう。恋愛関係のもつれかなにかだろうと私と平面は予想している。辻君は江川さんの膝に手を置いて話していた。その手を払いのけたいと思った。江川さんには気を強く持ってほしいが、たぶんだめだろう。
コの字型に並べた机の真ん中部分に座った平面は受講前の簡単なあいさつをはじめた。私はペットボトルに入った水を用意して、平面の後ろで待機する。
平面があいさつを終えて、私に受講生に水を配るよう合図しようとしたとき、宮本さんがすっと手を挙げた。
「先生」
「はい」
呼ばれた平面は返事する。
「色には意味がありますか?」
宮本さんはまっすぐに平面を見て言った。
平面が返事をしないので、宮本さんはさらに、
「みんないろんな色を出せると思うんですけど、そのひとつひとつの色にはなにか意味があるんでしょうか」
と言い、
「たとえば赤は情熱、みたいな」
と付け足した。
平面は黙っている。宮本さんがまた話し出しそうになったのを手で制した。平面は私の方を振り向いて、なにか言ってくれ、というジェスチャーをした。
「あの、どんな色が出るか、それはとても楽しみなことだと思います」
私は言う。
「けれど、どの色を出そうというのは狙ってできることではありません。先生でも難しい技術であると聞いております」
「返事になってません」
宮本さんは淡々と言う。
「思い浮かべるエピソードや、そこから感情をどう伝えるかにたしかに色は左右されます。自分がこの色ならうまく出せるというのがわかってきている人も受講生さんの中にはいらっしゃると思います」
私はしゃべり続ける。
「その色がなにを意味するか、という質問でしたよね。はっきり言うと、色自体はなにをも意味しないです。表出したその色から自分のことをどのように掘り下げるかが大切だと私は考えています」
私が話し終えると宮本さんはうつむいて、しばらく考えた後首を振った。
「わかりません」
宮本さんは言う。
「うまくできません、私だけ、うまく」
「宮本さん」私は言う。「今日は私と一緒にやってみましょう」
宮本さんは頷いた。
平面が小さくため息をつく。勝手なことを言って申し訳ないとあとで謝った方がいいだろう。
「では」
平面は私に受講生のコップへ水を注ぐよう指示する。私はそれぞれのコップに水を注いでいく。辻君のコップに水を注いだとき、おつかれさまです、と辻君は私に言った。ありがとうと言うのも無視をするのも間違っている気がして、私は小さく会釈を返した。
受講生たちはストローで水とジェルをかきまぜていく。混ぜられた液体は軽く濁って、すぐに透明になる。
「両手でのみものを包んで、エピソードを思い浮かべてください」平面は言う。「どんなエピソードでも構いません。最近起こったことでも、遠い昔の悲しかった思い出でも、嬉しかったことでも、頭に思い浮かべやすいものを想像してください。そのエピソードはあなたの気持ちをどう揺るがしますか?」
平面はさらに続ける。
「気持ちの揺れをそのまま手に伝えてください。振動として伝えるのではなく、気のような形で、手からのみものに送ってください」
今日は市倉姉妹が来ていない。学校の用事があると親御さんから連絡があっての欠席だ。吉村さん、宮本さん、山田さん、辻君、江川さんの五人を今日は指導することになる。
山田さん、辻君、江川さんは平面のことばとジェスチャーでたいがいを理解できるくらいには能力があるので、吉村さんさえうまくフォローできれば、宮本さんにつきっきりになっても大丈夫そうだった。
「平面、ごめん」
みながエピソードを思い浮かべることに集中している中、私は平面に謝る。
「なにが?」
平面はやはり少し怒っている。
「今日は宮本さんに基本つく感じで、それから随時吉村さんのフォローに入るから、三人のこと見ておいてもらっていい?」
「全員のことを見てるよ私はいつも」
平面は言う。
「そうだよね、ごめん」
平面は返事をせず、山田さんの飲み物の色が白くなってきているのを見つけ、素早く立ち上がって指導を行いに向かった。
早々に自力でのみものに色をつけることをあきらめ、私のことを穴が開きそうなくらい見つめている宮本さんの前に私は座った。
「できないんです」
宮本さんは眉を下げて困り顔を作りながら言う。五十歳ほどの宮本さんがするにはあまりに子どもっぽい表情だったので、私は苦笑いをしてしまう。
「まず、コップをしっかり持ちましょう」
私は宮本さんの手を外側から包んでコップに密着させる。宮本さんの手はひどく筋ばっていた。
「それからエピソードを思い浮かべます。なんでもいいです、なにか印象的な出来事はありますか?」
「半年前に飼っていた犬が死にました」
「では、それを頭に思い浮かべ」
「すごくかわいい犬でした」私の言葉を遮って宮本さんは言う。「おりこうで、餌は食べていいと指示を出すまで絶対に食べないんです。毛並みもさらさらで撫で心地がよくって」
「宮本さん」私は言う。「お話しするのではなく頭で思い浮かべてください」
「あんなにいい犬だったのにもう死んでしまったんです」
「宮本さん」私は言う。「私に話すのではなくて、頭で、思い浮かべてください」
「できません」
「お口を閉じて、想像してみてください」
「できません、やりたくありません」
宮本さんは頑なに言う。
「やりたくないのですか」
私が聞くと、
「頭で想像すると見破られてしまいます」
と宮本さんは答えた。
「見破られる?」
「わたしを見張っている団体がいるんです。わたしを勝手に繋げようとしてくるんです」
あ、これはだいじょうぶではないやつかもしれない、とわたしは思いはじめる。平面の方を振り返ると、平面は、ほらやっぱり、という顔をした。
「宮本さん」
私は言う。
「はい」
「その団体へ言いたいことっていっぱいあるわけでしょう」
「ありますよ、もうやめてほしいんです」
「それを頭に思い浮かべながら手に力を送ってみたらどうですか」
「あ」宮本さんは目を丸くして言う。「それならできます」
「うん、やってみましょう」
私が言い終える前に宮本さんは目を閉じて手に力を込め始めた。わあっとのみものに明るい黄色が差し込んでくる。
「あ、そうです、うまいです」
宮本さんは集中している。明るい黄色は細かく枝分かれしていき、のみものの中に黄色い毛細血管がびっしりはびこっているような状態を作った。のみものがこんな状態になるのを見たのははじめてだった。私はすこしうろたえたが、そのまま続けさせた。
なにを言っても宮本さんにはもう聞こえないようなので、私は宮本さんの前を離れ、吉村さんのところへやってきた。吉村さんも全く色のついていないのみものを手にしている。
「どうしたらいいですか?」
と吉村さんが言ったとき、ぱあん、と音がした。振り返ると宮本さんのコップが割れていた。使い捨て用の薄手のプラスチックでできたコップである。そのプラスチックのコップがガラスのように粉々に割れて、中に入っていたのみものがテーブルの上に広がっていた。
宮本さんの手からは血が出ていた。コップを割ったときに切ったらしい。私がまだ固定されていない黄色の毛細血管模様ののみものに触れようとすると、
「だめ」
と平面が私の手を掴んで避けさせた。平面は雑巾を持ってきて、直接触れないように気をつけながらのみものをビニル袋に入れた。テーブルを拭き上げた後ビニル袋に雑巾を入れて縛った。
「これ捨てておいてくれる?」
「わかった」
私は答えて袋を持って立ち上がった。宮本さんは震えていた。山田さんが宮本さんを慰めた。残りの三人は自分ののみものに集中しきっていた。吉村さんののみものにはいつまで経っても色がつきそうになかった。
袋を地下のゴミ捨て場に捨てて帰ってくると、宮本さんがいなくなっていた。四人はのみものを固定させ終わっていた。山田さんは白と黒のマーブル、辻君は黒、江川さんは緑とオレンジの混ざった色、吉村さんはなにも色のついていないのみものを持っていた。
平面は宮本さんを帰らせた上、吉村さんに指導をしなかったのだ、と思って私は少し腹が立った。私が腹を立てても仕方のないことだった。この講座の講師は平面だった。
「じゃあ、お手本見せてもらっていい?」
「え」
平面が言うので私は驚いた。そして思い出した。私はきょう皆の前で手本を見せることになっていたのだ。
「うまくできないかもしれない」
と私が言うと、吉村さんが笑った。なぜ笑われたのかよくわからず私は困惑した。
だいじょうぶだから、やってよ、と平面が言う。しぶしぶ私が受付からテーブルを運んでくると、平面がその上にジェルの入ったコップを置いた。
私は水のボトルを持ってきて、コップに注ぎ、ストローで液体をかき混ぜる。両手で包んでエピソードを思い浮かべ始めた。
ハイキングである。
小学生の時だった。学校の行事でハイキングに行くことになり、浮かれて準備をした私はお弁当を持ってくるのを忘れてしまった。母親に連絡をしたが間に合わず、みんなにおかずを分けてもらう約束をして山へ向かうバスに乗った。
バスが山に着くと、整列して山を登ることになった。といっても友達同士で並んで歩くため、列はゆるやかに崩れていった。私も友達のいるあたりに合流しておしゃべりしながらだらだら歩いていると、後方がざわついてきた。振り向くと、母親が山登り用の装備をばっちり身に着け小学生たちをぐんぐん追い越している。
母は私を見つけると大きな声で名前を呼び、駆け寄ってきた。はい、これ、お弁当、と渡されたのは立派なお重だった。
母はその後一緒に山を登り、頂上で二人でご飯を食べることになった。母はとても目立っていた。蛍光色の服を着て、本格的な登山リュックに携行食と飲み物をいっぱいに詰め込み、杖を持って歩いてきて、なにより私の隣を離れようとしなかった。母が目立つということは私が目立つということだった。とくにクラスの中心人物でもない私が正月にしか使わないような三段のお重に入ったお弁当を母親と食べているところは物珍しかったらしく、皆が写真に撮っていった。恥ずかしくて仕方がなかった。
目を開けると飲み物の色が、紺色、黄色、紫色、オレンジ色と宇宙のような色合いに変わっているのが見えた。そういう色合いのものを出そうと思ってエピソードを作ったので私は全く驚かなかった。
私はのみものを自分がこうしたいという色に変えることができる。平面にはできない、いままでいろいろな人たちを見てきた限りでは私だけができる技術である。
希望通りの色にするためには、希望通りのエピソードを作ってやればいい。ハイキングのエピソードは全くの創作だ。エピソードで動かされた気持ちを手に伝えるときの加減ではなく、エピソードを調整することで色を自在に変えているのだ。暗いエピソードなら暗い色になるというわけではないところが難しいが、直感的にこういうエピソードならこうなるという公式が私の頭の中ではすぐに導き出せる。
受講生たちから拍手が起こった。私は照れ笑いをしながら、固定されたのみものを手に取り、みなさんもどうぞ、飲んでくださいね、と言った。
「さすがだね」
平面は言う。
「緊張したよ」
のみものを飲みながら私は答える。しゅわっと炭酸の入った柑橘系の甘い味が口の中に広がった。
「こつはなんですか?」
山田さんが聞いてくる。
「あんまり、わからないで直感的にやっているから」
と私は少し濁して言う。
「本当にすごいです、表現力の違いだなあと思います」
山田さんは自分ののみものと私ののみものを見比べながら言う。
「ありがとうございます」私は言う。「山田さんの白は私には出せない色なので、すごいなと思っていますよ」
「そうですか?」
山田さんは照れ笑いを浮かべた。
「いつから助手をやっているんですか?」
聞いてきたのは辻君だった。
「この講座をはじめてからだから、そんなに長くないですよ」
「どうして助手になったんですか?」
「立て続けに聞くのやめなよ」
山田さんが辻君をたしなめる。辻君はどうしてですか、ともう一度言った。
「この講座の前身にあたる講座を受講していたからです」
「そこでヘッドハンティングされたんですね」
辻君は顎に手を当てて言う。
「そういう感じではなくて、気が合う友達として手伝っているというのが近いかも」
「どうやったら助手にしてもらえますか?」
「え」
「どうやったら助手にしてもらえるんですかね、ぼく、先生くらいうまくなりたいんです」
同じことを二度言った辻君は、山田さんに、もう、しつこいよ、やめなさい、と言われてしぶしぶ質問をあきらめたようだった。
どうして皆助手になりたいのだろうか? 強いて言えば毎回の飲み代を出してもらうくらいで、給料をもらっているわけではなく、扱いがとてもいいわけでもない。平面と私が友人だから続いている関係である。
平面がほとんど神格化されているから、平面に指導を受ければなにかすごいものになれるのではないかという期待があるのかもしれなかった。
私は平面から指導を受けたことがほとんどない。講座受講生だった頃にも講座の時間中は放っておかれていた。その後の飲み会になると平面は私を呼んでのみものの技術に関すること以外のいろいろな話をしたが、のみものについての話をされた試しがない。平面に師事したおかげでここまで来られたなどと思ったこともない。平面に師事したという気持ちも正直に言うとあまりない。
辻君ののみものは真っ黒だった。
皆が帰った後、平面はちょっとこじゃれたイタリアンで飲みたいと言った。いつもの飲み屋街はくたびれた感じの店が多いので、そんなおしゃれな店がある訳ないだろう、と言い合いながらうろうろしていると、あった。席数こそ少ないが、白と赤と緑でまとめたしゅっとした雰囲気のあるおしゃれなイタリア料理店だった。
入店して席に着くとすぐに細長いパンが出された。いつ食べていいのかわからず私は手をつけなかったが、平面はワインが来る前にぼりぼりと食べ終えてしまった。
カプレーゼとチキンの香草焼き、薄焼きのピザを注文して、ワインはおすすめのものを持ってきてもらった。
乾杯すると平面は苦々しい顔をして、
「辻君」
と言った。
「ああ、辻君」
「辻君、江川さんと一緒に帰っていったね」
平面は渋い顔のままストローでスパークリングワインを飲む。
辻君は帰ろうと立ち上がりかけた江川さんを捕まえて、ちょっと駅まで一緒に行きませんか、と誘い、連れ添って帰って行ったのだった。
「あれは食われたね」
「食われたって言うのやめてよ」私は冗談混じりで抗議する。「ほんと江川さんもったいないな」
「なにが?」
「もう来なくなっちゃうでしょ」
私が言うと平面は声を上げて笑った。
「来るよ江川さんは」
「でもいままで辻君が目を付けた人は」
「皆来なくなったよね」
平面はワインを飲み終えて二杯目を頼む。なんでもいいからおすすめをくれと言ったら赤ワインが来た。ストローを差し替えて平面は赤ワインをごくごく飲む。グラスを傾けたり揺らしたりすることによって空気を含ませてなんとかという理論を唱えている人が、ストローでワインを飲む平面の姿を見たら卒倒ものだろう。
「でも江川さんはまた来る」
平面はストローから口を離して言った。
「ずいぶん自信あるね」
「あの人は知ってしまったんだよ、のみものの楽しさを」平面は言う。「それは男がどうこうなんかに左右されない」
「なるほど」
カプレーゼがやってくる。平面はフォークを取ったが、かなりの重さがあったため、手がぐにゃりと曲がってしまった。私は店員を呼んで平面のフォークをデザート用のものに取り替えてもらった。
「ありがとう」
平面は言う。
「いえいえ」
「そういうところだよねあなたのいいところは」
すぐにやってきたデザート用のフォークで、平面はトマトを刺して口に運んだ。
「黒かったね」
私は言った。
「辻君ののみものでしょ」平面はテーブルにひじを突いて姿勢をだらりと低くする。「あれはいけないね」
「やっぱりよくないんだ」
「基本的に色によって善し悪しはないんだけど、白と黒だけはちょっとねー」
「なにがどう悪いの?」
「悪いのよ、とにかく」
平面はモッツァレラチーズとトマトをいっぺんにフォークで刺そうとして失敗し、トマトだけを刺して口に運んだ。
「そうなんだ」
「難しいな、性格が悪いから黒いとかってことじゃないんだけど、でも黒はよくない」
「よくわからないけど」私は言う。「そういうものなのね」
「今日は大変だったな」
平面はひじをつきながら食事を続けようとする。私は平面をたしなめようか悩んで好きにさせておくことにした。
「宮本さんでしょ」
「だからほっといたのに」
愚痴っぽく平面は言う。
「わかってたんだ」
「わかってたよ」
「ごめん、出過ぎたことした」
「いや、あなたが潰れるよりずっといい」
平面は言う。私は間の抜けた返事をした。自分が潰れるというイメージがすぐには沸かなかったのだ。
「だいじょうぶ? 驚いたでしょ」
「驚いた」
私は正直に言う。
「あんまり深く考えない方がいいよ」
平面に慰められて、私は自分が宮本さんを気にかけすぎたことが宮本さんの爆発に繋がったのだろうと気が付いた。宮本さんのことは放っておけばよかったのに、変に心配したり気にかけたりしたから、私には寄りかかってもいいと思ってしまったのかもしれない。もともとの宮本さんの気質にターボをかけてしまったのは私の半端な優しさだ。
「深く考えてる」
平面に言われて私ははっとなる。カプレーゼの色が妙に鮮やかに見える。
私はフォークをとって、平面の残したモッツァレラチーズをぐさりと刺し、食べた。噛むと、モッツァレラチーズの繊維のようなものをぶちぶちと断ち切っている感じがした。これがいいモッツァレラチーズの証なのかそうでないのかはよくわからなかった。やや不快に思われる食感だった。
「この講座は平面のものだから」私は小さい声で言う。「邪魔にならないよう気をつけます」
「いや邪魔してくれていいんだよ、わたしにしかできないこともあるにはあるけれど、あなたはわたしにできないことができると思っている」
「買いかぶりだよ」
「そんなことない、自分を卑下しすぎてる、もっと自信もっていいよ」
平面は言った。チキンの香草焼きと薄焼きのピザが同時に来た。
「自信ねえ」
「あなたくらいのみものをうまく操れる人なかなかいないよ」
「平面の方が何倍もすごいじゃない」
「わたしは平面だからうまいの。平面じゃない人で、あんなにうまくできるなんてなかなか希有な才能だよ」
「ねえ」私は言う。「なんで平面だとのみものをうまく操れるの?」
「言ってなかったっけ」
平面はきょとんとしてから店員を呼び、次のワインを持ってくるよう頼んだ。
「平面はコップに接する手の面積が大きいから」
やってきた赤ワインにストローを差し替えて平面は一気に飲んだ。
「あとはまあ、いろいろ」
「いろいろね」
「うん、いろいろ」
平面はメニューをください、と店員に声をかけた。なにか追加で頼もう、と言いながらしばらく見ていたが、ぱたんと閉じて、次のワインを持ってきてほしいとだけ店員に伝えた。
私は薄焼きピザをかじった。
「ねえ、わたしの学生の頃のあだ名は」
「パラッパラッパーでしょ」
平面の言葉を遮ってわたしは言う。
「ちがう、ウンジャマラミー」
平面は言った。
「なにそれ」
「続編」
「続編?」
「パラッパラッパーの」
平面は新しいワインにストローを差し替えて一気に飲む。
「ねえ泊めてもらっていい?」
「いいよ」
「いつもありがとう」
ワインを飲み終えた平面は一万円札をポケットから取り出して起き、ぐったりとテーブルに突っ伏した。私は残っているチキンの香草焼きを食べた。鶏胸肉を下手に調理したからぱさぱさで、飲み物がほしくなった。手元にはワインしかなかった。ワインを水のように思い切り飲んだら酔ってしまった。頭がくわくわする。意識が遠のいていきそうな予感がある。薄焼きピザをかじりながら片手間に平面を丸めたらぐちゃぐちゃになってしまった。
ぐちゃぐちゃの平面を抱えて会計を済ませ、店を出た。外は寒かった。一枚上着を足せばよかったと私は後悔した。適当に巻いた平面は家まで向かう間に何度も崩れた。そのたびに私は平面を巻き直した。平面はぐっすり眠っているようだった。
今日の講座は人数が少なかった。山田さん、江川さん、それに市倉姉妹の四人がきっちり正座をして講座が始まるのを待っていた。
和室を包む妙な緊張感の正体が分からない市倉姉妹は不安そうな顔をしていた。宮本さんと吉村さんが欠席であることも二人の不安を強めているようだった。山田さんと江川さんはぎこちなく会話を交わしていた。山田さんの明るさを持ってしても固まった空気は打開されなかった。
平面が挨拶を始めた。私は、なぜこの人たちは平面の講座を受講しているのかを考えていた。公民館の掲示板に貼ってある講座の誘いのポスターは、のみものを作る講座です、とMS明朝で書いただけのひどく簡単なものであった。そのポスターから皆は何を読みとったのだろう。講座を受講し始めたばかりの頃の山田さんに、どうしてこの講座を受けようと思ったのかと聞いてみたことがあった。答えは、楽しそうだから、だった。楽しそうな講座は彼女たちにとって楽しい講座となったのだろうか。
平面の挨拶は長かった。長く話せば話すほど宮本さんのことに触れない不自然さが強く感じられるように思えた。四人は神妙な顔をして平面の話を聞いていた。私は水の入ったペットボトルを取ってきて平面の話が終わるのを待ったが、挨拶はいつまでも続きそうに思われた。どこかで遮らなくてはいけないのかもしれないが、喉の構造が立体的でないからか、ほとんど息継ぎをしないでしゃべる平面の話には切れ目がなかった。盛り上がりも盛り下がりもなかった。
ぼんやりと平面の話を右から左に聞き流していると、いつの間にか話は終わっていた。四人と平面の視線が私に刺さっていた。私は急いでペットボトルの水をそれぞれのコップに注いでいく。
今日はおそらく市倉姉妹のフォローに回った方がいいだろう。市倉姉妹の前に座って、振り返り、山田さんと江川さんの様子を見た。山田さんは何のエピソードを頭に思い浮かべようか悩んでいるようだったが、エピソードさえ決まればすぐにのみものを白くすることができそうだ。
江川さんがコップを手で包んで目を閉じた瞬間、のみものはぼわっと黒くなった。
「あの」
市倉姉妹の妹、千佳が私に話しかけた。
「なんですか」
「調子が悪いみたいです」
市倉姉妹の姉、真奈が言った。
「二人とも?」
「はい」
「そうです」
「どうする、帰る?」
市倉姉妹は顔を見合わせて、小声でなにかを話し合い始めた。二人は制服ではなく揃いのジャンパースカートを着ていた。
「ねえ」
平面が言う。いつの間にか私の後ろに平面が立っていたのだった。
「もうちょっといたら? この人がのみものの色を変えるところが見られるよ」
「え」
私は思わず声を上げた。今日も私がのみもののパフォーマンスをやる手はずになっているとは聞いていなかった。
「ほんとうですか」
真奈は言った。
「見たいです」
千佳は言った。
「じゃあもうちょっと頑張ってみて。わたしが教えるから」
平面は言って私を後ろへ下がらせた。
私はコの字に並べた机の内側から出て、受付のところに座り、四人と平面をぼんやり眺めた。ぼうっとしている場合ではなく、エピソードを考えなくてはならなかった。私は頭の中でエピソードの構想を練ろうとした。何も思い浮かばなかった。もわもわとした何かで頭の中がいっぱいで、そこに想像の余地はなかった。
江川さんののみものはどんどん黒くなっていった。江川さん自身も困惑しているようだった。
私は黒いのみものを眺めながら、ふと辻君と寝たときのことを思い出した。どうだったかはあまり覚えていない。唇を合わせようとして歯が当たったことだけをはっきり記憶している。辻君は少し前歯が飛び出しているからだ。
私は辻君と寝たことがある、という言葉を何度か頭の中で繰り返してみた。江川さんと私は同じ人と寝たことがあるという意味では姉妹だ。どっちが姉に当たるのだろうか。本当の姉妹は先に生まれた方が姉なのだから、そういう姉妹は先に入れられた方が姉だろう。では私が姉だ。妹にのみものの色の調整の仕方を教えにいこうかと思ったが、それよりも自分のエピソードを考える方が優先だった。のみものの実演までにエピソードを作ることができるか、ややぎりぎりではあったが、なんとかできそうな気がしてきた。
「すいません」
顔を上げるとのみものを持った山田さんが立っていた。
「はい」
「あの、どうしても白くなっちゃうんですけど、どうやったらほかの色を出せるようになりますか」
山田さんはまっすぐ私を見つめて言う。いや、今はエピソードを練るからちょっと無理、とは伝えにくかったので、私は受付用の机にのみものを置くよう山田さんに言った。
「エピソードはどんなことを思い浮かべていますか」
山田さんに聞く。
「いろいろです。最近の仕事の合間に食べたおやつのこととか、小さいときに犬が死んだこととか、学生時代によく行っていた本屋のこととか」
「いろいろですね」
「そうなんです」
山田さんは頷く。
「ちょっとやってみましょう、エピソードはなんでもいいです」
私が言うと山田さんはコップを手で包み目を閉じた。エピソードを思い浮かべているらしい。コップの中ののみものがどんどん白く色づいていく。ときどきぷかっと黒色が混じるが、基本的には白一色である。
山田さんの手を私の手で包むと、山田さんの手がとても温かいことに気がついた。温かく、細く長い指で、なめらかな手だ。この手と性行為をしたらとても気持ちがいいだろう。考えがすぐにいやらしい方向へ行ってしまうのはさっきまで辻君のことを考えていたからかもしれない。
私は山田さんの指を撫でる。山田さんの指がぴくりと反応する。
「もう少し優しくコップを包んだ方がいいです」
適当なことを私は言う。山田さんは真剣なので、はい、と言って指の力をゆるめた。指の間接のひとつひとつが私の手を誘ってくるように感じられる。これはいけない、こんなことを未成年のいる場でしてはいけない。
山田さんの手にむしゃぶりつきたい気持ちを抑えて私は、
「少しエロティックなエピソードを思い浮かべてもらえますか」
と言った。
山田さんはわかりましたと小さな声で言う。のみものの色に黒色が混ざってくる。黒か、と私は思った。山田さんも辻君と寝たことがあるのかもしれない。私は山田さんの指がコップに触れる度合いを少し調整する。黒色に混じってやわらかいピンク色が発生しはじめていた。
「あ!」
目を開けた山田さんは嬉しそうに言う。
「固定するまでもう少しがんばって」
「はい」
私は席を立った。山田さんを遠くから見てみようと思ったのだ。山田さんは私が離れても小さな机に向かってひとり集中し続けていた。背筋がすっと伸びている。縦縞の入ったスタンドカラーのシャツは山田さんによく似合っていた。
そろそろのみものが固定される時間だった。
江川さんののみものはぼやっとした黒色になり、市倉姉妹は色こそ薄いが何色もが混ざったうつくしいのみものを作り上げていた。山田さんののみものはベースが白色で、そこにピンクが差し込んでいる。黒色は消えてしまったらしい。
あのピンク色は私がいやらしいことを想像するよう指示して染めさせた色だ。誰もがいやらしいことを思い浮かべればいつでも必ずのみものをピンクに染めることができるわけではない。山田さんが、いま、いやらしいことを想像するとピンク色になるとわかっていて私は指示したのだ。いやらしいことがピンク色になるというのは直接的でおもしろいと思ったのだった。
のみものを飲み始めた山田さんの口元を見ていると、平面が私の肩をつついた。
「ジェルとコップ用意するから、小さい机持ってきてくれる」
私はのみものをピンク色中心に組み立てることに決めた。私がいまピンク色をつくるためにはいやらしいエピソードを考えればよかった。私は受付用の机を運びながら、山田さんとのいやらしい行為を想像した。この妄想によって皆の前でのみものの色を変えるパフォーマンスをすることの罪深さに貧血を起こしそうになった。
パフォーマンスはうまくいったといえるだろう。少しずつトーンの違うあらゆるピンク色をつぎつぎに発生させてみせた。市倉姉妹は私の変化させたのみものを飲みたがったので、エピソードの種類からして大変申し訳ないと思ったがふたりにあげてしまった。甘くてフルーティーですっぱくて微炭酸だ、と市倉姉妹は大喜びだった。
講座が終わり片付けをして、平面とふたりで公民館を出ると、電柱に寄りかかるようにして辻君が立っていた。そのポーズがあまりに格好付けたものだったので私は笑ってしまった。
「辻君?」
平面が言った。
「うそつきばっかりですよ」辻君はだしぬけに言う。「ほんとうにうそつきが多い」
芝居がかった感じの言い方に私はまた笑ってしまいそうになったが、平面が真剣に話を聞こうとしているのを見て笑いが引っ込んだ。
「山田さんはうそをついている」
「そうね」
辻君の言葉に平面は頷く。
「先生の言葉にもうそがある」
「そうかしら」
平面まで芝居のような話し方をする。今時芝居でもなかなか聞かないようなしゃべり方だ。
「先生の助手もうそつきだ」
「そんなことはない」平面は強く否定した。「それはない」
「助手はうそをついています」
「うそをついていると言えばいいわけじゃない」
私は自分の話をされているというのにすっかり場から取り残されていた。平面と辻君はにらみ合っている。辻君は口の端にすこし笑みを浮かべはじめた。ふたりは、少なくとも辻君はこの芝居のようなやりとりを楽しんでいる。
「先生、僕を助手にした方がいいですよ」
辻君は腕を組んで言う。
「するわけがない」
「受講生をそんな風に否定していいんですか」
「いまは受講生と先生の関係じゃない、ただの人間と人間の対立」
「自分のこと人間って思ってるんですか?」
辻君は鼻で笑う。だめだ、これは平面が激怒するフレーズだ、と私は焦った。平面は余裕の表情をしているが怒りで体が震えている。下敷きをびよんとはじいたときのような音が平面から鳴っていた。
私はとっさに辻君に飛びかかった。辻君は抵抗をしなかったので、どうしていいかわからなくなり、そのまま抱きついた。辻君は抱かれたままになっていた。
「いまのうちに逃げて!」
私まで芝居がかった言い方をしてしまった。平面はわかった、と言って走っていった。
平面が角を曲がって見えなくなるまで私は辻君を強く抱きしめていた。辻君が全く抵抗しないので、私は辻君を抱きしめる腕をゆるめた。辻君と目が合った。呆れたような顔をしていた。どうして私が呆れられなくてはいけないのか、すべて辻君のせいではないか、と私は思った。こんな変な空気をつくったのは辻君だ。
私は走って平面を追いかけた。辻君は私を目で追った。何度振り返っても辻君は私のことを見ていた。
角を曲がってすぐのところに平面がいた。平面は私の肩をぽんぽんと叩くと、
「飲みに行こう」
と言った。
平面が選んだのは焼鳥屋だった。店の外まで煙がもうもうと上がっていて、燻されてしまいそうだった。平面は煙のことは気にならないようで、ひょいひょいと軽い足取りで中に入っていった。店内に入るとさらにひどく煙たかったが、席に着く頃にはもう慣れていた。
座敷でよろしいですか、と店員は平面に聞いた。平面はそれでいいですと言った。平面はティッシュで地面に触れていた部分を丁寧にふき取り、器用に足を折り畳んで正座をした。
注文を聞きにきたので、平面はハイボール、私はカシスソーダを頼んだ。あと、アスパラの肉巻きとねぎまと砂肝を二本ずつ、と平面は言った。私はもやしのナムルを頼んだ。
お通し代わりのキャベツと一緒に辻君がやってきた。
「辻君」
私は言った。
辻君は靴を脱いで平面の隣に座り、ジンジャーエールを頼んだ。ついでに串ものをぜんぶ三本に変更してくれと言った。平面はふつうの顔をしていた。まるでもともと三人で飲みに行くことが決まっていたかのようだった。
飲み物が来ると辻君はおつかれさまでした、と言ってジンジャーエールの入ったジョッキをひょいと持ち上げた。私はジョッキを合わせた。そのあと辻君は机に置かれた平面のジョッキにジョッキをかつんと当てた。私も平面のジョッキにジョッキをかつんと当てた。
平面はストローでハイボールをぐいぐい飲んだ。辻君はジンジャーエールにちょっと口を付けるとキャベツを食べ始めた。私もキャベツを食べた。ごま油とにんにくのきいたぱりぱりのキャベツだった。
「助手に」
「だめ」
平面はすごい速さで断った。もやしのナムルがやってきた。
辻君はもやしのナムルに箸をつける。辻君の口の中でもやしが噛み砕かれていくのをぼんやり眺めながら、私は、
「山田さんのついているうそってなに」
と言った。
「平面だよ」辻君は言う。「あいつは」
「平面?」
でも、と私は思う。平面という存在は名前を持つことを許されていないはずだった。それに、山田さんには立体感があった。とても温かい手を持っている普通の人間のように私には思えた。
「平面をうまいこと肉で盛り上げて人間みたいに見せてる」
辻君は言った。
「平面を立体にするなんて無理だよ」
私は言う。
「無理じゃない」
「でも」
私はちらと平面を見る。平面はハイボールを飲み干して店員を呼び、梅干しの入ったあたたかい焼酎を注文して席を立った。
「平面」
「ちょっとトイレ」
平面がトイレに行かないことを私はもちろん知っているし、おそらく辻君も知っているはずだった。
私は平面を引き止めるために、平面、と呼んだ。もう一度呼ぼうとした私を辻君が手で制した。平面は振り返らずまっすぐ店の外へ出て行った。
「でも?」
辻君が話の先を促す。
「でも」私は言う。「そうしたらみんな立体になってるんじゃない?」
「なんで?」
「立体になった方が、人間の方が都合いいことが多いから」
「出た出た」
辻君はキャベツを箸で摘んで器の外に放り投げた。放り出された葉っぱをよく見ると虫食いの穴が開いていた。そのくらい気にしないで食べればいいのにと私は思った。
「出たってなに」
「平面を下に見ている」
「見てないよ」
「見下してでもいないと、人間の方が都合がいいなんてこと言えないよ」
辻君はまたキャベツを器の外に放り投げた。私は辻君の放り出したキャベツを手で摘んで、辻君の取り皿に乗せた。辻君は黙ってそのキャベツを食べた。
「下になんか見てない」
「はいはいわかった」辻君は言う。「主張はよくわかりました」
「見下してないから」
「はーい、わかりました」
言い返そうとすると梅干しの入ったあたたかい焼酎がやってきた。辻君がキャベツを食べながら焼酎を受け取って、平面の座っていた席に置いた。
「うそついてるでしょ」
「誰が」
私は聞き返す。
「私? だから、見下してないって」
「違う、その話じゃない」
辻君は通りかかった店員を呼び止めてキャベツのおかわりを頼んだ。あいよーと店員は言った。
「エピソード」辻君は言う。「作ってるでしょ」
「作ってる?」
「本当には起こっていないエピソードでのみものの色を変えてない?」
「うん」
私は頷く。
「だめなんだよ」
「なんで」
「なんでとかじゃなく、のみものの色を変えるときに思い浮かべるエピソードは創作じゃだめなの。自分の体験したことじゃないとだめ」
「そんなの知らない」
私は言う。キャベツのおかわりが来る。辻君は自分の取り皿にキャベツを山盛りにした。
「知らないじゃないよ。だめなの」
じゃくじゃくとキャベツの繊維を噛み砕きながら辻君は言う。
「誰が決めたの?」
「さあ」
「知らないんじゃん」
私はキャベツに箸を伸ばしながら辻君に言う。芯の部分をこりっと奥歯で噛んだ。
「とにかく、だめなんだよ」
「そんなの聞いたことない」
串ものが出されると同時に平面が戻ってきた。平面は足の裏にあたる部分の汚れをティッシュで拭き取って座敷に上がり、正座して焼酎をストローで飲んだ。
「助手にしてくださいよ」
「だめ」
平面は砂肝の串を手に取った。やきとりの重さくらいであれば平面もぐにゃりとなることなく手で掴むことができる。平面にもできる、という考え方をしてしまうのが平面に対する差別心のあらわれであるとしたら、私は平面に対して長い間上から目線であったことになるなとふと思った。
「ごめん」
私は平面に向かって言う。
「謝るなよ」辻君は言う。「謝ると認めたことになるし、謝ってもどうしようもない」
「だいじょうぶ」
平面は梅干しをストローの先でつつきながら言った。
「わかってると思うけど先生はいま大丈夫じゃないからな」
辻君はねぎまをとって、肉、ねぎ、肉、ねぎ、とリズミカルに食べていく。じゃあ私はどうすればいいのだろうと思ったが、何をしてもだめだし、何をしなくてもだめで、つまりどうしようもないのだった。
「明日ひま?」
平面は私に聞いてくる。
「ひまだよ」
「明後日と明明後日は?」
「ひまだよ」
「ひまばっかりだな」
辻君が茶々を入れる。平面は気にせず、
「旅行に行こう」
と言った。
「旅行? いきたい」
「でしょ」
「俺は?」
「辻君はだめ」
平面が笑いながら言う。私は残っていたもやしのナムルを取り皿に移して少しずつ食べた。辻君はぶつぶつ文句を言っている。前歯がでっぱっている。なで肩である。やせていて腰が細い。私はこの人をもう好きではない、とは言い切れなかった。
「どこに何しに行く?」
私は平面に聞く。
「車で二時間くらいのところに行く」
「どこ?」
私は言う。
「それはまだないしょ」
「よくわかんないけど、行く」
「俺も」
「辻君はだめ」
平面が笑いながら言い、座布団を枕にして眠り始めた。
「先生」
辻君が平面を起こそうとするので私は止めた。
「寝かせてあげて」
「連れて帰れないだろ」
「私の家に泊めるから」
私は立ち上がってテーブルをぐるりと迂回し、辻君の後ろに座って平面をぐるぐると巻いた。
「え」辻君は言う。「巻いていいの?」
「うん、持ちやすいから」
「すごいな」辻君は箸を置いた。「なんか、すごいわ」
ぐるぐるに巻いた平面を私の家の床に置いておくと、寝息のリズムで巻きが甘くなったりきつくなったりした。それを私は朝になるまで眺めていた。
八時頃になると平面は自然にほどけて、起きあがった。
「シャワー借りていい」
「いいよ」
私は今日着ていく服を選びながら言った。平面のシャワーははやい。ざあっと浴びて拭き取るだけだからだ。
入れ替わりで私がシャワーを浴びた。シャンプーをしてコンディショナーをつけて、体をあちこち洗って、コンディショナーと体を流して、顔を洗う。上がった後には化粧水と乳液と美容液を使う。そのあと化粧をする。平面のなにもかもをさっと済ませる様子を見ていると、そういう一連のすべてが無駄に思えてくる。
私は平面を長く待たせて支度を終えた。平面は私が支度をしている間に外へ出て電話をかけ、レンタカーを借りる手配を済ませたらしい。
「ありがとう」
私が言うと平面は、
「いえいえ」
と軽く答えた。
レンタカー屋は歩いて数分のところにあるようだった。私はふと、平面は運転ができるのだろうか、と思った。私は免許を持っていない。平面は取ることができないだろうし、そもそもアクセルを強く踏むだけの脚力が平面にはない。力が入らずへなっと曲がってしまう様子が簡単に想像できた。
「私、免許持ってないよ」
私は平面に言う。
「そうだろうと思ってた」
平面は言う。
ではどうするつもりなのだろう、と思いながら道を曲がり、大きな道路に出た。レンタカー屋が見えてくる。店の前に山田さんが立っていた。山田さんは道路の向かい側で信号を待っている私たちを見つけると大きく手を振った。平面は大きく手を振って返した。私も手を振った。山田さんは嬉しそうにさらに大きく手を振った。平面も曲げられる限界まで手を振った。腕がちぎれる、と平面は言った。私は笑った。
「お誘いありがとうございます」
山田さんは言う。
「今日お休みなんですか」
「わりあい融通のきく仕事で」
私の問いに山田さんは答える。
「ごめんね、運転任せちゃって」
平面は言う。
「大丈夫です。楽しみです!」
山田さんは足取り軽く店内に入っていった。あれこれの手続きを手早く済ませると、私と平面が店内に呼ばれた。店員さんがそもそもレンタカーというものはどういうものかという説明をしはじめた。なんのための時間なのだこれはと思ったが、平面がいるから貸す側が慎重になっているのだと説明の終盤になって気がついた。別に平面が運転するわけではないのに、と言いかけて、辻君の言っていたことが本当ならば山田さんは平面なのだったと思い出した。
もし山田さんが平面なのだとしたら、免許を持っているのはおかしい。平面には名前がないから免許を取得することが難しいはずだし、ぺらぺらだからアクセルもブレーキも踏むことができないだろう。平面上に肉を盛り上げて人間のように仕立てる、と辻君は言っていた。そうすれば運転も可能なのだろうか。
私は鍵を受け取っている山田さんをちらりと見た。まったくもって普通の人間と変わらない。平面に肉を盛り上げたなどという粘土細工のようなことをしたような不自然さは山田さんの体にはなかった。
「じゃあ、行きましょう!」
と言った山田さんの二の腕を私は思わず握ってしまった。ふにふにとしていて筋肉の少ない二の腕だった。勢いのまま、ぐにゃぐにゃに揉みしだいてみるが、平面が中に隠れている様子はなかった。
「セクハラだ」
平面は笑って言う。
「わたし別に嫌じゃないです、二の腕触られるの」
と言った山田さんはわたしの腕を掴んで、反対側の二の腕に私の手を持っていく。
「左右平等に揉んでください!」
私は言われたとおり左右平等に揉んだ。
山田さんが運転席に座り、助手席に平面、後部座席に私が乗ることになった。平面はカーナビに目的地を入力して、そこに向かって走るよう山田さんに言った。目的地まではだいたい二時間ほどかかるようだった。
「ではいきましょう」
眼鏡をかけた山田さんが言う。レンタカー屋を出発して大きな道路に出る。山田さんは加速も減速もなめらかに行った。急ブレーキを踏むこともなかった。もし平面だとしたらこんなにうまく運転ができるわけないだろうと私は思った。
「お菓子食べます?」
山田さんは言う。
「いいね」
平面は目的地を確認しながら言う。
「助手さんすいません、わたしの鞄から好きなの取り出してもらえますか」
「わかった」
山田さんの鞄は後部座席に置いてあった。私は山田さんの鞄の中を覗く。人の鞄の中を覗くのは許可をもらっていても背徳感のある行為だった。鞄の中には膨らんだレジ袋と財布と携帯電話と生肉の模様のポーチが入っていた。なぜ生肉の模様のポーチを使っているのだろうか。聞いてもよかったが、頼まれたもの以外をじろじろ見たというのはあまり好ましくないことだと思ったので、おとなしくレジ袋の中からアーモンドクラッシュポッキーを取り出す。
「アーモンドクラッシュポッキーの中身の少なさどう思います?」
山田さんは私に聞いてくる。
「少ないんだっけ」
「少ないですよ! ひと箱食べてもぜんぜん物足りない」山田さんは言う。「たぶん、アーモンドとチョコでコーティングされているから、ノーマルのポッキーに比べて一本あたりの占める面積が大きいんです。そのせいでたくさん箱に入らないんですよ」
と山田さんは分析した。
「だからふた箱買いました、食べてください」
レジ袋にはアーモンドクラッシュポッキーがふた箱入っていた。
山田さんのことを明るいひとだとは思っていたが、こういうアクティブな面白さを持っているタイプだったとは知らなかった。私は少し驚いた。
「じゃあ、ひと箱ちょうだい」
平面が言うので、私は、
「持てる?」
と聞いた。
「持てるよこのくらい」
平面は笑って答えた。
「持てないものもあるんですね」
驚いて言うのは山田さんだ。そうなのよ、と平面は言う。
平面の手がどのくらいの重さのものまでを持つことができるのか、わりあい付き合いの長い私でもよくわかっていない。平面自身もそこまできっちり把握していないらしい。酒のつまみを手に取った瞬間腕がぐにゃりと曲がってしまうことがときどきある。
前方の座席のふたりがアーモンドクラッシュポッキーのひと箱を分け合い、後部座席の私がもうひと箱を食べることになった。ひと箱にはふた袋のアーモンドクラッシュポッキーが入っている。私はひと袋分を残して平面に渡した。いいよ、食べなよ、と平面は言う。そのためまるまるひと箱を私が食べることになった。
思えば平面と旅行をするのははじめてだった。平面の家か、私の家か、講座か、飲み屋か、それらを繋ぐ交通手段でしか平面とは会っていなかった。
平面と山田さんはわいわいと世間話をしている。私はアーモンドクラッシュポッキーを黙って食べた。食べ終わった後、口の中にナッツが残っている感じがあった。舌で探してもなかなか見つからなかったので、私はナッツが残っている感じをそのままにしておくことにした。そのうちナッツの感じは気にならなくなった。ふと思い出したとき、また気になった。私はもう一度ナッツのことを忘れた。二度忘れると再び気になることはなかった。
「助手さんは」
山田さんが私に声をかけた。
「なに?」
「平面じゃないんですか」
「え」
私は口ごもる。山田さんからそう切り出されると思わなかったからだ。
「平面じゃないよ」
「そうなんですね」
「山田さんは?」
「私? 私は平面じゃないですよ」
山田さんは笑って言った。
「そうなの?」平面がアーモンドクラッシュポッキーの空き箱を手でもてあそびながら言う。「てっきり平面だと思ってた」
「平面っぽいですか?」
「いま平面に肉を付けて平面じゃなくする技術があるじゃない、あれかと思ってたの」
正直に平面が言うので私は驚いた。人が平面かどうかについて、こんなにはっきりと話していいものなのだろうか。
「そういうのがあるんですね、知らなかった」
山田さんはウィンカーを出して車線を変更する。
「辻君が言ってて」私は言う。「辻君が、山田さんは平面だって」
「辻君が?」
「そう」
平面が相槌を打つ。
「そういうところあるからな辻君」
苦笑いをしながら山田さんはアクセルを踏む。
あ、箱、邪魔ですよね、と山田さんは平面を見て言った。私は平面からアーモンドクラッシュポッキーの箱を受け取って、二つを手に持った。
「レジ袋の中にもうひとつレジ袋があるので」山田さんは言う。「それに入れてもらえますか」
レジ袋の中のレジ袋を私はすぐに見つけだすことができた。レジ袋の中のレジ袋を取り出して、アーモンドクラッシュポッキーの空箱を二つ入れる。ごみを山田さんの鞄に入れてよいものかしばらく悩み、鞄の脇に置くことにした。
トイレ休憩を一回挟んで、私たちは目的地周辺に到着した。カーナビが目的地周辺ですと告げたところはあまりに何もない場所だった。山田さんが困っていると、平面が、もう少し進んでから右に曲がってほしいと言った。その通りにすると民家があった。
平面は民家の前で車を止めさせて、車を降り、門についているチャイムを鳴らした。一言二言会話すると、平面は車を中に進めろというアクションをした。山田さんは車を玄関前まで進めて私を下ろした。やたらに大きな家の玄関からおじいさんが顔を出し、車を止めるところはもう少し奥にあるから、そこに置いてくれということを山田さんに伝えた。
山田さんが車を出すと、私とおじいさんは二人取り残された。話すことがなくて、二人でもじもじしてしまった。玄関には表札がなかった。なにさんという人なのだろうと思っていると、門の前で降りた平面がのんびり歩いてやってきた。
「おかえり」
おじいさんが言う。
「ただいま」
平面は言った。
山田さんが走ってやってきて、
「あの、車停める場所、池の脇でよかったですか」
とおじいさんに言う。
「合ってます、ありがとうございます」
おじいさんは頭を下げて、家の中に入っていった。平面もついていこうとするので、ちょっと、あのおじいさんは誰、と私は平面に耳打ちした。
父です、と平面は言った。
平面に父親がいたということを私ははじめて知った。
「まあどうも、遠くまで来ていただきありがとうございます」
出迎えてくれたのはこれ以上ないくらい母親感のあるお母さんだった。小花柄のニットを着て白いエプロンをつけているお母さんは私たちをソファに座るよう促した。ありがとうございます、と私と山田さんは言ってソファに腰掛けた。濃い紺色の合皮が張られたふかふかしたソファだった。平面はいろいろな装置がつけられている赤い座椅子に座った。背もたれを倒すと腹筋や背筋などさまざまな運動ができるようになっている、通信販売で人気の品だ。
「お二人は、あの子のお友達?」
「そうです」
山田さんが言った。
「いま教えてる講座の生徒さんと、助手」
平面は正確な情報を伝える。
「そうなの、まー、お仕事はなにをしてらっしゃるの?」
「事務職です」
はっきりと山田さんが言うので、私も、
「事務職です」
と答えた。
「すてきすてき」
平面のお母さんは満足そうに頷くと、菓子盆をテーブルの上に置いた。手作りらしいクッキーに、個包装されたクッキー、数個をまとめて包装されているクッキーなど、クッキーばかりが盛られている。
「いま紅茶を淹れているから少し待ってね」
「お母さん」平面が言う。「用意してくれた?」
「うん、用意してある」
平面のお母さんは台所に駆けていきながら言う。
「持ってきて」
「ちょっとゆっくりしてからでもいいでしょ」
紅茶の蒸らし時間を気にしている平面のお母さんに、平面は呆れたような顔をする。私と山田さんは笑った。平面は普段あまり表情が豊かな方ではない。
「車の運転はできるの?」
お父さんが私に聞く。
「すいません、できないんです」
「そうなんだ、最近の人は免許持ってないっていうよね」
お父さんはアーモンドの一粒まるごとついたクッキーに手を伸ばす。平面もクッキーを手にとって食べる。私と山田さんもクッキーを手にとる。ほろりと崩れる感じがとてもおいしかった。平面はあまり固いものを食べることができないのでこういう食感に焼き上げているのだろう。
「はい、お紅茶です」
お母さんが紅茶を運んでくる。平面の分にはストローが刺さっていて、さすがお母さんはよく理解しているなと私は思う。ただ私や山田さんに出された素敵なティーカップと違って、キャラクターの大きく描かれたマグカップで持ってきたことを平面はずいぶん嫌そうにしていた。私と山田さんはまた笑った。
「お仕事はどういうことをしているの?」
「事務職」お父さんの質問に平面がかわって答える。「さっき言ってたでしょ」
「事務職にもいろいろあるからさ」
お父さんは私を手で差して、あなたは何をしているの、と聞いた。
「私は」
どう答えようか私は悩む。
「事務職なの、それでいいでしょ」
平面は無理矢理話を切り上げてお父さんの手にクッキーを渡す。お父さんはクッキーをもぐもぐと食べて黙った。
「お母さん」平面は言う。「持ってきて」
はいはい、と言ってお母さんは奥の部屋へ引っ込んでいった。しばらくしてお母さんはお父さんを呼んだ。平面のお父さんは立ち上がって奥の部屋へ向かう。
「ごめんねうるさくて」
平面は私と山田さんに言う。
「実家に連れてきてくれたんだね」
私は言う。素敵なご家族だと思います、と山田さんも言った。
「仕事のこととかどうでもいいのに」
ため息をつきながら平面は言う。
「でも、失礼な話ですが、お仕事されてると思ってませんでした」
「私?」
「はい」
山田さんに言われて私は考える。どのあたりが仕事をしていないように見えるのだろうか。自分では毎日いわゆるオフィスカジュアルのような服装をしているつもりだったし、鞄もそれなりのものを持つように気を使っていた。
「どの辺がですか」
私は山田さんに聞く。
「なんとなくです」
「なんとなく、仕事をしていなさそう」
「はい」
「それ、一番いやだな」
私が言うと平面が笑った。確かになんとなく仕事してなさそう、と平面も言う。だからどういう特徴によって仕事をしていなさそうに見えているのか、ということを聞こうとすると山田さんが、
「すいません、言い過ぎました」
と謝った。それでこの話は終わりだという雰囲気ができた。
私は、私のどの要素によって働いていないように見えるのかもっと聞きたかったが、お父さんとお母さんが二人で大きな発泡スチロールでできた箱を持ってきたので、掘り下げて聞くことをやめた。
「なんですか? これ」
「のみものの素になるジェル」平面は言う。「ありがとう」
「いえいえ」
お母さんは発泡スチロールでできた箱を床に置くと、菓子盆を持って台所へ行き、クッキーをたくさん足して戻ってきた。お父さんはアーモンドが一粒まるごとついているクッキーに手を伸ばす。平面もクッキーをかじる。私と山田さんもクッキーを食べた。ほろほろしていた。
「水と混ぜるやつですか」
山田さんがクッキーを口に含んだままで言う。
「そう」
平面は答えた。
「お母さんが作ってるの?」
「知らない」私の言葉に対して平面はきっぱりと言う。「とにかくジェルはジェル」
「お母さましか用意できないものなんですか?」
「そう、だからお母さんが死んだら講座は終わりかな」
「えー」
山田さんはクッキーを手に取りながら抗議の声を上げる。平面のお母さんの手作りクッキーをずいぶん気に入ったらしい。
「こら、お母さんを殺すな」
お父さんが、アーモンドが一粒まるごとついているクッキーを食べながら言う。
「殺してないよ、仮定の話」
「お母さんは死なない」
お父さんはきっぱりと言った。
「いやいや、死ぬよ」
「死なない」
「死ぬって」
「死なない」
お父さんは平面の目をまっすぐに見て言う。平面もじっとお父さんの目を見ていたが、長い膠着状態に耐えられなくなって、目をそらした。お父さんはまたアーモンドが一粒まるごとついているクッキーを取って食べた。私と山田さんは黙って発泡スチロールの箱を持ち上げ、車に積んだ。積み込み終えたときに平面が家から出てきて、そのまま出発することになった。お父さんとお母さんに別れの挨拶をできなかったことが気になったが、平面が機嫌を悪くしているのは明らかだったので、何も言わなかった。
山田さんは平面の実家を出て少し進んだところで車を停め、カーナビを平面の方へ向けた。平面は自分の家の住所を入力した。車は再び発進した。
「ごめん」平面はぽつりと言う。「来てくれてありがとう」
「お昼ごはんどうします?」
山田さんは言った。時間はお昼をやや過ぎていた。私はなにか食べてもいいかなと思ったが、平面は、
「クッキーでおなかいっぱいになっちゃった」
と言った。山田さんも、
「そうですね、じゃあまっすぐおうちに向かいましょう」
と言ったので、私も同意することにした。
「先生」
「なに?」
「変な話、どうやって生まれたんですか」
「わたし?」
「はい」
「わたしは平面だから」平面は言う。「生まれるとかはないかな」
「そうしたら、いまのお家にいらっしゃった方々っていうのはどういう関係に当たるんですか」
「父と母だね」
「産みの母ではないということですか?」
「そうだね」
平面は頷く。山田さんが突然ぎりぎりのことを言い始めたので私は冷や汗をかいたが、平面はふつうに受け答えをしている。
山田さんのすっと懐に入っていく感じが不思議だった。どうしてそんなに危ないところをつついても平気でいられるのか私にはわからなかった。
「先生は、どうやってこの世に生を受けたんですか」
「それはね」
「やめようよ」
私は思わず言ってしまう。山田さんがバックミラー越しに私を見た。ひどく冷たい目をしていた。平面は座席に深くもたれかかるように座り直し、何度も位置を調整した。ぺらぺらした頭が揺れるのがちらちらと見えた。
どうしてこんな風になってしまうのかわからなかった。平面と二人で話しているときはぎくしゃくすることはない。もしなにかあっても謝って済ませる程度のことが多い。謝ってもどうしようもないぐちゃっとした感じになってしまうのはだいたいいつも誰かが間にいるときだ。
私は寝たふりをした。いまさら寝たふりをしても遅いとわかっていたがとにかく寝たふりをした。
私は働いていない。一回も就職したことがない。アルバイトですらしたことがない。事務職ではなく無職だ。だからといってお嬢様だというわけでもなく、ごく普通の家に育って仕送りで生活をしている。もう三十歳を過ぎているというのに、である
働いていないのを悪いと思ったことはない。人にはいろいろな生き方がある。けれど、仕事をしていないと言うとあれこれ就職の口を探してきてくれてしまう人がいるし、ときおりありがたいお説教をされることもある。そういう意味では多少面倒だなと感じるときはある。逆に言えばそのくらいの気持ちしかない。だから過度に私のことを守らなくていいのだと平面に伝えたいのだが、絶対にいまのタイミングではないということはさすがの私にもわかったので、とにかく寝たふりをした。
平面と山田さんは小声でなにか話していた。私に内緒にしたいような話ではなく世間話をしていて、気を使って声を小さくしてくれているのだとわかっていたけれど、なにを話しているのか聞き耳を立ててしまった。魚の揚げたものに塩が合うかそれとも醤油がいいかという話だった。驚くほどたわいのない内容で私は笑いそうになった。
気がつくと眠っていた。平面の家の前で山田さんにゆるく揺すぶられて起きた。しばらく目が覚めきらなくて、ジェルの入った発泡スチロールの箱を運びながら山田さんに、魚の揚げたのにはレモンだ、と言い続け、山田さんと平面に笑われた。
平面の部屋はほんとうにすっきりしている。ワンルームの部屋には冷蔵庫とちょっとした書き物をするためのテーブルだけがある。台所はほとんど使われていない。平面は料理をしないのだ。
「置いておけばいい?」
「うん、小分けとか冷蔵庫にしまうのはあとでやる。ありがとう」平面は言う。「お茶かなにか飲んでいく?」
「ありがとう」
車に戻っていた山田さんを呼びに家を出ると、車と山田さんはいなくなっていた。平面に知らせに家に戻ると、
「山田さん、先に車戻して帰るって」
と平面が言った。メールかなにかが平面の携帯電話に届いたらしい。
私は床に座って平面がお茶を淹れてくれるのを待った。ミントとローズヒップどちらがいい、と聞かれたので、ミントで、と答えた。戸棚からミントのティーパックを二つ取り出した平面は、台所に二つ置いてあったマグカップにティーパックを入れ、ポットのお湯を注いでしばらく蒸らし、頃合いをみてティーパックを引き上げた。
「どうぞ、悪いけど取りに来てくれる?」
「ありがとう」
マグカップからはミントのさわやかな香りがする。平面はマグカップからスポイトで紙コップにミントティーを少量移し、居間に移動すると床に正座してごくごくと飲み干した。すぐに二杯目を取りに台所へ戻り、また居間へやってきた。
「持とうか」
「なにを?」
「マグカップ」
「持つって?」
「持つの」
私は言い、台所へ向かう。花瓶にストローがたくさん差してあった。その中から一本を選び平面のマグカップに刺した。平面の横に座ってマグカップを持った手を差し出す。
「はい」
「赤ちゃんじゃないんだから」
マグカップに刺さったストローに平面は口を近づける。平面がストローに口を近づけることは、私の手に平面の口が近づくことだった。平面のほのかなあたたかさを感じながら私は平面がミントティーを飲むのを見ていた。平面はミントティーを一気に飲み干した。
「喉乾いてたの?」
「うん」
「おかわりつくるよ」
「いろいろやらせちゃってごめんね、ありがとう」
平面を居間に残して私は台所に立つ。ティーパックを戸棚から取り出し、もっと大きなマグカップはないかと戸棚の奥を見ると、歯ブラシと歯磨き粉と電動ひげ剃りのセットが出てきた。平面のものではなかった。平面はひげを剃らないし、平面には歯がなかった。誰のものか聞くのも変だなと思って戸棚を閉めた。
平面は駆け寄ってきて私を抱いた。
「どうしたの」
私は言う。
「いいじゃん」
平面は私を強く締め付けている。
「いいけど、お茶淹れられないよ」
「がんばって淹れて」
「がんばるけどさ」私はポットにお湯が残っていないことを確認して、水を入れ、再沸騰させた。「やけどしないでね」
「しない」
平面は断言する。
私は平面に抱かれながらお湯が沸くのを待った。平面の背中をぽんぽんと叩くと手がバウンドした。平面というのはこんなに弾力のあるものだったかと私は不思議に思った。
ポットの湯をマグカップに注ぎ、少し蒸らすとミントティーができあがる。平面に、できたよ、と声をかけるが、平面は私を抱いたまま動こうとしない。
「平面」
「なに」
「お茶できたよ」
「うん」
「このまま移動しちゃうぞ」
「いいよ」
私は平面に抱かれたまま、平面を引きずって居間の中央まで移動した。座るよ、と言っても平面は私を離さなかったので、そのままぺったりと座り込んだ。平面の足が私の正座した足の下に入り込んだ。私は足を開いて、平面と向かい合わせで座る形をとった。
「平面」
「なに」
「私、うそついている?」
「ついてないよ」
「ほんと?」
「ついてない」
「辻君が言ってた」
「なんて?」
「私はうそつきだって」
「言ってたね」平面は言う。「うそつきじゃないよ」
「そうなの?」
「そうだよ」
「ありがとう」
「いえいえ」私の背中を平面の平べったい手が撫でる。「あ」
「なに?」
私は聞き返す。平面は困ったような顔をしている。
「あのね」
平面は口ごもっている。私は、言っていいよ、なに、と耳元でささやく。平面はあちこちを見て悩んでいたが、決意を決めて、
「平面じゃないよね?」
と言った。
思わぬ質問に私はちょっと身を引く。平面は真剣な表情である。
平面の部屋には絨毯もなにも引かれていない。フローリングの床に私たちは直接座っている。
「私?」
「うん」
「違うよ」
「名前がないのに?」
「ああ」私は言う。「それは」
「いいや」
平面は私を強く抱きしめる。背中を軽く叩くと手がはじかれた。どこを叩いても手が勢いよくはじかれる。いつから平面はこんなに弾力を持つようになったのだろう。
私の頭を平面は優しく撫でた。静電気が起きて髪の毛が平面の手にくっつき、ぱちぱちと音がした。平面はひどく困った顔をしたので私は笑ってしまった。平面は困った顔をやめなかった。私は笑い続けるしかなかった。
ものを書くために使います。がんばって書くためにからあげを食べたりするのにも使うかもしれません。
