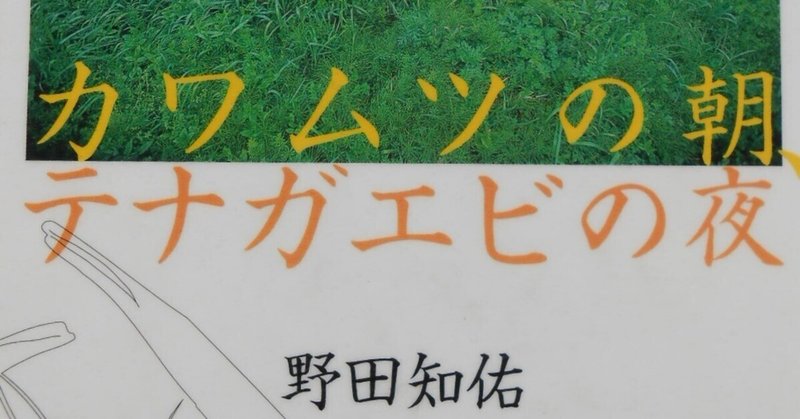
言葉の宝箱 0122【大人になるというのは自由になるということなのだ】

収録の『お遍路』には関する詳しい記述がある。
一二〇〇キロを歩き抜ける。体力と気力と計画性。
具体的な数字をあげられると不思議と現実味が帯びてくる。
・四国の春はお遍路の鈴の音で始まる。
冬の間、寒風の中を辛そうに歩いていたお遍路も、
春の陽を浴びて足取りが軽い(略)
お遍路の行程はだいたい一日二五キロ前後。
毎日七~八時間から一〇時間は歩く。
八八か所を全部まわると約一二〇〇キロ。四〇日~五〇日かかるそうだ。
宿泊費が五〇〇〇円~七〇〇〇円。雑費を入れて一日約一万円かかる。
一度に全部まわらずに、四国四県のうち一県ずつまわる人、
お札所の何番から何番までと区切ってまわる人など、
いろいろやり方がある(略)
お遍路のほとんどが銀マットを丸く巻いてリュックに縛りつけている。
彼らの装備のほとんどがアウトドアグッズ。
何キロかの荷物を背負い、長時間歩くのだから、どうしてもそうなる(略)別れ際、お遍路たちが合掌していくのも気持ちのいい光景だ。
近くの食堂に入った。隣のテーブルでお遍路さんが食事をしている。
この町の人だろうか、
一人のお爺さんが「お接待させてください」といって一〇〇〇円札を一枚、お遍路の前に置いた。彼は悪びれず合掌してそれを受け取った。
ぼくと視線が合うと、その人はいった。
「初めはお金を出されて困惑しましたが、
この頃はこんなお接待にも慣れました。
いろんなものをもらいますよ(略)」
現在の遍路道は国道が多い。
歩き遍路(車でまわる遍路に対してこう呼ぶ)の目から見れば、
今の道路は歩行者、自転車など弱い者にはとても苛酷にできている。
トンネルの中など歩いている遍路は、
轟音と風圧で吹き飛ばされそうな感じだ。
日本の道路は歩く者にはつくづく不便にできている。
歩き遍路にとって一番の悩みは、
お接待の一つとして乗せてあげますといって車を停める人だという。
好意でいっているのが分かるので、無下に断れず、
しかし一度乗ると歩くのが辛くなる。
何回か車に乗せてもらった後、
歩くのが嫌になり、途中でやめて帰る人もいるそうだ。
長距離を何日も歩くという普段やっていないことをやることで、
日常的な枠を越えて、
それまで気がつかなかったもの、見えなかったものを見る。
歩き続ける、歩きぬくという行為に意味があるのだから、
気楽に乗せてあげます、などといってはいけないのだ P149
・自分の親が働くのを毎日目の当たりにしている子供は、
地に足のついた生活感の中で育っていくのだろう P42
・子供は親離れ、親は子離れから第一歩が始まるのだ P50
・犬を見て恐がって逃げる子より、
犬に石を投げる子の方が見込みがある(略)
多分、初めてナイフを持つ子は自分の指を切るだろう。
そんなことは誰もがやることで、大したことではない、
この次からは気をつけるようになる。ナイフは危ない。
だから、ナイフをうまく扱えるようになろうと教える P65
・「カヌーの旅を際立たせているのは、
それが他のものより急激に人を純粋にすることだ。
汽車で一〇〇〇マイル旅してもダメな奴はダメなままだし、
自転車で五〇〇マイル、ペダルを漕いでもブルジョアはブルジョアのまま。しかし、カヌーを一〇〇マイルも漕げば、人はすぐに自然の子になる」
こんなことをいう首相を持つカナダを、いい国だと思う P96
・ディック・ターナーの本の中にこんな一節がある。
「カナダ北部での暮らしの困難さ。
ここでの生活は毎日が自分へのチャレンジだ。
その辛苦と孤独の代償として、
われわれは自由と自立、自己への信頼感を手にする」 P101
・人は慣れる生き物である。
汚い所に住めば汚さに、きれいな所に住めば、そのきれいさに慣れ、
不感症になる。
四国の人は日本中の川がみんな
四万十川、仁淀川、海部川のようにきれいだと思いこんでいる P109
・今、田舎ではお金より人間が必要なのだ。それも若い人たちが。
町起こし、村起こしというのはくだらんイベントをやることではない。
若い人間を増やすことに尽きる。
若い人が住みたくなるような町や村をつくることだ P147
・せっかく何不自由のない家庭に育ちながら、
少年は自制心のない親たちの愛情過多の中で溺れ死にそうになっていた。
いずれ彼は爆発し、親たちに暴力で報復するようになるに違いない P196
・身体障害者を兄弟に持つ子供の顔つきがどれもしっかりしていて、
思量深いものであるのに気づく。
社会的弱者、ハンディを持つ人間と接することで、
彼らはなにかを感じ、考えるのであろう P198
・田舎で暮らす時は自己を強烈に主張して、
あの人はあんな人だからと周囲の人に諦めさせなければならない。
育ちも考え方も趣味も価値観もまるで違う人たちの間に入る時は、
彼らと距離を置いてつき合った方がいい。
自己のエゴを殺して生きるのが嫌だから田舎に来たのだ。
みんなと同じように、周囲と同化して生きるのでは意味がない。
自我を一〇〇パーセント満足させて生きること、
自由に生きることを人生の最大優先時とする。
田舎に移り住むには強さが必要だ。
周囲に迎合せず、自分の生き方を貫く強さがいるP200
・集落は役場に、役場は県に、県は国になにもかも頼っている。
お金をもらおうと卑屈になっている。
少しでもお金をもらわねば損だといった
貧乏根性がこの国に充満している P210
・それに大きくなると周囲の馬鹿な大人のいうことを無視して、
自分が好きなように生きることができるようになる。
大人になるというのは自由になるということなのだ P215
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
