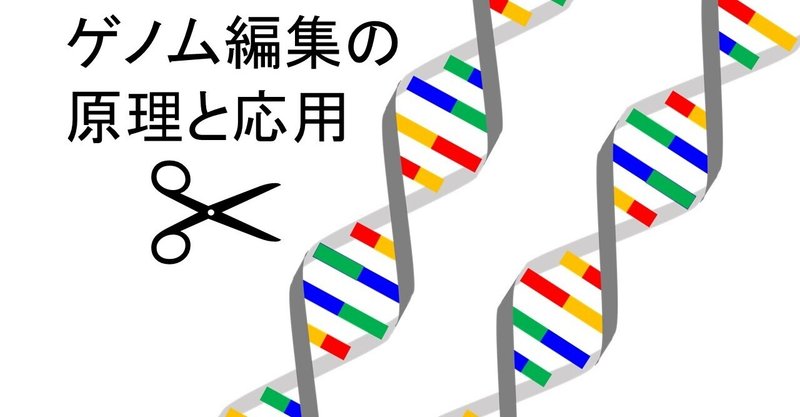
ゲノム編集の原理と応用
生物の設計図であるゲノムを、あたかもワープロソフトで文章を書き換えるかのように自在に編集する―そんな未来がすぐそこまで来ています。2020年、ゲノム編集技術を開発した二人の研究者がノーベル化学賞を受賞しました。二人が開発したゲノム編集技術は「CRISPR-Cas9」(クリスパー・キャスナイン)と呼ばれています。
従来の遺伝子改変技術に比べて圧倒的に簡便で、生物種を問わず機能するこの技術が生まれたことは、生物を思うままに改変することが決して夢ではなくなったことを意味します。それは農作物、畜産物だけでなく、人間をも含んでいます。
これからやって来るゲノム編集時代の大きな流れを前に、私たちはどんな社会を望むのか、一人一人が考えていくことが大切だと思います。ゲノム編集とはどのような技術か。どのように社会に影響を与えうるか。この記事がそれを知っていただくきっかけになれば、と願っています。
ゲノムに関わる基礎知識
ゲノム編集の原理についてお話しする前に、「ゲノム」「遺伝子」「タンパク質」の三者の関係について説明します。そもそもゲノムとは何か。ゲノムとは、DNAから成る、生物の体の設計図全体を指します。遺伝子はそのうちの一部の領域です。一つ一つの遺伝子の情報が読み込まれ、体を構成する部品であるタンパク質ができます。

図:用語の説明
DNAは糖とリン酸でできた背骨が2本向かい合わせになった、二重らせん構造をとっています。背骨の上にはアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類の塩基が並び、長い鎖のように連なっています。二本の鎖の塩基同士は向かい合い、AとT、GとCが、互いに相手になるようにペアを作っています。ペアになる相手の塩基は決まっているため、DNAは2本の鎖のうち一本あれば、もう片方の鎖の塩基の並びが分かるようになっています。

図:DNAの構造
鎖のように連なった4種類の塩基-その配列が、どのようなタンパク質を作るかを規定する暗号です。つまり、遺伝子とはA、T、G、Cの4文字で記述されたタンパク質の設計図と言えます。ゲノム編集では、この配列を乱すことで遺伝子を機能できなくさせたり、あるいは塩基を入れ替えることで出来上がるタンパク質の構造を変化させるといった操作を行い、個体の形質を変化させます。
ゲノム編集の原理
ゲノム編集とは簡潔に言うと、ゲノムの狙った場所に、積極的に、生物種を問わず、変更を加えることのできる技術です。従来の遺伝子改変技術は、積極的に変異を導入できるけれど場所は運任せであったり(化学変異原処理、放射線照射など)、適用できる生物種が限られていました。
CRISPR-Cas9が登場する前にもZFN(Zinc-finger nuclease)、TALEN(Transcription activator-like effector nuclease)といった先駆的なゲノム編集技術がありましたが、今はゲノム編集と言えばほとんどCRISPR-Cas9と、そこから派生した技術の数々を指しています。
ここから先は
¥ 120
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
