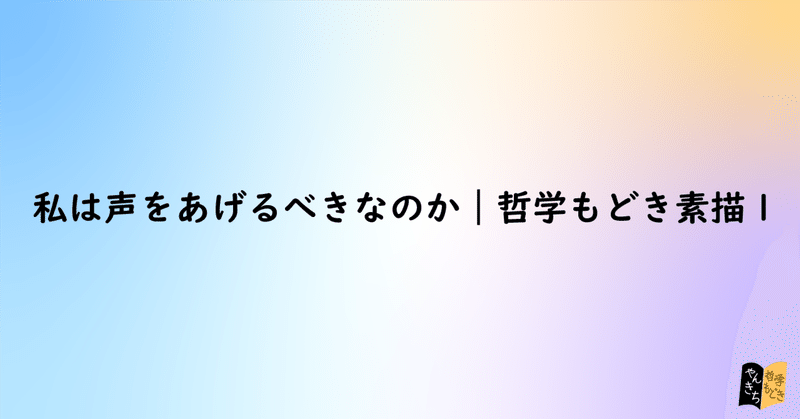
私は声をあげるべきなのか|哲学もどき素描1
最近新しいコミュニティに参加するようになって、社会運動に参加する方々に出会いました。
今まで社会運動に参加したことのある方に出会ったことがなかったため、単純に「なぜ社会運動に参加するんだろう?」という疑問と「なぜ私は社会運動に参加しないのだろう?」という疑問が浮かびました。
そんなときにシンポジウム「なぜ人々は社会運動に参加しないのか」というものがあることを知り、2023年6月18日(日)にオンラインで参加してきました。
この記事では今まで社会運動に参加しなかった私がこのシンポジウムに参加して思ったことを率直に書いていこうと思います。
明らかにしたかったことと、明らかになったこと
私がこのシンポジウムに参加して明らかにしたかったことは「なぜ私は社会運動に参加しないのか」ということでした。
普段、私は社会人として生きている中で息苦しさは感じているし、もっとこうなったら生きやすいなと思うこともあり、さらに同じ想いを抱えた人が社会運動をしていることも知っていました。
ですが、今まで社会運動に参加しようと思ったことは一度もなかったのです。
今回、基調講演をされた鎌田華乃子さんの発表で、社会運動に参加された方に「社会運動に参加しなかった理由」をインタビューした内容がありました。
そのインタビュー内容を聞いて、自分が社会運動に参加しない理由が見えてきました。
私が社会運動に参加しなかったのは「社会を変えようと思っていないから」でした。
冒頭で私は普段から社会で生きていくことへの息苦しさを感じていると書きました。
ですが、その息苦しさは生きられないほどではないのです。
我慢すれば生きられるし我慢して上手に振舞ってる自分すごいじゃん、みたいな気持ちもある。
やりたいことが溢れている普段の生活の中で時間を割いて社会運動に参加したところで社会が変わるのか?
変わったとして、それは一体いつになる?
じゃあ別にこのままでも良い。
頑張ってる人が頑張ってくれて、もしも生きてるうちに今より生きやすくなればラッキー。
これが自分の正直な気持ちだなと気づきました。
考え・学びと繋がった部分
今年になってから私はジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル』とミシェル・フーコーの『狂気の歴史』を読んでいます。
この二人は、社会の中で排除されるものが社会のどんな構造によって排除されているかを考えている方たちです。
現時点でこの二人から私が読み取っているのは
「いかに巧妙に排除の構造がつくられているか」
ということで、その排除の構造を変えたり壊したりする方法は見えていません。
社会運動にはその力があるのか。
もしもこの排除の構造をどうにかする力があれば
「頑張る人が頑張ってどうにかなればラッキー」
ではなく
「変えてみようかな」
という気持ちに変化するかもしれません。
その力があるかどうか、今回だけではまだわかりませんでした。
ですが、実際に変えたい方向に近づくことができた社会運動もあったそうです。
社会を変えたいと思ったときの選択の一つとして社会運動という形があるんだということが今回の学びの一つでした。
まとめ|社会を変えたいというより生きやすく生きたいだけ
今回のシンポジウムで自分が社会運動に参加しなかったのは、社会の行く末を他人任せにしているからだと気付きました。
さらに言い換えれば、私は社会を変えたいという思いよりも自分が生きやすいように生きたいだけなんだなぁと改めて思いました。
ですが、話を聞いていると、社会運動に参加している方々も実はそうなのかもと思ったのです。
自分にとことんわがままになって、それが社会をより良くするための方向と同じ方向であれば、もしかしたら社会を変えられるのかもしれないですね。
まぁ、より良い社会っていうのも、何なのかわからないのですが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
