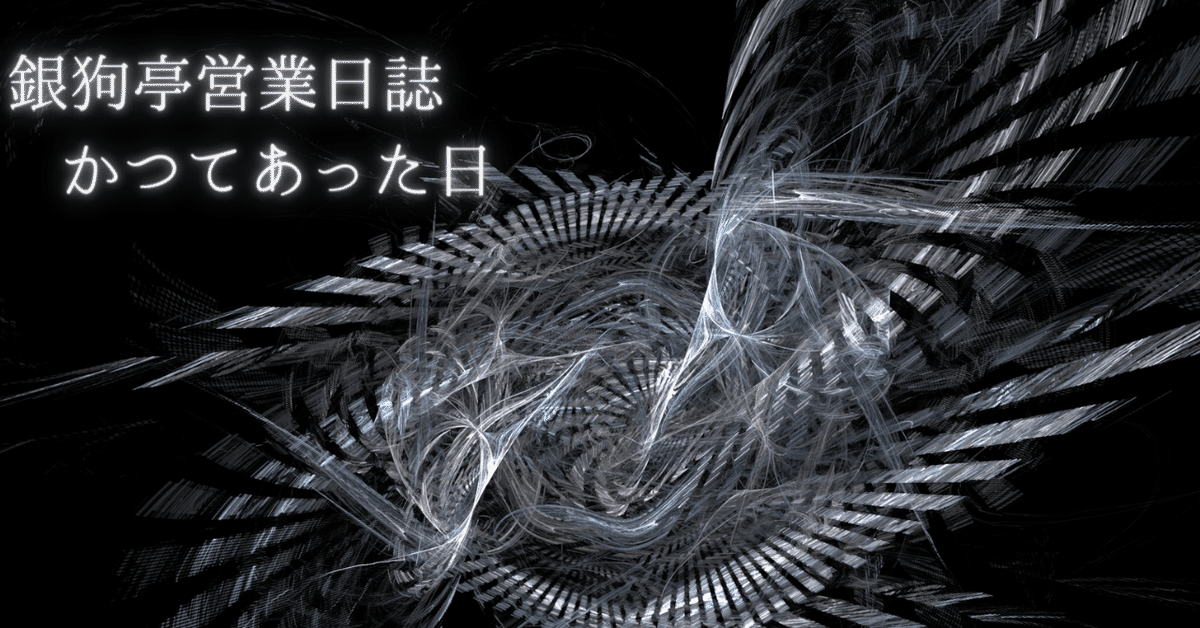
SS:銀狗亭営業日誌2:かつてあった日
駆ける。
駆ける。
駆ける。
月の無い夜を。
星も無い夜を。
駆ける。
駆ける。
駆ける。
有象無象を切り裂いて。
行く手をふさぐ全てを切り捨てて。
そして、私は
誰の手を
とれたのだったか。
* *
32月789日
雷、ときどき石礫。
大破砕の影響が続いている。
安全なルートの確保が急務だが、いまだに負傷者が運び込まれ続けているためそちらの回す人手が足らない。
水薬もこれ以上薄めてはただの色水だ。軟膏はとうに切れ、材料はどこにもない。
何が錬金術だ。
何が魔術だ。
私は、奇跡が、【魔法】が欲しい。
432月6789日
雪、雷、ときどき氷の礫。
行商人が荷物を運んできた。急いで錬金に入る。
水薬を作りながら話を聞くと、周辺のエリアはどこも同じようなものだという。彼の能力がなければまともに身動きすら取れないような口ぶりだ。
一体いつまで続くのか。
水薬が完成し、半分を行商人の荷台に積んでいた時、彼は思い出したように言った。
「西側、三つの次元が混じった挙句に時間遡行が発生しました。絶対に近寄ったらダメですよ」
時間遡行?
詳しく話を聞こうとしたが、助手が呼んでいる。返事をし、振り返った時には行商人はもう行っていた。相変わらず、早い。
△4月99999日
晴れ。風も無し。ただし、空は塗りつぶしたような黒。
大破砕以降、日誌にかけられた日付の魔術が狂ってしまっていたが、ついに数字意外の文字が使われてしまった。
体の傷を癒し、武器の修復を終えた端から元負傷者達が東へ向かう。
私と助手がそれを見送る。それしか我々には出来ない。
しかし、空の黒さはなんだろうか?
時折赤いラインが走るあれは?
助手が厳しい目でそれを眺めている。時折こんな雰囲気を持つ彼だが、問いかけてもはぐらかされてしまう。
彼は何か知っているのだろうか?
◉◉月▼▲日
黒、黒、黒だ。時折、赤。
もう日付の感覚がなくなってしまった。
大破砕から何日が経った?
まだ時空嵐は収まらないのか?
負傷者の数は減ったが、それに反比例するように深手を負った者が増えた。
錬金術で治せる限界ギリギリの患者も多い。薬が、足らない。
前にあの行商人が来てから何日経った?
次はいつ来る?
うたた寝をしてしまった後、野戦病院と化した裏庭に行くと、助手がベッドに眠る一人の男の手を取って祈っていた。
ああ、ダメだ。
一目で分かってしまった。彼は助からない。
と、助手が何かを呟くと、男の体が光り輝いていく。
まぶしさに思わず目を背け、向きなおしたそこにあった物に、私は驚愕した。
ベッドにぽつりとある、銀色の玉。いや珠。
「――おい、お前……それは」
「先生……私は」
”賢者の石”。そのなりそこない。
なりそこないと言えど、絶大な力を持つ、【奇跡】に近いそれ。
助手はそれを拾い上げると、私の手に握らせた。
「先生、彼らの命を、覚悟を、後の人たちに使ってください」
「白銀……お前っ!」
「先生、今は」
この激情を目の前の頼りなさそうな男にぶつけるのは容易だ。
だがそんな男が錬金術師として私よりも高位だということ。
この「石」があれば今も苦しんでいる彼らを救うことが出来ること。
それらが私を押しとどめる。
そうだ。
私は、私の役割を果たそう。
××◇××月LLLLLL日
黒。赤いライン。
運ばれてくる負傷者の数が増えたが、片っ端から治療をしている。治療を施した一部の人たちが手伝いを申し出てくれたおかげで何とか回せている。
どうやら我々のところの割り当てが多くなってしまったようだ。
だが問題ない。
この「石」が摩耗しきらない限り。
22月105日
久々に日記の日付が「わりと」まともな数字を表している。
時空嵐が落ち着きはじめたのだろうか?
と、外への扉を開けた瞬間絶句した。
黒だ。
空も、地面も境界線のない黒がそこにあった。
そして、その黒に浮かぶように、ひと際の黒が居た。
「嘘だろ」
高位存在。
大破砕の原因。
つまり、私たちの【終わり】がそこにいた。
咆哮。
迸る黒い閃光。
割れるガラス。
砕ける壁。
悲鳴。
――ああ。ここまでか。
だが、終わらなかった。
一筋の赤が。いや紅が。
終わりに激突したのだ。
「あああああああああああああああああ!!!!」
「GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!」
絶叫が響いた。
一人の男だった。煤けた黒髪、ボロボロの黒衣、鎧のほとんどはなくなったのか、右腕にガントレット。そしてレギンス。どれもが黒だった。
ただ、その鋭い眼光だけが真紅に輝いていた。
【終わり】に突き刺していた刃を抜き放ち、返す刃を脳天に振るう。
だが【終わり】が腕を振るってそれを防ぎ、彼を弾き飛ばした。
奴の胸を貫いたがそこにコアはなかった。
高位存在、もしくはアークデーモンと呼ばれるそれ。
私の故郷を、大切な■■を奪った存在。
許さない。
今度こそ、逃がさない。
振るった刃ごと弾きとばされたが、すぐさま、ぐっと闇を踏みしめる。
この闇を、夜を駆けるのもとうに慣れた。
そこに『ある』と思えば在り、『ない』と思えば無い。
闇を蹴り飛ばし、刃は引くように構える。
焔が見える。
引き延ばされた時間が、圧縮された空間が、私の眼には朱く見える。
――何度でも、消滅するまで切り刻んでやる。
私の知覚外の激闘がそこで繰り広げられていた。
はっと我に返る。彼に何か出来ることはないか。
振り返って駆けだそうとしたとき、私は眼を疑った。
助手が死んでいた。
顔の半分と、胸がごっそり吹き飛び、血だまりの中で死んでいた。
そしてそれを見下ろす助手を見た。
「ああ、『先生』」
助手の死体を見下ろす助手が言う。
「この世界の私は、人の役に立ててましたか?」
私は言葉が出なかった。
彼の雰囲気に飲まれたからだろうか。
美しい銀髪と、銀の瞳に惹かれてしまったからだろうか。
ただ、一つ頷くことだけできた。
「そうですか」
彼は”はにかんだ”のだろうか?
「それは良かった」
そう言って彼は、死体に手をかざす。
あっ、と声が出る前に、彼は死体を石に変えてしまった。
ちっぽけな、白い石に。
それを当然のように飲み込むと、懐が光り始めた。
彼がそれを取り出す。仮面だ。銀色に輝く、砕けたガラスを寄せ集めて人の顔をかたどったような仮面。
「それではアイツを助けてきます。なに、大丈夫ですよ」
彼は微笑むと、その微笑みを仮面で隠した。
「もう、何度もやってますから」
* *
4月9日
久々に古い、別の次元にかつてあった『銀狗亭』の日誌を読み返してみた。
どこの次元にもあるこの日誌はその”役割”ごとに同期して、いついかなる時も読むことができる。
たとえそれが失われた次元にあった日誌でも。
大破砕。
前時代にあったそれを記録した書物が、これ以外にどれほどあるのだろう。
「白銀」
呼ばれて顔を上げれば、黒髪に赤い瞳の男がそこにいた。
「狩ってきた。朝食にしてくれ」
カウンターに上げられたそれは、しっかり処理のされた鳥肉だった。
ため息が出る。全くこいつは。
「ステーキでいいか?」
「何でもいい」
デキャンタに残った昨晩のワインをグラスに注ぎ、一息に飲み干す。
相変わらず酒の飲み方が適当過ぎる。
「あのなぁ闇乃」
「なんだ」
一言言ってやろうと思ったが、やっぱりやめた。
代わりに再びため息。
「ちょっと待ってろ」
ああ、庭でローズマリーをとってこよう。
そう思って入り口の扉を開けると、まぶしい光が降り注いだ。
手をかざし、空を見上げる。
どこまでも続くような青空がそこに広がっていた。
#小説 #短編小説 #ショートショート #ファンタジー #ファンタジー小説 #異世界ファンタジー #projectF #銀狗亭
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
