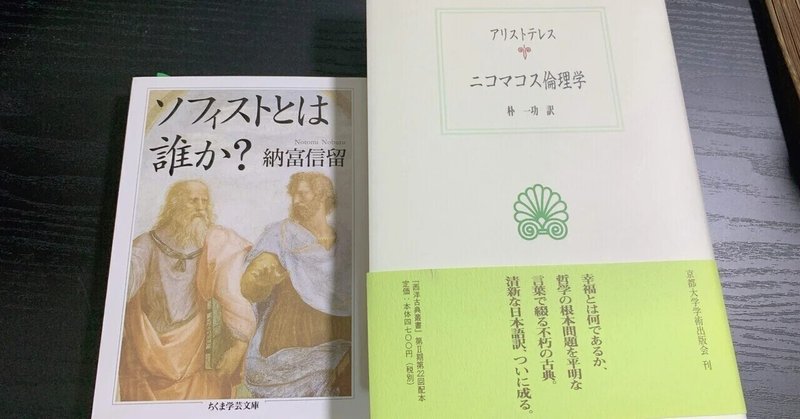
快楽と幸福。“teleiosな状態”はどこにあるのか。リストテレス『ニコマコス倫理学』をよむ(10)。
アリストテレスの『二コマコス倫理学』(朴一功訳、京都大学出版会)と納富信留『ソフィストとは誰か?』(ちくま学芸文庫)を交互に読んでいくという試み。
今回は、アリストテレス『ニコマコス倫理学』の第10巻。いよいよ最終巻。毎回注記してますが、巻といっても、現代的な感覚でいえば“章”に近いです。今回は、幸福に関する内容。アリストテレスが、ひとまずこの本において述べられたいことのゴール(そして、その先)が述べられています。
読書会での設定文献は↑の翻訳だが、最近になって以下の文庫版の存在も知りました。ここでは西洋古典叢書版を用いますが、たまに光文社古典新訳文庫版を参照することもあるかもしれません。
今回は、訳文に関して、光文社古典新訳文庫版を参照しています。
※ 急にnoteでAmazonリンクのサムネイルが機能しなくなったので、出版社サイト、もしくはHonto(ジュンク堂書店)のリンクに変えてます。
摘 読。
終局/目的状態としての快楽
アリストテレスは、エウドクソスの快楽主義、つまり分別がある人間も、それがない他の動物も、すべてのものが快楽をめざすという考え方を検討する。エウドクソスはすべてのものがめざすのが快楽であるなら、それがすべてのものにとって最善であると考えた。とはいえ、エウドクソスは快楽を最高善(the good)と考えたというよりも、ひとつの善(a good)と捉えた。アリストテレスは、この点を継承する。
そのうえで、アリストテレスは快楽を運動や生成過程の終局(teleios; 目的)として捉えている。運動や生成過程それ自体が快楽であるとはみない(第4章1174a19)。というのも、運動や生成過程は「途上」であり、「部分」でしかないからである。たとえば、建築の場合、あくまでも快楽に至るのは、その運動や生成過程が全きものとなるときである。また、「歩いている」ときそのものが快楽になることはないというのが、アリストテレスの主張である。したがって、アリストテレスの考え方に立つならば、快楽は「時間のうちにはない」。
ただ、快楽と活動が無関係であると言っているのではない。「良好な状態にある感覚による知覚の、感覚の感知の範囲内にある対象のうちでもっともすぐれた対象に向かっての活動が、もっとも完全」であり、「快楽はこうした活動を、完成させる」(第4章1174b22-24)。それゆえ、快楽は「(活動に)付随する或る終局」なのである。このことゆえに、快楽は連続的に生じない。また、生きることは活動であるがゆえに、望ましいものであるところの「生きること」を完成させてくれるのが快楽なのである。
また、これまでの巻でも言及されてきたように、快楽といっても多様な種類がある。そのなかでアリストテレスが重視するのは、やはり徳である。徳に根ざした高潔性にもとづいて活動するところの「善き人」にとって快楽としてあらわれるものが、人間がめざすべき快楽であると、アリストテレスは主張する。ここには、アリストテレスの規範的主張が含まれているとみていいだろう。
観想的生活と実践的生活:幸福とは。
第10巻第6章以降は、ここまでの話を踏まえて幸福の議論に移る。ここで論じられている幸福も、やはり徳にもとづく活動のうちにあるとされる(第6章1177a10)。
そのなかで注目されるのは、アリストテレスが観想的な生活こそ幸福であるという点である。アリストテレスは実践的な生活を二次的な幸福と位置づけ(第8章)、知性にもとづく活動を観想的生活としてより重要なものとして捉えている。そして、この観想的生活は余暇のうちにあるとみている。つまり、実践は余暇のため、あるいは静かでゆったりした状態を実現するためと考えられている。
もちろん、アリストテレスは実践それ自体を否定するわけではない。アリストテレスは、これを「外的善」(第8章1179a2)と呼ぶ。そして、ソロンの言葉を引く。
幸福な人々とは、外的なものを適度に調達されて、かれが考えたようなもろもろのもっとも美しいことをやり遂げて、そして節制ある生活を送り続けた人なのである。
アリストテレスが考える幸福な生活、理解できなくはない。ここは私見のところで考えたいところだが、奴隷制度なしには成り立ちえないのではないかという思いも浮かぶ。
倫理学から政治学へ
ようやく『ニコマコス倫理学』の終局に辿り着いた。
アリストテレスが考えてきたこと、それは欲動に駆動される人間が、より「幸福」に生きるためには、徳をめざすような正しい訓練の機会を得て、節制ある高潔な人になっていくことが欠かせない。法もまた、この文脈において必要となる。アリストテレスの議論において、法は「劣悪」な行為やそれをなす人を罰し、「美しいものを愛し、醜悪なものを厭う」ような生き方へと変えるようにするはたらきが期待されている。その際、父権的な支配にもとづくからではなく、あくまでも思慮深さと知性に発する分別をあらわす言葉であるがゆえに、法は強制する力を持つともアリストテレスは指摘する。
その根底には、公共的な正しい配慮がつくりあげられることが最善であるという考え方がある。人間が善き人になれるのは、もろもろの法を通じてであるとアリストテレスがいうとき、ここでの法はもちろんポリスでの立法をさしているが、きわめて教育的な観点が入っている。
そして、この法の良し悪しを判定できるのは、専門技術を持ち、理論的観想の力を持つ人ということになる。その基盤になるのが知識なのである(第9章1180b20)。もちろん、経験も必要である。経験がある人こそ、作品にかんして正しい判定を下し、どのような手段を通じて、またどのようなやり方で作品が仕上げられるかを知っており、どのようなものがどのようなものとうまく適合するかを知っている。経験のない人は、作品が良い出来か悪い出来かに気づけばそれで充分であると、アリストテレスは言う。法は、政治学の作品なのである。
このような議論に立脚して、実際にどのような社会秩序が形成・構築されうるのかを論じ始める。それが『政治学』である。
私 見。
観想的生活への憧れと反撥。
私が、経営学という実践にかかわっているからだろうか。観想的生活を上に置き、実践的生活を下に置くという発想には、やはり直感的に反撥を感じないわけではない。ことに、アリストテレスが引用するソロンの言辞、これは他の誰かが「外的善」を実現しなければ、観想的生活とそれにもとづく幸福が成り立ちえないことを、結果的には示しているように思う。それをアリストテレスがわかっていないわけではない。でなければ、この『ニコマコス倫理学』のなかで取引をはじめとして、生活実践においてもとめられる思慮や節制などに言及することはないだろう。
そして、こういった観想的生活の重視という考え方は、ヨーロッパ思想の根底としてポジティブにもネガティブにも、きわめて強力に作用しているようにも感じる。このあたりは、西洋哲学の歴史において、つねに意識されていたようだ。個人的には、手許にあるアーレントの↓の本を想起した。
ちなみに、このような観想的生活を地でいっていたように私が感じる(ここでは、ポジティブな意味合いである)のは、吉田健一である。吉田健一のような知性、見聞、生活のありようなど、憧れる。しかし、私自身にとってはるかかなたにあるものであることも事実だ。
それ以上に、経営学にかかわって、むしろ八尾というまちにかかわって、こういった観想的生活が成り立つには、同時に実践的生活が成り立つのが大前提であるとも強く思う。
あえて、ここでだから書いてしまうが、新しいラグジュアリーが真に社会において「一つの善」として根づくためには、この観想的生活と実践的生活の橋渡しが必要になるように思う。新しいラグジュアリーだけではないだろう。いわゆるデザインをめぐる思想たちに共通する点だと、私は思う。これは、とある政治勢力がなぜ支持されているかを考えざるを得ない地域に私が住んでいるから感じることなのかもしれない。
アリストテレスが生きた時代は、奴隷制度が通常であった。現代においてはどうなのだろうか。
全き状態としての快楽。
ここについても、読んでいて最初は「うん?」と思った。たとえば、レベッカ・ソルニットが著した↓の本など、歩くことそれ自体から得られる快楽について論じているとみることもできそうだし、
あるいはインゴルドの『ラインズ』をはじめとする諸著作は、運動/活動の軌跡としての生成過程に目を向けているともみることができそうだ。
ただ、アリストテレスは運動(キネーシス)を軽視しているわけでもない。あくまでも、運動そのものが快楽なのではなく、それによってもたらされる全き状態をもって「快楽」と呼んでいるのだ。
これ、たとえば私が能を観るときのことをリフレクティブに考えてみるとどうなるだろうか。例えば、先週の土曜日(2024年3月9日)に「三人の会」で谷本健吾による『野宮』を観た。いくつかの失錯はあったが、トータルとして充実した舞台だった。そのなかで、「牛の小車」のあたりで舞台を一巡してさらに大小前で小さく回り、そのあとに序之舞へと続いて、まだそのあとがあるのだが、それぞれが連綿とつながりながら六条御息所の心情が結果的に立ち現れてくるところなどは、『野宮』という曲の趣が舞台上に成就していたといっていい。ここで「結果的に」といったのは、もともとこの曲の演出(型や節、囃子)が構造的にそう組み立てられているからでもあり、また演者がそれを身体化しえた結果でもある。さらにいえば、観る側に準備があるということも加わるであろう。
このような事態を考えた場合、たしかに運動/活動の軌跡=生成過程の「全き状態」(ここでの「全き」とは、理想状態そのものと捉えるべきか、あるいはその過程によってもたらされるteleiosな状態と捉えるべきか)として、私はこの舞台に「快楽」を覚えたと説明することはできそうだ。ただ、同時に途中の段階でもそれを感じていたのも事実である。
とはいえ、演劇などのように「終局」が定まっている場合は、まだ「全き状態」を措定することは難しくない。
別のケースを考えよう。
例えば、企業において新規事業を考えるという状況があるとする。ここにおいて、新規事業がうまくスタートしたことによって得られる「快楽」はどういうものであろうか。
※ そもそも、実践的生活における幸福を二義的なものとみているアリストテレスにとってみれば、適切な事例ではないかもしれない。
新規事業がうまく立ち上がったことの快楽というのもあるだろう。ただ、別の観点からすると、そのプロセス自体に快楽を覚えるということもありそうに思う。
それに、going concernという状態を考えたときに、「終局」「全き状態」をどこにみるのかという問題も生じよう。「全き状態」も時間の推移とともに変容する、と考えてもいいのだろうか。そうなると、快楽は時間と関係ないというアリストテレスの主張と矛盾するかもしれない。
しかし、この点、サービスデザインなどを考えるとき、意外と根深い問題といえそうな気もするのである。
倫理学と政治学。
『ニコマコス倫理学』を読んできて、ひじょうによく組み立てられた議論であるなと痛感した。人間の欲動を十分に認識したうえで、他者との関係性のなかで「節制」の重要性を論じ、そのような基準にもとづいて活動することを「徳がある」と規定し、そのような徳にもとづいて行為する人を高潔であると捉え、この高潔さによってもたらされる快楽を幸福な状態と、アリストテレスは主張する。
おそらく、アリストテレスもこのような状態を一つの理想形(Idealtyps)と考えていたのだろう。ただちにそれが現実であるとは見ていなかったように思う。だからこそ、この『ニコマコス倫理学』のあとには、具体的な社会秩序をいかに形成しうるのかということを議論するための『政治学』が接続されなければならなかった。
このような社会秩序の形成原理として「法」を捉えるという発想は、やはり重要である。しかも、アリストテレスは「徳をめぐる基準」が法として規定されることを要求する。古代ギリシアにおける法の観念と、現代社会における法の観念には隔たりもあるだろう。にもかかわらず、法をどのように形成するのかということが社会秩序の構築にとって、きわめてcriticalであることを示しているのは、やはり重要である。
これは、いわゆる成文法だけの問題ではない。アリストテレスも、徳が法に反映されることを基本としているように読めるが、必ずしも完全に重なり合うとも考えてはいないように思われる。徳と法という概念構成は、企業をめぐる課題を考える際にもきわめて重要な視座である。
経営学が軍事的な言語体系(例えば、戦略など)で論じられるようになったという指摘がある。しかし、軍事的な言語体系が前面に出る前は、どちらかといえば技術、会計、そして政治的な言語体系が混在していた。もちろん、今でもこれらの言語体系は生きている。ただ、企業やそれをめぐる生態系を捉える際に、政治的な言語体系に目を向けることは、大きな意義がある。北野利信の↓の本は、この点を主張している点で興味深い。
おわりに。
これで、ひとまず『ニコマコス倫理学』と『ソフィストとは誰か』の交互読解も一区切りである。十分に理解しえたかどうかはさておき、やはり古代ギリシアにおける哲学・思想が、さまざまなかたちで現代に影響を及ぼしていることは、十分に感じられた。そして、それが現代的な課題を考えるうえで、そのままでは使えないにしても、多くの示唆を与えてくれることもあらためて確認できた。
アリストテレスの議論にしても、『ニコマコス倫理学』だけで判断するのは危険だろう。ただ、そこをすべて読解していく余裕があるかどうかは別である(笑)
そして、今回の読解を通じて、なぜポパーが『開かれた社会とその敵』を著したのかも、少しクリアになったように思う。プラトンとアリストテレスを完全に並べてしまうべきではないにしても、ポパーが(おそらく、自分自身を善き人の一人とは自認していたような気もするが)マルクスを批判する線上でプラトンを厳しく批判し、アリストテレスに対してはいくぶんその手を緩めながらも、やはり基本的にはプラトンの延長線上に位置づけているように思われるのは、エリート主義的な全体主義への危険性を内包していることへの批判があったと言えそうである。
『ニコマコス倫理学』、そう簡単に読める本ではないが、しかしやはり読むべき本の一冊である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
