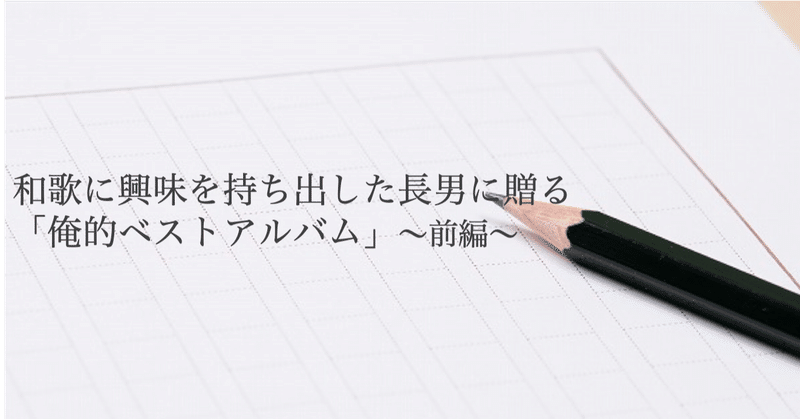
和歌に興味を持ち出した長男に贈る「俺的ベストアルバム」 〜前編〜
小学四年生の長男が「音読の宿題をするよ」と言って、“はれしそらあおげばいつもくちぶえをふきたくなりてふきてあそびき”と読み出したので、頭の中が「???」となった。うまく処理できずにいると「いしかわたくぼく」と聞こえてきたので、ようやく長男が短歌を読んでいることに気がついた。
「それは短歌という日本に昔から伝わる歌だよ、今度は五・七・五・七・七で区切って読んでごらん」と教えてあげたら、「晴れし空 仰げばいつも口笛を 吹きたくなりて 吹きてあそびき」と聞こえてきた。
「どう? 前よりも美しく響かない?」と長男に聞いたら、何かスイッチが入ったようだった。昔から長男は芸術的なものに興味を惹かれる傾向がある。
じゃあそれならということで、長男に和歌の「俺的ベストアルバム」を送ることにした。僕は専門家ではないし、古典の授業も真面目に受けていなかったので詳しい解説はできないけれど、高校時代の僕が感じた「なんかわかんないけどこれいい!」って気持ちが長男に伝わればいいなと思う。
選んだ曲はボーナストラックを含めて十一曲。前編、後編の二回に分けてお送りする。
一曲目
唐衣 着つつになれし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思う(在原業平)
からころも きつつになれし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもう
まず一曲目は、九○○年頃にリリースされた歌物語集「伊勢物語」に収録されているナンバー。在原業平の作品と伝えられている。
もう自分は必要のない人間だと京を離れ、友と二人で東国へと旅をしている途中、見事に咲いたカキツバタを題材に読んだ歌である。
着慣れた服を妻に例え、その妻を京に残して随分と遠くまで来てしまったなぁ、としみじみと思っているわけだが、この歌には様々な技法が盛りに盛り込まれている。
まず各句の頭文字、これを一文字ずつ取ると「か・き・つ・ば・た」になる。続いて唐衣、これは「着る」の枕詞になっていて、さらに「唐衣着つつ」で「なれ」という言葉が続くようになる。その「なれ」は「着慣れる」の「慣れ」と「馴れ親しむ」の「馴れ」のダブルミーニングだ。
これだけではない、「つま」は着物の「褄(着物の裾の端の部分)」と京に残した「妻」、「はるばる」は着物を張るを意味する「張る張る」と遠くまで来たことを意味する「遥々」、「きぬる」は「着ぬる」と「来ぬる」がそれぞれ掛かっている。
初めてこの歌の解説を聞いたとき、「やりすぎだろ!」って思うくらいの衝撃を受けたのを覚えている。ちょっと技巧に寄りすぎた説明になってしまったが、そのときの気持ちを共有したいと思ったので、あえてそんな書き方をしてみた。
二曲目
東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな(菅原道真)
こちふかば におひおこせよ うめのはな あるじなしとて はるをわするな
続いてのナンバーは、一○○六年頃にリリースされた勅撰和歌集「拾遺和歌集」から。超絶有能で右大臣にまで昇進した菅原道真だったが、そのあまりにも早い出世ぶりに嫉妬を買い、ついに太宰府に左遷されてしまう。その出立の折、屋敷の梅の木を見て詠んだ句と伝えられている。
これは僕にとって萌え要素満載の歌だ。
まず「東風」と書いて「こち」と読む。「本気」と書いて「マジ」のような、中二心をくすぐる言葉にまず心を奪われる。
そして梅の木。道真公は「わたしがいなくなっても春を忘れるんじゃないよ、ちゃんと東風に乗せて香りを届けるんだよ」と語りかけているわけだが、何となく梅の木にツンデレなものを感じてしまう。「べ、別にアンタのために咲くわけじゃないんだからねっ!」
とどめが飛梅伝説(とびうめでんせつ)だ。道真公が祀られている太宰府天満宮にある御神木の梅の木、なんとこの梅、道真公に会いたくて京から遥々飛んできたというのだ。雨の降る夜に屋敷の扉を叩く音がして、開けたらずぶ濡れの梅ちゃんが「来ちゃった…」って、こんな萌え萌えな梅の木がいままであっただろうか、いやない。
三曲目
願わくば 花の下にて 春死なむ その如月の 望月のころ(西行法師)
ねがわくば はなのしたにて はるしなむ そのきさらぎの もちつきのころ
さっきとはガラリと雰囲気を変えて、一一八○から一一八五年の間にリリースされたとされる西行法師の歌集「山家集」から、渋めのナンバーをお届けする。
「できることなら二月十五日(旧暦)の満月の夜、満開の桜の下で死にたいものだ」という意味なのだが、この二月十五日というのは釈迦の亡くなった日だ。ただ「月の綺麗な夜に」とか「満開の桜の下で」とか言うのとはワケが違う。釈迦入滅の日と同日を願うところに西行の強い意志が感じられる。
西行は元々は武士だ。出家前は佐藤義清(さとう のりきよ)という名で、鳥羽上皇の北面武士として仕えていたとの記録がある。北面武士とは院御所の北側の部屋に近衛として詰めていた武士だ。当時まだ武士の身分というのは低いものであったが、上皇を警護するのが役目なので、家柄が良いのはもちろんのこと、武芸に優れ、教養も高く、容姿端麗で…とまぁエリート中のエリートしかなれなかった(同じ頃、平清盛も北面武士として仕えている)。
ところが義清は何を思ったか、そんな名誉ある北面武士の立場を捨てて出家をするのである。理由はいまでもよくわかっていないが、出家の際、「行かないで」と泣きじゃくって足にすがりつく四歳の娘を縁側から蹴り落としたというファッキンなイカれエピソードが残っていることから、かなり意志の強い人間だったということが推測される。
そんな彼の強い意志は、一一九○年の二月十六日、つまり釈迦入滅の翌日に亡くなるという形で見事に成就する。満月の光が満開の桜を照らす、さぞかし美しい夜だったことだろう。
四曲目
秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる(藤原敏行)
あききぬと めにはさやかに みえねども かぜのおとにぞ おどろかれぬる
ここで九○五年(九一二年とも)にリリースされた勅撰和歌集「古今和歌集」からシンプルなナンバーを。
「秋が来たのかどうかなんて目に見えないからよくわからなかったけれども、いつのまにか風の音が秋なもんだから、わたし思わず驚いちゃいましたよ」なんて意味なのだが、この何のひねりもない素直さが好きだ。
いまは天気予報の精度が高いから、「ああ、来週くらいから秋っぽくなりそうだな」なんて考えながら衣替えの準備を始めたりできる。けれども当時の人たちはそうはいかない。「あ〜、残暑が厳しいなぁ。まったくいつになったら涼しくなるのやら…」なんてボヤいていた数日後に空気がヒンヤリしだすのだ。その変化の早さにさぞかし驚いたことだろう。この歌は、現代人が忘れてしまった感覚を思い出させてくれる気がするのだ。
五曲目
天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に 出し月かも(阿倍仲麻呂)
あまのはら ふりさけみれば かすがなる みかさのやまに いでしつきかも
こちらも古今和歌集から。
奈良時代の遣唐留学生であり且つ唐の役人でもあった阿倍仲麻呂の詠んだ歌だ。三笠の山とは春日大社の東にある花山のこと。
天の原とは神々のいるところという意味で、転じて空を指す。そんな遥か彼方に浮かぶ月を見て、「あれは故郷の春日にある、三笠の山に上る月と一緒なんだよなぁ」と望郷の念に駆られているのである。
仲麻呂は非常に優秀で、唐の官僚養成機関である太学で学んだのち科挙に合格、七二五年より唐の皇帝玄宗に仕えた。玄宗といえば楊貴妃に惑わされて唐の混乱を招いた皇帝として知られるが、開元の治(七一三〜七四一年)と呼ばれる善政を敷いて唐を大いに栄えさせた人でもあるため、その評価は分かれている。
唐の役人として順調に出世を重ねた仲麻呂であったが、やはり日本には帰りたい。何度か玄宗に帰国の許可を願い出るも、仲麻呂を気に入っていた玄宗から許可が下りることはなかった。しかし在唐三十五年目を迎えた七五三年、痺れを切らした仲麻呂は遣唐使船に乗って日本に帰ることを決意、そのときの送別の宴で詠んだのがこの歌だとされている。
ところが不運なことに船は嵐にあって漂流。命は助かったが、今のベトナムまで流されてしまう。何とか長安に戻れた仲麻呂は帰国を諦めたのか、再び遣唐使船に乗ることはなかった。そして七七○年、願いは叶うことなく七十三年の生涯を閉じるのである。
「天の原…」の歌が詠まれたのは亡くなる十七年前だが、彼の叶わなかった願いが歌に重なって、それが歌に深みを与えている気がする。
ちなみに海外に行ったときは、夜空に浮かぶ月を見て「ああ、いつも日本で見ていた月と一緒だ」と阿倍仲麻呂ごっこをするのが僕の恒例になっている。たった一週間程度で帰るくせに、何とも安っぽい仲麻呂である。
後半へ続く(キートン山田っぽく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
