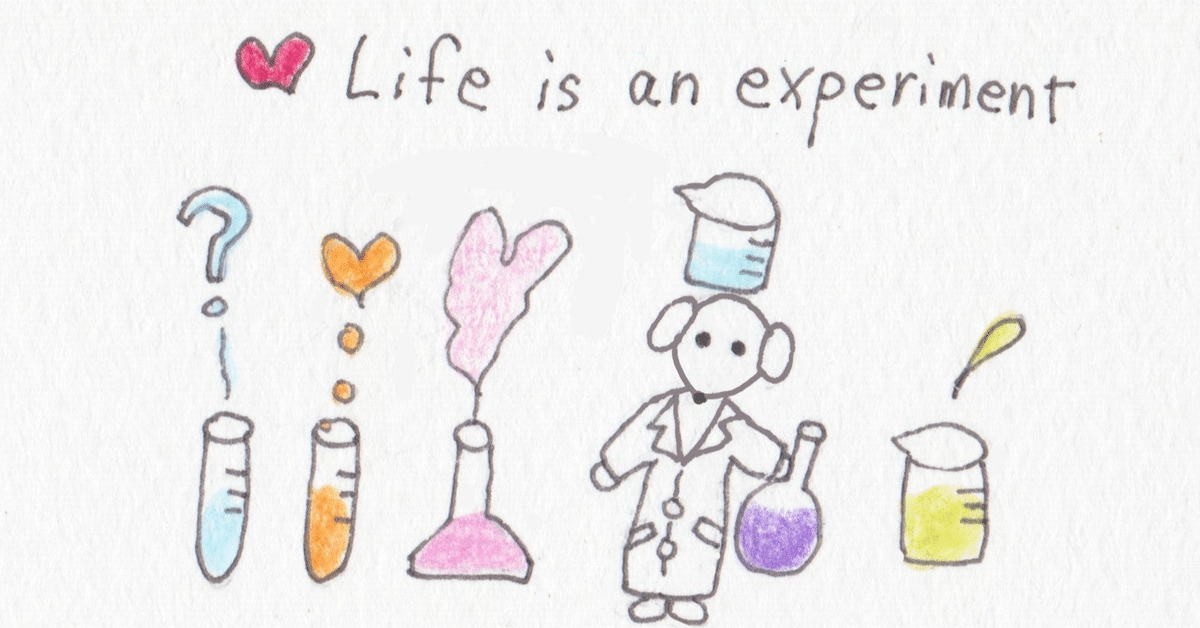
理科の実験記録を一人一台端末で行う
理科の実験が好きです。
教科書を眺めてるよりも楽しいですし、実際に事象を目で鼻で耳で確かめられるのがいいです。
たっぷりと時間をかけて実験をさせるために実験記録はスプレッドシートに入力させています。
今、受け持っている5年生は4年生の12月から理科を教えているので、そこからかれこれ一年以上たちました。
これから実施する「もののとけかた」の単元で使用しようと思っているスプレッドシートを紹介します。今のところ3種類です。
1つ目は、とかす前ととかした後の重さが変化するかを調べる実験

B列にとかす前の「塩」と「ビーカーに入れた水」を合わせた重さを半角数字で入力します。
C列にはとかした後の「食塩水」の重さを半角数字で入力します。
D列に「とかした後-とかす前」の差が表示されます。
2つ目は2つの実験を一つにまとめたシート
Aの実験では「水の量」を変えて、水の温度は変えずに、それぞれの水にとけた塩の量を記録していきます。
単位には表示形式からカスタム数値で「はい」というさじの数を付けています。
共同編集をしますので、一つ目のもそうですが、全ての班の記録を全体で確認することができます。

Bは同様に「水の量」を変えずに、「水の温度」を変えてとける量を記録します。
ちなみに、D5のセルに「全角」で数字を入力しています。当然、数値として認識されないので、平均にはエラーが表示されます。このことをオリエンテーション時に確認しています。半角と全角の違い、切り替える方法、小さなことですが、これらを事前に指導しておくことがスムーズな活用には必須です。

3つ目が実験対象をミョウバンに変えたシート
同じシートであることや大きな数値も入力できること、平均が計算されることを伝えます。
また、もし、間違えたときは、「変更履歴」から元の状態を復元できることも伝えます。
そして、変更履歴では、誰がその操作をしたかもわかることを伝えて「イタズラをすると名前と犯行時刻が履歴として残されていること」も伝えます。ここを指導しておくことで隠れて悪さをしがちなイタズラっ子に対しての抑止効果が期待できます。

こんな感じの実験を今週から始めます。
あくまでも理科の教科としてのねらいを達成するためのICT活用について考えていきたいと思います!!
そのうち、シートを配布できる形にしようと思ってます。
使ってもらいながら、よりよく改良できるといいなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
