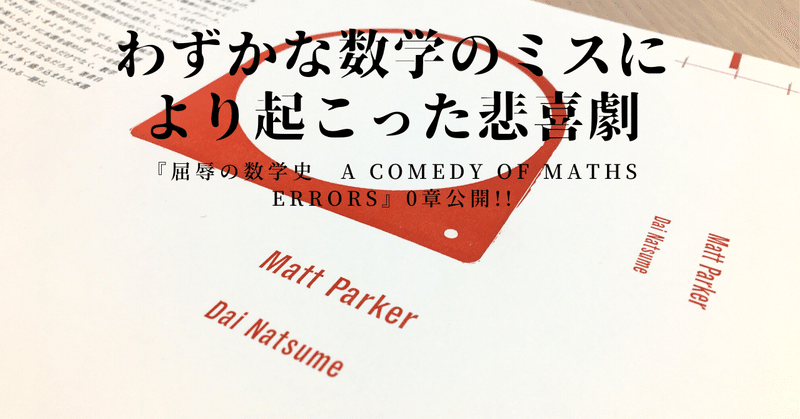
【ペプシ・ポイントで戦闘機を手に入れようとした男の話】人気YouTuberで数学者の著者が語る、数学のミスから起こった悲喜劇!!
ユリウス暦を使っていたロシア選手団が、オリンピックに2週間も遅刻した。プログラム・コードのミスにより、ゲーム上のガンディーが核兵器を好む指導者になった。不適切な用途でExcelを使ったことで、JPモルガン・チェースは60億ドルもの損失を被った。
これらはすべて、わずかな数学によるミスが原因だ。
2022年4月に発行した『屈辱の数学史 A COMEDY OF MATHS ERRORS』(マット・パーカー著 夏目 大訳)は、このような小さな数学のミスにより起こった、おかしくも悲しい出来事の数々を語った一冊であり、原書はイギリス『サンデー・タイムス』紙で数学本初のベストセラー作となった。著者のマット・パーカーは、イギリスでスタンダップ数学者、YouTuberとして活躍している。本書では、その軽快な語り口も楽しんでほしい。
この度、重版出来にともない、本書より「0章」を全文公開!!
__________________________________
第0章 はじめに
1995年、ペプシコ社は、ペプシコーラを購入すると「ペプシ・ポイント」が貯まり、ポイントを景品と交換できるキャンペーンを実施した。75ポイントでシャツ、175ポイントでサングラス、1450ポイントでレザージャケットがもらえる。3つをすべてそろえて身に着けると、いかにも90年代という出で立ちになる。テレビには、実際にすべてを身に着けた少年が登場する。
ただ、CMはそれでは終わらない。その後はペプシらしく、大げさでバカバカしい展開を見せる。シャツ、サングラス、レザージャケットの少年は、何とジェット戦闘機「ハリアー」で学校へ行くのだ。CMによれば、700万ポイントを集めればハリアーがもらえるということらしい。
もちろん、ジョークだ。常識で考えれば、ハリアーがもらえることなどあり得ない。コメディとしては良くできている。ただ、制作者はあまり数字に強くはなかったようだ。700万ポイントは確かに大きな数字のように思える。だが、誰も実際に貯めてやろうと思わないくらいに大きいかどうかは、よく確かめなかったのではないか。
世の中には、数字に強い人もいる。当時、アメリカ海兵隊は、垂直離着陸ジェット戦闘機ハリアーIIの導入に際し、1機あたり2000万ドルもの費用をかけていた。だが、ペプシコ社はご親切にも、アメリカ・ドルをペプシ・ポイントに交換する手段を用意してくれた。10セント支払えば、1ペプシ・ポイントが手に入ったのだ。軍用機の中古市場があるのかどうか私はよく知らないが、2000万ドルもする戦闘機が70万ドルで手に入るのならお買い得だ。その価格で本当にハリアーを手に入れようとしたのが、ジョン・レナードである。
CMはジョークだったのかもしれないが、ジョンは大真面目だった。キャンペーンでは、ペプシ・スタッフ・カタログにつけられた専用の用紙を使って景品を申し込むことになっていた。15ポイント以上貯めた人は、不足分を1ポイントあたり10セントで補うことができる。あとは、送料と手数料合わせて10ドルを負担すれば、好きな景品を受け取れるというわけだ。ジョンはすべて定められたとおりにした。専用の用紙と、ペプシを買って貯めた15ポイント、そして70万8.5ドル分の小切手を、弁護士を通じてペプシコ本社に送った。70万ドルもの大金をジョンは集めたわけだ。それだけでも本気だとわかる。
ペプシコ社は「CMのようにハリアー戦闘機が登場することは、現実にはあり得ない。CMをユーモラスで面白いものにするための演出にすぎない」と主張して、ジョンへの景品支給を断った。しかし、ジョンは弁護士を立てて徹底的に争う姿勢を見せた。ジョンの弁護士は「ペプシコ社が広告での約束を果たすことは当然の義務であり、即座にハリアー戦闘機を依頼人に景品として支給するよう取り計らうべきだ」と反論した。ペプシコ社が応じなかったため、ジョンは訴訟を起こし、裁判で争われることになった。
この件では、問題のCMが「明らかなジョーク」だと言えるのか否か、誰かが真面目に受け取ってもしかたがないと言えるのかどうかが、大きな議論となった。裁判所の公式の判決文を読めば、裁判官がこの一件をバカバカしいと思っていたことがよくわかる。「このコマーシャルは真面目なものと受け取れるとする原告の主張により、裁判所は、なぜこのコマーシャルが面白いかを説明せざるを得なくなった。ジョークの面白さを説明するほどつらい仕事はない」というくだりだけでそれは明らかだろう。
だが、裁判所は実際にこのジョークのどこが面白いのかを説明してくれたのである。
CMに出てくる少年は、ハリアーで登校し、「バスより絶対速いね」と言う。だが、実際にハリアーで登校するのは簡単ではない。住宅地で戦闘機を操縦するのは困難だし、非常に危険だからだ。結局は公共の交通機関を利用するほうがずっと楽なのだが、その現実はまったく無視されている。
生徒が戦闘機に乗ってきたとしても、着陸できる場所のある学校などないし、戦闘機が着陸することで生じる混乱を許容する学校もないだろう。
ハリアーの役割が戦闘であることは明白である。地上あるいは空中の標的を攻撃するのが仕事だ。武装偵察、航空阻止作戦、自衛、攻撃のための対航空機戦争に利用されるものである。その戦闘機をまったくの目的外の登校に使う描写が真面目なわけがない。
結局、ジョン・レナードがジェット戦闘機を手に入れることはなかったし、レナード対ペプシコ事件もいまでは法学史の一部となっている。私は個人的にこの裁判の結果を心強く思っている。私もよくユーモアとして大げさなことを言いがちなのだが、こうした判例があれば、私のジョークを真面目に受け取る人がいても身を守ることができるだろう。それが嫌なら、私の言うことを聞き流すたびに「パーカー・ポイント」がもらえるという制度を始めてもいい。ポイントを貯めると私の写真と交換できる(送料、手数料は別途必要)。
ペプシコ社は再び同じ問題が起きないよう、コマーシャルに修正を加えた。ハリアーをもらうのに必要なポイントを7億ポイントにまで引き上げたのだ。本当なら最初からそのくらい大きな数字にすべきなのに、そうしなかったのが驚きではある。700万ドルのほうが面白いと思ったからではないだろう。おそらく適当に大きな数字を選んだだけで、その数字がどれほどのものかは考えていなかったのだ。
人間というのは総じて、大きな数を把握するのが苦手だ。ある数字が別の数字より大きいことはわかっても、その差がどのくらいなのか、正しく認識することがなかなかできない。私は2012年にBBCニュースに出演して「1兆はどのくらい大きいか」という話をした。その頃、イギリスの債務残高がちょうど1兆ポンドを超えたというので、BBCは私を番組に出して、それがどのくらい大きな数かを説明させようとしたのだ。当然、「ものすごく、本当に大きいです。ではスタジオにお返しします!」などと叫んでもだめだ。どうにか納得してもらえるような説明をしなくてはならない。
私はこういう場合によく「時間」を使う。100万、10億、兆がそれぞれに違う数字であることは誰でも知っている。しかし、どのくらい違うかはよくわかっていない人が多いのではないだろうか。たとえば、100万秒は、11日と14時間より少し短いくらいだ。長い時間ではあるけれど、そのくらいは待てなくもない。2週間よりは短い。しかし、10億秒となるとどうか。10億秒は31年を超える時間だ。
いまから1兆秒後は、西暦3万3700年になる。
こう説明すると、すぐにわかってもらえるのではないだろうか。10億は100万の1000倍、1兆は10億の1000倍だ。100万秒はだいたい3分の1ヶ月で、10億秒は330ヶ月くらい(1000ヶ月の3分の1くらい)だ。そして、10億秒が31年くらいだとしたら、当然、1兆秒は3万1000年くらいということになる。
私たちは日々、生活する中で数が直線的なものであること、また数と数の間隔はどれも同じであることを学ぶ。1から9まで数えたとしたら、どの数も前の数より1だけ大きい。1から9までの間の中間の数はどれか、と尋ねれば、誰もが「5」だと答えるだろう。だが、これはそう教わったからにすぎない。教わったとおりを素直に信じている羊のようにおとなしい人たち、目を覚ましてほしい。人間が数を直線的なものと思うのは生まれつきではない。元来、人間は数を直線的ではなく、対数的なものととらえる生き物である。幼い子どもたちや、教育に洗脳されていない人たちは、1から9までの間の中間の数は3だと思う。
実は「中間」にも種類がある。1つは「対数的中間」だ。これは、足し算ではなく、掛け算の中間だと言っていい。1×3=3で、3×3=9 となる。足し算ならば、1に4を2回足せば9になる。だが、掛け算だと、3を2回掛ければ9になる。つまり、1から9までの間の「掛け算的な中間」は「3」ということだ。教育を受ける前の人間にとって、中間とは後者の「掛け算的中間」のことである。
アマゾンの先住民族であるムンドゥルク族の人たちに、1個から10個までの点の集合を見せ、どの集合が中間かを尋ねると、皆、3つの点の集合を中間だと答えるという。幼稚園くらいの子どもに同じ質問をすれば、親が特別に早く教えていない限り、おそらく同じように答えるだろう。
教育を受けることで、比較的小さな数は直線的だと感じるようになるのだが、あまり扱うことのない大きな数は、大人になっても引き続き対数的なものととらえる人が多い。1兆と10億の間の違いを、100万と10億の間の違いと同じように感じてしまうのだ。どちらも1000倍だからだ。だが、実際には1兆と10億の間の違いのほうがずっと大きい。10億秒ならば、31年という人の一生に収まりそうな時間だが、1兆秒は3万年以上にもなってしまう。3万年後には、人類自体が存続していないかもしれない。
私たち人間の脳は生まれつき数学が得意ではない。ただ、一方で数や空間に関して優れた能力、幅広い能力を持って生まれていることも事実である。小さな子どもでも、紙に書かれた点がだいたいいくつかあるかはわかるし、点の数を足したり、引いたりといった簡単な計算をすることもできる。人間が生まれてくるのは、言語や記号を使った思考を必要とする世界であり、われわれはそういう世界に適応できる力を持って生まれてきてはいる。ただし、生存やコミュニティ形成に必要な能力と、本格的な数学に必要な能力とは大きく違っている。数を対数的にとらえることは誤りではないが、数学には、数を直線的にとらえる思考も必要になる。
数学を本格的に学び始めた時点では、人は誰も何もわからない愚か者だ。進化が私たちに与えてくれた能力では間に合わないので、意識してそれを超える能力、生物として生きる上では合理的でない能力を身に着ける必要がある。分数、負の数などの奇妙な概念を、直感的に理解 できるような能力を持って生まれている人はいない。だが、私たちは時間をかけてゆっくりと、そうした概念の扱いを学んでいく。いまは学校があるので、全員が強制的に数学を学ばされる。学校で数学に触れているうちに、私たちの脳は次第に数学的に考えられるようになる。しかし、 使わなくなれば、せっかく身につけた能力は衰え、脳は再び生まれたときの状態へと戻ってし まう。
イギリスには以前、売り出されたその週にすべて回収になったスクラッチ式の宝くじがあった。発売元のキャメロット社はその理由を「消費者の混乱を招いたため」とした。「クール・キャッシュ」という名のそのくじには、温度が印刷されていた。購入者がくじを削ると、別の温度が現れるのだが、その温度がもとの温度よりも低ければ「当たり」である。ところが、購入者の中には、負の数の理解に問題のある人が多かった。たとえば、こういう声があった。
私が買ったカードのうち一枚には、-8と印刷されていました。削って現れた温度は-6と-7だったので、私は「当たった」と思いました。宝くじ売り場の店員さんもです。しかし、店員さんがカードを機械にかけると、「外れ」と出たんです。私はおかしいと思いキャメロット社に電話しました。電話に出た担当者は何やら長々と説明をし、あくまでも-6度は-8度よりも高く、低くない、と言い張ります。しかし、私はどうしても納得ができません。
人類はこれほど数学が苦手だということだ。にもかかわらず、現代社会は数学に大きく依存している。信じがたいことだし、恐ろしいことだとも言える。一人ひとりは生まれつき数学が得意ではないのに、種全体では、生まれつきの脳の能力をはるかに超えて数学を探求し、数学を利用している。生まれつき持っているハードウェアの能力をはるかに超えることを成し遂げてきたのである。直感だけに頼らずに学習を続けているからこそ、とてつもないことができるのだが、直感ではわからないことだからこそ、誤りが起きやすいのも確かだ。何かを間違えても気付かないことが多く、ちょっとした間違いが恐ろしい結果を招く場合もある。
いまの世界は数学を基礎として成り立っている。コンピュータのプログラミングも金融も工学も、一見違っているようで、どれも根本は数学である。だからどの分野でも、些細に見える数学のミスが、驚くような事態を引き起こす。古いものから新しいものまで、数ある数学のミスの中から、私が特に興味深いと思ったものを集めたのがこの本だ。読んで面白いだけでなく、知らなかったことを知ることのできる本になっていると思う。カーテンを開き、普段は舞台裏で人知れず働いている数学の正体を、詳らかにしたと言える。魔法のごとき現代の最新技術の背後では、数学という魔法使いが、そろばんや計算尺を手に昼夜を問わず働いている。数学がどれほどの仕事をしているかは、何か問題が起きたときにだけ明らかになる。その仕事が高度なものであるほど、問題が生じたときの損害は大きい。高いところに上がるほど落下の衝撃は大きいということだ。私は決してミスをした人たちを物笑いの種にしたいのではない。私自身がそもそもミスの多い人間なので、とてもそんなことはできない。ミスが多いのは誰も同じだ ろう。実は、本書を作る際にもいくつかミスをしたが、面白いのでそのうちの3つはそのまま残してある。すべてに気付いた人はぜひ、教えてほしい。
__________________________________
【著者略歴】マット・パーカー Matt Parker
オーストラリア出身の元数学教師。イギリスのゴダルマイニングという歴史ある(古過ぎるのではと思うこともある)街に暮らす。他の著書に『四次元で作れるもの、できること(Things to Make and Do in the Fourth Dimension)』がある。数学とスタンダップ・コメディを愛し、両者を同時にこなすことも多い。テレビやラジオに出演して数学について話す他、ユーチューバーとしても活躍。オリジナル動画の再生回数は数千万回以上、ライブのコメディー・ショーを行えば、毎回、満員御礼という人気者だ。
【訳者略歴】夏目 大(なつめ・だい)
大阪府生まれ。翻訳家。大学卒業後、SEとして勤務したのちに翻訳家になる。主な訳書に『6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む』ジャン=ポール・ディディエローラン(共にハーパーコリンズ・ ジャパン)、『エルヴィス・コステロ自伝』エルヴィス・コステロ(亜紀書房)、『タコの心身問題』ピーター・ゴドフリー=スミス(みすず書房)、『「男らしさ」はつらいよ』ロバート・ウェッブ(双葉社)、『南極探検とペンギン』ロイド・スペンサー・デイヴィス(青土社)、『Think CIVILITY』クリスティーン・ ポラス(東洋経済新報社)など多数。
__________________________________
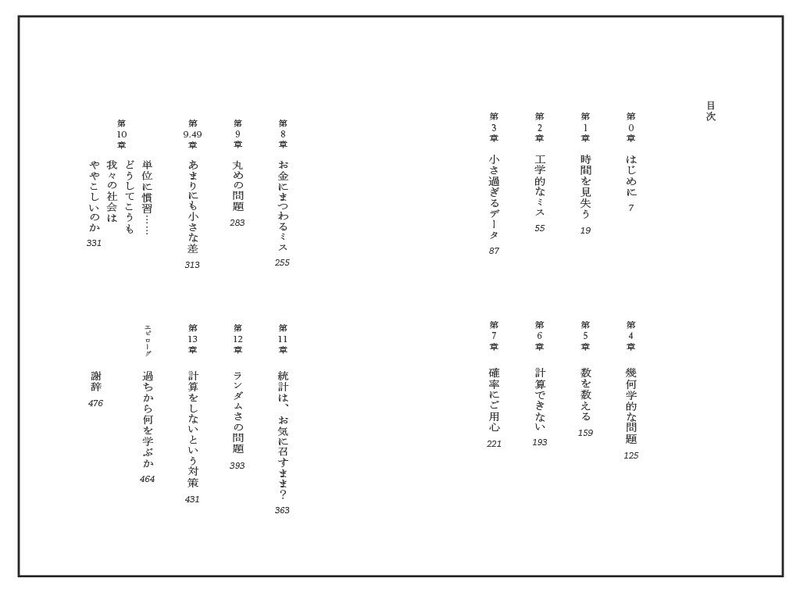
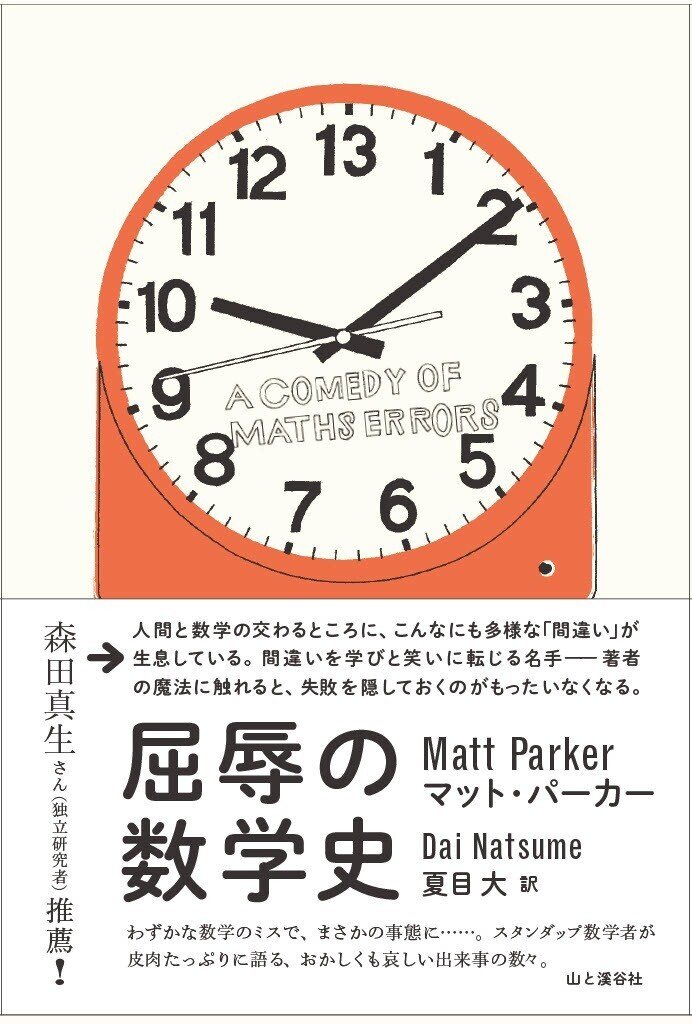
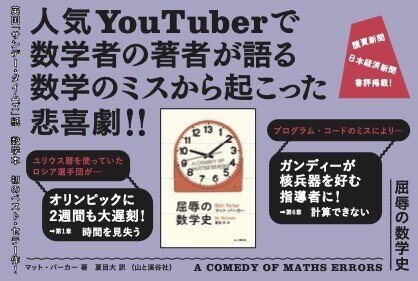
記事を気に入っていただけたら、スキやフォローしていただけるとうれしいです!
