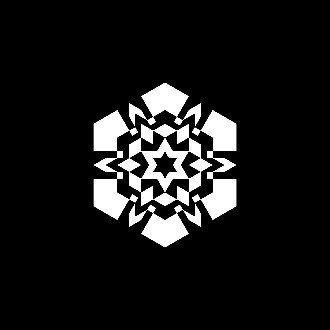【表現辞典】霊石典[となえる(唱える)]全文無料・解説つき
霊石典
今回は[となえる(唱える)]です。
霊石典で言葉を学ぶ基本的な手順をお伝えします。[唱える]という言葉の本質がどこにあり、文章表現でどのように活かすと良いのか、わかりやすく解説します。
初回ということで、今回は引用欄を用いて、各項目についての解説を記します。次回以降の記事に、この引用欄はありません。
となえる(唱える)
用例
○呪文を唱える
○異議を唱える
○唱歌
〈↑〉最初に用例をいくつか示します。熟語なども含めることで、多様な使われ方を学びます。
○折口信夫『鬼を追い払う夜』
「福は内、鬼は外」と言うことを知って居ますか。此は節分の夜、豆を撒いて唱える語なのです。
〈↑〉名作家の実例を取りあげます。
霊石典では、このように、まず最初に用例を示します。国語辞典のように意味をいきなり定義するのではなく、実際にその言葉がどのように使われているかを知ることで、言葉が本来持っている意味やニュアンスを、余すところなく体感していただけます。
意味
○声に出して言う。とくに、詩歌や呪文または自説や主張などを、気持ちを込めて声に出す。
次に、その言葉の意味を記載します。単なる表面的な説明にとどまらず、その言葉の本質を掴めるよう、一歩踏み込んで、勘所を押さえて解説します。
関連語
○「声に出す」というだけの意味なら、[言う]と同じ。
○なにかの感情を込めて言葉を発するという意味なら、[叫ぶ][唸る][呻く]も似たような立場にある。
同じ意味の言葉、似ているがニュアンスが違う言葉、反対の意味の言葉などを取り上げます。周辺の言葉と比べることで、その言葉の輪郭を浮き彫りにします。
表現についての考察
[唱える]は、行為としては[言う]と同じです。しかし、「詩を言う」「異議を言う」とは使いませんし、それでは表現として軽く感じます。なぜなら、[唱える]が対象とするのが、主に詩歌や自説であり、それらは話し手が特別な意志を込めて口にする文言だからです。その文言じたいに深い意味があり、その文言をつうじて何かを叶えたいという意図を、話し手は持っているのです。ゆえに、深い意図なく発せられる「おはよう」や「おいしい」に[唱える]は使いません。
ですが逆に、その文言に深い想いが込められていて、相手の気持ちを変えようとする強い意志があるなら、聞きなれない表現ですが、「愛の言葉を唱えた」という使い方も可能ということです。愛の言葉には、相手の心を動かす力が込められています。その言葉の力を信じ、相手に自分の気持ちを伝えたいと願う話し手の意志を、[唱える]が受け持つのです。「愛の言葉を言った」「愛の言葉を囁いた」よりも、発言者の真心を示す力が[唱える]にはあります。
この項目が霊石典の最大の特徴です。言葉を実際の文章表現のなかで使いこなせるようになるのが、霊石典の目標です。そのために、これまでの項目で得られた知識をもとに、その言葉の本質を明示するとともに、その言葉が持つ力をいかに文章表現に活用するか、実例を交えながら考察します。
さいごに
[唱える]を霊石典の最初に取りあげたのは、「言葉には霊力が宿っている」ということを、[唱える]が示しているからです。「呪文」「歌」「愛の言葉」には、人の心を強く動かす、目に見えぬ力が宿っています。言葉に宿った霊力を信じ、相手の心を変えようと、願いを込めて口に出す行為が[唱える]なのです。まさに、「言葉に宿った力を掘り起こして文章表現に活用する」という、霊石典の原点を完璧に表しており、まず最初に学ぶのに相応しい語句だと思い、第一回に[唱える]を取りあげました。
このような流れで、今後も様々な言葉を取り上げます。取り上げた言葉を使いこなせるようになるのはもちろんですが、読んでいるうちに、必ずや言葉について学ぶセンスが磨かれるはずです。みなさまの執筆する文章が一段と輝きを増すよう、これからも霊石典の編集を続けてまいります。どうぞ、よろしくお願いします。(編者:山田星彦)
派生記事
Forever 19 summer vacation !