
十二年越しの伏線回収 (著:千秋 明帆)
「山田組文芸部」は2019年に発足された文芸部です。現在は会員4人、準会員1人で活動しています。指定されたテーマに沿って小説を書き、季節ごとに文芸誌を発刊します。第7号のテーマは”映画”です。
『十二年越しの伏線回収』
千秋 明帆
隣で動く気配がしても、前を見つめつづけた。
白黒しかない画面の中で浮かび上がるThe Endの文字と共に右側だけ沈み込むソファーも、薄暗い部屋に落ちる衣擦れの音も、左頬を照らした蛍光灯の眩しさも、何もかもを無視して前だけを見つめる。
「じゃあね。」
静かな声は、肩をひと撫でして去っていった。
エンドロールすら無い、余韻に満ちた物語の終わり。止まるテープの音だけが空しい。
閉まる時だけ軋むドア。ガダン。鍵を回して、やや無音。カチェン。ポストの底を合い鍵が叩いた後、ほんの僅かな左足の踵を擦るようにして歩く足音は少しずつ、小さくなっていく。遠のいて、遠のいて。遠のいて。
遠くの音は、やがて途絶えた。これで、終わりだ。
立ち上がり、電気を付けた。左側の空いたラック、間の抜けた洗面台、隙間だらけの本棚。白色の電灯が濡らす部屋は、少し苦しい。少しずつ消えていったものを、まざまざと見せつけてくる。まだ見ぬポストに入った鍵。昨日見た隙間だらけの靴箱。そして冷えた左肩。今日で全部なくなった。元に戻っただけなのに、喉の奥が閉まるようで、震えるようで、苦しい。
一緒にいるための大きな理由とか、劇的な出会いとか、激烈で濃厚な時間とか、そんなものなんてなくて。サークルなんていうありふれた出会い、映像という好みの一致、たった三年半。ゆっくりと重ねた肌の一体感のまま取り留めのない話をして。映像製作に関わりたいと前を見る君の視線の先とまでいかなくても、指先をなでる程度共にあれたなら良いと漠然と思っていて。いつか隣でなんて少しの未来を語っていたけれど、でも君はその程度には収まらなかった、それだけだ。待っていてなんて明言せず、ただ最後に映画を観たいと言った君との穏やかな終わり。これが世間の言う激しい恋だとか、熱い愛ではないとわかっていた。
そうして終わった思い出に、サブスクリプションは容赦がない。あの頃わざわざビデオをショップまで行ってレンタルしていた白黒映画も見放題となってしまった。タイトルを目にしただけで青春を抉り出す、かっこつけて借りたアレとか何度も見直したソレとか。アルバイトの給料日前の葛藤、ビデオゆえのテープ劣化によるノイズ、レンタル返却を忘れたときの後悔…。
ここまでくると感傷に浸ることすらできない。感傷ゆえもう一回見ようとすら思えずにいたタイトルたちがスイスイと画面を流れていく。どことなく空しさを覚える。なんというか、思い出が次々と脳裏を過ぎていくが、速すぎて虚しい。これ彼女と話題にしたタイトル。レンタルして一緒に観たやつ。映画館まで観に行ったやつ。これも観たときは彼女と一緒だった、いやこっちは別れた後か。これは別の人と。これは、一人になった最近の。でも不思議と、というのか。速すぎるからこそチクチクとしたものとかモヤモヤしたものとか、まったくなかった。歳によるものか、鈍感になってしまったのか。
ふと、最後に見た映画を見つけてしまった。美しい女優、短い休日、そして青春の終わり。重ねてしまいそうで見たくなかった、有名タイトル。でも痛みはない。ただ鼻を掠める、ピオニーの香り。彼女の使っていたボディクリームの香りだ。気付いたのは、あの時の、ポストから鍵を取り出して部屋に戻った瞬間。そして、飛び込んだベッドから強く。何もない部屋に、香りだけ残してった。返却用の袋から、微かに感じた。タイトルに深く結びついていたのだろう。ありもしない香りが鼻腔をかすめた気がした。
そういえば人間の記憶は聴覚から欠落していくらしい。確かに声が思い出せない。視覚はどうだろう。顔もおぼろげだ。あのしなやかな背中の感触も味も上書きされたため覚えていない。だから痛くもないのだろうか。芳香だけ残して、じゃあねの一言で、終わった彼女との思い出。良い思い出なのかな。いつかまた、思い出したことすら良い思い出のうちになっていくのかな。そんなことを思いながら、サブスクリプションアプリを閉じてネットニュース一覧を眺める。
トップニュース一覧から少し下に移動したとたん目に飛び込んできた文字と写真に一瞬思考が停止した。そして、声を上げて笑ってしまった。こんな偶然もあるのだ、いや、これすらも何か決まっていたのかもしれない。よく言う、運命的な何か。
取り上げられた話題には、独自の世界を撮ろうと奮闘する女性監督の名前と顔写真、インタビュー内容が書かれていた。かつて口に馴染んでいた、あの名前が。かつて映画館で客席を見て輝いていたあの目が。部屋の中で見せていたあの背中で監督席に座り、あの指先で指示を飛ばしている。サブスクからのネットニュースでまさかここまで華麗な流れになっていたとは。圧巻すぎて笑うしかない。しかし、納得してしまった。あいつなら、やるだろうな。人生を演出したいと豪語していたことを、ふと思い出す。
あんなにも有名な映画で、劇的に終わらせて。別れに名残とかなく、別れの返事もさせず。あんなやつもいたな程度ではなく、強く思い出させるための、なんだろう、意地のようなものだったんだろうか。やりたいことができたからという、お互いにさらりとした別れだった。なのに脳裏に残っている。そして華々しい活躍でいつかやりたいことをやり遂げた報告を大々的にする。こんなことされたら、鮮やかに思い出すしかない。過去の何人かとかではなく、一番に。鮮烈に。確かに狙い通りではあったんだろう、激しい恋でも熱い愛でもなかったのに一番心に居座っているのは、彼女なのだから。
感心したり浸っていたから知らなかった。
まさか、やりたいことというのは「映画のワンシーンのような忘れられない別れをした彼女が有名になってプロポーズする」だったと言い放つために玄関先に彼女が立っていたなんて!
To be continued?
「十二年越しの伏線回収」の千秋 明帆が、 おすすめの映画を紹介
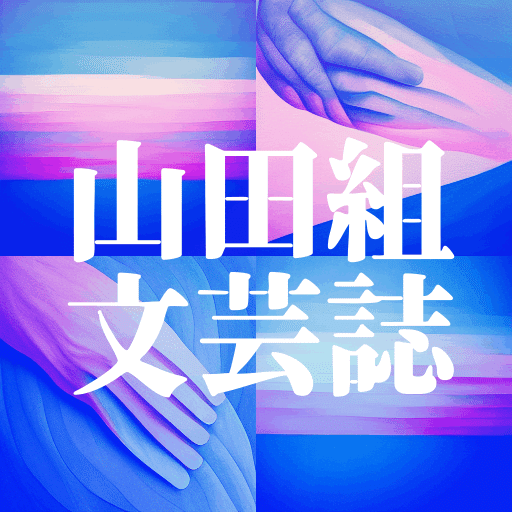
山田組文芸誌 第7号「映画」
山田組文芸誌 第6号「ライバル」
入部希望の方はTwitterのダイレクトメッセージへご連絡ください▼
https://twitter.com/yamadagumibun
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
