
ドリーム座の休日(著:高平 九)
ドリーム座の休日
高平 九
夢見橋の石の欄干にもたれて川の流れを見ていた。昨夜の大雨のせいでいつもよりずっと水面が近く見える。寛之は濁った水の勢いに焦りのようなものを感じて川の終点である港の方角に目を移したが灰色の空以外には何も見えなかった。
午前七時。雲が空を覆っているので今はそれほど暑くはない。予報では昼にはまた晴れるそうだ。寛之はショルダーバッグからペットボトルを取り出しマスクを顎に下げて水を少し口に含んだ。
この町で散歩を始めてから1週間になる。東京にいるときも朝の散歩は習慣だったが、50年ぶりに戻ってきた故郷を噛みしめるように毎日違うルートを歩いた。スマホを見るとすでに5千歩を超えている。1日1万歩を目標にしているので、そろそろ家を目指すことにするか。
スマホのアプリで帰路を確認する。この夢見橋周辺には様々な思い出があるが、建物が変わっていて記憶と現実の町の姿がなかなか重ならない。鮮明だったはずの記憶がすっかりぼやけていた。スマホがなかったらただの徘徊老人になっていたかもしれない。そう考えると怖ろしいような可笑しいような気分になった。
今年で64歳になる。中学2年のとき両親が離婚をして東京の中野にある母親の実家に行ってから半世紀が過ぎた。夢は映画監督になることだった。しかし大学の映画サークルでさえ自分より才能のある奴がたくさんいた。結局は大手の銀行に就職し四年前に退職するまで38年間銀行マンとして働き続けた。
今年の春、疎遠だった父親が危篤だと病院から連絡があった。急いで駆けつけたがすでに息を引き取った後だった。母と別れた後も父は再婚せずこの町でひっそりと生きていた。持ち家とわずかな預金を寛之に遺すという遺言書が病室の戸棚に残されていた。母親か妻が生きていれば反対しただろう。だが2人とももういなかった。今年32歳になる長男は誰を真似たのか映画の専門学校を出て助監督をやっていた。中野の家は安アパートで暮らす長男夫婦に譲って、寛之は故郷の町に帰ることにした。
父の家は新しく建て替えられていた。かつての家の面影は1階の和室にある場違いな大黒柱だけだ。黒光りのする柱には従兄弟たちとの背比べの傷が残っていた。もしかすると今の寛之の境遇を父は知っていたのかもしれない。自分の死が間近に見えたとき父はこの家を寛之に譲るためにリフォームしたのだ。妻に先立たれ仕事もせず長い休日をただ何となく過ごしている一人息子のために。そう思いつくと胸が痛んだ。50年のあいだ寛之の方はまったく父親を振り返らなかったからだ。
二階には書斎らしき部屋があった。父親の蔵書はすでに処分されて書棚は空だった。窓際に高価な洋材の机があり、その上に古びた映画のパンフレットと日に焼けて茶色に変色した脚本が置かれていた。
パンフレットは『ローマの休日』のもので、表紙の隅に寛之の幼い字の署名があった。アン王女の写真はまるで泣いているようだった。脚本の方にも少しきどった寛之の字で『牢番の休日』と題名が書かれていた。大学の映画サークルにいたときに書いた本だった。江戸時代の中年の牢番とお姫様のふれあいを描いた物語。もちろん『ローマの休日』を下書きにしている。サークルで制作する映画の脚本として書いたものだが結局採用されなかった。だが寛之はそれらを父親に送った覚えはなかった。送ったとしたら母親だろう。寛之の知らないところで父と母はまだつながっていた。それに気付いたとき裏切られたような気持ちなった。
橋を渡って表通りに向かって歩いた。川と表通りの間にも大きな通りがあって「夢見銀座」と呼ばれていた。入り口には今も「ゆめみぎんざ」と書かれた大看板が寂しく掲げられている。通りを覗くと左右の歩道には昔と同じように商店街共同の日除けが伸びていた。ランプの形をした街灯も昔のままだ。しかし櫛比した商店の多くのシャッターは堅く口を閉ざしていた。
寛之の目は自然に夢見銀座の一画に注がれた。今はシャッターか並んでいるそこにはかつて小さな映画館があった。いわゆる封切館ではない。古い映画ばかりを上映する名画座だった。寛之が町を出るとき廃業してスーパーマーケットになったはずだが、それも今はなくなってしまっていた。「ドリーム座」を思い出すと喉に苦い味が広がった。寛之はその苦みを飲み込んで表通りに向かって歩いた。
かつては市電が走っていた表通りでは、来週の旧盆に数百人の踊り手たちが練り歩く、この町最大の祭りが予定されていた。
通りに出て右に折れた。雲が切れていきなり強い日射しが通りを襲った。目眩を覚えて目をつぶった。水分補給はしていたつもりだったが、曇り空に油断したか。バッグからペットボトルを出そうとしたとき、一瞬、陽炎のなかに市電が見えたような気がした。いや、そんなはずはない。いよいよ熱中症か。逃げ込めそうな日陰を探すと、歩道に並んだビルの隙間に1メートルほどの幅の魅力的な路地を見つけた。寛之はよろよろと路地に逃げ込んだ。路地の中は涼しくて気持ちがよかった。すっきりした頭で表通りを覗いたが市電は見えなかった。
大きく深呼吸をしてペットボトルのぬるい水を一口飲んだ。ここは不思議に路地特有のいかがわしい匂いがない。清潔で澄んだ空間だ。壁もひんやりして気持ちがよかった。しばらくいればこの路地にいれば体調も戻るに違いない。
ふと路地の奥を見ると、長方形に切り取られた出口に色鮮やかな絵らしきものが見えた。そこは夢見銀座のはずだが、今見えるのは灰色のシャッターではなくペンキで描いたような絵だった。よく見るとどうも男の顔のようだ。顎の線に見覚えがあった。もう一度深呼吸をして自分の体調を確認すると路地の出口に向かって歩き出した。
路地を出ると正面に大きな看板があった。『ローマの休日』と太い字でレタリングされた文字の左右に男女の上半身が雑に描かれている。さっき見えたのはグレゴリー・ペックの顔の一部だった。もう一人のティアラを髪に挿した女性はオードリー・ヘップバーン。
「まさか、ここはドリーム座……」
そんなはずはなかった。ドリーム座はとっくに廃館になった。でも、入り口の上には「ドリーム座」と看板が掲げられていた
寛之が呆然と看板を見上げていると、学生帽を被った少年とその連れの野球帽の少年がそばに立ってこちらを見ていた。いつの間にか夢見銀座には人があふれていた。シャッターを下ろしている店などどこにもない。商店街にはかつての活気が戻っていた。
「おせえぞ。……ホラ、これ」
学生帽の少年が指にはさんだ紙切れを差し出した。戸惑っていると少年はそれを寛之の手の中に強引に握らせた。
「いいか。帽子を目深に被って半券を見せて通るんだ。オドオドするんじゃねえぞ」
少年はそう命令すると帽子の庇を下ろしながら入り口に向かった。わけがわからず野球帽の少年の方を見ると、幼いしもぶくれの顔が寛之を見上げて、
「ヒロちゃん、グスグスするな」
とまだ声変わりしていない声で言った。
「ソウちゃん?」
寛之のなかにふいに少年の名が浮かんだ。
「おい」
入り口に向かった学生帽が振り向いた。
「シュンちゃん?」
その色黒のにきび面にも見覚えがあった。従兄の俊平だ。野球帽はその弟の聡太。彼らは寛之の家の隣に住んでいた。実家の大黒柱の傷も3人で付けたものだ。
「早く」
聡太が背中を強く押した。つんのめって自分の靴を見た。ズック。真新しいズックを履いていた。
「行くぞ。顔を伏せろ」
もぎりの女性が鋭い視線を寛之たちに向けた。俊平の指示のとおり下を向いて半券の持つ手を挙げた。今にも「待ちなさい」という声がしそうで息が苦しくなった。入り口のガラスに自分の姿が映った。真新しい学生帽を被ったやせた色白の中学生。驚いたことにそれは13歳の寛之だった。
「止まるなよ、ヒロちゃん」
背後から聡太のきつい声がした。
映画のポスターが貼られた廊下を3人は黙って進んだ。微かに劇場内の音が洩れている。売店の近くに来ると俊平の背中の緊張が緩み、振り返って笑った。
「じゃあ食い物と飲み物はヒロのおごりな」
「うん……」
制服のズボンのポケットから財布を取り出した。中には千円札が2枚入っていた。伊藤博文の肖像の古い千円札だ。母親が3人分の映画代とおやつ代を持たせてくれたものだろう。代金を払うとき売店の女性から咎められるのではないかと顔が熱くなり手が震えた。半券は再入場のときに使うものだと父親から教えられていた。従兄弟たちは先に入っていて半券で再入場したのかもしれない。でも、自分は来たばかりだ。入場券を買わず半券で入れるはずがない。自分は悪いことをしたのか。だが、そのことを俊平に問い質す勇気はなかった。
劇場の扉はあふれた客の身体に押されて半開きになっていた。ドアの間からは遮光用の臙脂色のビロードがはみ出している。中から英語の声がくぐもって聞こえてきた。
「片目をつぶれ」
扉の前に立つと俊平が命じた。
入る前には片目をつぶっておくんだ。中で目を開けると暗闇に慣れているからすぐに空いている席を探せる。そう教えてくれたのは俊平だった。しばらくの間その場で目をつぶってから「行くぞ」という俊平の合図で扉の中に突進した。
大人の身体の間に俊平が自分をねじ込む。その隙間に寛之もすかさず細い身体を押し入れた。大人たちの熱く汗ばんだ肉の感触が嫌だった。
当時の映画館では客は飲んだり食べたりしたゴミを椅子の下に捨てるのが当たり前だった。入れ替えもないから座席の下には1日分のゴミがたまっている。その甘いような酸っぱい匂いを嗅いだ寛之は、吐き気を覚えてその場にしゃがんでしまった。
「おい、だらしねえな。俺について来なよ」
四つん這いになった聡太が片目で寛之を見ていた。聡太は11歳だったが背が低くてぽっちゃりとしたあどけない顔をしている。だが、寛之のようになんでも俊平を真似るのではなく、自分の特性を生かして自分の道を切り拓くことを知っている。寛之も聡太を見習って四つん這いで大人の脚のあいだを通り抜けた。
大人の壁を抜けて劇場が見渡せるところに出ると寛之は片目を開けてみた。劇場の中がよく見えた。壁には立ち見の客が隙間なく並んでいた。通路や階段にも客が座っている。巨大なスクリーンでは若い女が黒服の男の頭をギターで殴っていた。どよめくような笑い声がした。どの客の顔もスクリーンの明かりに照らされて輝いていた。一瞬すべてを忘れて人々の笑顔に見とれた。
「ヒロ、こっちだ」
俊平の声がした。見ると壁側の階段を屈んだ姿勢の俊平が上がって行く。壁に並んだ観客の足を踏まないように俊平の背中を追った。
俊平は親子連れの席に接した階段に隙間を見つけて腰を下ろした。尻の下には新聞紙を敷いている。新聞紙は通路や階段のいたるところに落ちていた。始めから床に座るのを覚悟でみんな新聞紙を持参してくるのだった。俊平のすぐ下に腰を下ろした。床が湿って冷たかった。新聞紙を拾いそこねた。聡太も寛之の下に席を占めたがちゃっかりスーパーのチラシを敷いている。
「ほらよ、これ敷けよ」
俊平が持っていた新聞紙を渡してくれた。
スクリーンでは危機的な状況を脱したアン王女と新聞記者のジョーがキスをしていた。
一番の見せ場のはずなのに寛之はスクリーンの物語に集中できなかった。半券だけで入ったことが気になっていた。何かに心臓をきつく掴まれているような感じがした。寛之の悩みも知らず、下から聡太の暢気な寝息が聞こえてきた。振り向くと俊平も目をつぶっている。
この時代には映画は大抵2本立てだった。目当ての映画の間にもう1本どうでもいい映画が上映される。どちらも前評判のいい映画が同時上映などほとんどない。
人気のある映画だけを繰り返すと、ずっと居すわる客が増えるだろう。そうならないようにつまらない映画を同時に上映するのさ。自然に客が入れ替わるからな。
真偽のほどはわからないがこれも俊平に教えられたことだ。
だから、どうでもいい映画の途中から入場する客もいた。その映画が終わって席を立ったら座ろうという魂胆だ。だが実際には、どうでもいい映画の後で立つ客などほとんどいない。座りたければ人気作品の途中で入って、それが終わった後の空席を狙うのが映画好きの常識だった。
ただ、一人で来ている男性客などは暇に任せて二度、三度と観て行くこともある。だから俊平のように家族連れやカップルの横で待つのが定石だ。恋愛映画を大人に付き合って何度も観る子どもはいないし、カップルの本当のお楽しみが映画ではないことくらいは寛之にも分かっていた。
いい映画は最初からゆっくり観たい。ここで観てしまうと結末が分かって興をそがれる。だから従兄弟たちのように眠るのが一番だった。目をつぶると声だけが身体に染みてきた。 これは夢なのか。いや、これは記憶だ。中学1年生の夏、このドリーム座で従兄弟たちと『ローマの休日』を観た。そのとき半券を使ってタダで映画を観たという罪の記憶はまだ寛之の中に残っていた。だからいまだにドリーム座のことを思い出すと苦い気持ちになるのだ。ただその記憶は尻切れトンボだった。
父が机の上に残した『ローマの休日』のパンフレット。寛之にはそれを買った記憶がない。劇場で『ローマの休日』を観たのは一度きりだ。ということはパンフレットもそのときに買ったことになる。しかし覚えがまったくなかった。確かに家を出るまでパンフレットは寛之の宝物だった。それなのに買ったときのことを覚えていないなんて。もしかするとパンフレットも盗んだものなのだろうか。
客がざわつきはじめた。目を開けるとスクリーンにはエンドロールが流れて、気の早い客が席を立ち始めている。
「おい」
俊平の声がした。近くの家族連れが立っていた。俊平は3つ空いた席の一番奥にすかさず座り端の席に帽子を脱いで置いた。寛之は俊平の帽子を取って端の席に腰かけ聡太を待った。聡太は客の渦に巻き込まれてしまっていた。
「そこ空いてる?」
と尋ねてきた女性がいた。真っ赤な口紅を塗った、いい香りのする人だった。聡太の席には俊平の帽子を置いてあったが、寛之は帽子の上にさらに手を置いて首を横に振った。女性は悲しそうに頷いて他の空席を探しに行ってしまった。
「いい女だったな。聡太よりあの人の隣がよかったよ」
俊平は自分の帽子を取り上げながら言った。聡太が席に着いたころ、エンドロールが終わって明かりが点いた。
予告編が終わって同時上映の映画が始まった。恋愛を絡めたサスペンス映画だった。女性の裸や暴力シーンがやたらと多くて寛之たちには刺激が強すぎた。聡太は靴を脱いで座席の上で膝を抱えて目をつぶっていた。寛之も女性が裸になると見ていられず目を閉じた。
幼いころ両親はよく映画館の前でどの映画を観るかで言い争った。父親は洋画派で母親は邦画派だったからだ。物別れになると夫婦は別々の映画館に入った。そんなとき寛之はたいてい父親について行った。甘ったるい恋愛映画より派手なアクションのある洋画が好きだったからだ。だが、あるとき予告編でベッドの上に横たわる女のシーツを男が剥ぐシーンがあった。全裸の女性の白くて大きな尻が画面いっぱいに映し出された。そのとき以来、母親と映画に行くことが増えた。興味がなかったわけではない。だが眠りにつく前に裸で横たわる女の白い尻が浮かんできては寛之を悩ませた。
頃合いを見計らって目を開けたが、まだ女性は半裸だった。白人の女の裸体が寛之の下半身を熱くした。誰かに身体の変化を見られはしまいかと慌てて帽子を膝に載せた。さりげなく聡太を見るとつぶっていたはずの目がわずかに開いていた。その向こうでは俊平がやはり帽子を膝に載せて、その中に入れた手をゆっくりと動かしていた。にきび面の恍惚とした横顔をスクリーンの明かりが濡らしていた。寛之はまた眠ったふりをした。
2歳年上の俊平はいつも寛之の先を走っていた。部屋の本棚には名前を聞いたことがないような作家の小説がずらりと並んでいた。筒井康隆やフレドリック・ブラウンの小説を読んだのも俊平の影響だった。SFや映画の雑誌もあった。柔道が得意で寛之はよく練習台にされた。勉強もよく出来た。何をやっても敵わない相手だった。
2つ下の聡太は大人の顔色をうかがうのがうまい。早熟な俊平よりもいつまでも愛らしい聡太を誰もが可愛がった。寛之はどちらかというと内向的で大人に対して媚びを売るのは苦手だった。だから大人に媚びながら、裏で舌を出してみせる聡太が憎らしかった。
一人っ子だった寛之はいつもこの従兄弟たちと比較された。それがとても嫌だった。小学校のときはクラスの人気者だった。だが、中学生になり坊主頭にしてブカブカの制服を着た自分を鏡で見たとき、まるで楽園から追放されたような気分になった。初めての試験の結果にも愕然とした。学年順位は4百人中3百番台。何事でも自信というのは大事だ。自信を失うと何もかもがうまくいかなくなる。得意だったはずの体育も身体が思うように動かない。色白の整った顔をにきびが荒らし始めたのもこの頃だ。勉強もできない運動もダメではクラスの中心にはいられない。
だから従兄弟たちが両親とともに交通事故で亡くなったとき、ほんの少しだけほっとしたのを覚えている。2人の呪縛から解き放たれたように感じてしまったのだ。だが喪失感は日増しに膨らんでいった。父親は酒を飲むと大黒柱の傷を撫でながら涙を流した。柱に刻まれた背丈を越えることのできない甥たちのことを不憫に思っていたのだろう。やがて母と寛之が去ってからは息子のことも思って傷を撫でていたのかもしれない。
ようやく目当ての映画がはじまった。『ローマの休日』は美しかった。オードリー・ヘップバーンの演じるアン王女はローマの夜の賑わいに誘われて街に出る。公園のベンチで眠ってしまった王女をうだつの上がらないアメリカ人新聞記者のジョーが見つけて、仕方なくアパートに連れ帰る。
ジョーを演じるグレゴリー・ペックの声が好きだった。滑らかで優しく、声だけで人柄がわかる気がする。映画館の広い空間に反響するジョーの声は、ローマを流れる豊かな水のように物語の中へと観る者の心を誘った。
「なあ、おいら読めない字があるんだよ。字幕読んでくれよ」
さっきから聡太がもぞもぞと落ち着かないことが気になっていた。小学5年生には浮かんでは消える字幕スーパーを追うのは難しかったのだ。
字幕スーパーの「スーパー」は「スーパーインポーズ」の略、フィルムに他のフィルムを焼き付ける技術のこと。1秒の英語の台詞を4文字にまとめて翻訳して、一度に表示するのは1行13字、2行まで。それを6.5秒だけ流す。
それも俊平の受け売りだ。
この頃の字幕は縦に表示された。背景が白い建物だったりすると読みにくい。しかも活字ではなく手書きで複雑な字は略字が使われていた。句読点はなく句点は全角のスペース、読点は半角のスペースで代用された。聡太の年齢で6.5秒の間に字幕すべてを読むのは難しいだろう。だがそれは寛之も同じだ。読めない字を飛ばして読んでも最後まで読み切れないことがあった。助けを求めて俊平を見たが完全にスクリーンに集中しているように見えた。寛之は仕方なく聡太に顔を寄せて字幕を小声で読んでやった。
遅刻して出社した新聞社で昨夜拾った女性がアン王女であることを知ったジョーは、独占スクープをものにできると喜び、アンに小遣いをやって街に出ることを促す。
アンが美容室で髪を切るシーン。ショートヘアになったアンの輝くような美しさに劇場の人々は一斉にため息を漏らした。
「おいら、長い髪の方が好きだったな」
駄菓子を食べながら聡太がひねくれた独り言を言う。
アンがスペイン階段でジェラートを食べる有名なシーンでは、
「なんかアイス食いたくなってきた」と言った。
聡太の言葉に苛つきながらも寛之はスクリーンに集中しようと努めた。
アンを尾行していたジョーはローマ観光に付き合うと申し出て、カフェでカメラマンのアーヴィングを紹介する。「アン王女の休日」という独占スクープを写真入りで売り込むためだ。アンとジョーはスクーターでローマの町を走り回り、その様子をアーヴィングが隠し撮りする。カフェでのジョーとアーヴィングのコミカルなやり取り、それにスクーターを運転するアンが町を爆走するシーンでは劇場が爆笑の渦に包まれた。
物語に集中して字幕を読むのを忘れていると聡太が肘でつついてきた。
「もっとちゃんと読んでくれよ。兄ちゃんなら全部読めるぜ」
だが、物語が佳境に入るにつれて聡太の催促はなくなった。字幕などなくても画面が物語の世界に連れて行ってくれるからだ。寛之は言葉を超えた映像の力に感動していた。
最も有名な「真実の口」のシーン。観客もアン王女と同じようにジョーの手がなくなったかと思い息を呑み、そしてジョーのユーモアに魅了される。
夜のダンスパーティ。アンを連れ戻しに来た黒服の男たちとの乱闘。アンはギターで男の1人を撃退する。1回目に観たシーンだ。ここでも客たちの笑い声が劇場にあふれる。 一転してアンとジョーのキスシーン。
独占スクープになるはずだった写真をジョーは水をかけて台無しにしてしまう。記事にすることでアンとの思い出を汚したくなかったのだ。
帰国するアン王女の記者会見。「今回の訪問地でどこが最も印象に残りましたか」という質問に「ローマです」と答えるアン。密かに見つめ合うアンとジョー。颯爽と会見会場を出て行くジョーの姿にしびれる。
さっきと違いエンドロールが流れても立つ人がいない。壁にもたれている客も通路に座っている客も、誰もが目にためた涙を光らせて、じっとエンドロールを見つめている。その幸福そうな笑顔をスクリーンの光が祝福していた。
そのとき寛之は思い出した。まさにこの瞬間、映画を作る人になりたいと強く思ったことを。
エンドロールが終わり明るくなると、寛之はあふれて止まぬ涙を拭いながら大人たちの間を縫って入り口に走った。
そして、もぎりの女性に黙って千円札を差し出した。
「なに?」
「ごめんなさい。僕ら入場券を買わずに入ったんです。中学生2人と小学生1人です。本当にごめんなさい」
制服姿の女性は若くてまだ頬にそばかすを残していた。彼女は眼鏡をついっと上げて坊主頭の少年を見つめた。
「なんで終わってから払いに来たの」
「キレイな映画を汚したくなかったんです」
考えて言ったことではなかった。だがジョーがアンとの思い出を汚したくなかったように、自分もこんなに美しい映画を汚してはいけないと強く思っていた。
女性は寛之の手から千円札を受け取ると、
「ちょっと待っててね」
と言って入場券売り場に入った。再び出て来た女性は釣銭の硬貨を寛之の手に握らせ、『ローマの休日』のパンフレットを差し出した。
「これ上げる。映画を汚さないでありがとうね」
寛之はまだインクの匂いのするパンフレットを抱えて、満足そうな笑顔の客たちと一緒に映画館を出た。
「ヒロ」
声に振り返ると薄暗い映画館の中に俊平と聡太が並んで立っていた。
「ごめん。僕……」
寛之は自分のしたことが俊平と聡太を裏切ったような気持ちに襲われた。
「お前、やっぱり馬鹿正直だな」
「ヒロちゃんはいい子過ぎるんだよ」
言葉とは違って2人は満面の笑顔だった。
「お金払ったからもう大丈夫だよ。一緒に帰ろうよ」
寛之が言うと2人は困った顔をした。
「なあ、映画の夢、諦めんじゃねえぞ。俺らはもう夢なんか見られねえんだからさ」
「兄ちゃん、タダ見なんてしたからバチが当たったんだぞ」
「うっせえなあ。俺らの物語は終わったんだから仕方ねえんだよ。あと寛之に託そうぜ」
「大丈夫かあ。ヒロちゃんで……もういい歳みたいだぜ」
聡太の憎まれ口も気にならなかった。
「ごめんな。忘れててごめんな」
涙があふれた。
涙を拭って目を開けると俊平も聡太もいなかった。ドリーム座もなかった。ただ灰色のシャッターが暑さに耐えるように並んでいた。
51年前のあの日、寛之は父親が勤めから帰るのを待っていた。そして『ローマの休日』のパンフレットを見せながらその日あったことを正直に打ち明けた。父親は何と言っただろう。思い出せない。だが、書斎に置かれたパンフレットと脚本、そして残された大黒柱で父のメッセージはおおむね理解できた。
『牢番の休日』はいい本だぞ。5年も休んだんだ。そろそろ長い休日を切り上げて新しい人生を歩んだらどうだ。
寛之はスマホで長男に電話をかけた。
「あのな、いい脚本があるんだ。どうだ。一緒に1本撮ってみないか」
〈了〉
著者・高平 九 のTwitterはコチラ⬇︎
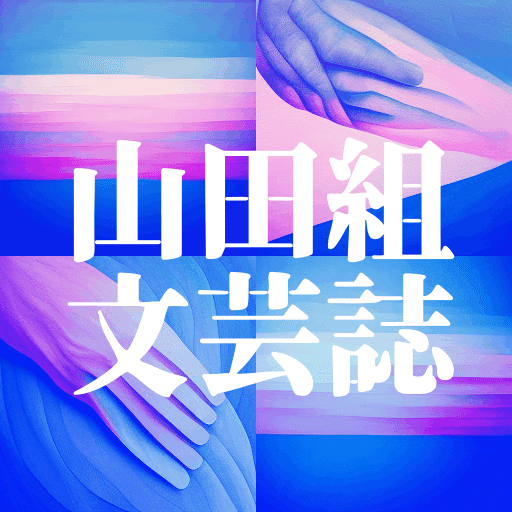
山田組文芸誌 第7号「映画」
山田組文芸誌 第6号「ライバル」
入部希望の方はTwitterのダイレクトメッセージへご連絡ください▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
