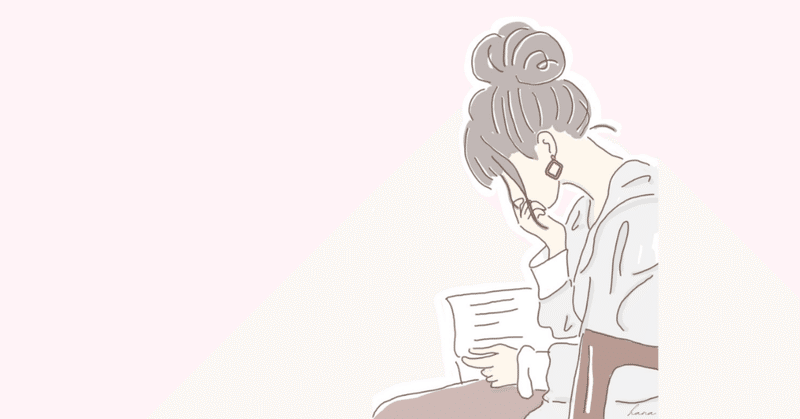
自分を知り、自分の特徴を生かす
みなさま、おはようございます 渡辺です。週末はあいにくのお天気でしたが、如何お過ごしでしたでしょうか?僕もHさん同様、スーパー銭湯とか好きだったのですが、コロナ禍以降すっかり出不精になってしまいました。また最近は家に誰もいないというのもあり、寒い日は家のお風呂に何度も入ったりしています。
今週は、年末に読んだ 「静かな人の戦略書」- ジル・チャン を紹介したいと思います。
「仕事の戦略」
既に皆さまお気づきのように、僕は結構内向的な人間でして、2020年にステイホームになった時に、一部の方々は外に出られないのが辛かったかもしれませんが、正直僕は余り苦になりませんでした。
またこの本のイントロダクションで35項目の「自分のタイプ」を知るテストがありましたが、かなり高得点で内向型傾向ということで、定性的にも定量的にも内向型確定ですね。
みなさまも内向型、外向型、両向型とさまざまかと思いますが、大切なことは
自分を知り、自分の特徴を生かす
ということで、今週はお付き合い頂ければと思います。
まず、PART1は、「仕事の戦略」ということなのですが、戦略的に得意なことで勝負するという事です。
内向的な人が頑張って、外向的になろうとしたりすると疲労度も半端ないですし、逆もまた然りです。
僕自身、人前で話をしたり、発表したりするのは、とても緊張してしまうので、その分事前にたくさん練習して、アドリブを極力減らすようにしています。あと対面カジュアルに話しかけるのが上手くなければ、slackをうまく活用するとか、逆に本当に重要な話は電話や対面で話すようにするとかです。
こんな感じで、残りの3日間も読み解いていきますので、適宜自分のタイプに置きかえて考えてみてもらえると良いかと思います。
それでは、今週もよろしくお願いいたします!
「人間関係」術
みなさま、おはようございます 渡辺です。引き続き寒い1日になりそうですので、暖かくお過ごしくださいませ。
この本の日本語版の序文で、以下のように書かれています。
子どものころから身近な存在だった「ドラゴンボール」の孫悟空や「ONEPIECE」のルフィなど漫画の主人公たちも、みんな外向型だった
確かにな。と思うと同時に、日本の漫画カルチャーが浸透しているのに少し嬉しくなりました。さて、本日は「人間関係」術です。
内向型と外向型は、「正反対」のようなものでもありますが、白黒や0-100できっちり分けらるものでもなく、グラデーションだったり、内向型の人もある面においては外向型だったり、逆のパターンもあったりします。
この陰と陽のように、互いが存在することで己が成り立つというのは、チームで仕事をするうえで、絶大な効果を発揮することになるでしょう。
そのための、3つのコツを紹介します。
1.「遂行能力」を発揮する
仕事をするうえで必要なのは、「結果」と「遂行能力」です。タイプの違いこそあれ、ミッションん達成に向けて、自分のタスクを遂行し、他のメンバーが自分のタスクを遂行できるようなサポートが出来れば、大事なメンバーの一人になりますね。
2.「敬意」を払う
お互いのスタイルやチームを尊重する。問題発生して自分の手に負えない時には、正直に率直に話すことで、チームとして解決の方向性を見出す。
3.「苦戦」する仲間に手を差しのべる
自分の得意分野、誰かの不得意分野かもしれません。メンバーが不得意な分野で困っていたら、積極的に手を貸してあげることで、感謝もされるし、チーム全体で見たらとても生産性が向上します。
如何でしたでしょうか?それでは、本日もよろしくお願いいたします!
「人前」で生かす
みなさま、おはようございます 渡辺です。なんか久しぶりに晴れてきた気がします。
この本の著者は、名前から想像の通りアジア系の方が書かれているのですが、本の中では多くの論文や本からの引用もあるのですが、それらを書かれているのは欧米圏の方で、当然のことながら内向型って人種問わずなんだなと気づきます。
さて、本日は「人前」で生かす です。
ネットワーキングが得意な人もいれば、苦手な人もいるかと思いますが、僕は余り得意ではありません。そういう意味では、携帯電話の発明はなんか忙しそうに見せることが出来るという意味で偉大でしたね。
とはいえ、やはり普段話さない人と話すというのは、自分の考えを整理するきっかけにもなりますし、新たな視点を得る良い機会になります。ということで、今日も3つほどコツを紹介します。
1.「無理のない目標」を設定する
出来るだけ具体的で達成可能な目標を設定するということです。例えば僕だと、「最低ひとりには自分から話しかける」とかです。一人に話しかけると、すごく盛り上がることもありますし、全然盛り上がるならないことも。相手を間違えて、ひたすら長話に付き合わされることもあります。でも、これで目標達成!あとは、適当に話しかけられるのを待っててもいいですし、うまく行ったら、なんとなく気になる人に話しかけて過ごせばOKです。
2.人を知るには己を知る
自分の事を簡潔に紹介する良い機会にするということ。以前全体会議で早川さんが何種類かの自己紹介のパターンを持っておくと良いというお話をされたかと思いますが、そのイベントに相応しい自己紹介を考えて実際に話してみて、相手の反応を見るというゲームを楽しんでみるというのは如何でしょうか?
3.主催者側の手伝いをする
特に初めての場所とかでしたら、早めに到着して主催者側に何か手伝えることがないか尋ねてみるのもよいですね。主催者側と繋がれることで、誰かを紹介してもらえる可能性もありますし、手伝うことで感謝されますし、逆に参加者から話しかけてもらえる可能性もあがります。
ぜひ、イベントとか苦手な方は、次回のタイミングで試してみてください!
それでは、本日もよろしくお願いいたします!
「潜在能力」
みなさま、おはようございます 渡辺です。なんか久しぶりに晴れてきた気がします。一方で来週は雪予報がでてますね。寒くなるのでしょうか?
さて、「静かな人の戦略書」最終日は、「潜在能力」です。
内向型と外向型の両方で構成されたチームが非常に効果的というのは、すでに多くの研究によって証明されています。一方で、タイプの違う人たちがしっかりとコミュニケーションをとってチームの絆を深める為には、お互いがどんなタイプかを理解する必要があります。
今日は、アメリカの心理学者ウィリアム・マーストンが考案した性格類型検査「DISC」の4つのタイプ別コミュニケーションについて見ていきます。
主導型
目標指向で状況をコントロールしたいタイプです。このタイプには、要点を明確にし、迅速かつ正確なコミュニケーションを心がけましょう。企画書の概要を1枚にまとめたサマリーを添付し、要旨とポイントを明確にしたうえで、自分なりの評価や提案を加えるとよいです。
感化型
社交的で、新しいことがすき。このタイプは、新しい考え方をオープンに受け入れるので、自分の方から定期的に声をかけることを心がけましょう。企画書は見栄えにも力を入れ、新規性と裏付けをさらっと説明できるとよいですね。
安定型
温かい人柄で、伝統や和を尊重します。このタイプは、「全社目標の達成」といった錦の御旗大事にする一方で、他のメンバーが反対している件を押し切るのは難しいです。企画書はより実務的な内容にし、前例を多く示すと良いです。
慎重型
じっくりと考え、データや分析を重視します。このタイプは、思いつきには飛びつかないので、しっかりとした事前準備が必要となります。企画書は分厚く、詳細なデータを準備し、フレームワークを多く活用するとよいでしょう。
という訳で、「静かな人の戦略書」をお送りしました。初日にもお伝えしましたが、「自分を知り、自分の特徴を生かす」ことで生きやすくなるとよいですね。
それでは、今日はTさんの最終出社や全体会議、明日は創立記念日でお休みですね。今週もあと1日。本日もよろしくお願いいたします。
(2022.01.16-01.19)
サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。
