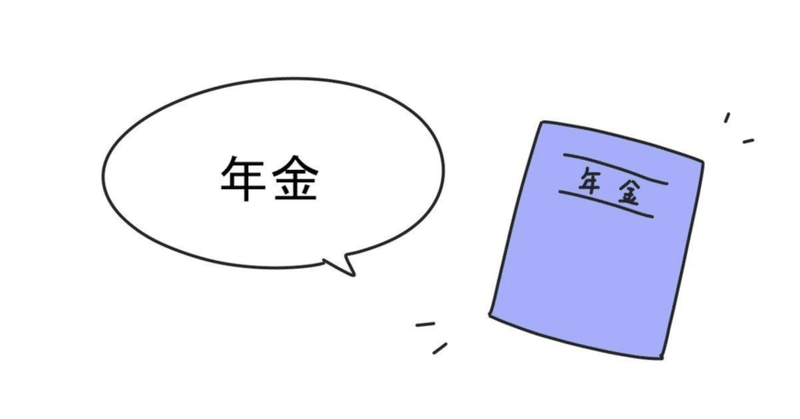
年金の「繰り下げ受給」は「むしろ損」になる?
おはようございます、ひらっちです。今日からGWの長期連休に突入したという方も結構いらっしゃるのでしょうか?
僕はなんとかGW前の農作業を片づけて、連休中は休み前にため込んだ原稿と格闘する日々が続きそうです…まあ、毎年のことなので何とも思っちゃいませんが。GWも変わらず仕事というお仲間の皆さん、一緒に頑張りましょう!!人が休んでいる時に頑張れば、きっとどこかで報われるはず(^^♪
<いつものように簡単な自己紹介です>
僕は、地方国立大学を卒業後、ブラック企業で営業マンを経験。その後、フリーランスのライターとして独立開業、さらに数年後、新規就農して農業をスタートさせ、2020年現在、好きな仕事を選びながら人生を謳歌する「ほぼセミリタイア生活」を実践しているアラフォーです。
このnoteでは、特に20・30代のビジネスパーソンの皆さんに、僕の経験に基づいた「人生を楽しく過ごすための技術」を提供し、少しでもたくさんの方に「幸せな毎日」を掴んで欲しいと考えています。どうかお付き合いください。
現在、『マイナビ農業』で不定期連載中! 農業にご興味のある方はぜひこちらもご覧ください!
■年金改正ラッシュの目玉、「繰り下げ受給の上限年齢が75歳へ」がスタート!
あらためまして、ひらっちです。今日は、久しぶりに「お金」がテーマです。なかでも「年金」にフォーカスを当ててみたいと思います。
皆さんは、今年が「年金制度の改正ラッシュの1年」だって、ご存知ですか?
2022年は、4月からさまざまな改正が順次施行されていきます。なかでも大きな注目を集めているのが、公的年金の繰り下げ受給の上限年齢が、これまでの「70歳」から「75歳」へと延長になった点です。以前から話題になっていたので「知っているよ!」という方も多いのではないでしょうか。
そもそも「繰り下げって何なの?」という方のために、ここで基本的な部分をおさらいしてしましょう。
年金制度は支給するタイミングを、繰り上げたり、繰り下げたりできます。
僕は、個人的にこの「繰り上げ」「繰り下げ」という表現が、結構分かりにくくて苦手です。どうです? 皆さんは、パッと聞いて分かります?
繰り上げとは、要するに「65歳よりも早くもらい始めること」、一方の繰り下げとは、「65歳よりも遅くもらい始めること」です。「繰り下げ」は「繰り延べ」みたいなイメージで考えておくと分かりやすいかもしれませんね。
これだけを聞くと、こんな反応が返ってきそうです。「いやいや、ひらっちさんよ! 65歳よりも遅く始めるなんてバカじゃないの? 早くもらう一択じゃん!」。そうですよね、これだけの説明ではそうでしょう。
ただ、「繰り上げ」「繰り下げ」は、それぞれの支給開始年齢に応じて、支給額が変動します。「繰り上げ」は1カ月あたり0.4%または0.5%減額、「繰り下げ」は1カ月あたり0.7%増額となります。
つまり、支給を遅らせた方が毎月の金額が増えていく。そのため、「もし金融資産に余裕があるなら、できるだけ繰り下げし、75歳まで支給を遅らせて84%増額した方がいいよね」ということが巷で言われているわけです。
ちなみに僕も、このnoteで過去にこんな記事をアップしています。
上記でも述べている通り、僕は基本的に「75歳で84%増を狙おう」派です。ただ、これはあくまで、僕のような「フリーランスで年金支給額が少ない人」の場合です。サラリーマン生活を続け、しっかりと年金が受け取れる方の場合には、引き延ばしたにも関わらず、受け取れる年金額がそれほど増えないというケースが考えられます。
それは「額面ベースの年金」が増えるのと同じように「手取りベースの年金」が増えるわけではないからです。
■年金繰り下げの最適解は「70歳前後」?
本来、年金は「長生きリスクに対する保険」です。
そもそも保険とは、起こる確率は低いけれど、もし発生した場合には損失が大きい事柄に対し、みんなでお金を出し合って備えるもの。高確率で起こり、致命傷にはならない程度の損失については、おのおのが貯金などをして対応する方がいい。
医療保険などが最たる例ですね。「医療=お金がかかる」というイメージが強いですが、頻繁に起こる一方で、高額療養費制度を使えば、生活が破綻するほどの出費になる可能性はないですから。
この大原則に照らせば、ほとんどの人が65歳まで生きる長寿大国・日本では、平均寿命手前まで生きることは、想定される範囲内のリスク。ここは本来、自分で何とかしないといけない領域というわけですね。
では、保険の趣旨たる「確率は低いけれど、もし発生した場合損失が大きいリスク」とは何かといえば、「平均寿命を超えて、思っていた以上に長生きしてしまうリスク」ということになります。要するに、この長生きリスクに備えることが「年金保険のメインの目的だ」というわけです。
ただ、そうはいっても気になるのが「トータルでの損得」という人も多いでしょう。これに対して、厚生労働省は「70歳から受給すると81歳11か月、75歳からなら86歳11か月で、65歳から受け取り始めた場合よりも総額が大きくなる」としています。
厚生労働省の「簡易生命表(令和2年)」によると、2020年の日本人の平均寿命は男性が81.64歳、女性が87.74歳です。これはあくまで平均寿命で、65歳まで生きた人の「平均余命」で考えると、もう少し長生きすることが想定されます。
上記を踏まえると「トータルで得したい」のであれば、「年金の繰り下げは70歳前後」が最適解になるケースが多いと思います。相対的に平均寿命が長い女性や、飲酒・喫煙をせず健康体の方は、もう少し遅い方が得できるかもしれませんけどね。
■多額の年金をもらえる人は、あえて支給額を減らし、住民税非課税世帯に?
…とここまできて、違和感を覚えたという方は、かなりマネーリテラシーが高い方だと思います。すでにお気づきの方もいっしゃると思いますが、上記の試算は、あくまで「額面ベースの話」です。家計は、額面だけでは語れません。イケメンだからって旦那に最適かどうかは分からないのと一緒ですw
収入は「額面」ではなく「手取りベース」で考える必要があります。年金には、金額に応じて所得税や住民税がかかります。さらに社会保険料も支払う必要がある。年金収入は金額が少ないため、多額の所得税や住民税がかかることはほとんどないですが、社会保険料はかなりの金額になるケースがあります。
そこで問題になってくるのが、繰り下げによる年金増額です。例えば、65歳で年金200万円支給される人が繰り下げをした場合、70歳で42%であるはず増額が30%程度に、75歳で84%であるはずの増額が65%程度に抑えられてしまう可能性があるのです。そうなれば、年金の損益分岐点となる年齢はさらに後ろにずれていくことになります。特に女性よりも平均寿命が短い男性は、トータル金額でかなり損をする可能性が高いので要注意です。
経済アナリストの森永卓郎さんは、上記を踏まえたうえで、年金支給額が多い人は、むしろ繰り上げをして支給額をあえて減らし、「住民税非課税」という地位を選ぶのも選択肢の一つだと指摘しています。(下記参照)
個人的には、安易に支給額を減らすのは「長生きリスクに備える」という年金保険の本来の趣旨から外れる行為であり、想定以上の長生きをした時には厳しい生活を強いられるということをきちんと念頭に置くべきだと思います。
とはいえ、「住民税非課税世帯」であることが、生活防衛術としてめちゃくちゃ強力であることは確かです。コロナ禍の給付金などでも浮き彫りになりましたよね。あえて「貧者の盾」を手に入れるというのも、「損得だけを考えるならあり」だと思います。
■まとめ
いかがでしたでしょうか? 巷では「繰り下げ=得」という意見が大勢を占めているようですが、これはあくまで「額面」をベースにしたお話であり、自分自身の平均余命、手取りベースの年金額などを考慮したうえで、冷静に納得のいく選択をすることが重要だと思います。
結局のところ、世の中にたくさんあふれるお金の話は、あくまで一般論であることが多く、万人に当てはまるものではありません。あなたの人生は、あなただけのもの。これは、お金についても同じです。専門家の意見やメディアの情報に頼りきることなく、自分でベストな回答を導き出せるだけのマネーリテラシーを養いたいものですね(^^♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
