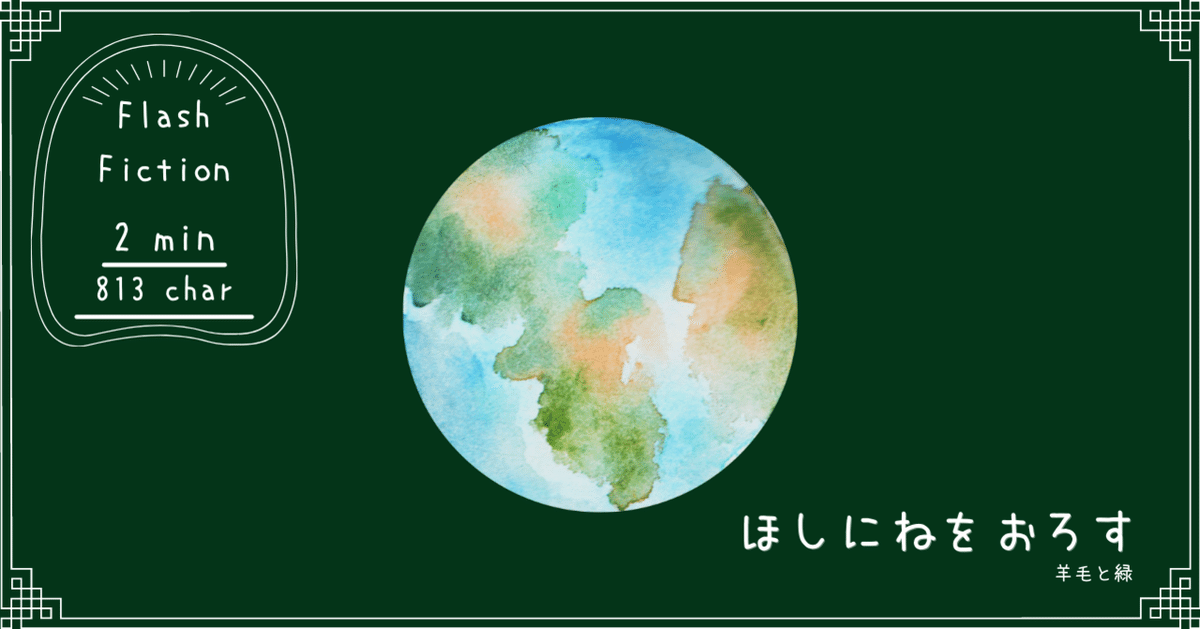
ほしにねをおろす
裸足になって草原を歩く。
綿の靴を脱ぎ捨てて、靴下はどっかに放ってしまって。
彼女は楽しそうに跳ねて回るけど、ぼくはそこそこにしておきなと止める。
昨日の昼頃、そのせいで背の高い草に足をかすめて切ってしまったばっかりなのに。
それに、この前はミミズを思いきり踏みつけて泣いてたのに。
裸足になると星に根を張る事ができる気がするのって言うけれど、それだって気がするだけだろう。
家の中くらいでいいと提案してみたことがある。ガラスやごみを踏んで怪我をすることもないし、なによりぼくがいちいちひやひやする必要もない。近くに「ワルグマ・パサウレ」でもあればきっと彼女を連れ出して、そこで一緒に休日を過ごすと思う。けれど、近くにあるのは少し大きくて草の生い茂った公園で、どうにもこれは引っ越しでもしなければ変わることもないだろう。
どこかへ連れ出したくて、それでも近場にはコンクリートで固められた道しかないから、ぼくらはよく海に出かけた。公園よりもずっと安全だし、海のない場所で生まれ育ったぼくらには波の音は飽きなかったから。そのたび、彼女はよく白くてひらひらする服を選び、麦わら帽子を好んでかぶった。形から楽しむことがずっと楽しんでいられるコツであると、胸を張りながら教えてくれた。
裸足であるくことは好きだった。なによりも自由になれた気がしたから。あのときやこのときだなんて振り返るほどの思い出はなくても、ただ歩いていることが好きだった。歩いている最中は、いつも同じ模様をしている壁に囲まれることもないし、時間がずっと身近なものになってくれる。
太陽と。地面と。風の音と。
あらゆるものがぼくを取り囲んで放してくれないはずなのに、ぼくはその中にいることで気分が悪くなるようなことはなかった。
「ねえ、わかった?」
ふと、風にまぎれて彼女の声が聞こえた声がした。
「ああ、わかったよ」
目の前を歩く彼女の声かはわからなかったけれど、口ごもりながらこたえておいた。
ご清覧ありがとうございました。
よろしければ、こちらもどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
