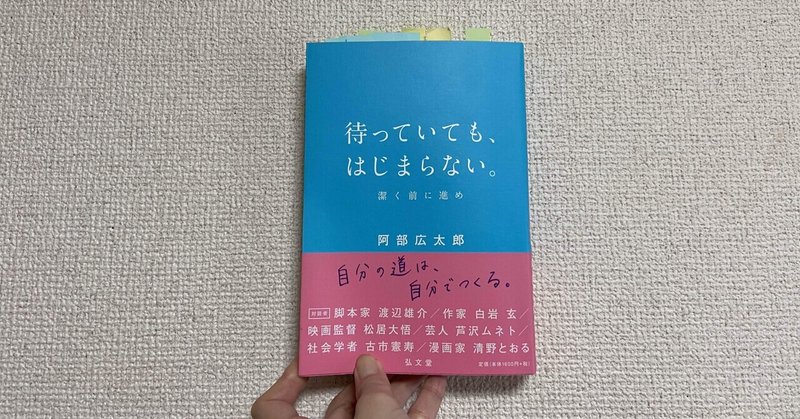
毎年お正月はちょっと落ち込む。でも「待っていても、はじまらない。」
お正月。普段よりもゆったりと時間が流れて、好きなテレビを心ゆくまで見ながら、お酒も飲んじゃったりして、身体と心を休ませられる至福のとき。
…のはずが。
その幸せに浸れる時間は意外と短くて、
時間があればあるほど「このままでいいのか?」
「何かしなければいけないのでは?」となぞの焦燥感に駆られ始める。
まずは今年やりたいことを書き出そう!と毎年恒例のWishリスト作りに励んでみるも、
いろいろやりたいことがある自分と、
時間があるのにどこから手をつけていいのかわからない自分がいて、その乖離に悩む。
結局このまま何もできないのでは…?4月病のように今はやる気に満ち溢れているけど、結局続かず終わってしまうのでは…?と思って、勝手に落ち込んでしまう。
そんな風にお正月はなぜだかちょっと落ち込んでしまって、それは毎年恒例で、昨日もそれに襲われた。
元旦から何があったわけでもなく勝手に落ち込む自分にバカバカしさも感じつつ、
打破するためにとにかく何か一つ行動しなきゃ。
そう思ってWishリストの中にある「本を読んで感想をnoteに書く」をやろうと思った。
選んだのは阿部広太郎さんの「待っていても、はじまらない。―潔く前に進め」
阿部さんは去年言葉の企画という企画講座で大変大変お世話になり、言葉や企画を越えて生き方の面であまりにも大きな影響を受けた恩師だ。
阿部さんを知ったきっかけは、SNSに何かの記事が流れてきたことだよな…としばらく記憶がぼんやりしていたけれど、記憶を辿ったらそれはこの記事でした。
で、すっかり読んだ気になっていたけれど恥ずかしながら完全版をちゃんと読んでいなかった自分に気づいて。
この機会にあらためて、熟読しました。
ただ本を読むというよりも、本に導かれながらモヤモヤしてる自分に、都度問いかけて対話していくようなかんじで。
1冊の本を読み進めるだけでこんな体験ができるのか…と、新感覚でした。
阿部さんが各業界のそうそうたる方々と対談された内容に加え、阿部さんご自身のお話も綴られているこの本。
そこから受け取ったメッセージがちょっと落ち込み気味の自分にどう刺さり、これからの自分にどう繋げようと思ったか。いくつか綴ってみたいと思います。
◻️作家 白岩 玄さん
・自分の原点を大切にする
ポルトガルに行かれた旅行記を、ご自身で紙を切って本のかたちにして手書きで文字を書かれて…カバーにバーコードも書いて出版社の名前まで。
そんな完全な手作り文庫本が原点となって、現実に起きたことをフィクションに作りかえるという小説の書き方に挑戦してみたい…という今の思いにつながっているという、白岩さん。
自分が昔好きでやっていたことって軽視しがちで忘れがちだけど、自分も小学生の頃から本や雑誌を作ってクラスのみんなに感想をもらうことが何より嬉しかったな…って、思い出して今でもそのシンプルな喜びを積み重ねていきたいという思いは変わってないなと、思い出しました。過去の自分はおいしく積み重ねていかないといけないですね。
◻️映画監督 松居 大悟さん
・ダサくても行動すればいい
ヨーロッパ企画の上田 誠さんやクリープハイプの尾崎世界観さん。ダサいとわかっていながら、何度もメールしたりDMしたりとにかく形にするための行動、アプローチを続けたという松居さん。
自分の好きな人、憧れている人に対して勝手に線引きしてアプローチすることを諦めていないだろうか?そう自分に問いかけ直しました。
ダサくても、失うものはない。迷ったら行動すればいい。
◻️芸人 芦沢ムネトさん
・友達が喜んでくれるものを描く
芦沢さんが描くふてぶてしくて時々ロックなネコのキャラクター「フテネコ」。Twitterにアップしたらお友達のミュージシャンの方々が反応し、一気に広まった…というお話。
どんな文章を書けば、多くの人に読んでもらえるんだろう。ぼんやりした読者像を持つのではなく、まず自分自身や自分の身近な誰かが喜んでくれるものを書けばいいのかもしれない。
これは阿部さんから教わったことでもあるけれど、あらためて希望をもらいました。身近な誰かが、もしかしたら自分の書いたものを思わぬ場所に届けてくれるかもしれない。
・人生の伏線回収
芸人でありながらも、美大を目指していたこと、バンドをやっていたことが全部無駄にならず今に繋がっている。そうやって人生の伏線を回収している、芦沢さん。
コピーライター×人事の掛け合わせで講義を立ち上げ、活躍されている阿部さんもそうだ。
私も自分の特技について、就活のときは英語や音楽と書いていた。でも、英語はもともと帰国子女で、親がそれを忘れないように英会話を習わせてくれたから忘れてないだけで、自分の意志で身につけたものではない。だからそれを武器にするのはずるい気がして、あまり全面に出してこなかった。
音楽も、バイオリンは親が気づいたらやらせてくれていたもので、大学のオーケストラに入ったもののみんなが憧れる伝統あるオーケストラだと知ったのは入った後で、自分の実力の無さや音楽への興味の浅さを痛感した。
だから特技と言いながらも後ろめたさがあって積極的に語りたくないものでもあったりしたけど、それを全部無駄にせず今に繋げられたら自分にしかない道が作れるのかも…?そんな風に思える視点を、いただきました。
◻️社会学者 古市 憲寿さん
・自己紹介できる自分を持つ
いろいろやるのはいいけれど、何をやっているのかわからなくなったらダメ。何をやってるかわからない人と、もう一度会おうとは思わないですよね?と語る古市さん。
企画講座「言葉の企画」で、自分は何者にもなれず、自分は自分にしかなれないんだということを学んだけれど、その言葉に甘えてはいけないな…と思いました。自分は自分にしかなれない、でもそのままの自分でいいということでは必ずしもなくて。どんなふうに自己紹介できる自分でいたいのか?まだ自分の中で固まってないな…と反省しました。
◻️コピーライター 阿部 広太郎さん
・リアクションではなくアクション
振られた仕事をひたすらにやっていく。反応して、反応して、反応して、終えるだけの一生でいいのだろうか?リアクションではなくアクションが大事なのでは?という阿部さんの言葉。
去年は自分のキャリアとも向き合う機会が多くて、このまま今の部署や会社にいていいのかな?なんてところまで思ったりしたけれど…
少しずつはみ出していけばいい。そう教えてくださったのも、阿部さんでした。
今の環境をガラッと変えることが必ずしも正解ではなくて。自分の思いを起点に、少しずつでもこれまでの枠をはみ出していくこと。それは自分の意志を伝えに行くことからはじまるんだ、ということ。はみ出す感覚を大切にして、行動することは自分の中で今年の大きなテーマになりそうです。
・自分の居場所を増やすこと
多くの人と出会い、仲を深めることは楽しいし、ありがたい。でも、その先に何があるのだろう。
「この出会いを活かせる力が自分にはない」とある日気づいたという、阿部さん。
私も誰にも嫌われたくなくて、八方美人になってしまって、その先に何が待ってるのか?とわからなくなるときがあって。
でも、自分の居場所を増やすことは誰に対してもいい顔をしていくということではなくて、出会う先々で「自分が関わる人には幸せになってほしい」と思うことなんだ、という阿部さんの言葉を読んで私も自分の居場所を増やし、一つひとつの出会いを大切にし、自分自身にも相手にも還元していきたい…とあらためて思いました。
なので、これを読んでくださっているあなたとの出会いも、本当に大切にしたいです。
ここまで読んでくださりありがとうございます。
企画講座「言葉の企画」を終えた今だからこそ、
企画生同期のみなさんともこの本についてぜひ語りあえたら…と、思いました。
待っていても、はじまらない。
潔く前に進みます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
