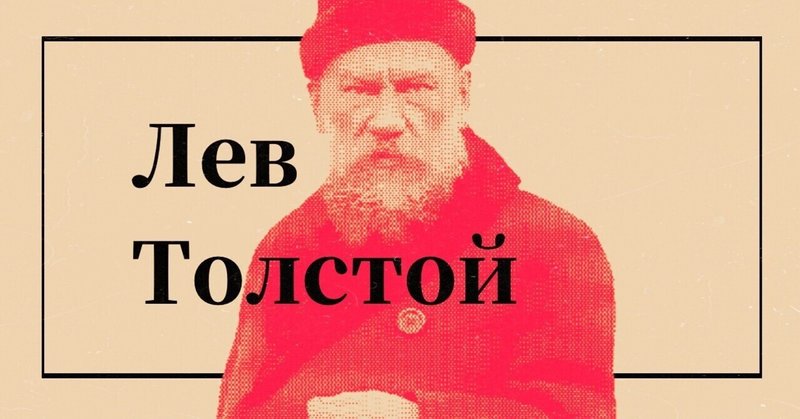
人生が無意味だと思ったら、トルストイを読もう。
トルストイと聞くと、『戦争と平和』や『アンナ・カレーニナ』など何やら難しくて長い作品を書いたロシア文学の巨匠というイメージがあって、敬遠する人が多いかもしれない。
しかし彼は「人々のための文学」を目指した作家でもあり、50歳を越えたあたりからは平易かつ奥深い短編をいくつか執筆している。
本記事で紹介する『イワン・イリッチの死』も、そのような作品の一つである。
これは死ぬ間際に「自分の全生涯は無意味だったんじゃないか」と気づいてしまった男の物語だ。
男が抱えていた問題は、普遍的であると思う。
トルストイの時代から100年以上経た今でも、私たちは「人生の意味」という不安に悩まされている。
しかも、この作品は短い。
文庫本にして100ページ程度である。
文学、特に海外文学を読み慣れていない人でも比較的挑戦しやすいという点で、非常におすすめできる。
さて、ここから先は小説の内容について解説する。
重大なネタバレは避けるが、何も知らない状態で物語に触れたい方は、まずご自身で一読してから本記事に戻ってきていただければ幸いだ。
ありふれた人間の死
『イワン・イリッチの死』は、イワン・イリッチの葬式からはじまる。
それがとても寂しい葬式なのだ。
まず、以下の場面を読んでいただきたい。
イワン・イリッチの妻と、彼の友人であるピョートルが話をしている。
「ああ、ピョートル・イワーノヴィッチ、なんという辛いことでしょう、なんて恐ろしい辛いことでしょう、なんて恐ろしい辛いことでしょう!」といって彼女はまた泣きだした。ピョートル・イワーノヴィッチは吐息をつき、彼女が洟をかんでしまうのを待っていた。洟をかんでしまうと、彼は「どうぞ信じて下さい……」と言った。すると彼女はまたくどくどと話しはじめた。そして明らかに肝心の用件らしく思われることを切りだした。用件というのは、夫の死を機会として国庫から金を取ることはできないだろうか、という問題なのであった。
夫の葬儀の場で、妻が気にしているのはお金のことである。
彼女がピョートルの前で涙を流し、夫の死を嘆いて見せるのは、実は気まずいお金の話を切り出すための言い訳みたいなものだ。
しかし、彼女だけが薄情なわけではない。
ピョートルもイワン・イリッチの訃報を受け取った際、彼の死が次の人事異動にどのような影響をもたらすかをまず最初に考えている。
なぜそんなことになってしまったのか。
イワン・イリッチはよっぽどの悪人だったのか。
いや、そうではない。
彼はごく普通の、気持ちのよい、礼儀正しい人間だった。
ごく普通の人間だったからこそ、このような最期を迎えたのである。
彼の死に顔を見てみよう。
死体は語りかける。
私たちはみんな彼と同じであると。
死人はすべての死人と同じように、いかにも死人らしく、こわばった四肢を棺の底敷きに沈めながら、ずっしりと重たそうに横たわっていた。永久に曲ってしまった首を枕にのせ、落ちくぼんだこめかみのあたりにのある黄色い蝋のような額と、上唇へのしかかっているとがった鼻を、いかにも死人らしくめだたせていた。(中略)しかし、すべての死人の例にもれず、彼の顔は在世の時よりも美しく、だいいちもっともらしかった。その顔には、必要なことはしてしまった、しかも立派にしてのけた、とでもいうような表情があった。のみならず、この表情のうちには、生きている者に対する非難というか、注意というか、そんなものが感じられた。
ありふれた、また恐ろしい人生
葬式の場面が終わると、イワン・イリッチの全生涯の回想が始まる。
曰く…
「イワン・イリッチの過去の歴史は、ごく単純で平凡だったが、同時にまたきわめて恐ろしいものであった」
彼は典型的なブルジョワ家庭に生まれ、その地位にふさわしい、俗物的な喜びを求めてきた。
そんな彼の人生最大の幸福といえば、昇進とそれにともなう引越しである。
立派な地位と新しい家。
上機嫌で部屋の飾り付けをしていた彼は、しかし、その最中にイスから落下し、横腹を打ちつける。
この小さな傷が原因となり、彼は不治の病に侵されるのだ。
イワン・イリッチは、肉体的にも精神的にも耐え難い苦しみを味わう。
イワン・イリッチの主な苦しみは嘘であったーーなぜか一同に承認せられた嘘であった。彼はただ病気しているだけで、決して死にかかっているのではない、ただ落ちついて養生しさえすれば、なにか知らないが大変いいぐあいになる、といったふうな気休めであった。しかし、彼自身にはよくわかっていた。たとえどんな事をしてみても、さらに悩ましい苦痛と死のほかには、結局、どうもなりようはないのである。この偽わりが彼を苦しめた。
この偽わりのほかに、あるいはこの偽わりの結果、イワン・イリッチの身になると、なによりもまた苦しいのは、誰ひとりとして彼自身の望んでいるような、同情の現わし方をしてくれないことであった。
イワン・イリッチは長いあいだ苦痛を経験したため、時とすると、ある一つの願いがなによりも強くなることがあった。それは自分自身に白状するのもきまり悪いほどであるが――彼は、病気の子供でも憐れむようなぐあいに、誰かから憐れんでもらいたいのであった。 子供をあやしたり慰めたりするように、撫でたり、接吻したり、泣いたりしてもらいたい。彼は自分が偉い官吏で、もう髭も白くなりかかっているのだから、そんなことはできない相談だと承知しながらも、やはり、そうしてもらいたかったのである。
彼は少しずつ、自分の人生が欺瞞であったことに気付く。
彼は夫らしく、偉い官吏らしく、立派な人間らしく振る舞うことに執心してきた。
それが彼の生活に「快い愉快さと上品さ」を与えていた。
しかし、死の苦痛がイワン・イリッチを目覚めさせる。
以下は、彼がおそらく初めて自分の人生に真正面から疑問を呈する場面である。
少し長い引用となるが、トルストイの卓越した心理描写を味わえる名文なので、ぜひ読んでみてほしい。
結婚……それから思いがけない幻滅、妻の口臭、性欲、虚飾! それから、あの死んだような勤め、金の心配、こうして一年、二年、十年、二十年と過ぎていったがーーすべてはいぜんとして同じである。先へ進めば進むほど、いよいよ生気がなくなってくる。自分は山へ登っているのだと思い込みながら、規則正しく坂を下っていたようなものだ。まったくそのとおり。 世間の目から見ると、自分は山を登っていた。ところが、ちょうどそれと同じ程度に、生命が自分の足もとからのがれていたのだ……こうしていよいよ終りが来た、もう死ぬばかりだ!
それでは、いったいどうしたというのか?なんのためだろう?そんな事があるはずはない! 人生がこんなに無意味で、こんなに穢らわしいものだなんて、そんな事のあろうはずはない!よし人生が真実これほど穢らわしい、無意味なものであるにもせよ、いったいなぜ死ななければならないのだ?なぜ苦しみながら死ななければならないのだ?なにか間違ったところがあるに違いない。
自分は幸福を求めて正しい道を生きてきたはずなのに、
なぜ人生は苦しいのか。
なぜ人生は無意味なのか。
なぜ、なぜ…。
イワン・イリッチの問いは、現代を生きる私たちの胸にも切実に響く。
彼は残されたわずかな時間を費やして、これらの問いに向き合った。
そして、見出す。
本当の生を。
・・・・
いま再び、イワン・イリッチの死に顔を思い出してほしい。
トルストイはその顔を全ての死せる人間と同様に「美しい」と書いた。
私たちはみんなと彼と同じなのだ。
もしあなたの生き方に、イワン・イリッチと似たような部分があると感じるならば。
もしあなたが今、人生は無意味なんじゃないかと感じているならば。
凡百の自己啓発本を捨て、私はこの本を読むべきだと思う。
「イワン・イリッチは最期の瞬間、いかにして人生を見出したか」
その答えはぜひ、作品を手に取って自ら見つけてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
