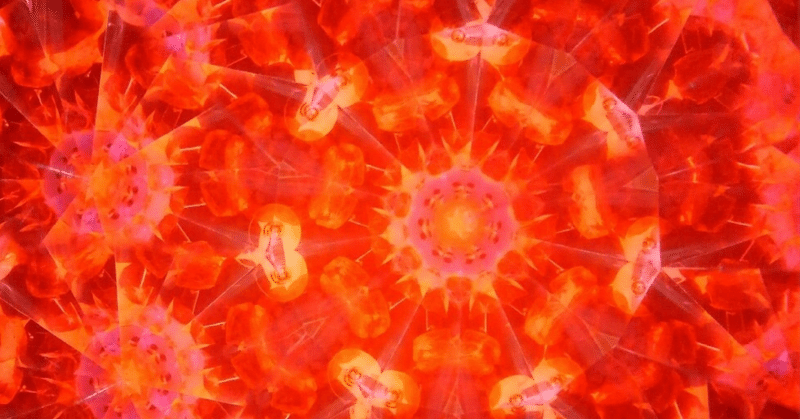
--赤い境界線--
部屋の照明には全て赤いカバーが被せられており、何もかも異様に見づらく、無言で進んでいく彼についていくのがやっとだった。
リビングに通され、勧められるままにルージュ色のソファに腰かけた。彼は「見せたいものがある」と言い、部屋から出て行った。
このソファは太陽の下では茶色なんだろうか、この丸いテーブルは白っぽいぞと私は緊張感を紛らわすためにこの空間を楽しもうと努力した。
何の変哲もないアパートの一角、晴天にもかかわらず、雨戸を閉め、外の喧騒も届かない。
このアトリエは完全に世間から隔絶され、独立した空間だった。
友人のつてで人形作家である彼を紹介してもらったが、その友人もつれて来るべきだったと後悔し始めていた。
彼は大きく細長い箱を担いで戻ってきた。テーブルの上に置かれると、それが何かの棺を模していることが分かった。
その木棺は赤い照明に交じることなく全体が黒く塗られ、側面には銀色に塗られたアラベスク模様が赤く反射している。仄かに檜の甘い香りが漂った。
彼が棺の上半分の蓋を外すと、眼を閉じた長髪の女性が姿を現した。薄ピンクの肌が生気を感じさせ、私は恐ろしさに鳥肌が立つ思いだったが、肩や腹のあたりを見るとそれは球体関節人形だった。
「生きてるように見えるだろ」
彼は得意そうに語りかけた。
「一瞬驚きましたよ。このために全ての照明を?」
「そうだ。先にネタを明かしたらつまらないからな。これが生きていると思った時、そして人形だと分かった時、君はどう感じた?」
「棺を見た時、何かしらの作品だと身構えたつもりだったのですが、照明や緊張感による錯覚のせいか、それがやけに人間らしく思えて、他者と対峙するときのある一定のストレスというか。なおかつその姿の「もう生きていない」という無数の黒い影が心臓を這うような不快感に襲われました。ただ、人形だと分かった瞬間は安心しました」
私は彼のひたむきな試みに応えようと詳細に感想を述べた。
「今はもうただの人形にしか見えない?」
「ええ、もう」
「そうか。ありがとう。じゃあこれは失敗作だ」
彼は棺の蓋を閉じた。
その瞳は悲しそうな眼をしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
