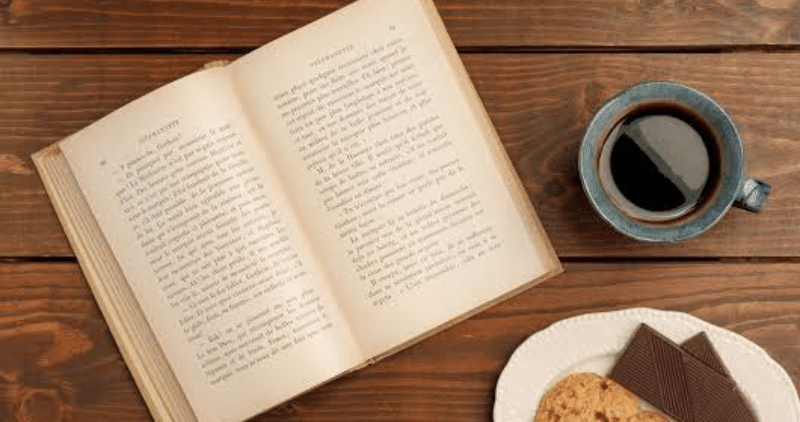
コモンとコミュニティ
一年で一番寒いこの時期、テレビではオミクロン株による新型コロナ感染拡大と北京冬季オリンピック報道で連日かまびすしいが、どちらも薄皮一枚外側で行われているような感じで、一人置いてけぼりを食っているように思うのは私だけだろうか。
それはさておき、過日、幼児期以来の入院生活を送るという人生で稀有な機会があり、改めて健康の大切さが身に染みた、前期高齢者の村上です。わがことでは監事という大役を仰せつかっています。
入院するにあたって、前半は術後ということでほとんど動けないだろうけど、暇を持て余すにちがいないと容易に想像がついたので、気になりつつ読みそびれていた本を2冊持ち込むことにしました。
今回は、そのうちの1冊、『人新世の「資本論」』に触発されたことがらを書こうと思います。
さて、以前のnoteにも書いたことがありますが、私は市職員OBです。 現職の時に地域コミュニティ構築に携わったことがあり、定年退職後、その御縁で地域コミュニティの中間支援を行っている高松市コミュニティ連合会に5年間お世話になっていました。
私と地域コミュニティとの関わりは、思いがけない人事異動から始まります。思いがけない、としたのは、前の職場ではまだ丸2年しか経っていなかったという事情からです。
異動の3年ほど前から、高松市では市内全域で地域コミュニティの構築が進められていましたが、いくつかの地区の組織化が遅れていました。当時の担当部長から地域コミュニティ推進担当主幹として未組織地区の構築及びコミュニティセンター整備を担当せよと命ぜられた私ですが、自治会はともかく、地域コミュニティについてはさしたる予備知識もなく、コミュニティって何?コミュニティ協議会、コミュニティセンターって何?何?という状況でした。
着任早々、担当者から引継ぎを受けましたが、真っ先にレクチャーしてくれたのが、コミュニティの語源でした。実際には諸説あるようですが、その時は、ラテン語の“コモ”と“ニテ”から成り、コモは“みんなで”、そしてニテには“守る”という意味がある、したがって“みんなで” “守る”のがコミュニティだという説明でした。何を守るのかと問うと、“(みんなの)大事なもの”だと。 そうか、“みんなで” “大事なもの”を“守る”のがコミュニティなのかと素直に受け止めました。
完全に納得したというわけではありませんでしたが、その時の私には、翌日からの組織構築、そしてそれが片付けば、人・物・財政・情報と多岐にわたる支援策の策定と実施…、やらなければならない事柄が山積みで、正直言って、それ以上語源について突っ込む余裕がなかったのです。

『人新世の「資本論」』については話題の本という認識はあったものの、恥ずかしながら内容についてはほとんど把握していませんでしたが、読み進めていくうち、素直にこれはスゴイなと思いました。資本論を軸に、現代社会における気候変動等の世界規模の様々な問題を、経済、化学、地学、心理学から地政学等々、学問の境を越えて縦横無尽に飛び回りつつ、絡んだ糸を撚り合わせて見事に壮大な理論、物語を創り上げていきます。悲しいかな私の理解力ではその全体像や真髄には到底到達できませんが、人類にとって出口のないこのギリギリの状況を変えうるのが共同体、つまりコミュニティである、ということは伝わってきました。また、コモンに関する記述を読んだとき、ふいに例の“コモ”と“ニテ”が脳裏に蘇ってきました。 今まで漠然と意識下に追いやっていたコミュニティの語源、コモとニテをつなぐミッシングリンクが見つかったような気がしたのです。
コモンとは、著者の表現によると、あらゆる人にとって生活に欠かせないもの、です。別の表現としては共有資産、共益などもあります。かつての共同体は規模も小さいため、その組織体において構成員に豊かな恵みをもたらしてくれる山や川、森林や田畑などの自然環境や全員が集まれる大きな集会施設であったり、ときにはそうしたものをコントロールする仕組みや共同体意識などもコモンとして認識されます。物質的なものだけでなく精神的なものもコモンなのです。
翻って私がその構築に関わった地域コミュニティですが、コミュニティとして確かに”(みんなの)大事なもの”は必要条件ではあるかもしれませんが、必ずしも十分条件ではないのではないか、という気がしてきました。
高松市の地域コミュニティが今一つ殻を破り切れていない理由の一つがここにあるのではないか、とも思いました。
もちろんコミュニティ協議会も、みんなの大事なものを体系化し可視化するための仕組みを持っています。コミュニティプランの策定です。ただ、如何せん協議会の区域は、原則小学校区という徒歩圏域の規模に設定はしているものの、かつての村落共同体と比べると、はるかに広大で、また構成員も広く住民だけでなく通勤・通学者や法人までを想定しているため、”(みんなの)大事なもの”をまとめようとすると、あれもこれもと最大公約数的にならざるを得ず、したがってどうしても焦点がぼやけてしまうきらいがあります。
”必要欠くべからざるもの”と”大事なもの”。“コモン”と“大事なもの”は「似て非なるもの」とまでは言わないまでも、その差は思った以上に大きいのではないのか、という思いを強くしています。 あれこれ要らない、最小公倍数として、たった一つでいいから、そのコミュニティにとって必要欠くべからざる“何か”を確立できたら、そのコミュニティの求心力、団結力は強くなるに違いないと思います。

この作業をコミュニティプラン策定の中でやるためには、今まで以上に区域内からあらゆる属性、年代層、分野別組織等々、縦・横・斜めのふるいでもって細かく要素を抽出しまとめ上げていくという大変な作業が必要となるでしょう。しかし、この作業抜きには本当のコミュニティは完成しないというのもまた確かな気がします。

“みんなで” “コモン” を “守る” のが “コミュニティ”。
幸い、今、私は役員の一人として地元のコミュニティ協議会に参画する機会を得ており、また、当地区のコミュニティプランの改訂作業はコロナ禍により中断、停滞しています。
私は、今後、自らの実践活動として、このコミュニティプランの改訂作業を通じてこの仮説の検証を試みていきたいと思っています。
============
わがことからイベント開催のお知らせです♪

私からはじまるコミュニティワークvol.4「わたしの活動自慢大会」
■概要
日時:2022年3月5日(土)14:00~16:00(13:30受付)
場所:高松市ヨット競技場大会議室(高松市浜ノ町67-1)
参加費:1,000円
■スペシャルゲスト
食の劇場 代表 岡本裕介さん
発表者の募集は締め切りましたが、聞くだけ参加の方はまだまだ募集を受け付けています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
