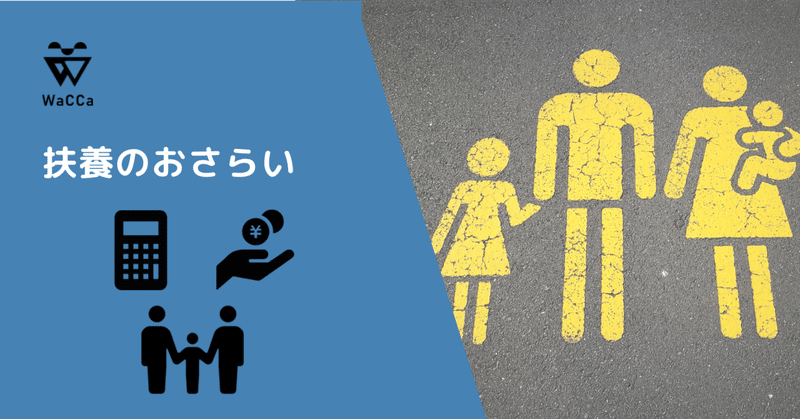
扶養のおさらい
こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。
昨日の衆議委員の予算委員会で、岸田総理が社会保険上の扶養に関する条件、所謂「130万円の壁」について見直し検討を進める考えを示したことが報道でも話題になっていました。
家族の扶養に入りながらパートなどで働く人が、130万円を超えると扶養の対象外となってしまうため、「もっと働きたい!!」と思いながらも、扶養を維持するために泣く泣くセーブしている、なんて話もよく聞きますが、今回はそんなホットな話題にちなんで、混同しがちな社会保険上の扶養と税法上の扶養の違いについて少し書いてみます。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、言葉の通り社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。
例えば夫婦間で、夫が妻(妻が夫)の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することになるため、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。
要するに被扶養者にとってメリットがあるものです。
社会保険の扶養控除の対象となるのは、扶養者の3親等内の親族が該当します。なお、配偶者の場合は生計維持の関係があれば別居でも可能ですが、子、孫、父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹以外の親族は同居が必要とされています。
冒頭にも記載した収入面の条件として、被扶養者は年間130万円未満であることと、扶養者の収入の半分以下である必要があります。
130万円以上となる場合、被扶養者の勤務先で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入し、自身で保険料を負担する必要があるため、130万の壁を意識して働かれる方も多いでしょう。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、所得税や住民税の負担を軽減させるための制度となるので、社会保険上の扶養とは異なり、扶養者本人がメリットを受けることができる制度になります。
扶養の対象となるのは、6親等内の血族および3親等内の姻族で同一生計となることです。また、原則は同居している必要がありますが、遠方の学校に通う学生の一人暮らしなどは、同一生計としてみなされるので例外的に対象となります。
また、年齢的な制限もあります。対象となる年の12月31日時点で16歳以上であることが対象の条件となります。これは、昨今「所得制限を外すか否か?」で議論をされている児童手当が創設されたタイミングでできた制約です。(つまり、16歳未満の扶養控除を無くした代わりに、児童手当ができた、というイメージです。)
収入の基準についても、社会保険とは異なり、基準は103万円以下(合計所得48万円+給与所得控除55万円)であるかというところになります。ただ、配偶者に限っては年間収入が103万円を超えた場合でも控除がまったく0になる、ということはなく、配偶者特別控除というものがあります。こちらは、扶養者の収入にもよりますが、被扶養配偶者の収入が、201万円までであれば、扶養者の税負担が軽減される制度です。被扶養配偶者の収入に応じて段階的にメリットも変わってくるものになります。
最後に
扶養の考え方の違いについて簡単にまとめてみましたが、こちらは人事労務に係るお仕事をされてない方でも、日常的に知っていて損は無い情報かと思いますので、是非参考にしていただければと思います!
また、今後は現行制度自体が見直しされる可能性もあるので、もし具体的な話などが出てきましたら、また改めてご紹介していければと思います。
そして毎度ですが、Twitterもやっているので、ご興味ある方はそちらのフォローもお願いします!!
それでは!
○●━━━━━━━━━━━・・・‥‥……
執筆 WaCCaの人
Twitterアカウント WaCCaの人
ホームページ 株式会社WaCCa
……‥‥・・・━━━━━━━━━━━●○
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
