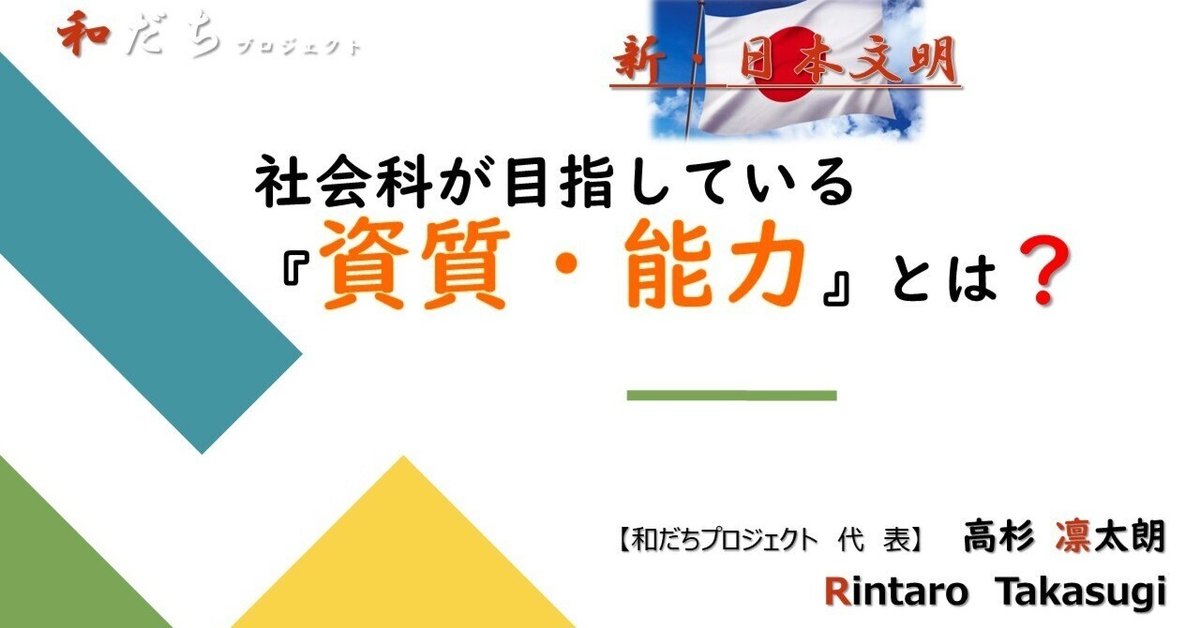
#2 社会科が目指している『資質・能力』を問う
おはようございます。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
前回は、『社会科を学ぶ意味』についてお話をしました。
今回は、
『社会科の目標と身につけさせたい資質・能力』について
お話をしていきます。
よろしくお願いします。

1)義務教育は、『国家プロジェクト』である。

皆さんは、『教育基本法』というものを知っていますか?
学校での教育は、この『教育基本法』をもとにして行われています。
『教育基本法』とは、
我が国の教育に関する基本的な考えや
教育制度に関する基本事項を定めた法律です。
教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つこと
から、いわゆる「教育界の憲法」として位置づけられています。
1947(昭和22)年に制定され、2006(平成18)年に改正しました。
これは、第一次安倍政権下で改正され、
『教育の目標』にはじめて、
「伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに」という
条文が盛り込まれました。
『教育基本法』は、
前文と第1章から第4章までで構成されており、全部で18条まであります。

義務教育とは、「国家戦略」です。
わが国をどのような方向にかじ取りしていくか、
その方向に向かって必要な人材を育てていくことが使命です。
しかし、人を育てることは、簡単なことではありません。
教育者は人間であり、子供も人間です。
国が決めたことを、決まった教え方をして
わが国の将来を担う人材が育成されるかというわけではありません。
そこで、我が国では、
教育の「内容」と「方法」を分けて考えることにしました。
目指すべき「目標」と教えるべき「内容」については国が定め、
どうやってそれを実現するのかといった「方法」については
現場の教員が担っているのです。
つまり、役割分担をしているのです。
2)『学習指導要領』が示す「学び方」とは?

そして、
『教育基本法』の理念の実現に向けて、
目指すべき「目標」と教えるべき「内容」を示し、
必要となる教育課程の基準を大綱的に定めたものを
『学習指導要領』と言います。
『学習指導要領』が果たす役割の一つは,
公の性質を有する 学校における教育水準を全国的に確保することです。
教育の指針(カリキュラムや教科書など)であり、
10年ごとに社会の変化に即したように改訂されます。
戦後から現在に至るまで、8回の改訂を経てきました。
子供たちの教科書や時間割は、これをもとに作られています。
歴史的には、「社会科」は戦後に発足した教科の一つです。

そして、
2017年に小学校の学習指導要領が改訂されました。
現在は、この指導要領をもとに教育が行われています。
今回の改訂は、僕はかなり画期的だと感じています。
「学力」の捉え方が改められたのです。
『学校教育法』の
第30条第2項の「小学校教育の目標」には、
「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、
基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、
これらを活用して課題を解決するために必要な
思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、
主体的に学習に取り組む態度を養うことに、
特に意を用いなければならない。」
としています。
これは、学力の三要素と呼ばれ、
①何ができるようになるか
②どのように学ぶか
③何を学ぶか
が資質・能力の3つの柱として示されました。

資質・能力の3つの柱は、
社会と連携・共同しながら、
未来の創り手となるための重点とされています。
『学習指導要領』が次に改訂されるであろう2030年の社会は、
AIの台頭や国際情勢が目まぐるしく変動し、
社会的変化が加速度的に人間の予測を超えて進展する社会になる
と考えられ、
そのような予測困難な社会が展開する時代に、
一人一人が未来の創り手となるためには、
基礎的・基本的な知識や技能の習得によって、
「主体的・対話的で深い学び」が実現され、
その過程で「学び方」も身につけ、
臨機応変に対応することができる能力を育てることの必要性が
高まっているのです。
3)社会科の究極目標である「公民的資質」とは何か?

では、社会科を通して、
どのような資質・能力をはぐくもうとしているのでしょうか?
『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』には、
このような力をはぐくむことを目指していると書かれています。
「見方・考え方」「課題解決の学習活動」という
社会科で重視すべき学習過程と
「公民としての資質・能力の基礎」という
究極目標が総括的に描かれています。
(1)は、「知識・技能」
(2)は、「思考力・判断力・表現力等」
(3)は、「学びに向かう力・人間性」
についての目標が示されています。

では、
社会科の究極目標である「公民的資質」とはどのようなものでしょうか。
これは、
昭和43年の学習指導要領に総括目標として登場して以来、
継続して使われてきました。
「公民的資質」とは、
簡単に言うと社会の中で生きる人間としての資質です。
人が社会の中で生きていれば、必ず問題に直面します。
そうした問題を解決するためにはどうすればよいのかを考えながら、
情報を活用しつつ、解決していける土台づくりをしていくという考え方
です。
さらに、
平成20年度の学習指導要領改訂では、
「日本人としての自覚をもって国際社会で主体的に生きるとともに、
持続可能な社会の実現を目指すなど」と説明も新たに加わりました。
個人としての生き方だけではなく、日本人として、共同体の一員として、社会の人々と力を合わせて問題を解決していくという考え方
です。
この2つの考え方を持つ「公民的資質の基礎」を育成することが、
社会科が目指すところなのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本には、綿連として受け継がれてきた「よさ」がある。
少しでもよりよい社会を創ることができるように努力してきた先人の知恵や働きを知ることで、何が我が国の社会で正しいとされているのかを学ぶ。
このような日本人のよさを共感しあうことを通じて、
その子も将来、私たちと同じように社会の形成者の一人となり、
日本のよさを受け継いでくれる存在になる。
そのために、
必要なことを学ぶことが「社会科の本質」である。
と僕は思います。
日本人が2683年以上紡いできた「和の国づくり」とは何か?
なぜ大切なのか?
どのように受け継いで、つないでいくのか?
を学ぶことを通して伝えていきたいのです。
日本に生まれた日本人が、
日本に生まれたことを幸せに感じ、
日本に生まれた子供達が、
日本に生まれたことを誇りに感じる。
そんな想いを社会科を通して育みたいのです。
一緒に、日本国を楽しく学んでいきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
